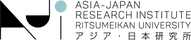アジア・マップ Vol.01 | ウズベキスタン
《エッセイ》ウズベキスタンの都市
サマルカンド―青の都のマルチリンガルな日常
サマルカンドといえば「青の都」としてつとに知られる、ウズベキスタン第二の都市である。「サマルカンド・ブルー」という表現もよく耳にするが、これはイスラーム建築の丸屋根や壁面を美しく飾る、技巧を凝らしたレンガやタイルが生み出す濃淡様々な青のことである。夏の強い日差しを受けた紺碧の空にこの青はひときわ映え、いつまでも眺めていたくなる。
サマルカンドはその古名をマラカンダといい、かつてシルクロードの商人として名をはせたソグド人の故地ソグディアナの中心であった。現在は考古学的な遺跡となっているアフラシアブの丘がそれにあたる。やがてモンゴルの征西により灰燼に帰したこの都をティムール(1336-1405)が征服により拡大した帝国の各地から連れ帰った職人らを動員して壮麗な帝都として復興した。今私たちが目にするサマルカンド、つまり世界遺産にもなっているレギスタン広場、ティムールの墓廟グリ・アミール、壮大なビビ・ハヌム・モスク、アフラシアブの丘のシャーヒ・ズィンダ廟群などティムール朝期以降のイスラーム建築の特徴を備えた歴史的建造物が散在する街並みは、ティムールの築いた帝都を下地としている。
近年では、2016年9月に亡くなった初代大統領イスラム・カリモフ(1938-2016)のサマルカンドにある墓所が周辺の再開発を伴って大規模なメモリアル・コンプレクスとなり、ウズベキスタンの人々にとってもサマルカンドに来たら一度は寄ってみる場所になっている。
サマルカンドはまた、ウズベキスタンの主要都市ながらブハラと並んでタジク人が多く居住する都市としても知られている。かつては中央アジアのテュルク語(ウズベク語)とペルシア語(タジク語)を母語とする住民が、バイリンガルな都市文化とサマルカンド人というアイデンティティを共有していた。19世紀後半にロシア帝国が中央アジアを征服すると、サマルカンドはトルキスタン総督府領に組み入れられた。その後ロシア革命によってソヴィエト政権が成立し、1924年にソ連体制のもとで民族別の共和国が成立するにあたって、サマルカンドは、ブハラとともに、ウズベキスタン(ウズベク・ソヴィエト社会主義共和国)に帰属することになった。1930年にタシュケントに遷都されるまで、サマルカンドはソヴィエト・ウズベキスタンの首都だった。逆に、サマルカンドやブハラのタジク人からすれば、由緒ある歴史的都市をその民族領域であるタジキスタンが獲得する機会を奪われたということにもなる。1980年代後半、ソ連末期の改革ペレストロイカの時期には、タジキスタンの知識人らがブハラとサマルカンドをタジキスタンの帰属にせよという要求を掲げたこともあったほどである。サマルカンドでは今でも日常的にタジク語が飛び交うのは珍しいことではなく、ふだんウズベク語やロシア語で仕事をしていても、家庭生活はタジク語だという人に私も何人も出会ったことがある。生活上の便宜からパスポート上の民族籍をウズベク人としているタジク人も少なからずいるだろう。
さて、2017年に中央アジアでロシア語話者が話すロシア語に関する言語学的調査に協力した時、サマルカンドでインタビューに応じてくれた人々からは、まさにウズベキスタンが、そしてこの都市が経験した近現代史の息吹を肌身に感じるようなお話をいくつも聞かせてもらうことができた。そして何といっても、もともとウズベク語とタジク語のバイリンガル文化の伝統があるこの都市で、ソ連時代を経て現在もロシア語で生活している人々の背景と言語状況が、自分の想像をはるかに超えて多様であることにあらためて驚かされたのである。
とりわけ印象深かったのは、ロシア語学を専門とする大学教員ナージャさん(仮名)の語りである。彼女はタジク人の父と、ウラル・コサックの血を引くというロシア系の母の間に1950年代前半に生まれた。母方の祖父はコサックのアタマン(指導者)だったそうである。ナージャさんの両親がどこでどのように出会ったのかは残念ながら聞きそびれてしまったのだが、彼女自身はサマルカンドで生まれ育った。父は数学の教授だったというから、ソヴィエト的なエリートの家庭に育ったことになるだろう。家庭生活はもっぱらロシア語だったそうで、現在の自分の言語能力を3点満点で評価するとしたら、ロシア語3、英語2、ウズベク語とタジク語は1とのことだった。
学生時代の懐かしい思い出といえば、ロックが流行っていたこと。ソ連ではいわゆるハード・ロックやパンクは「退廃的」「資本主義による精神汚染」として禁止されていたが、西側の音楽はそれなりにどこからか入ってくるもので、ナージャさんの世代はビートルズやローリングストーンズなどを当たり前のように聞いていたらしい。学生コピーバンドがいくつもできて、当時は楽器の入手さえさぞ困難だっただろうと思うのだが、競うように練習したり仲間うちで成果を発表したり、バンドに参加しなくてもいずれかのコピーバンドのファンになったりして、青春を謳歌していたそうだ。ナージャさんは「首都(タシュケント)とは違って、サマルカンドまでは当局もそれほど目配りしなかったんじゃないかしら」と推測しつつ、自分が夢中になったのは、実はイギリスのロック・バンド、ピンク・フロイドだったと明かしてくれた。
ペレストロイカの時期は、「えらく面白かった」そうで、言論の自由が拡大したことによりそれまで接したことのなかったような情報が次から次に出てくるので、ソ連の負の側面を初めて知ることに驚きとまどいながらも、まさに鵜の目鷹の目だったそうである。そのように情報と知識を吸収することがいかにわくわくすることだったか、そしてそれにいかに自分が貪欲だったか、ナージャさんは昔を懐かしみながら、目を輝かせるかのように熱心に語ってくれた。
私はといえば、このような生き生きとしたライフ・ヒストリーを聞かせてもらい、とかく名所旧跡に心を奪われがちなサマルカンドで、そこに暮らす人々が経験してきた生身の現代史に触れたような、新鮮な感慨を覚えたのだった。ナージャさんは、ロシア風の名とタジク風の姓を持ち、ロシア語で生活し、父親の母語であるタジク語やウズベキスタンの国家語であるウズベク語よりも英語のほうが得意だと言う。しかし彼女はここサマルカンドではけしてマージナルな存在ではなく、サマルカンド人としてゆるぎなく暮らしているように感じられた。青の都のマルチリンガルな日常は実に奥深いのである。
【参考文献】
宇山智彦編『中央アジアを知るための60章』明石書店、2010年。
帯谷知可「サマルカンドのイスラム・カリモフ廟を訪れて」『日本中央アジア学会報』第14号、2018年、59-66頁。
帯谷知可編『ウズベキスタンを知るための60章』明石書店、2018年。
小松久男「二つの都市のタジク人―中央アジアの民族間関係」原暉之・山内昌之編『スラブの民族』(講座スラブの世界第2巻)弘文堂、1995年、250-274頁。
木村暁「繫栄する青の都―ティムール朝から現代まで」『K』No. 3、2022年、28-35頁。
書誌情報
帯谷知可「《エッセイ》ウズベキスタンの都市 サマルカンドー青の都のマルチリンガルな日常」『《アジア・日本研究 Webマガジン》アジア・マップ』1, UZ.4.03(2023年1月10日掲載)
リンク: https://www.ritsumei.ac.jp/research/aji/asia_map_vol01/uzbekistan/essay02/