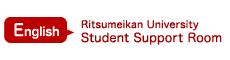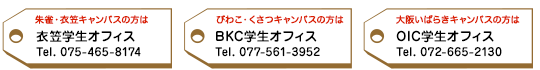2017.03.06
素敵な偶然
先日魚好きの我が子と一緒に映画『ファインディング・ドリー』のDVDを観ました。その中でドリーのあるセリフが心に残りました。それは「一番素敵なことは偶然起きるの。それが人生よ」というものでした。
考えてみれば私の人生においても『素敵』かは別として、様々な局面で偶然の出来事が大きく影響しています。あの時あの大学に不合格になっていなかったら、今の職業についてはいなかっただろうなぁとか、あの時あの友人の飲みの誘いに乗らなかったら、今関西に住んでいることもなかっただろうなぁとか・・。素敵な偶然や不幸な偶然など、様々な偶然の出来事が寄せ集まって、今の私が出来上がっているように思います。そしてまた、後からそうした偶然を振り返る時、あたかもそれが起こるべくして起こった運命であったかのような不思議や、ひとつひとつの偶然が何か一つの物語として繋がっているように感じたりもします。つまりそうした偶然に対する驚きに心奪われた時、人はそこに物語性や神秘性のようなものを感じたりするのでしょう。
カウンセリングの中でも、このような驚くべき偶然ともいうべき出来事に時々出くわします。全くの偶然の重なりが新しい発見の契機となったり、AかBかで悩んでいるときに全く予想だにしなかったCという要素が偶然現れて、事態を大きく好転させたり・・。あたかも隠れたシナリオライターがいるのではないかと思わせられるような、そういう意味の感じられる偶然に出くわした時、人が生きていくことの不思議さや趣深さを感じずにいられません。
逆に人生に偶然の出来事が絡まず全て必然の予定調和だったとしたらどうでしょうか。
それはなんとも味気ない世界であるように、私には感じられそうです。あるいは完全な自由はむしろ自由と感じられないといった逆説的な倦怠や、それともあらゆる全てが自分で選んだ結果であるという事態はあまりに重たすぎて耐え難い、といった感覚に私だったら苛まれるかもしれません。
しかし冷静に考えてみればその様な事態はあり得ないことでしょう。なぜなら人は自分で意図してこの世に生まれてくるものではなく、ある日気づいたらこの世界の中に存在していたわけです。生まれる時代や国や性別やなどなどを、選べるわけではなく、つまりは存在の始まりの部分に大きな偶然が横たわっていると言えるでしょう。人間のこうした事態を『被投性』という言葉で表すこともあります。人はまさにこの世界に『投げ込まれて』いる存在なのだと。
もしかすると、偶然にまつわる驚きに心奪われるということは、自分の存在の根幹が自分の意図や意思によって作られているものではなく、自分の意思を超えたところにあるということや、まさに無力にもこの世界に投げ込まれているということに気づき、その不思議を味わい、またそこから自分なりの物語を作っていくといったことの、契機としての意味も持っているものなのかもしれません。
話がちょっとややこしい方向に行ってしまいましたね。
ドリーの素敵なセリフと出会ってからほんの数日後、「人生において重大なことは偶然の出来事だ」といった異口同音の発言を、ある社会学者の対談の中で私は『偶然』目にしました。彼はまたそのことに関して「この次のページを開くとどんな事が起こるだろうというワクワク感があるから、人生のページを開き続けるのだ」といった意味のことを話していました。
二つの言葉との出会いが偶然に重なったことに私なりに意味を感じ、今回このテーマを書いてみました。全ての『偶然』に対して、『ワクワク感』や『一番素敵なこと』と捉えるのは難しいようにも思います。けれども、先のややこしい方向の存在の不思議な感覚と一緒に、そういうポジティブな偶然もあるから捨てたもんじゃないという気持を持ち続けたいなと思っています。
考えてみれば私の人生においても『素敵』かは別として、様々な局面で偶然の出来事が大きく影響しています。あの時あの大学に不合格になっていなかったら、今の職業についてはいなかっただろうなぁとか、あの時あの友人の飲みの誘いに乗らなかったら、今関西に住んでいることもなかっただろうなぁとか・・。素敵な偶然や不幸な偶然など、様々な偶然の出来事が寄せ集まって、今の私が出来上がっているように思います。そしてまた、後からそうした偶然を振り返る時、あたかもそれが起こるべくして起こった運命であったかのような不思議や、ひとつひとつの偶然が何か一つの物語として繋がっているように感じたりもします。つまりそうした偶然に対する驚きに心奪われた時、人はそこに物語性や神秘性のようなものを感じたりするのでしょう。
カウンセリングの中でも、このような驚くべき偶然ともいうべき出来事に時々出くわします。全くの偶然の重なりが新しい発見の契機となったり、AかBかで悩んでいるときに全く予想だにしなかったCという要素が偶然現れて、事態を大きく好転させたり・・。あたかも隠れたシナリオライターがいるのではないかと思わせられるような、そういう意味の感じられる偶然に出くわした時、人が生きていくことの不思議さや趣深さを感じずにいられません。
逆に人生に偶然の出来事が絡まず全て必然の予定調和だったとしたらどうでしょうか。
それはなんとも味気ない世界であるように、私には感じられそうです。あるいは完全な自由はむしろ自由と感じられないといった逆説的な倦怠や、それともあらゆる全てが自分で選んだ結果であるという事態はあまりに重たすぎて耐え難い、といった感覚に私だったら苛まれるかもしれません。
しかし冷静に考えてみればその様な事態はあり得ないことでしょう。なぜなら人は自分で意図してこの世に生まれてくるものではなく、ある日気づいたらこの世界の中に存在していたわけです。生まれる時代や国や性別やなどなどを、選べるわけではなく、つまりは存在の始まりの部分に大きな偶然が横たわっていると言えるでしょう。人間のこうした事態を『被投性』という言葉で表すこともあります。人はまさにこの世界に『投げ込まれて』いる存在なのだと。
もしかすると、偶然にまつわる驚きに心奪われるということは、自分の存在の根幹が自分の意図や意思によって作られているものではなく、自分の意思を超えたところにあるということや、まさに無力にもこの世界に投げ込まれているということに気づき、その不思議を味わい、またそこから自分なりの物語を作っていくといったことの、契機としての意味も持っているものなのかもしれません。
話がちょっとややこしい方向に行ってしまいましたね。
ドリーの素敵なセリフと出会ってからほんの数日後、「人生において重大なことは偶然の出来事だ」といった異口同音の発言を、ある社会学者の対談の中で私は『偶然』目にしました。彼はまたそのことに関して「この次のページを開くとどんな事が起こるだろうというワクワク感があるから、人生のページを開き続けるのだ」といった意味のことを話していました。
二つの言葉との出会いが偶然に重なったことに私なりに意味を感じ、今回このテーマを書いてみました。全ての『偶然』に対して、『ワクワク感』や『一番素敵なこと』と捉えるのは難しいようにも思います。けれども、先のややこしい方向の存在の不思議な感覚と一緒に、そういうポジティブな偶然もあるから捨てたもんじゃないという気持を持ち続けたいなと思っています。
学生サポートルームカウンセラー
2017.02.02
迷う
迷うことの多い人生を送ってきました。
小4の時、友人4人で友人宅近くの裏山を抜けるとどこに行くのか探検しようという話になり、深く考えずにそれとなく踏み固められた道を「埋蔵金のありかに繋がっていたらどうする!?」と、あり得ない空想話をしながら登っていきました。埋蔵金の使い道について話していると突然視界が開け、舗装された山道へと繋がり、埋蔵金という淡い野望は打ち砕かれました。とはいえ今度は当初の目的「この道はどこに繋がっているのか?」を確認しようと、日が差し込む明るい山道を心躍らせて登っていきました。徐々に山道は下り始め、日がかげるひんやりとした山道が続くと、この世とは違うところに通じているのではないかとドキドキし始めました。さらに、日が暮れて辺りが暗くなったことで不安をいっそう募らせた4人が、ハイテンションで“CHA-LA-HEAD-CHA-LA”を歌っていると、ぼんやりオレンジ色に灯る光が飛び込んできました。
オレンジ色の光は少し先の集落のある民家から漏れており、その民家に駆け込んで初対面のおばさんに事情を説明し、快く電話を貸してもらいました。親切なおばさんと電話、友人の親の車という文明の利器によって少年4人は難を逃れました。こうして探検という名の迷子は幕を閉じました。
しかしながら、歴史は繰り返すものです。
GPSで現在地や目的地までの道程を把握できるスマホという文明の利器が発達してからも何かにつけ迷っています。
数年前のこと。沖縄の宮古島に行きました。夕食後に浜辺で酒を飲みながら星を見ようという話になり、友人と2人、宿から一番近い浜辺を目指しました。googleマップによると10分で着くとのこと。『10m先、右方向です』という機械的な女性の声を疑うこともなく、音声案内通りに歩きました。でも、10分経っても20分経っても、海や砂浜が見えるどころか潮の香りもしません。なんなら私たちがいるはずの場所がマップ上に表示すらされないのです。スマホへの信頼を失った2人はとにかく明るい方向を目指しました。タクシー会社という看板が飛び込んできました。が、タクシーは出払っていていません。その後も大きいと思われる道を歩いていると、運よくタクシーが通りかかりました。乗車し運転手さんに「どこどこの浜辺に行きたい」と伝えてから、スマホを頼りに歩いたが迷ったこと、宿はどこそこだと話していると、運転手さんは一言。「反対方向さぁ~」…。
ようやく辿り着いた浜辺に座って、星を見ながら酒を飲むという至福の時間を過ごしていました。すると…ぼんやりとオレンジ色がかった明かりが、真っ暗な水平線に浮かんできました。見てはいけないものを見ているのでは…?さっきの運転手さん、実は…?恐るおそる友人に告げてみました。友人にも見えていたのでちょっと安心しましたが、その正体がしばらく分かりませんでした。徐々にその光が水平線より高く浮かび上がるにつれ、妖艶かつ儚げで、いざなうように水面に映るその光は三日月によるものだと分かりました。日の出ならぬ、月の出を見ていたのです。
迷ったものの人の温かさに助けられした。迷って必要以上に時間とお金をかけて、運転手さんが浜辺まで運んでくれたおかげで、抜群のタイミングで神秘的な月の出を見ることができました。迷うことの多い人生を送ってきて、その上この文章の落としどころも迷ってはいますが、要は迷うことで得られるものもあるんじゃないか、とも思っているのです。
詩人ゲーテも「人は努力する限り迷うものだ」と書いています。大学生という期間、進路や就職、友人や恋人、家族などの人間関係、自分とは何か…と何かにつけて迷うことが多い時期だと思います。迷う、迷っているということは何かを求めているのでしょう。迷うことの多かった私としては、そうした時、他の人に“Help!”を求めるのも、カウンセラーに相談するのも、ひとつの方法ではないかなと思います。
小4の時、友人4人で友人宅近くの裏山を抜けるとどこに行くのか探検しようという話になり、深く考えずにそれとなく踏み固められた道を「埋蔵金のありかに繋がっていたらどうする!?」と、あり得ない空想話をしながら登っていきました。埋蔵金の使い道について話していると突然視界が開け、舗装された山道へと繋がり、埋蔵金という淡い野望は打ち砕かれました。とはいえ今度は当初の目的「この道はどこに繋がっているのか?」を確認しようと、日が差し込む明るい山道を心躍らせて登っていきました。徐々に山道は下り始め、日がかげるひんやりとした山道が続くと、この世とは違うところに通じているのではないかとドキドキし始めました。さらに、日が暮れて辺りが暗くなったことで不安をいっそう募らせた4人が、ハイテンションで“CHA-LA-HEAD-CHA-LA”を歌っていると、ぼんやりオレンジ色に灯る光が飛び込んできました。
オレンジ色の光は少し先の集落のある民家から漏れており、その民家に駆け込んで初対面のおばさんに事情を説明し、快く電話を貸してもらいました。親切なおばさんと電話、友人の親の車という文明の利器によって少年4人は難を逃れました。こうして探検という名の迷子は幕を閉じました。
しかしながら、歴史は繰り返すものです。
GPSで現在地や目的地までの道程を把握できるスマホという文明の利器が発達してからも何かにつけ迷っています。
数年前のこと。沖縄の宮古島に行きました。夕食後に浜辺で酒を飲みながら星を見ようという話になり、友人と2人、宿から一番近い浜辺を目指しました。googleマップによると10分で着くとのこと。『10m先、右方向です』という機械的な女性の声を疑うこともなく、音声案内通りに歩きました。でも、10分経っても20分経っても、海や砂浜が見えるどころか潮の香りもしません。なんなら私たちがいるはずの場所がマップ上に表示すらされないのです。スマホへの信頼を失った2人はとにかく明るい方向を目指しました。タクシー会社という看板が飛び込んできました。が、タクシーは出払っていていません。その後も大きいと思われる道を歩いていると、運よくタクシーが通りかかりました。乗車し運転手さんに「どこどこの浜辺に行きたい」と伝えてから、スマホを頼りに歩いたが迷ったこと、宿はどこそこだと話していると、運転手さんは一言。「反対方向さぁ~」…。
ようやく辿り着いた浜辺に座って、星を見ながら酒を飲むという至福の時間を過ごしていました。すると…ぼんやりとオレンジ色がかった明かりが、真っ暗な水平線に浮かんできました。見てはいけないものを見ているのでは…?さっきの運転手さん、実は…?恐るおそる友人に告げてみました。友人にも見えていたのでちょっと安心しましたが、その正体がしばらく分かりませんでした。徐々にその光が水平線より高く浮かび上がるにつれ、妖艶かつ儚げで、いざなうように水面に映るその光は三日月によるものだと分かりました。日の出ならぬ、月の出を見ていたのです。
迷ったものの人の温かさに助けられした。迷って必要以上に時間とお金をかけて、運転手さんが浜辺まで運んでくれたおかげで、抜群のタイミングで神秘的な月の出を見ることができました。迷うことの多い人生を送ってきて、その上この文章の落としどころも迷ってはいますが、要は迷うことで得られるものもあるんじゃないか、とも思っているのです。
詩人ゲーテも「人は努力する限り迷うものだ」と書いています。大学生という期間、進路や就職、友人や恋人、家族などの人間関係、自分とは何か…と何かにつけて迷うことが多い時期だと思います。迷う、迷っているということは何かを求めているのでしょう。迷うことの多かった私としては、そうした時、他の人に“Help!”を求めるのも、カウンセラーに相談するのも、ひとつの方法ではないかなと思います。
学生サポートルームカウンセラー
2017.01.13
試験前にお勧め 呼吸法
寒さ厳しくなってきましたね。
試験が近づいてきて、心身ともに緊張しやすい時期です。
どんなに心身の調子がすぐれない時でも、できることがあります。呼吸法です。
体操やウォーキングなど、体を動かすものはつい億劫になりがちですし、
安静を必要とする場合は、かえって逆効果になることもあります。
その点、呼吸法は寝た状態でも、座ってもできますし、
ほとんど体の動きを伴わなくても、心身に対する影響力は、見逃せないものがあります。
心をいつでも軽やかに保っていくために、呼吸法はいつでもどこでもできる、
お勧めの方法です。
--------------
寝ても座っても立っててもいいです。背筋は伸ばしておきます。
まず、背骨をパイプに見立てて、頭のてっぺんから背骨に吸い入れ、
お腹をふくらませます。
吐く時は、反対にお腹から背骨を通して、頭頂へ吐いていきます。
吸うときは鼻から、吐く時はすぼめた口から吐きます。
3回行います。
次に、片手でも重ねた両手でもいいので、体に触れます。
気になるところ、患っているところ、どこでもいいです。
--------------

例えば、こっている肩、痛む腰、胃の上や、足の先でもいいでしょう。
その手を当てている部分に吸った息を入れていくというイメージで呼吸をします。
実際にそこに息を入れることはもちろんできません。
そんなふうにイメージするということです。
吸うときには、
その部分に、ヒーリングエネルギーないし、
太陽の光、神の祝福、好きな色、新鮮な酸素、
なんでもいいので、
気持ちの良い癒しのエネルギーを
送り込むようにイメージします。
そこがふくらみ、
満たされていく感じがします。
吐く時は、
口をすぼめてシューッと吐いていきますが、
手の触れた場所が、
吐く息とともにこりや力みが
取れゆるんでくるイメージ、
ないし、悪いもの、老廃物、痛み、
ネガティブな感情などが、
口から排泄されるイメージを持ってもいいでしょう。
一か所につき3回くりかえします。
気になる場所をひと通り行ったら、
最後は背骨のパイプ呼吸を3回行って仕上げます。
試験勉強の合間に、よかったら試してみてくださいね。
試験が近づいてきて、心身ともに緊張しやすい時期です。
どんなに心身の調子がすぐれない時でも、できることがあります。呼吸法です。
体操やウォーキングなど、体を動かすものはつい億劫になりがちですし、
安静を必要とする場合は、かえって逆効果になることもあります。
その点、呼吸法は寝た状態でも、座ってもできますし、
ほとんど体の動きを伴わなくても、心身に対する影響力は、見逃せないものがあります。
心をいつでも軽やかに保っていくために、呼吸法はいつでもどこでもできる、
お勧めの方法です。
--------------
寝ても座っても立っててもいいです。背筋は伸ばしておきます。
まず、背骨をパイプに見立てて、頭のてっぺんから背骨に吸い入れ、
お腹をふくらませます。
吐く時は、反対にお腹から背骨を通して、頭頂へ吐いていきます。
吸うときは鼻から、吐く時はすぼめた口から吐きます。
3回行います。
次に、片手でも重ねた両手でもいいので、体に触れます。
気になるところ、患っているところ、どこでもいいです。
--------------
例えば、こっている肩、痛む腰、胃の上や、足の先でもいいでしょう。
その手を当てている部分に吸った息を入れていくというイメージで呼吸をします。
実際にそこに息を入れることはもちろんできません。
そんなふうにイメージするということです。
吸うときには、
その部分に、ヒーリングエネルギーないし、
太陽の光、神の祝福、好きな色、新鮮な酸素、
なんでもいいので、
気持ちの良い癒しのエネルギーを
送り込むようにイメージします。
そこがふくらみ、
満たされていく感じがします。
吐く時は、
口をすぼめてシューッと吐いていきますが、
手の触れた場所が、
吐く息とともにこりや力みが
取れゆるんでくるイメージ、
ないし、悪いもの、老廃物、痛み、
ネガティブな感情などが、
口から排泄されるイメージを持ってもいいでしょう。
一か所につき3回くりかえします。
気になる場所をひと通り行ったら、
最後は背骨のパイプ呼吸を3回行って仕上げます。
試験勉強の合間に、よかったら試してみてくださいね。
学生サポートルームカウンセラー
2016.12.01
個性に負けないために
個性というものは本来、尊重されるべきものですが、「個性的」という言葉は時としてポジティブな意味では用いられないことがあります。「自分らしさ」が周りの人たちのそれと大きく異なっていて、協調性が低いと評価されたときなどにネガティブな「個性的」という言葉が使われがちなようです。
「自分らしさ」が受け入れてもらえなかった経験を持ち、そのことを自覚してしまった人は往々にして、人見知りになったり無口になったり消極的になったりします。さらにこれは、時として負のスパイラルへの入り口となってしまい、「自分らしさ」を消したにもかかわらず、友人に恵まれないという事態に陥ってしまうことがあります。こうなってしまうと大変で、自力ではなかなか脱出できなくなってしまいます。
受容されない、という経験は、トラウマのようになってしまうケースもあり、次の一歩を踏み出す際の大きな壁になってしまいがちです。このような場合には、「誰か」に助けてもらうのが一番です。かならず受け入れてもらえる相手と話をし、他者とのコミュニケーションのとり方を探っていく、次に踏み出していく勇気を持てるための準備をする、といったことをしてみることが大切です。
僕自身も、高校生のときに部活動でお世話になった恩師の先生に「卒業」の際に次のような言葉をいただきました。『いつでも遊びにおいで。ただ、しょっちゅう遊びにくるようではよくない。それは、新しい場所の居心地がよくないということだから』。いまも、この言葉を大切に考えています。だめになったら帰っていけるけれども、その存在は重たくない、そういう場所を提示してもらえたことで、僕は大いに救われました。「いま」が満たされている人は、『あのころはよかった』などと考えることはあまりなく、ふとしたときに思い出して、昔いた場所を訪れたりするものなので、その場所が重荷になってはいけないのです。
本学には、学生サポートルームや障害学生支援室、ピアサポーター制度など、多くのサポート体制が整っています。学部の教員や職員ももちろん、その一翼を担いたいと思っているわけですが、そういった大勢のメンバーが、「いま現在、一時的に」居場所を見つけられない皆さんの居場所を提供しています。
個性を隠蔽してしまうのではなく、どう発揮すればいいかを考える「仮の居場所」として、ぜひそういう場所や人を活用してもらえればと思います。決して、「仮の居場所」を「安住の地」にしてしまって入り浸ってしまうのではなく、ふと思い出して遊びに行ける場所にしていけるように、踏み出していってもらいたいな、と思っています。
いまの居場所に満足している人は、ぜひ、そうやって困っている人がいないか目を配ってあげ、一緒になって個性の発揮の仕方を考えてあげる、そういう存在になってください。自分で「痛み」を経験した人や、他人の「痛み」を共有した人はきっとその分だけ強くなれます。『配慮は他人(ひと)のためならず』です。
「自分らしさ」が受け入れてもらえなかった経験を持ち、そのことを自覚してしまった人は往々にして、人見知りになったり無口になったり消極的になったりします。さらにこれは、時として負のスパイラルへの入り口となってしまい、「自分らしさ」を消したにもかかわらず、友人に恵まれないという事態に陥ってしまうことがあります。こうなってしまうと大変で、自力ではなかなか脱出できなくなってしまいます。
受容されない、という経験は、トラウマのようになってしまうケースもあり、次の一歩を踏み出す際の大きな壁になってしまいがちです。このような場合には、「誰か」に助けてもらうのが一番です。かならず受け入れてもらえる相手と話をし、他者とのコミュニケーションのとり方を探っていく、次に踏み出していく勇気を持てるための準備をする、といったことをしてみることが大切です。
僕自身も、高校生のときに部活動でお世話になった恩師の先生に「卒業」の際に次のような言葉をいただきました。『いつでも遊びにおいで。ただ、しょっちゅう遊びにくるようではよくない。それは、新しい場所の居心地がよくないということだから』。いまも、この言葉を大切に考えています。だめになったら帰っていけるけれども、その存在は重たくない、そういう場所を提示してもらえたことで、僕は大いに救われました。「いま」が満たされている人は、『あのころはよかった』などと考えることはあまりなく、ふとしたときに思い出して、昔いた場所を訪れたりするものなので、その場所が重荷になってはいけないのです。
本学には、学生サポートルームや障害学生支援室、ピアサポーター制度など、多くのサポート体制が整っています。学部の教員や職員ももちろん、その一翼を担いたいと思っているわけですが、そういった大勢のメンバーが、「いま現在、一時的に」居場所を見つけられない皆さんの居場所を提供しています。
個性を隠蔽してしまうのではなく、どう発揮すればいいかを考える「仮の居場所」として、ぜひそういう場所や人を活用してもらえればと思います。決して、「仮の居場所」を「安住の地」にしてしまって入り浸ってしまうのではなく、ふと思い出して遊びに行ける場所にしていけるように、踏み出していってもらいたいな、と思っています。
いまの居場所に満足している人は、ぜひ、そうやって困っている人がいないか目を配ってあげ、一緒になって個性の発揮の仕方を考えてあげる、そういう存在になってください。自分で「痛み」を経験した人や、他人の「痛み」を共有した人はきっとその分だけ強くなれます。『配慮は他人(ひと)のためならず』です。
学生部副部長
理工学部教授
川方 裕則
2016.11.04
「いつの間にか忘れる」ということ
小学2年生の頃だったと思います。今でもあると思いますが、チョロQという、ぜんまいばねで走るミニカーのおもちゃがはやっていて、私もひとつ所有していました。とても気に入っていて、肌身離さずといった感じでいつも遊んでいました。しかし寝るときには、押し入れの中にしまわないといけません。あるとき、次のような疑問が浮かびました。「このチョロQは、押し入れの戸を閉めて誰も見ていない時にも、本当にそこにあるのだろうか?」。それとも、押し入れを開けて、私の目にとまったときだけ、そこに現れるのではないか。
そんな馬鹿なと思いながらも、とても気になったので、押し入れの戸をほんのちょっと開け、中をのぞいてみましたが、暗くて見えません。そこでもうほんのちょっとだけ開けてみると、一筋の光が差して、そこに黄色のチョロQが見えます。でも当然ですが、見えているときにそこにあっても、自分の疑問の答えにはならないということにすぐに気がつきます。
そこで私は、チョロQに細い糸を結びつけ、本体は押し入れの中にしまって、糸は戸の隙間から外へ出しておくという工夫をしました。この糸を引っ張って、そこに重さが感じられれば、チョロQは確かにそこにあるということです(自分で言うのも何ですが、小学生の頃だけ、私は天才児だったのです!)。実際やってみると、重さは感じられたのですが、しかし、これでもダメだと気づきます。というのは、今やチョロQと糸は一体のものになっているので、糸が外に見えているのでは、チョロQ全体が隠れていることにはならない。糸も押し入れの中にしまわないといけませんが、それだと引っ張れません。
他にもいろいろ考え実験したのですが、長くなるので省略します。ついには、近所のお医者様に協力してもらって、X線で押し入れの中を調べるという計画も思いつきましたが、これも、X線が当たっているときだけ、そこに存在するという可能性がありますし、そもそも、押し入れの中のチョロQの調査に、お医者様が協力して下さるとは思えなかったため、言い出せずにそのままでした。
それで、結局この問題はどうなったのかというと、よく覚えていないのですが、どうやらいつの間にか忘れてしまったようです。いくら考えてもいい方法が思いつかないのと、きっと他に何か関心をひかれることができたのでしょう。
それから40年。かつての天才児は、紆余曲折を経て、今では臨床心理士という資格をいただいて、心理カウンセリングの仕事をするようになりました。
カウンセリングでお聴きする悩み事は様々ですが、中でも人間関係に関するものはとても多いです。そして、人間関係の難しさの根本原因のひとつは、他人が心の中で本当は何を考えているのか、確かめる方法がないということのようです。
男子学生のAさん。キャンパスを歩いていると、どこからか笑い声が聞こえる。あれは自分のことを笑っているのではないか?自分の容姿や振る舞いが、嘲笑の対象になっているのでは?そんなことが気になって、家に閉じこもることが多くなってきました。
女子学生のB子さん。付き合っている彼氏が、バイトに行っていると言っているけど、本当はウソで、別の女性と会っているのではないかと気になって仕方がない。二人で会っているときの彼はとても優しくて、信頼できそうに見える。でも、自分の目の前からいなくなると、急に不安になるといいます。時にはバイト先まで確かめに行ってしまう。姿を確認してそっと帰ってくるのです。自分でも何をやっているんだろうと思うけれどやめられない。
そんな悩みを聴きながらいつも思うのは「可能性はゼロではないなあ」ということです。人の気持ちをのぞいて確かめてみる方法がない以上、100%の保証などできません。ですから、カウンセラーとしての私は、AさんやB子さんに「大丈夫だよ。心配ないよ」などという気休めを言うことはできません。ふつうに考えたら大丈夫なことくらい、彼ら自身分かっています。でも、ゼロではない可能性のことを思うと、気になって仕方なくて苦しいという気もちを否定することなどできません。
そこで私自身も「どうしたらいいのだろう?」と思いながら、一所懸命お話を聴き続けます。すると、当初の悩み事から少しずつ離れていって、さまざまな話題が広がっていきます。育った家庭や両親のこと、最近腹の立ったこと、嬉しかったこと、好きなマンガのこと、中学の時に遭ったいじめのこと、気になりはじめた就活のこと、最近見た印象的な夢のこと等々。そんなお話を一所懸命お聴きしていると、不思議なことに、当初の訴えだった悩み事が少しずつ薄らいできて、いつの間にか忘れてしまうということが起きてくるのです。
「不思議なことに」と書きましたが、本当は臨床心理学という学問を深く学ぶことで、そこで何が起きているのか、相当程度、理解することができます。しかし、一番大切なことは、人間には「いくら考えても仕方のないことは、絶対の保証が得られなくても、いつの間にか忘れてしまう」という能力が備わっている(あるいは後からでも育てることができる)らしいということです。そのおかげで私たちは、安心して楽しく暮らしていくことができているようです。
かつてチョロQ問題に深く悩んだ私からすると、それで本当にいいのかという疑問もあるのですが、そんな疑問もいつの間にか忘れて、忙しく働いている毎日です。
そんな馬鹿なと思いながらも、とても気になったので、押し入れの戸をほんのちょっと開け、中をのぞいてみましたが、暗くて見えません。そこでもうほんのちょっとだけ開けてみると、一筋の光が差して、そこに黄色のチョロQが見えます。でも当然ですが、見えているときにそこにあっても、自分の疑問の答えにはならないということにすぐに気がつきます。
そこで私は、チョロQに細い糸を結びつけ、本体は押し入れの中にしまって、糸は戸の隙間から外へ出しておくという工夫をしました。この糸を引っ張って、そこに重さが感じられれば、チョロQは確かにそこにあるということです(自分で言うのも何ですが、小学生の頃だけ、私は天才児だったのです!)。実際やってみると、重さは感じられたのですが、しかし、これでもダメだと気づきます。というのは、今やチョロQと糸は一体のものになっているので、糸が外に見えているのでは、チョロQ全体が隠れていることにはならない。糸も押し入れの中にしまわないといけませんが、それだと引っ張れません。
他にもいろいろ考え実験したのですが、長くなるので省略します。ついには、近所のお医者様に協力してもらって、X線で押し入れの中を調べるという計画も思いつきましたが、これも、X線が当たっているときだけ、そこに存在するという可能性がありますし、そもそも、押し入れの中のチョロQの調査に、お医者様が協力して下さるとは思えなかったため、言い出せずにそのままでした。
それで、結局この問題はどうなったのかというと、よく覚えていないのですが、どうやらいつの間にか忘れてしまったようです。いくら考えてもいい方法が思いつかないのと、きっと他に何か関心をひかれることができたのでしょう。
それから40年。かつての天才児は、紆余曲折を経て、今では臨床心理士という資格をいただいて、心理カウンセリングの仕事をするようになりました。
カウンセリングでお聴きする悩み事は様々ですが、中でも人間関係に関するものはとても多いです。そして、人間関係の難しさの根本原因のひとつは、他人が心の中で本当は何を考えているのか、確かめる方法がないということのようです。
男子学生のAさん。キャンパスを歩いていると、どこからか笑い声が聞こえる。あれは自分のことを笑っているのではないか?自分の容姿や振る舞いが、嘲笑の対象になっているのでは?そんなことが気になって、家に閉じこもることが多くなってきました。
女子学生のB子さん。付き合っている彼氏が、バイトに行っていると言っているけど、本当はウソで、別の女性と会っているのではないかと気になって仕方がない。二人で会っているときの彼はとても優しくて、信頼できそうに見える。でも、自分の目の前からいなくなると、急に不安になるといいます。時にはバイト先まで確かめに行ってしまう。姿を確認してそっと帰ってくるのです。自分でも何をやっているんだろうと思うけれどやめられない。
そんな悩みを聴きながらいつも思うのは「可能性はゼロではないなあ」ということです。人の気持ちをのぞいて確かめてみる方法がない以上、100%の保証などできません。ですから、カウンセラーとしての私は、AさんやB子さんに「大丈夫だよ。心配ないよ」などという気休めを言うことはできません。ふつうに考えたら大丈夫なことくらい、彼ら自身分かっています。でも、ゼロではない可能性のことを思うと、気になって仕方なくて苦しいという気もちを否定することなどできません。
そこで私自身も「どうしたらいいのだろう?」と思いながら、一所懸命お話を聴き続けます。すると、当初の悩み事から少しずつ離れていって、さまざまな話題が広がっていきます。育った家庭や両親のこと、最近腹の立ったこと、嬉しかったこと、好きなマンガのこと、中学の時に遭ったいじめのこと、気になりはじめた就活のこと、最近見た印象的な夢のこと等々。そんなお話を一所懸命お聴きしていると、不思議なことに、当初の訴えだった悩み事が少しずつ薄らいできて、いつの間にか忘れてしまうということが起きてくるのです。
「不思議なことに」と書きましたが、本当は臨床心理学という学問を深く学ぶことで、そこで何が起きているのか、相当程度、理解することができます。しかし、一番大切なことは、人間には「いくら考えても仕方のないことは、絶対の保証が得られなくても、いつの間にか忘れてしまう」という能力が備わっている(あるいは後からでも育てることができる)らしいということです。そのおかげで私たちは、安心して楽しく暮らしていくことができているようです。
かつてチョロQ問題に深く悩んだ私からすると、それで本当にいいのかという疑問もあるのですが、そんな疑問もいつの間にか忘れて、忙しく働いている毎日です。
学生サポートルームカウンセラー
2016.10.01
SMAP解散報道から考える、喪うこととその再生について
この夏もいろいろなニュースがありました。その中でも、リオオリンピックの最中に日本中を駆け抜けたSMAPの解散報道は老若男女問わず、そこそこの衝撃を与えたのではないでしょうか。私自身も、特別に大ファンというわけではないのですが、音楽を聴くようになった小学校時代から思い返すと、SMAPの曲はつかず離れず耳に届いていたおり、切ない気持ちになりました。
今回の解散報道を、少し無理やり心理学らしく話してみると、“お母さんとお父さんの仲がうまくいかなくなって、子どもを家に置いてお母さんが出て行ってしまった家庭”のようだと考えることができるような気がします。末っ子の香取くんは、幼い頃からSMAPに入り、マネージャーの方をお母さんのように慕い、SMAPという家で活動していました。お母さんが家を出た原因は、姑と小姑との確執だったのでしょう。けれど、末っ子の香取くんからすれば、「なぜ、長男である木村くんがお母さんを守れなかったのか」と怒りを募らせても不思議ではありません。元々、香取くんは木村くんを尊敬し、慕い、憧れの対象として見ていました。だからこそ、母親を喪うという喪失体験に際して、一番一緒に戦ってほしい存在だったのではないでしょうか。父親不在のSMAP家で、お母さんを喪った香取くんの怒りが、父親代わりの木村くんにより強く向けられたのかもしれません。
四男の草彅くんは、末っ子の香取くんと仲良しなので、「香取くんの気持ちを尊重する」と考えても不思議はありません。三男の稲垣くんは、真ん中の子がとりがちな、“周りに合わせる”という行動をしています。次男の中居くんは、兄と弟たちの仲を何とか取り持とうと頑張ったのかもしれませんが、残念ながらそれは叶いませんでした。
大切な人を喪う(死別だけでなく、関係が途切れてしまうことも指します)ことによる悲嘆には、悲しみや無念さだけでなく、怒りの感情を伴うことが多いことが分かっています。そして、その怒りは、最も信頼できる人に向けられやすいのです。
喪失体験から回復するまでの道のりを“喪の作業”と呼びます。この“喪の作業”は、1.無感覚の段階(激しい衝撃に呆然とし、ショックを受けている状態)、2.否認・抗議の段階(喪失を認めようとせず、認めさせようとする者に抗議する状態)、3.絶望・失意の段階
(激しい失意、不安、抑うつといった心理的反応が現れる状態)4.再建の段階(喪失を次第に受け止め、事実と折り合いをつける状態)という過程を辿り、個人差はありますが、最後の段階にいくまでには莫大な時間とエネルギーを要します。私たちは生きている限り、喪失を繰り返します。いかに喪失を乗り越えるかということの重要性について、改めて考えさせられた夏でもありました。
今回の解散報道を、少し無理やり心理学らしく話してみると、“お母さんとお父さんの仲がうまくいかなくなって、子どもを家に置いてお母さんが出て行ってしまった家庭”のようだと考えることができるような気がします。末っ子の香取くんは、幼い頃からSMAPに入り、マネージャーの方をお母さんのように慕い、SMAPという家で活動していました。お母さんが家を出た原因は、姑と小姑との確執だったのでしょう。けれど、末っ子の香取くんからすれば、「なぜ、長男である木村くんがお母さんを守れなかったのか」と怒りを募らせても不思議ではありません。元々、香取くんは木村くんを尊敬し、慕い、憧れの対象として見ていました。だからこそ、母親を喪うという喪失体験に際して、一番一緒に戦ってほしい存在だったのではないでしょうか。父親不在のSMAP家で、お母さんを喪った香取くんの怒りが、父親代わりの木村くんにより強く向けられたのかもしれません。
四男の草彅くんは、末っ子の香取くんと仲良しなので、「香取くんの気持ちを尊重する」と考えても不思議はありません。三男の稲垣くんは、真ん中の子がとりがちな、“周りに合わせる”という行動をしています。次男の中居くんは、兄と弟たちの仲を何とか取り持とうと頑張ったのかもしれませんが、残念ながらそれは叶いませんでした。
大切な人を喪う(死別だけでなく、関係が途切れてしまうことも指します)ことによる悲嘆には、悲しみや無念さだけでなく、怒りの感情を伴うことが多いことが分かっています。そして、その怒りは、最も信頼できる人に向けられやすいのです。
喪失体験から回復するまでの道のりを“喪の作業”と呼びます。この“喪の作業”は、1.無感覚の段階(激しい衝撃に呆然とし、ショックを受けている状態)、2.否認・抗議の段階(喪失を認めようとせず、認めさせようとする者に抗議する状態)、3.絶望・失意の段階
(激しい失意、不安、抑うつといった心理的反応が現れる状態)4.再建の段階(喪失を次第に受け止め、事実と折り合いをつける状態)という過程を辿り、個人差はありますが、最後の段階にいくまでには莫大な時間とエネルギーを要します。私たちは生きている限り、喪失を繰り返します。いかに喪失を乗り越えるかということの重要性について、改めて考えさせられた夏でもありました。
学生サポートルーム カウンセラー
2016.09.01
(中年の)部活のススメ
去年の秋、私は初めてママさんバレー部に入部しました。こっそり入っていたのですが、何かの折に周囲の人に知れるたび、「え?なんで?」という反応が返ってきました。それまでバレーボールはおろか、特に運動していたわけでもないのに、突然この歳になってなぜそのような突飛な行動に出たのか?出られるのか?と不思議がられるのです。私の中ではわりあい明快な理由があったので、聞かれたらこんな感じのことを答えていました。長年運動しなければと思い続けているものの、ランニングは三日坊主どころか一日坊主、色々買ったエクササイズDVDもほこりをかぶっている、ジムに入って出かけていくのは面倒だし時間がかかりすぎる・・・ということで、近所で拘束力あるかたちで運動ができる場所がママさんバレー部だったのです。球技はまあまあ好きだし、主力メンバーをよく知っていたので、いじめられる心配(?)がなかったのも後押ししてくれました。
そんなわけで、わりと地域の強豪チームだと知りつつ、もちろん戦力外でお荷物にしかならないこと必至でしたが入部させてもらったのでした。私の運動部経験といえば、中学時代のテニス部だけ。それすらなかったら、さすがに入る勇気がもてなかったかもしれませんが、とはいえ、大昔の話です。初めて行った時はドキドキの連続でした。まず、誰かが「集合~」と言います。皆さんさっと駆け足で監督さん(OBの男前な女監督さんがいました)のもとに集まるので私も慌ててついて行き、お話を聞きます。ママさん同士のゆるいサークルを勝手にイメージしていたので、これだけでもびくびくです。「サイドからの攻撃が」どうのこうの、など私には目が点になるようなお話ばかり。でももちろん質問などせず、黙って聞きました。それから円になって準備体操を始めるや、「いーち、にー、さーん、しー」と号令のような声かけを順番にしていきます。独特のトーンがあるので、私もその節回しをなんとか真似して声かけをします。そして、いざ練習が始まると、専門用語ばかりで何を言ってるのか分からない。ここでもまた、見よう見まねで何とかついていきます。最後の練習試合になると、それはそれでまた別の声かけがありました。「声出してー」とよく言われるのですが、独特のハイトーンボイスで「ナイサーいっぽん~(ナイスサーブを一本)」、「さあいけ(味方チームのサーバーに対して)」「さあこい(相手チームのサーバーに対して)」「きるよきるよ(得点され続けている流れを切るよ)」など、最初は意味すら分からない言葉をまさか私が偉そうに発するわけにもいきませんし、やはりここでも黙って分からないままついていきます・・・プチご近所留学、異文化体験です。
こうしてふり返ると、確かに周囲の「よく入ったね」という驚きも無理ないことでした。体育館の床には色とりどりのラインが引かれていて、どれがバレーボールのコートなのかすら分からない状態でよく飛び込んだものです。知らぬが仏でもあり、ほどよく(?)面の皮が厚くなっている中年だからこそできたのかもしれません。そして、そのようなド初心者の私をよくぞ温かく受け入れ、しかも熱心に指導してくださる良き先輩方に感動します。私は微動だにできない速球に体ごと飛び込んでレシーブしたり、ビシーッと思いきりアタックできる先輩方、どなたももれなくおばちゃんですが、中学生が先輩に憧れるような気分で「かっこいい~~」と思います。そのうえ、意地悪なダメだしなど一切なしです。ミスをしたら、どういうことに気をつければいいか的確に助言し、その部分を改善する練習メニューを考えてくれます。そんな先輩方のかっこいい姿や熱意を見せられたら、のほほんと汗かけたらそれでいいわぁーと言っているわけにはいきません。少しでも早く反応できるように、いいフォームでうてるように、大真面目に練習に取り組んでいます。雨乞いをして、実際雨で練習が中止になると喜んでいた中学時代とは大違いです。練習して少しでも上達できるってなんて素敵なこと、と本気で思えます。そして、試合の開始前には、男前の女監督さんが「(私に対して)点差ついたら出すから準備しといて。(チームに対して)あんたらは出してあげられるように点とってきぃー」と送り出すのでした。かっこいい。おばちゃんパーマの女監督さんにほれそうになる瞬間です。
とまあ、こんな具合に、私が入ったママさんバレー部は、意外にも理想の部活を絵に描いたような部活のパラダイスでした。いつか・・回転レシーブとはいかないまでも、飛び込んでレシーブできるようになることを夢見ている今日この頃です。
そんなわけで、わりと地域の強豪チームだと知りつつ、もちろん戦力外でお荷物にしかならないこと必至でしたが入部させてもらったのでした。私の運動部経験といえば、中学時代のテニス部だけ。それすらなかったら、さすがに入る勇気がもてなかったかもしれませんが、とはいえ、大昔の話です。初めて行った時はドキドキの連続でした。まず、誰かが「集合~」と言います。皆さんさっと駆け足で監督さん(OBの男前な女監督さんがいました)のもとに集まるので私も慌ててついて行き、お話を聞きます。ママさん同士のゆるいサークルを勝手にイメージしていたので、これだけでもびくびくです。「サイドからの攻撃が」どうのこうの、など私には目が点になるようなお話ばかり。でももちろん質問などせず、黙って聞きました。それから円になって準備体操を始めるや、「いーち、にー、さーん、しー」と号令のような声かけを順番にしていきます。独特のトーンがあるので、私もその節回しをなんとか真似して声かけをします。そして、いざ練習が始まると、専門用語ばかりで何を言ってるのか分からない。ここでもまた、見よう見まねで何とかついていきます。最後の練習試合になると、それはそれでまた別の声かけがありました。「声出してー」とよく言われるのですが、独特のハイトーンボイスで「ナイサーいっぽん~(ナイスサーブを一本)」、「さあいけ(味方チームのサーバーに対して)」「さあこい(相手チームのサーバーに対して)」「きるよきるよ(得点され続けている流れを切るよ)」など、最初は意味すら分からない言葉をまさか私が偉そうに発するわけにもいきませんし、やはりここでも黙って分からないままついていきます・・・プチご近所留学、異文化体験です。
こうしてふり返ると、確かに周囲の「よく入ったね」という驚きも無理ないことでした。体育館の床には色とりどりのラインが引かれていて、どれがバレーボールのコートなのかすら分からない状態でよく飛び込んだものです。知らぬが仏でもあり、ほどよく(?)面の皮が厚くなっている中年だからこそできたのかもしれません。そして、そのようなド初心者の私をよくぞ温かく受け入れ、しかも熱心に指導してくださる良き先輩方に感動します。私は微動だにできない速球に体ごと飛び込んでレシーブしたり、ビシーッと思いきりアタックできる先輩方、どなたももれなくおばちゃんですが、中学生が先輩に憧れるような気分で「かっこいい~~」と思います。そのうえ、意地悪なダメだしなど一切なしです。ミスをしたら、どういうことに気をつければいいか的確に助言し、その部分を改善する練習メニューを考えてくれます。そんな先輩方のかっこいい姿や熱意を見せられたら、のほほんと汗かけたらそれでいいわぁーと言っているわけにはいきません。少しでも早く反応できるように、いいフォームでうてるように、大真面目に練習に取り組んでいます。雨乞いをして、実際雨で練習が中止になると喜んでいた中学時代とは大違いです。練習して少しでも上達できるってなんて素敵なこと、と本気で思えます。そして、試合の開始前には、男前の女監督さんが「(私に対して)点差ついたら出すから準備しといて。(チームに対して)あんたらは出してあげられるように点とってきぃー」と送り出すのでした。かっこいい。おばちゃんパーマの女監督さんにほれそうになる瞬間です。
とまあ、こんな具合に、私が入ったママさんバレー部は、意外にも理想の部活を絵に描いたような部活のパラダイスでした。いつか・・回転レシーブとはいかないまでも、飛び込んでレシーブできるようになることを夢見ている今日この頃です。
学生サポートルームカウンセラー
2016.08.01
年をとるということ
先日、とあるロックバンドのライブに行きました。彼らはテレビの音楽番組に出演することがほぼなく、音楽チャートの順位も世間の知名度も決して高くはありません。かといって、まったく無名のマイナーバンドというわけでもなく、多くの有名なアーティストが彼らへのリスペクトを表明しています。彼らは今年で結成27年を迎えるのですが、27年間ずっと「売れていないなかでは売れている」という独自の地位に立ち続けている、ある意味稀有なバンドと言えるでしょう。
前に彼らを見たのは、かれこれ十数年前、京都の小さなライブハウスでした。私はまだ大学生で、彼らを見るのはそのときが初めてでした。ステージの中央でライトを浴びながら熱唱していたボーカルの男性は、「最高の夜にしようぜ!」「お前らついてこい!!」などと呼びかけ、拳を振り上げて観客を煽っていました。彼の表情は自らの才能への確信と、それを理解しない大衆への苛立ちに満ちていました。私はそんな彼の姿に激しくときめき、周りの観客と同じように拳を振り上げ、ステージ上の彼に届けとばかりに喉が枯れるまで叫んでいました。
それから随分時が経って、彼らの音楽を聴かない時期もありました。しかし最近、友人に薦められて新しいアルバムを手にとってみたところ、耳に飛び込んできた最初の一音から、彼らの世界にぐいぐいと引きずり込まれました。ほぼ反射的に「ライブに行きたい」と思い、チケットをとりました。「売れていないなかでは売れている」というくらいのバンドなので、とろうと思えばいつでもチケットがとれるのです。
ライブ当日、大阪のそこそこ大きいライブハウスで開演を待ちながら、私はだいぶ薄れてしまった十数年前の記憶を、小さくなった飴をなめるように繰り返し反芻していました。現在の彼らは、いったいどんな進化したパフォーマンスを見せてくれるのだろう。そんな期待が膨らむなか、客席の照明が消えました。
ステージに現れたボーカルの彼の顔は、老けていました。歌声の力強さこそ変わらず、見た目も実年齢からすれば若いものの、経た年月の分、確実に老いていました。何曲か歌った後、演奏がやんで、彼がおもむろに「実は…」と口を開きました。私は固唾を飲んで彼の言葉を待ちました。
「告白するけど…、俺たち、昔は若かったんだよ」
自虐的なその言葉に、会場はさざなみのような笑い声に包まれましたが、私は心の底から「せやな」と頷いていました。年をとった彼は、曲と曲のあいだ休憩するためにわざと長い時間をかけてギターをチューニングし、怪我をしないように非常に緩やかに客席にダイブし、そして再びステージに戻るときも若干まごつきながら登っていました。「四十後半で、こんなに人前で汗かく仕事をしているなんて」と苦笑いながら次の曲に移る彼、そんな彼をにやにやしつつ見守るメンバーも、おっさんそのものでした。
同時に私は気づきました。彼らが老いたのと同じだけ、私もまた老いていることに。今の私には「最前列にいく!」という気概もないし、無我夢中でステージに腕を振ったり、ぴょんぴょん跳びはねたり、きゃーきゃー叫んだりすることも減りました。体がつらいからです。さらには体だけでなく、心もそう簡単にはときめかなくなっているからです。
しかし、普段ならちょっとブルーになってしまうようなそうした事実が、そのときはそんなに嫌ではありませんでした。やたらと長い時間待った後のアンコールでは、メンバー全員が缶ビールを飲みながら現れ、演奏もせずにどうでもいいことをだらだらとしゃべっていました。ゆるい空気のなかでぐだぐだと笑い合う彼らは、以前よりもずっと自由に見えました。そしてそれを聞いている私も、2時間立ちっぱなしで疲れた体を休ませつつ、ただ口を開けて笑っていました。
最後に1曲、彼らが少し昔の曲を演奏してくれました。変わらない音と歌声にしばし心が弾み、若返った気分ではしゃぐことができました。翌日には喉が枯れていたし、本格的な筋肉痛が一日遅れでやってきたので、やはりブルーにはなったのですが、こうやってバンドもファンも一緒に年をとっていくのは、悪くないものだな、と思いました。
前に彼らを見たのは、かれこれ十数年前、京都の小さなライブハウスでした。私はまだ大学生で、彼らを見るのはそのときが初めてでした。ステージの中央でライトを浴びながら熱唱していたボーカルの男性は、「最高の夜にしようぜ!」「お前らついてこい!!」などと呼びかけ、拳を振り上げて観客を煽っていました。彼の表情は自らの才能への確信と、それを理解しない大衆への苛立ちに満ちていました。私はそんな彼の姿に激しくときめき、周りの観客と同じように拳を振り上げ、ステージ上の彼に届けとばかりに喉が枯れるまで叫んでいました。
それから随分時が経って、彼らの音楽を聴かない時期もありました。しかし最近、友人に薦められて新しいアルバムを手にとってみたところ、耳に飛び込んできた最初の一音から、彼らの世界にぐいぐいと引きずり込まれました。ほぼ反射的に「ライブに行きたい」と思い、チケットをとりました。「売れていないなかでは売れている」というくらいのバンドなので、とろうと思えばいつでもチケットがとれるのです。
ライブ当日、大阪のそこそこ大きいライブハウスで開演を待ちながら、私はだいぶ薄れてしまった十数年前の記憶を、小さくなった飴をなめるように繰り返し反芻していました。現在の彼らは、いったいどんな進化したパフォーマンスを見せてくれるのだろう。そんな期待が膨らむなか、客席の照明が消えました。
ステージに現れたボーカルの彼の顔は、老けていました。歌声の力強さこそ変わらず、見た目も実年齢からすれば若いものの、経た年月の分、確実に老いていました。何曲か歌った後、演奏がやんで、彼がおもむろに「実は…」と口を開きました。私は固唾を飲んで彼の言葉を待ちました。
「告白するけど…、俺たち、昔は若かったんだよ」
自虐的なその言葉に、会場はさざなみのような笑い声に包まれましたが、私は心の底から「せやな」と頷いていました。年をとった彼は、曲と曲のあいだ休憩するためにわざと長い時間をかけてギターをチューニングし、怪我をしないように非常に緩やかに客席にダイブし、そして再びステージに戻るときも若干まごつきながら登っていました。「四十後半で、こんなに人前で汗かく仕事をしているなんて」と苦笑いながら次の曲に移る彼、そんな彼をにやにやしつつ見守るメンバーも、おっさんそのものでした。
同時に私は気づきました。彼らが老いたのと同じだけ、私もまた老いていることに。今の私には「最前列にいく!」という気概もないし、無我夢中でステージに腕を振ったり、ぴょんぴょん跳びはねたり、きゃーきゃー叫んだりすることも減りました。体がつらいからです。さらには体だけでなく、心もそう簡単にはときめかなくなっているからです。
しかし、普段ならちょっとブルーになってしまうようなそうした事実が、そのときはそんなに嫌ではありませんでした。やたらと長い時間待った後のアンコールでは、メンバー全員が缶ビールを飲みながら現れ、演奏もせずにどうでもいいことをだらだらとしゃべっていました。ゆるい空気のなかでぐだぐだと笑い合う彼らは、以前よりもずっと自由に見えました。そしてそれを聞いている私も、2時間立ちっぱなしで疲れた体を休ませつつ、ただ口を開けて笑っていました。
最後に1曲、彼らが少し昔の曲を演奏してくれました。変わらない音と歌声にしばし心が弾み、若返った気分ではしゃぐことができました。翌日には喉が枯れていたし、本格的な筋肉痛が一日遅れでやってきたので、やはりブルーにはなったのですが、こうやってバンドもファンも一緒に年をとっていくのは、悪くないものだな、と思いました。
学生サポートルームカウンセラー
2016.07.01
ある日トイレで
数年前のことですが、某百貨店のトイレが改装されました。洗浄ボタンや音出し機能が側壁にすっきりまとめられ、モダンに印象が変わり驚きましたが、使用方法がすぐ側に貼られていたため、使い方に困る人はいないだろうと思っていました。
それからしばらくしてそのトイレに行った際、事件は起こりました。
あるご婦人が手前の個室に入ったまま出てきません。具合でも悪くなったかと順番待ちの列がざわつき始めた頃、中から『〇〇ちゃーん!どうやって流したらええの!?どうするのこれ?!』と叫び声が聞こえてきました。何度呼んでも奥の個室にいるらしき〇〇ちゃんから返事はなく、奥と手前の個室は閉ざされたまま。順番待ちの列に「どうやってマダムを救出する?」と焦燥感が漂い始めたその時、先頭のマダムが個室に向けて助け舟を出しました。『右の壁に水洗ボタンがありますよ。使い方も書いてありますよ』と声をかける先頭マダムの勇気に感謝しこれで個室のマダムも救われるはず、と我々は安堵しました。ところが、かえって慌てたのか、個室のマダムは『〇〇ちゃーん!早よ来てー!』を繰り返し、先頭マダムのアドバイスはかき消されたのでした。
中央のトイレのみが稼動する中順番が来てしまい、個室のマダムのその後は分からずじまいとなりました。無骨なレバー方式や大きい押しボタンの水洗トイレの普及率に感心しながらバスに揺られる帰り道、ある夏の出来事を思い出しました。
その夏、私はニューヨークのバスの中で途方に暮れておりました。当時私は学生で、留学中の友人を訪ねて空港から移動中でした。目的地が近づくのに、降車ボタンが見当たらないのです。観察しても誰もそれらしき物を押す気配がありません。しかし、運転席上の画面にバス停の名前が点滅すると停車し、点滅しないバス停は通過されてしまうことは見ていて分かりました。焦った私は思い切って乗客に尋ねました。「どうしたら降りられますか?」と。尋ねられたニューヨーカーは何がわからないのかがわからない、とキョトンとしていましたが、すぐに表情が明るくなり『次、降りたいの?』と聞いてくれました。必死に頷く私を見てその人は『こうするんだよ』とある物を押してみせてくれました。皆さん、何だかわかりますか?それは車内の手すりに貼り巡らされた黄色と黒のゴムコードだったのです。ゴムコードが降車ボタンの役目を果たしていたのですね。灯台下暗しとはまさにこのこと。それは乗車中、私がずっと目にしていたものでした。
人が慣れ親しんだ形状からイメージを切り替えて、新しい様式に慣れたり取り入れたりしていくのにはそれなりに時間がかかるものなのでしょう。そして焦ると、目の前にヒントや助け舟が出されたとしても見落としやすくなるものですね。
さて、久しぶりに某百貨店に行く機会があり、あのトイレのその後が気になり寄ってみました。貼紙が・・・増えていました!扉の内側にも大きく使用方法が掲示され、ボタンの真上には『ここを押すと水が流れます』と書かれた矢印型テープが追加されていました。いまや貼紙だらけでスタイリッシュはどこへやら状態のそのトイレ、定着するにはまだまだ時間がかかりそうです。
それからしばらくしてそのトイレに行った際、事件は起こりました。
あるご婦人が手前の個室に入ったまま出てきません。具合でも悪くなったかと順番待ちの列がざわつき始めた頃、中から『〇〇ちゃーん!どうやって流したらええの!?どうするのこれ?!』と叫び声が聞こえてきました。何度呼んでも奥の個室にいるらしき〇〇ちゃんから返事はなく、奥と手前の個室は閉ざされたまま。順番待ちの列に「どうやってマダムを救出する?」と焦燥感が漂い始めたその時、先頭のマダムが個室に向けて助け舟を出しました。『右の壁に水洗ボタンがありますよ。使い方も書いてありますよ』と声をかける先頭マダムの勇気に感謝しこれで個室のマダムも救われるはず、と我々は安堵しました。ところが、かえって慌てたのか、個室のマダムは『〇〇ちゃーん!早よ来てー!』を繰り返し、先頭マダムのアドバイスはかき消されたのでした。
中央のトイレのみが稼動する中順番が来てしまい、個室のマダムのその後は分からずじまいとなりました。無骨なレバー方式や大きい押しボタンの水洗トイレの普及率に感心しながらバスに揺られる帰り道、ある夏の出来事を思い出しました。
その夏、私はニューヨークのバスの中で途方に暮れておりました。当時私は学生で、留学中の友人を訪ねて空港から移動中でした。目的地が近づくのに、降車ボタンが見当たらないのです。観察しても誰もそれらしき物を押す気配がありません。しかし、運転席上の画面にバス停の名前が点滅すると停車し、点滅しないバス停は通過されてしまうことは見ていて分かりました。焦った私は思い切って乗客に尋ねました。「どうしたら降りられますか?」と。尋ねられたニューヨーカーは何がわからないのかがわからない、とキョトンとしていましたが、すぐに表情が明るくなり『次、降りたいの?』と聞いてくれました。必死に頷く私を見てその人は『こうするんだよ』とある物を押してみせてくれました。皆さん、何だかわかりますか?それは車内の手すりに貼り巡らされた黄色と黒のゴムコードだったのです。ゴムコードが降車ボタンの役目を果たしていたのですね。灯台下暗しとはまさにこのこと。それは乗車中、私がずっと目にしていたものでした。
人が慣れ親しんだ形状からイメージを切り替えて、新しい様式に慣れたり取り入れたりしていくのにはそれなりに時間がかかるものなのでしょう。そして焦ると、目の前にヒントや助け舟が出されたとしても見落としやすくなるものですね。
さて、久しぶりに某百貨店に行く機会があり、あのトイレのその後が気になり寄ってみました。貼紙が・・・増えていました!扉の内側にも大きく使用方法が掲示され、ボタンの真上には『ここを押すと水が流れます』と書かれた矢印型テープが追加されていました。いまや貼紙だらけでスタイリッシュはどこへやら状態のそのトイレ、定着するにはまだまだ時間がかかりそうです。
学生サポートルームカウンセラー
2016.06.01
遊園地に行った話
今年のゴールデンウィークに、身内の小学生と大人と私とで遊園地に行きました。ゴンドラに乗って山を登った先にある、古くて小さな遊園地です。
園内には、大小さまざまな子どもたちがひしめきあっていました。もちろん大人もいたのですが、乗り物の前に長い列を作っているのは、ほとんどが小さい人たちでした。私は小学生の付き添いだったので、その中に混ざって堂々と並びました。
船が振り子のように揺れるバイキングという名の遊具に乗った際には、背後の少女が3秒に1回ぐらいの割合で「しんぞうがとまる」と叫び、その声は永久に続くかと思われました。そのうち、前の少年が激しく身悶えを始めました。そして、ついに少年は「ちんちんがばくはつする」という呻き声を上げました。堰を切ったように繰り返される苦しげな声と、背後の絶叫とで、船上は、まるで子ども地獄のようでした。私は地上に降り立つまで、たいへんな努力で笑いをこらえました。
その後、人込みの中で、気付くと私はひとりになっていました。身内ふたりの姿がどこにも見えません。電話するか……と思った瞬間、思い出しました。バイキングに乗ったとき、自分のリュックサックを身内の大人に預けっぱなしにしていたのです。ポケットには小銭すらありません。私の周りでは、子どもたちが水の流れのように動き続けていました。空は青く、小さい人々の笑い声は絶えることがありませんでした。視界の全てに人がいて、空中でぐるぐる回ったり、高速で移動したりしていました。どれぐらい突っ立っていたのかは分かりません。その後、笑いながら走ってきた身内の小学生によって私は発見されました。
それから私たちは、巨大な駒の形をした、回転する遊具に乗りました。小学生が「外側がいい」と言うので私は内側に座ったのですが、その結果、とてつもない遠心力によって、あやうく小学生を押し潰すところでした。手すりを握りしめる私の掌は燃えるようでした。自分の体重との戦いの末、やっとスピードが落ち始め、機械は止まり、やれやれと息をつきました。そのため、機械がゆっくりと逆回転を始めた瞬間、私たちは真剣な目で見つめ合いました。
全体的に夢のように楽しい一日でした。
前回、山の上の遊園地に行ったのは、ずっと昔、20年ぐらい前だったと思います。身内の小学生は、そのときまだ存在していません。そして、当時一緒に行った大人は、今この世にいません。そのときのことは、今もはっきりと覚えています。冬の平日、静かな遊園地で、私が行くまで止まっていた機械が、私ひとりのために動かされました。空中を一周するたび、大人の顔が見えました。いつ見ても、ものすごく笑っていました。どうしてそんなに笑っているのだろう。私は不思議に思っていましたが、その答えは、じきに分かりました。乗り物に乗ってぐるぐる回っている間じゅう、私はずっと笑いっぱなしだったみたいです。
次に山の遊園地に行くのは、何年後になるのでしょう。身内の小学生はもう大人になっているでしょうか。今度は私がこの世にいなくなっているのでしょうか。もしそうなら、遊園地に来て、小学生が私のことを思い出したら面白いなと思います。
山の上の遊園地は、私にとってそういう場所なのかもしれません。20年後も30年後も、その先もずっと、存在していてほしいです。
皆さんにも、そんな場所はありますか?
園内には、大小さまざまな子どもたちがひしめきあっていました。もちろん大人もいたのですが、乗り物の前に長い列を作っているのは、ほとんどが小さい人たちでした。私は小学生の付き添いだったので、その中に混ざって堂々と並びました。
船が振り子のように揺れるバイキングという名の遊具に乗った際には、背後の少女が3秒に1回ぐらいの割合で「しんぞうがとまる」と叫び、その声は永久に続くかと思われました。そのうち、前の少年が激しく身悶えを始めました。そして、ついに少年は「ちんちんがばくはつする」という呻き声を上げました。堰を切ったように繰り返される苦しげな声と、背後の絶叫とで、船上は、まるで子ども地獄のようでした。私は地上に降り立つまで、たいへんな努力で笑いをこらえました。
その後、人込みの中で、気付くと私はひとりになっていました。身内ふたりの姿がどこにも見えません。電話するか……と思った瞬間、思い出しました。バイキングに乗ったとき、自分のリュックサックを身内の大人に預けっぱなしにしていたのです。ポケットには小銭すらありません。私の周りでは、子どもたちが水の流れのように動き続けていました。空は青く、小さい人々の笑い声は絶えることがありませんでした。視界の全てに人がいて、空中でぐるぐる回ったり、高速で移動したりしていました。どれぐらい突っ立っていたのかは分かりません。その後、笑いながら走ってきた身内の小学生によって私は発見されました。
それから私たちは、巨大な駒の形をした、回転する遊具に乗りました。小学生が「外側がいい」と言うので私は内側に座ったのですが、その結果、とてつもない遠心力によって、あやうく小学生を押し潰すところでした。手すりを握りしめる私の掌は燃えるようでした。自分の体重との戦いの末、やっとスピードが落ち始め、機械は止まり、やれやれと息をつきました。そのため、機械がゆっくりと逆回転を始めた瞬間、私たちは真剣な目で見つめ合いました。
全体的に夢のように楽しい一日でした。
前回、山の上の遊園地に行ったのは、ずっと昔、20年ぐらい前だったと思います。身内の小学生は、そのときまだ存在していません。そして、当時一緒に行った大人は、今この世にいません。そのときのことは、今もはっきりと覚えています。冬の平日、静かな遊園地で、私が行くまで止まっていた機械が、私ひとりのために動かされました。空中を一周するたび、大人の顔が見えました。いつ見ても、ものすごく笑っていました。どうしてそんなに笑っているのだろう。私は不思議に思っていましたが、その答えは、じきに分かりました。乗り物に乗ってぐるぐる回っている間じゅう、私はずっと笑いっぱなしだったみたいです。
次に山の遊園地に行くのは、何年後になるのでしょう。身内の小学生はもう大人になっているでしょうか。今度は私がこの世にいなくなっているのでしょうか。もしそうなら、遊園地に来て、小学生が私のことを思い出したら面白いなと思います。
山の上の遊園地は、私にとってそういう場所なのかもしれません。20年後も30年後も、その先もずっと、存在していてほしいです。
皆さんにも、そんな場所はありますか?
学生サポートルームカウンセラー