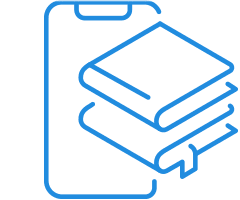国際関係学をいかに学んでいけばよいのかを、国際関係学の各領域の紹介、学習法の紹介、文献やWebサイト等の紹介などから説明しています。
元来は学内向けのものであり、場所の紹介や蔵書検索の方法等では学内向けの説明がされているところもありますが、学外の国際関係学を学ぶ人たちにとっても利用価値があるものです。したがって、利用者は学内者に限定していません。
IRナビが皆さんの本当のNavigatorになることを望むものです。
『IRナビ』は、皆さんが国際関係学という大海を航海していくうえでの海図(チャート)です。入学の直後から卒業論文の執筆まで繰り返し参照すべきガイドとして,国際関係学の学びの方向,技法,ルールについてのさまざまな情報をまとめています。
『IRナビ』は,「専門編」「テクニック編」「語学編」「地域編」という4つの部分からなっています。専門編を読めば,国際関係学の様々な領域(国際政治,戦争と平和,国際法,国際機構,国際経済学,国際協力,異文化・社会,情報・メディア,環境学,地域研究,ジェンダー論,メディア文化産業)の学び方がわかります。次に,具体的な学習の進め方や取り組み方については,テクニック編が役立ちます。ここでは,論文・レポートの書き方,プレゼンテーションの方法,レジュメの作り方,フィールド調査の仕方,データ収集の仕方,クロス履修の注意点についてまとめています。留学に関心がある人は,ぜひ留学の勧めに目を通して下さい。国際関係学部では,専門教育と並んで,語学と地域研究を学びの柱のに位置づけています。語学編には,英語,フランス語,スペイン語,ドイツ語,中国語,朝鮮語の6つの言語についての学び方の案内があります。地域編では,アジア,中東,アフリカ,ヨーロッパ,ラテンアメリカ,アメリカ合衆国・カナダとい6つの大きな地域をとりあげ,それらの地域を研究する方法を解説しています。
1回生の皆さんは,自分の関心を見つけ,基礎演習や語学科目の授業に積極的に取り組み,学びの姿勢やスタイルを確立していくために,ぜひ『IRナビ』を開いて下さい。2回生の皆さんは,専門科目・地域研究科目の履修や探究やゼミ(専門演習)のクラス選択に向けて,『IRナビ』を活用して下さい。3回生以上の皆さんは,タームペーパー(ゼミの期末レポート),そして卒業論文の執筆に向けて,改めて『IRナビ』を読み直してみましょう。特に,テクニック編の「卒業研究の仕方」は,皆さんが計画的に研究と論文執筆に取り組むうえで,参考になるところが多いはずです。卒業後にさらに国内あるいは国外の大学院への進学を検討している人は,同じくテクニック編の「大学院進学のすすめ」がヒントになるでしょう。
政治学・法学・経済学・歴史学・社会学などのような伝統的な学問と違って,国際関係学には,まだはっきりと定着したイメージはありません。皆さんの中には,この学部でどんなことをどのように学んでいけばよいのか,不安を抱えている人がいるでしょう。私たち教員は,こうした不安を払拭すべく,2002年に『IR』ナビの初版を作成しました。その後,年々の改訂やWeb版への移行を経て,今では,国際関係学の学びのガイドとして,他大学の国際系学部の先生からも高い評価を得ています。
皆さんがこの『IRナビ』という海図を手に、国際関係学の学びの大海へ自由に,そして大胆に漕ぎ出していくことを期待しています。