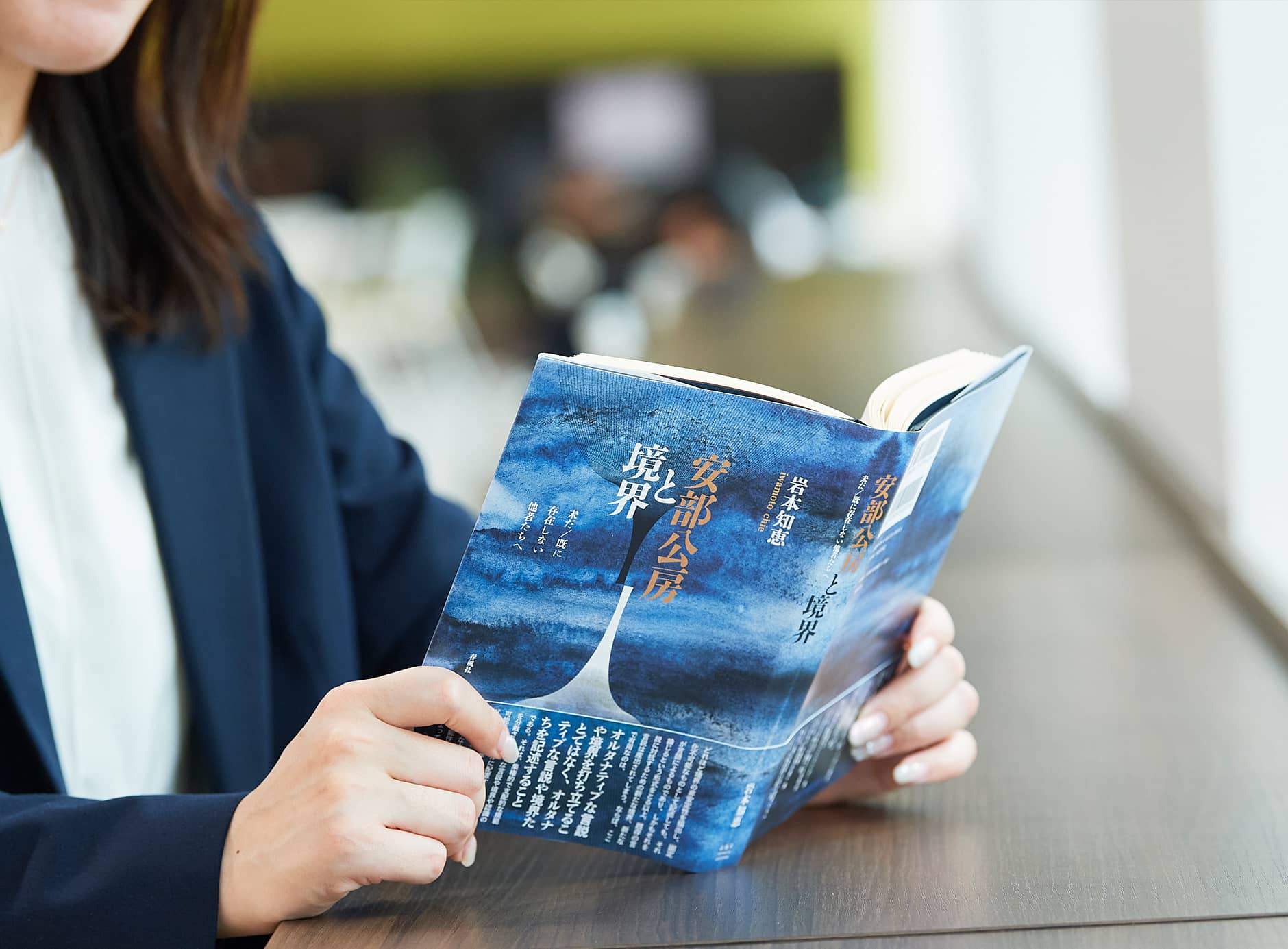研究テーマを教えてください。
岩本:近現代の日本文学を研究しています。とりわけ安部公房の作品に描かれる「排除の構造」と「他者」に着目。作品分析を通して、「排除される他者」や「何者かを排除する構造」について考えています。
これまでの研究を具体的に教えてください。
岩本:一つが『赤い繭』という短編についての論考です。これは主人公の身体が絹糸になり、繭へと変形するという変形譚の一つです。
主人公の「おれ」は「休むためには家がいる」にも関わらず、帰る家がないために休むこともできずに歩き続けています。疲れ果てて公園のベンチで休もうとしても、「こん棒を持った彼」に追い払われてしまいます。そのうち歩き疲れた「おれ」の足は、ほころび、ほぐれて糸になり、最終的には繭へと変形してしまいます。
私が焦点を当てたのは、本作の主人公にとって変形は決して比喩ではなく、自らの身体認識の変容であり、なおかつそれが身体に受ける権力の作用によるものだという点です。「家がない」主人公はいわゆる「浮浪者」ホームレスを表象しています。その「おれ」の身体が、なぜ絹糸になり繭になってしまうのか。作品が書かれた時代背景に目を向けると、見えてくるものがあります。作品が発表されたのは1951年、戦後の深刻な住宅難によって「おれ」のような「浮浪者」が社会問題となっていました。一方で「家」は、戦前の「家制度」や「戸籍法」によって、国家による国民把握の単位として機能していました。つまり「家」に居住しなければ、「国民」として社会福祉を受けることができない。「家」を持たないことは、社会的に共同体や国家から排除された存在になっていると読むことができます。しかし「おれ」は、共同体に帰属していないわけではありません。「こん棒を持った彼」に、法律を盾に追い払われる場面からもわかるように、「おれ」は、共同体の法・ルールに従わされています。つまり「おれ」は、共同体の権力下にいながら周縁化される存在として位置づけられているのです。
そして「おれ」の身体がほぐれて絹糸になっていく描写は、身体が自己ではないものとして排除されていく場面であり、変形は「おれ」の身体が「おれ」でないものへと転換する身体認識の変容のプロセスとして描かれます。この身体認識の変容を通じて、社会構造の中で幾重にも差別され、抑圧される人々の心情を見事に描き出しています。
ただし物語は、排除された人々の敗北というだけでは終わりません。特筆したいのは、「繭」への変形が、皮膚すなわち身体境界の曖昧化であり、「おれ」は流動的な自我や身体認識を獲得したとも読み解ける点です。それはもはや帰るべき家も必要としません。つまり共同体の権力内にいながら周縁化される人々は、法に従うほどままならない存在になり、その果てに法による身体の統制から逃れることに成功した。そうとも読み解きたいと考えています。
他の研究成果についても教えてください。
岩本:安部作品の分析を通して、ジェンダー・セクシャリティの規範や価値観を問い直し、作品を読み替えることも試みています。『他人の顔』の論考もその一つです。
この作品は事故で顔面が「ケロイドの蛭」に覆われてしまった「ぼく」が、他人、特に妻との関係性を修復すべく、本物の顔のように見える仮面を作り、別人になり切って二重生活をするという物語です。「ぼく」が目指す妻との関係修復は、主に性交の達成として捉えられます。
着目したのが、彼が回復したい「他人との通路」を「妻との性交」に結びつけていることです。読み解くと、「ぼく」が「回復」したいのは、実は社会のジェンダー規範によって押し付けられた、「男としてのアイデンティティー」であることが見えてきます。物語を通じて、結局「ぼく」の目論見は失敗します。「ぼく」が目指すべきは、身体に刻まれた「男らしさ」の言説を問い直すことであり、「男性性」から降りる方法を模索することだった。私はこの「ぼく」の失敗に、既存の価値観や規範をもとに、人を「まなざし」で「客体化」することへの抵抗の方途を読み取りたいと考えています。安部公房においては、彼のホモソーシャル的・ミソジニー的な言動が、批判的に捉えられることがあります。しかし少なくとも作品の中には、歴史的な「男性性」を批判的に捉える視線を見出すことができます。その意味で『他人の顔』は、現代のジェンダー論的な観点からも読むことのできる強度を持った作品だと考えています。
今後の展望をお聞かせください。
岩本:安部作品には、変形や、幽霊や人魚、人間が改造されたロボットなど、現実には存在しない非実在物表象がしばしば登場します。安部作品においてこうした非実在物表象が、人を差別し、排除していく構造に抗う意味を持って用いられているのではないか。そうした視点から、安部作品を中心に変形や非実在物表象が描かれる作品が、文学史上でどのような意義を持っているのかを研究したいと考えています。それに加えて、安部作品を対象にジェンダー規範の問い直しにも引き続き取り組んでいくつもりです。