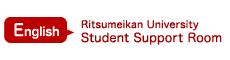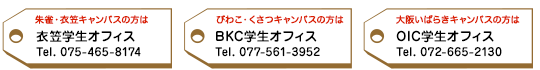2015.03.24
中年留学体験記
行ってみて苦戦したのは、英語のリスニングでした。学校(チューリッヒ)での講義や演習は、スイス人(スイスドイツ語が母国語)が担当することが多かったので、向こうも英語は外国語。イギリス英語でゆっくりした話し方の先生が多かったので、比較的、聴き取りやすかったように思います。しかし、イギリス人やアメリカ人の先生が担当するとき、またアメリカやカナダからの留学生が発言しているときには、なかなか聴き取りにくく、しょんぼり落ち込んでは帰宅していました。それで、同じ学校に通うアメリカ人とイギリス人に個人レッスンをお願いすることにしました。
2人のレッスンを毎週受けて、どんどんリスニング能力はあがりました。個別に向き合って、わからないその瞬間に質問したり、確認できるということがよかったように思います。また2人から欧米の習慣などについて教えてもらったのも、興味深く、楽しい思い出でした。さらにアメリカ人の友人は、日本での滞在経験があり、かつては文化人類学者だった人なので、彼女を通して日本の古い信仰・稲荷信仰について教えてもらったことは、貴重なことでした。
みなさんは語学が得意でしょうか?私はあまり試験勉強では好きではありませんでしたが、コミュニケーションのために英語を学ぶことはとても好きです。大学受験のときに、もっと単語や定型文を覚えておいたらよかったなあと思うこともしばしばですが、留学してみて、いつから学んでも遅くはないなあと感じました。
スイスでは、そこで暮らす日本人の方ともたくさん知り合いになり、みなさんが英語、スイスドイツ語、ドイツ語、フランス語と、たくさんの言葉を話すことにも驚きました。また現地で暮らす日本人は、ほかの国からの移住者に比べて、助け合って暮らしていることにも感激しました。これは、他の国からの留学生にも、うらやましいと言われるほどでした。私自身、たくさんの方に支えてもらったと感じています。
スイスでお世話になった方の中に、みなさんの先輩にあたる方がありますので、最後にご紹介したいと思います。Grüeziという、スイスに暮らす日本人向けの情報誌を年4回発行している、野嶋篤さん、立命館大学文学部で学んだ方です。私はこの情報誌で、日本人向けレクチャーの宣伝をしたり、カウンセリング希望者を募ったりしていました。関心あったら、こちらのサイトをみてください。スイスで暮らす人の様子がわかり、おもしろいですよ。
http://www.intercultura-gruezi.ch/
2015.01.07
理不尽をめぐる冒険
学生さんから薦められた某学園ものの漫画を読んでいて、その校訓が「勤労、協同、理不尽」であることを見つけました。映画化やアニメ化されたので、ご存知の方も多いかと思います。それを初めてみたときは、「学校なのに、勤労、そして、理不尽?」と少し抵抗感を覚えました。しかし、読み進むうちに、ふむふむと不思議に納得する自分がいました。
主人公は中学で挫折し、進学コースから逃げるように、家から遠方の農業高校に入学します。最初は、目的も夢もなく、農家を継ぐなど将来の目標が決まっているクラスメートに、劣等感をいだいていました。酪農科に所属したため、実習で家畜の世話に追われます。動物という命を預かる実習ですから、雨の日も雪の日も朝早くから遅くまで世話にくれるという、農業に縁のなかった主人公からすれば、理不尽な日常―勤労―がいきいきと描かれています。その中で、世話をしているうちに、情が移った家畜を食べることや、友人が、家計を支えるために、夢をあきらめて退学していくなど、理不尽なことにぶつかります。真剣に悩みながら、クラスメートや周りの人々とのかかわり―協同―を通して、徐々に自分にできること、やりたいことをみつけ、成長していく物語です。
残念ながら、理不尽な現状は、抗議したり、もがくことで、やすやすと変えることはできません。しかし、その現状に対する自分の感覚は、変えることができます。上記の実習のように、取り組めば乗り越えられるものもあれば、致し方ないと受け流したり、中には、主人公の友人のように、辛いけれど断念するしかないこともあるでしょう。ただのあきらめではなくて、断念したときは、苦しみや悲しみで一杯かもしれません。でも時間がたつにつれて、交錯する気持ちに折り合いをつけ、この辺が自分の限界と認めることで、そんな自分と和解できるのではないかと思うのです。
実は、大学生のころは、コメントの意味を考えたりはしませんでした。むしろ、若気の至りで、なんだか頼りなげな先生だなとさえ思っていました。それも、私の限界の1つだったのかもしれませんね。いくつになっても、限界を知るプロセスは、しんどいですが、みえてくると、なんだか少し楽になるような気がします。
2014.11.05
カエルの見る世界、「わたし」の見る世界
カエルは目があまりよくないのだそうです。あまり目がよくないというのは、ただぼんやりとしか見えないということではありません。カエルは、動いている小さな点ならよく見えるのですが、同じ点でも、それが静止しているときはよく見えないらしいのです。そして、目の前で小さな点が動くと目ざとくとらえ、すかさず舌を伸ばしてそれを捕らえるのです。そのような目や舌の働きは、ハエのように空中を飛ぶ小さな虫を食するのに適しており、カエルにはとても好都合です。このように、それぞれの動物はそれぞれなりの生活様式に適した形で世界を見ている、というのがその授業のテーマでした。だいぶ昔の話なので、どこまで正確にその授業を思い出せているのかわかりませんが、私の頭の中にはそんなふうに記憶されています。
それまで、どんな動物もだいたい同じように世界を見ているのだろうと何となく考えていたわたしには、カエルの見ている世界がわたしたち人間とはまるっきり違うという話がとても新鮮に感じられ、記憶に残ったのです。
同じころ、先天的に目が不自由だった人が大人になってから手術をし、生まれてはじめてものを見た瞬間の体験をある本で読みました。これもどこまで正確な記憶かわかりませんが、だいたい次のような話だったと思います。
その人にとって、はじめて目にした世界はさまざまな色が無秩序に乱舞しているようなもので、何が何だかわけがわからずとても混乱し、気持ちが悪くなったそうです。そして、その人がちゃんとものを「見る」ことができるようになるまでにはかなり時間がかかったようでした。外界にあるものを意味ある形や色として「見る」ことができるためには、何らかの「枠組み」があらかじめ形成されていなければならないようなのです。
目の見えなかった人がはじめてものを見ることができたときには、「いままで手で触ることしかできなかった○○はこんな色や形をしていたのか」と、感動しながら思うのではないかと考えていたわたしは、その人の体験に新鮮さというよりも衝撃のようなものをおぼえました。その体験は、目があきさえすればものを「見る」ことができるわけではないのだという事実をありありと示していました。
おそらく晴眼者も赤ん坊のときからいろいろな経験を通してだんだんとものを「見る」ことができるようになっていくのでしょう。赤ん坊がものを見てそれが何であるかを理解していく過程には知的な能力の発達という問題もあるので、赤ん坊の経験を目の不自由な人のそれと同列に考えるのは適切ではない面がありますが、いずれにしても、ものを「見る」にはそれを可能にするための「枠組み」が生体の内部に形成されている必要があるわけです。
このように、あらゆる動物は世界を見るための固有の「枠組み」を自分の内部に持っており、その「枠組み」を通して世界を見ていると考えられます。その「枠組み」は視覚的なものだけに関わるのではありません。あらゆる情報はその「枠組み」を通して入力され、処理されると考えられます。「枠組み」にはフィルターやレンズのような性質があり、情報を取捨選択したり屈折させたりするのです。
そのような「枠組み」には、それぞれの動物に固有のものがあるだけではなく、同じ動物でも個体差があって、人間の場合で言えば、人はそれぞれその人なりの「枠組み」を通してものを見、受けとめ、意味づけをしていると考えられます。たとえば、「何ごとにつけ、ものごとを悪い方へ悪い方へ考える」という「枠組み」を持っている人はいろいろなものがネガティブに見え、「何ごとにつけ、ものごとをいい方へ考える」という「枠組み」を持っている人にはいろいろなものがポジティブに見えやすいわけです。
古代ギリシャの哲学者エピクテートスは「人は外部のものによって直接的に心を乱されることはない。それを受けとめる考え方によって心を乱すのである」と言ったとのことで、ものごとの受けとめ方が人の気持ちを左右するということは古くから知られていたようです。何かのことで心配になったり腹が立ったりするときにも、そのような「気持ち」の背景にはものごとをそのように感じるような「受けとめ方」があると考えられます。ですから、受けとめ方を変えることで心配や腹立ちが和らぐこともあるのです。
上で述べたことを別の表現で言えば、わたしたちはみな自分なりの「色眼鏡」を通して世界や自分自身を見ている、ということになります。青みがかった「色眼鏡」を通して見ればものは青っぽく見え、オレンジがかった「色眼鏡」を通して見ればものはオレンジっぽく見えるわけです。いろいろなものがネガティブに見える人は、ものごとがそんな風に見えてしまう「ネガティブ色の眼鏡」をかけている可能性があります。ですから、ときにはふと立ち止まって、「もしかしたら、自分は知らず知らずのうちに色眼鏡を通してものを見ているのではないか」と考えてみるといいかも知れません。
2014.09.04
『我』という漢字の話
数年後の事です。その頃ぼくは臨床心理学を学ぶようになっていたのですが、ある時ふと思い出した漢字がありました。それは『義』という字の成り立ちに出てきた『我』という漢字です。『義』は“羊”と“我”から成り、神に捧げる犠牲の羊をさばき、牲体が神意にかなうものとして義(ただ)しいことを証明している様子を表している、“羊”は神に捧げる犠牲であり、“我”は人がノコギリを引いている姿である云々――。
――なるほど『我』とはノコギリ(を引く様)だったのか。
ぼくにはこの「我(とか自分とか自我とかの言葉で指されるもの)」とは「ノコギリ(刃物でありまた切る作用)」である、というお話は、非常に示唆に富むもののように感じられました。
自分というものは世界から分けられることで初めて成立します。そしてまた世界を切り分けてゆくことで、理解してゆく。世界は一つの事態ではなく、様々な事物に分かれている(分けている)ということを、一つ一つ切り分けてゆくことで、理解し構成してゆく。身で分けて、言葉で分けて・・・。「分かる」とは「分ける」であるという話がありますが、まさに『我』という漢字の成り立ち自体に、そういう作用が含まれていたのです。
そしてまた、より卑近なところで考えてみても、たとえば「自我に目覚める」とか「自我を確立する」とか、そういう作業には多かれ少なかれ、痛みや苦痛を伴います。まるで、保護と同時に干渉もして来る親という存在から自分を切り離すために、痛みをこらえながらギコギコと心のノコギリを引く・・といった場合のように。また友達や周囲から一旦自分を隔離して、サナギみたく閉じこもるということもあるでしょう。
でもそれらは当然の事態、当然の痛みだったのです。「我」とは、ノコギリなのだから。それは数千年前からある意味、宿命づけられ、また、保障もされている――もちろんクリティカルな、取り返しのつかなくなるような、そういうやり方はしてはいけないんだけれども、多少の痛みは仕方がないし、自然なことで、そこでの苦しみは、決して間違ってはいない、義(ただ)しいことなんだ――そんな気がしたのでした。
そして今回、この話を思い出しながら、自戒をこめてこんなことを思いました。真当に苦しんだり傷ついたり傷つけたりすることとは、義しいことである、けれどもそれこそが実は非常に難しい・・。「我」をもっと鍛えなきゃなぁ、と。
2014.7.31
つれづれ映画評 第三回「アンコール!!」
最近、好意や愛情、と言うか、より本心に沿った強い気持ちをあまり口にせず歳を重ねてきてしまったなと思います。
日常の決まり文句のようなものは言えますが、決まり文句は本心と違っても機械的に出せますからね。そうではなく、もっと心からの気持ち、それゆえ口にすると不安や気恥ずかしさでどうにかなりそうな思いは、避けて避けて通っている気がします。
言葉にするともう取り繕いようがなくなって、自分が弱い、無防備な存在のように感じてしまうからでしょうか。
まあ小心者なんですね。けれども「好きです」などと言って生じる恥や恐れの感覚に比べれば小心である方がマシなので、それをずっと続けているという感じです。
今回紹介する作品は、まさにそういう在り方で人生の終盤まで来てしまった男の話です。もうかなりいい歳です。立ち居振る舞いに華などありません。彼自身、華と言うか、他者に対する親密さ、気軽さみたいなものは表に出さないようにしてきたからでしょう。その代わり、彼は行動で自分の思いを表そうとします。奥さんもいい歳で体の自由が利かないのですが、彼女の生活を献身的にフォローします。ただ、言葉の代わりに行動で示そうとする人に共通すると思うのですが、その献身の背後にある肝心の愛情が相手に伝わりきらないのです。とはいえ長年連れ添った老夫婦はそれをもどかしく思うこともなく、当たり前のこととして受け入れています。夫は何でもない振りをして言葉数の少ない生活を続け、妻はそれを許しているという感じです。
物語は、奥さんの病状が悪化し、熱心に通っていたシニア合唱団の活動を続けられなくなるところで転機を迎えます。そこから、歌うどころか世間話すらままならない老人が妻に代わって合唱団に入り、人前で歌い、コンクールに出場することになるのです。この辺ありがちな展開ですが、彼が持つコミュニケーションへの恐れ、好意や優しさを示すことへの抵抗、それを事も無げにこなす合唱団メンバーへの嫌悪と憧れ、そういった要素が無理なく自然に(あるいはかなり計算された巧みさで)描かれているので退屈しません。そうなんだよ、俺もそうなんだよと何度も頷いてしまう説得力があります。
気持ちをうまく伝えられない― まあそんなもんだろと開き直るでもなく、克服しなければと気負うでもない、そういう心地良いバランスがラストまで続きふと気がつくと泣いている、という感動的な作品です。圧巻なのは、中盤、奥さんが夫に向けてシンディ・ローパーの古いヒット曲を歌うところ。「私はあなたの本当の色を知っている」そんなふうに誰かに言ってもらえるなんて、普通ナイですよね。だからこそ主人公である彼は、他者に対して一歩踏み出すことができたのだと大いに納得させられる、そして勇気をもらえる場面なのでした(と言うかめちゃ泣かされました)。
「アンコール!!」 ”Song for Marion”
監督:ポール・A・ウィリアムズ
キャスト:テレンス・スタンプ、ヴァネッサ・レッドグレイブ、ジェマ・アータートン
2014.06.01
大学生の時の不思議な話
僕ははじめに入った大学を途中でやめて、別の大学の心理学科に入り直したのですが、はじめの大学で今後の進路について悩んでいたとき、ある心理学の教授のところに相談に行ったことがあります。何回か通っているうちに、なかなかよく人の話を聴いてくれる先生だ、と思ったので、当面の問題には関係がないようにも思ったのですが、子どもの頃から(ほとんど物心ついた頃から)考えていた、というか心に引っかかっていたあることについて、初めて話をする気になったのです。それまでは家族も含めて、誰にもそのことについて話したことはありませんでした。それで、思い切ってその話をしてみたのですが、先生はいつもの通り、ただフンフンといいながら聴いているだけでした。
いつものように、先生の部屋を出て、自宅への帰り道、僕は「何か変だぞ?」と気づきました。最初はよく分からなかったのですが、あたりを見回してみて気づいたことは、ふだん通り慣れている道から見える風景が、今までと全く違って見えているのです。どうもうまくいえないのですが、なぜか全てが立体的に見え、電柱や木々、遠くの山まで、輪郭がくっきりとして、そこに確かに生き生きと存在している、ということが強く実感されました。まさに、世界の見え方が一変したのです。
何かの出来事をきっかけに世界の見え方が一変するということは、誰でも一度は経験したことがあるのではないでしょうか。恋人ができた・恋人と別れた・大会で優勝した・仕事で大失敗をした・感動的な本に出会った・大きな病気をした・病気から治った、等々。ただ、上に書いた僕の体験の不思議な点は、何も出来事らしい出来事は起きていないということです。そこにあったのはただ、僕が話して、先生が聴いてくれた、それだけでした。いつものことでもあり、その時は特別の感慨などもなかったのです。
カウンセラーになるための訓練の中で、その後も同様の経験を何度かしていますが、これほど劇的だったのは他にありません。人の話を「聴く」というだけのことが、大きな力を持つことがある。そうめったに起きることではないですし、何よりも先生が経験豊かなカウンセラーだったことが大きいのですが、しかし、この「聴く」ということの「力」を身をもって体験したことが、その後、自身がカウンセラーを目指す、大きなきっかけになったことは確かです。
これは何もカウンセリングに限ったことではなく、日常生活の中でも、友人の話、彼氏・彼女の話、サークルの先輩・後輩の話など、「よし、今日は覚悟を決めて、相手の話を30分間ひたすら聴いてみよう」と思うことが、人間関係の変化のきっかけになるかもしれません。
2014.03.03
キャンパスの謎エリア
衣笠キャンパスの学生サポートルームに出勤するときに、いつも通る学内の道があります。ある場所を通過すると、しばしば足元から「ニャー」という声が聞こえ、見ると猫が植え込みの中で寝そべっています。ああ猫がいるな……と思いつつ、遅刻を気にして振り切るように通り過ぎていたものです。
いつからか、その場所に小さな立て看板が置かれるようになりました。猫についての看板です。猫はひっかいたりするので、手を出さないでね、という主旨のかわいい看板でした。
どうやら、あの小さい猫は、人にかまわれるのが嫌みたいです。誰かが実際にかまってみて分かったのでしょうか。でも、人に近づかれたくないのなら、どうして猫は、私が通りがかったときに、あんなにかぼそい声でわざわざ鳴いて、こちらを振り向かせるのでしょう。そして、いつまでたっても大きくならないのはなぜ? この看板を作ったのは一体誰なの?……様々な謎が謎を呼びます。
謎めいた学内には、足を踏み入れたことのないエリアがたくさんあります。たくさんというより、ほとんどの場所が未知のゾーンです。なんといっても私はいつも、広いキャンパス内の決まった場所を通って出勤して、決まった場所に終日いるのですから。
そうして学生サポートルームという決まった場所に一日いると、何人もの学生さんが訪れては帰っていきます。やってくる人たちは、服に葉っぱがついていることもありますし、真冬なのにコートを着ていないこともあります。鞄を持っていない人に「鞄は?」と、あるとき質問したら、「研究室に置いてある」ということでした。コートを着ていなかった人も、学内のどこかに置いてあったのかもしれません。
学生さんたちは、それぞれ大学内のどこかに居場所があったり、慣れた場所があったりするのだろうなと思います。そのほとんどは、私が決して行くことのないエリアです。広いキャンパス内には、専門的な機材や膨大な資料があって、それらは一生私が目にすることのないものです。
そんな中、多くの学生さんたちの語りを通して、少しずつ、未知のキャンパス世界のイメージは私の中に作られてきました。ある建物の中には、きっと近未来みたいなメカがひしめき、また別の建物の中では、世界中の言語が飛び交い……。見ることのない世界はとてもまぶしく思われます。
でも、そもそも、私はどうしていつも同じルートを取って出勤し、昼休みもサポートルームの中にじっとしているのでしょう。外をうろうろしたっていいはずです。大学に勤務し始めてだいぶ経ってから、私は図書館で本を借りられることを知り、前から読みたかったたくさんの小説があるのを発見しました。他にももっと発見できることがあるかもしれません。大きくならない猫の謎もいつか解明されるのでしょうか。
そして最後に一言。悩み事のある学生さんへ。学生サポートルームという未知のエリアに足を踏み入れることから広がる世界があるかもしれません。いつでも扉を開いてくださいね。
2014.02.03
ネタ探しの旅
このホームページのコラムは、だいたい月1回の更新でサポートルームのカウンセラーが順番に書いています(“だいたい”“ほぼ”というゆるさも気に入っています)。2012年度からの試みでもうじき2年が経過しますが、毎月楽しみにしている方もいるかもしれませんね。かくいう私も新作が掲載されるのを心待ちにしている一人です。
それぞれのコラムでは、普段気に留めたことがないようなテーマが扱われたり、興味はあるけど詳しく知る機会のなかったことが織り込まれていたりして好奇心が刺激されます。また、カウンセラーの経験談や日ごろ感じていることが綴られている時には生活の知恵やヒントを頂くこともありますし、出勤日が違うなどあまり話す機会のないカウンセラーたちの考えや意外な一面に触れられるので、毎回楽しく読ませてもらっています。
ところが、これが書くとなるとけっこう難しくて、当番回が近づくたびに途方に暮れています。今回も「何書こう?」と困っていたのですが、自分の引き出しが足りないならば他者のアイディアをお借りしようと、ネタを求めて旅に出ることにしました。「何か案ないですかね?」と尋ねていく人から人への会話の旅です。
2月掲載予定ということで、“2月”で思い浮かべることを同僚や友人に尋ねていくと、予想以上に個性的な反応や連想が返ってきたのでした。『えっ2月?なにかありましたっけ?うーん』と唸る方もいれば、『2月・・大学生なら春休みの過ごし方とかですかね?』とアイディアを下さる方、『節分とか・・でも学生にはあまり馴染みないか・・イースター!?いや、あれは3月か』と行事の類を挙げてくださる方、『いっそ2月から離れたら?』と変化球で返す方、『その頃って実は一番寒いよね』『2月は甥っ子の誕生日だけど』と個人的な連想を述べる方など様々で、その都度「うーん」と共に唸ったり、「あっなるほど、それもありですね」と感嘆したり、「ですよねー」と相槌うったり、ネタ探しのつもりがいつしか甥っ子姪っ子自慢大会になっていたり、とやりとり自体も様々に展開し、思いのほか新鮮な体験となりました。
2月・・。みなさんは何を連想されますか?ネタ探しの旅で得られた反応のように、学生のみなさんにとっても思うところや過ごし方はそれぞれに異なるのではないでしょうか。『何もやることないなー、やりたくないなー』とこもって過ごす、やっとテストが終わったと一息つく、春休みでうきうきする、4月からの生活に向けて期待と不安でソワソワする、就活やバイトに追われる、などなど。なかには、休みの間に心身の不調を少しでも改善したい、困っている問題を整理したいと思う人もいるでしょう。春休みの間もサポートルームは開いています。必要を感じたらどうぞ訪ねてみてください。
2013.12.25
The Road Not Taken
この詩に私が出会ったのは、もう随分前のことですが、なぜかこの詩がとても印象深くて心に染み入るように響いたのを覚えています。ふり返れば、少なくとも今よりはずっとたくさんの分かれ道が眼前に、あるいは少し先に見えていて、ひとつひとつ選んでは進んでいくことが必要な時期だったのだと思います。それでも、当時はそれほど人生の岐路に立たされているというような実感、緊迫感はありませんでした(なので、この詩は今の私を表わしている、などとは思いませんでした)。選択について真剣に迷ったことは何度かありましたが、確かに行く末を見渡そうとしても限界がありましたし、つきつめて確信を持つというのは難しかったように思います。この詩の旅人のように、どっちかと言えばこっち、行ってみて違ったらその時考えればいい、というくらいの、どこか気楽な面もありました。この選択によって人生が大きく変わってしまう・・!とロシアン・ルーレットのような心境でいたら、とても恐ろしくて決断しきれないような気もします。
ああ、あの時、別の道を選んでいたらどうなっていたかなあ・・・と思うこと、誰しも一度ならずあるのではないでしょうか。だからきっと、『私の選んだ道』ではなく、”The Road Not Taken”なのかなと。この詩の最後の箇所で旅人が、この道を選んだことがどれほど大きな違いにつながったかとため息混じりに語っていますが、それは後悔なのでしょうか?それとも、人とは違う険しい道を選んだからこその生き方ができたのだという自負でしょうか?私が感じるのは、その両方でありどちらでもない、としか言いようのない感慨めいたものです。旅人がそのときに選べる道はひとつなのですから。
”The Road Not Taken”は、私のこころの中にも、きっと皆さんのこころの中にも、いくつもあるし、これからも新しくできていくことでしょう。時には、その道に思いを馳せるのも大事なひと時ですよね。来し方をふり返ることは、これからやってくる分かれ道の選択にわずかでも影響を与えうると思うからです。”Where there is a will, there’s a way” というように、分かれ道は外からやってくるとは限りませんから。
この一年、どんな道を旅してきたのか。もうすぐ新たに始まる一年を前に、そんなことを思いながら過ごすのもよいかもしれません。
2013.11.11
カミナリ、石うす、よだかの星-心的リアリティということ
小一のときだったと思います。ある昔話を絵本で読みました。もしかしたら、授業中にテレビで見たのかも知れません。題名もストーリーもよくおぼえていないのですが、それはまわすと塩が出てくる石うすの話で、石うすは最後に海に沈んでしまうのです。でも、その後ずっと(そしていまでも)それは海の底でまわり続けていて、だから海水は塩辛いのだ、という話でした。
海の底に石うすがあって、いまでも塩を出しながらまわり続けているというイメージに、小一のわたしはとてもリアリティを感じました。田舎育ちのわたしにとって石うすは身近な生活道具でもありました。そのこともあってか、いつも見慣れている海の底で本当に石うすがまわっているような気がしたのです。その話は海水が塩辛い理由を説明するものとしても説得力があるように思いました。
中一のとき、国語の教科書に宮沢賢治の『よだかの星』が載っていました。有名な物語なのであらすじは省略しますが、ラストシーンがとても印象的でした。ほかの鳥たちにいじめられたよだかが、星の世界まで行こうと空をどこまでも高くあがっていきます。そして、意識がなくなる直前、自分のからだが燃えて光っているのを見ます。こうしてよだかは青く燃える星になるのですが、物語は次の言葉で終わっていました。
いまでもまだ燃えています。
この言葉を目にしたとき、わたしは夜になったら実際に空を見て確かめてみたい衝動のようなものを覚えました。いまもなおよだかの星は燃え続けている-そのイメージに確かなリアリティを感じたのです。
上で紹介したわたしの体験は、まあ、たあいもないものかも知れません。雲の上でドラム缶を転がす鬼も、海の底で塩を出し続ける石うすも、夜空で青く光るよだかの星も、現実ではありません。でも、当時のわたしにとってそれらはみな実在感に満ちたものだったのです。
物理的には存在していないものに感じる実在感を「心的リアリティ」と言いますが、そんなものを感じるというのは心というものの不思議さです。わたしたちは物理的-客観的な世界と心理的-主観的な世界という二重の世界を生きていると言えるでしょう。心的リアリティは、わたしたちの心を豊かにもし、苦しめもします。わたしたちが喜んだり悲しんだりするのは心理的-主観的な世界においてであり、心的リアリティはわたしたちが「生きている」ことにかかわっています。
ところで、いまのわたしはカミナリの音を聞いても「雲の上で鬼がドラム缶を転がしている」とは思いませんし、「海の底で塩を生み出す石うすがいまもまわり続けている」とは信じていません。でも、夜空のどこかでよだかの星がほんとうに青く燃え続けているのではないか-そんな気がいまでも少しするのです。