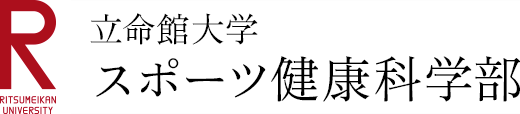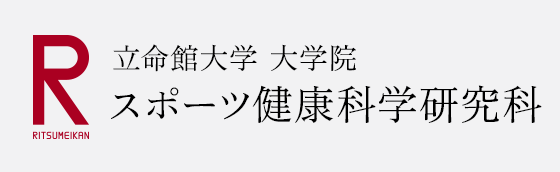2024.10.22 education
ニュース
educationのニュース
2024.07.22 education
日本キッズ食育協会 榊原理加先生にキッズの食育について講義いただきました。
2024.07.22 education
元PwCコンサルティング合同会社マネジャーの宇野カルロス冠章氏をお招きし、特別講演をしていただきました。
2024.07.09 education
スポーツ健康科学セミナーの授業にて、株式会社イシダ 慶野朱音氏をお招きし、特別講義をしていただきました。
2024年6月28日(金)、スポーツ健康科学セミナーの授業にて、株式会社イシダ 総務人事部 人事課 慶野朱音氏をお招きし、特別講義をしていただきました。
まず、イシダについてお話しいただきました。
イシダについて受講生に認知度を確認したところ、ほとんどの学生が今回の講義までイシダのことを知りませんでした。しかし、お話を伺い、イシダは私たちが生活する上で必ずと言ってよいほどお世話になっている会社であるとわかりました。
イシダの機械は、多くの食品を計量し、包装、検査し、商品を梱包しています。つまり、私たちが購入している食品の多くが、イシダの技術によって支えられているということです。
「全ての人々の生活を影ながら支え、食のインフラを支えている」
イシダは、私たちの生活に必要不可欠な存在であることがわかりました。就職活動では、BtoCの大手メーカーなど、名前を知っている企業に目が行きがちですが、イシダのように社会を支えているBtoB企業についても調べてみることで、企業研究の幅が広がると感じました。
次に、受講生からの質問をもとに、現在のお仕事や学生生活についてお話しいただきました。
慶野氏は立命館大学在学中の企業説明会でイシダと出会ったそうです。その時までイシダという企業を知らなかったそうですが、多くの人の生活、さらに社会全体を陰ながら支えているというイシダの活動が、自身のこれまでの経験や考え方と非常に親和性が高かったそうです。自分自身をしっかりと分析した上で、気になる企業の理念などについても調べてみることで、自分に合う企業を見つけることができるのではないかと感じました。
また、まだ知らない企業の説明会にも足を運ぶことで「思いがけない出会い」があるかもしれないと感じました。
普段あまり触れることのできないBtoB企業について知る良い機会になりました。ご講演ありがとうございました。
2024.07.04 education
オープンキャンパス開催!8月3日(土)・8月4日(日)
スポーツ健康科学部のオープンキャンパスは、模擬講義、体験企画、学部紹介、施設公開等を実施します。
是非ご参加いただき、スポーツ健康科学の幅広い領域を体感してください。
教授や先輩学生が企画を多数ご用意してお待ちしています!
上記のスポーツ健康科学部の各プログラムは予約不要ですが、キャンパス来場に事前申込が必要です。
オープンキャンパスサイト(OPEN CAMPUS 2024|立命館大学 入試情報サイト (ritsumei.jp))から「申込フォーム」を選択し、「OPEN CAMPUS 2024 8/3(土)びわこ・くさつキャンパス」または 「OPEN CAMPUS 2024 8/4(日)びわこ・くさつキャンパス」を選択し申し込んで下さい。
Live配信企画やスポーツ健康科学部以外の企画には、プログラムの事前予約が必要なものがありますので、ご注意ください。
立命館大学オープンキャンパス詳細は上記オープンキャンパスサイトをご覧ください。
ご参加をお待ちしております!
2024.06.27 education
2024/06/19 「運動処方特論」の授業において、リオールジム代表取締役の奥松功基先生に「これまでの研究活動や現在の取り組み」についてご講演頂きました。
2024.06.25 education
2024年6月20日(木)開催のGAT Programキャリア形成セミナーに、日本ゴルフ協会の長嶋淳治さんをお招きしました。
2024.06.26 education
オンライン学部説明会のご案内
受験生、保護者の方向けにスポーツ健康科学部で学べること、卒業後の進路、スポーツ健康科学部の特徴を説明します。
■実施日時:
①2024年7月3 日(水)16:30~17:10 (約40分)
(担当:後藤<専門分野・キーワード:トレーニング/栄養/休養(睡眠)>)
②2024年7月10日(水)16:30~17:10(約40分)
(担当:種子田<専門分野・キーワード:スポーツマネジメント/プロスポーツビジネス>)
③2024年7月16日(火)17:00~17:40(約40分)
(担当:真田<専門分野・キーワード:応用健康科学/運動処方>)
※同一内容ですのでご都合の良い日時にご参加下さい。
■参加方法: ZOOMで実施
申込はこちらからお願いします。
皆様のご参加をお待ちしています。
2024.06.21 education
スポーツ生理学の授業に、東京有明医療大学大学院 保健医療学研究科 准教授:髙橋 康輝先生をお招きしました。
2024.06.21 education
スポーツ健康科学セミナーの授業に株式会社講談社 ライツ・メディアビジネス本部 ライツ管理部 副部長の日比政広氏をお招きし、特別講義をしていただきました。
2024.06.18 education
6月6日のスポーツビジネス論に楽天野球団顧客戦略部マーケティング本部部長の谷口健人さんをゲストスピーカーにお迎えしました。
2024.06.06 education
スポーツ健康科学セミナーの授業に三菱UFJアセットマネジメント株式会社 常務執行役員の中川健氏をお招きし、金融の仕事と資産形成について特別講義をしていただきました。
2024.05.29 education
健康運動科学特殊講義に法政大学スポーツ研究センター講師の街勝憲先生に講義を行っていただきました。
2024.05.27 education
スポーツ健康科学セミナーの授業に株式会社オリエンタルランドの馬場俊亮氏をお招きし、特別講義を行いました。
2024.04.24 education
「スポーツ教育学特殊講義」にオーパルオプテックス株式会社所属江口貴彦様に特別講義をしていただきました。
4月23日2限に開講された「スポーツ教育学特殊講義」において、招聘講師として、オーパルオプテックス株式会社所属で、びわこ環境体験学習、カヌースクールなどのアウトドアアクティビティを運営・教育支援をされている江口貴彦様を招いて「野外教育実習計画立案における注意点、リスクとハザード、安全確保」と題し、講義をいただきました。
立命館大学出身でもある江口様より、環境体験学習および、野外教育実習を実施する際に、実施側が留意しておく必要がある事項について、実際のご経験をもとに講義いただきました。本講義では、実際に琵琶湖をフィールドとして、カヌーで横断する野外教育プログラムの立案・準備・実施を、受講生で協働しながら行うこととなっているため、江口氏からのリスク・ハザードの判別について、人的要因、物的要因さらには、自然環境といった環境要因、特に琵琶湖の風、雨、波、気温、水温などの特徴についても説明され、危機管理マニュアル、緊急連絡先と連絡網の作成などの具体的留意点について、具合的事例を紹介いただきながら講義をいただきました。
受講生は、将来スポーツプログラムの指導者として知っておくべき、リスク、ハザードの知識を理解するとともに、野外教育活動の指導における工夫についても併せて江口様に質問をするなど学びを深めていました。
今学期本講義において行う野外教育学習(カヌー琵琶湖横断実習)においても、オーパルオプティクス株式会者様にサポートをいただき、実施されることになっています。
2024.03.25 education
2024年度科目等履修生・聴講生の時間割表を公開しました。春学期の出願期間は3/25(月)9:00~3/27(水)17:00までです。

2024.03.07 education
GATプログラムキャリア形成セミナーを開催!ウィスコンシン大学ラクロス校 からギブリン奈央子先生をお招きしました。
2024.02.01 education
本学総合科学技術研究機構客員協力研究員・塚本敏人先生が、コペンハーゲン大学教授・Niels Secher先生や本学スポーツ健康科学部教授・橋本健志先生らと共同で取り組まれた国際共同研究成果が「Medicine & Science in Sports & Exercise」に原著論文として掲載されました。
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38115226/
運動をすると、様々な臓器から生理活性物質が生成されます(エクサカイン)。各臓器(骨格筋や心臓、脳など)で生成されたエクサカインは血液に放出され、全身を循環することで別の臓器などに供給され、運動による様々な生理変化をもたらします(臓器間のクロストーク)。エクサカインの反応性は、運動の取り組み方(強度や時間、頻度、様式など)によって異なることがあり、それによって生体にもたらす運動の効果も変わってきます。愛情ホルモンとして知られているオキシトシンは、抗うつなどの生理心理的作用だけに留まらず、血管機能や脂質代謝などの改善作用もあることが知られています。本研究は、全身を循環するオキシトシン濃度が高強度インターバル運動によって増加することを明らかにしました。
エクサカインは、静的休息を挟んで運動を反復すると、1回目の運動と2回目の運動でその反応性が異なることがしばしば観察されます。そこで、静的休息を1時間ほど挟んで、強度も時間も同じ高強度インターバル運動を反復し、その運動前後の血中オキシトシン濃度を検証比較しました。その結果、血中オキシトシン濃度は、1回目の高強度インターバル運動と2回目の高強度インターバル運動で同じくらい増加しました。つまり、全身を循環するオキシトシン濃度は、数時間内に実施する運動の回数に影響を受けず、その運動の都度増加することが明らかとなりました。
また、オキシトシンは主に脳で作られることで知られていますが、本研究では、高強度インターバル運動によって増加した血中オキシトシン濃度が、脳のオキシトシン放出と関連しなかったことも報告しました。そのため、高強度インターバル運動によってオキシトシンが増加するメカニズムは明らかでなく、運動時には他の臓器(骨格筋や心臓、精巣など)が主にオキシトシンを分泌している可能性があります。
Circulating plasma oxytocin level is elevated by high-intensity interval exercise in men
Tsukamoto H, Olesen ND, Petersen LG, Suga T, Sørensen H, Nielsen HB, Ogoh S, Secher NH, Hashimoto T.
Medicine & Science in Sports & Exercise. オンライン先行公開中.
doi: 10.1249/MSS.0000000000003360
2024.02.01 education
本学総合科学技術研究機構客員協力研究員・塚本敏人先生が本学部教授・橋本健志先生らと取り組まれた研究成果が「Scientific Reports」に原著論文として掲載されました。
https://www.nature.com/articles/s41598-023-48670-9
運動誘発性疲労の原因など、「乳酸」は悪役として誤認されてきました。近年では一転、運動時の重要なエネルギー基質であり、運動の健康増進効果をもたらすエクサカイン(運動をした時に、様々な臓器が産生する生理活性物質の総称)でもあるといった乳酸の好適な作用(用量依存)が明らかにされています。本研究では、静的休息を挟んで運動を反復したとき、運動によって増加する血中乳酸濃度がどのような影響を受けるのか検証しました。
一般的な運動処方として、1日の中で数回に分けて運動を行うことが推奨されています。しかしながら本研究では、静的休息を挟んで同じ中強度の有酸素性運動を反復した場合、1回目の運動と比較して、2回目の運動によって増加する血中乳酸濃度が低くなることを明らかにしました(研究1)。これは、運動時に供給される乳酸が好適に作用する臓器(脳や心臓など)において、その運動効果を減弱化させる生理現象であるかもしれません。
健康増進のための運動処方として、体重減少などを目的とする有酸素性運動と筋量増加などを目的とするレジスタンス運動の双方の運動様式に取り組むコンカレント運動プログラムがあります。我々は、研究1の知見を受けて、有酸素性運動を実施した後にレジスタンス運動を行うと、レジスタンス運動によって増加する血中乳酸濃度も低くなるのではないかと仮説を立て、その検証を行いました(研究2および3)。もしこの仮説通りであれば、コンカレント運動の実施順序(有酸素性運動→レジスタンス運動、あるいは、レジスタンス運動→有酸素性運動)が、血中乳酸動態に影響すると考えられました。しかしながら、レジスタンス運動前に有酸素性運動を実施してもしなくても、レジスタンス運動によって増加する血中乳酸濃度は同じ水準でした。なお、有酸素性運動前にレジスタンス運動を実施してもしなくても、有酸素性運動によって増加する血中乳酸濃度も同じ水準でした。つまり、コンカレント運動のように、異なる様式の運動に取り組む場合、運動を繰り返しても乳酸産性能には影響しない可能性を明らかにしました。
本研究は、一般的な運動処方の良い効力を少しでも引き出す理論構築のための基礎研究として、重要な意味を持つと考えられます。
The lactate response to a second bout of exercise is not reduced in a concurrent lower-limb exercise program
Tsukamoto H, Suga T, Dora K, Sugimoto T, Tomoo K, Isaka T, Hashimoto T.
Scientific Reports. 13, 21337, 2023.
doi: 10.1038/s41598-023-48670-9
2024.02.13 education
「スポーツ健康科学と未来」の授業にて、株式会社日立製作所Lumada Innovation Hub TokyoのChief DX Producerである浅見真人氏をお招きしました。
まず、日立製作所についてお話しいただきました。日立製作所は、地球環境を守りながら人々が生活できるために、優れた自主技術・製品の開発を通じて社会に貢献することを企業理念に掲げています。現在、「製品の提供」から「サービスの提供」へ、そして「競争」から「協創」へ方針を変更し、社会イノベーションを創出しています。
次に、日立製作所のDX戦略についてお話しいただきました。DXにおいてまず重要なことは、社内の人々が「やばい」と思うことである、とおっしゃっていました。例えば、工場などの現場で働いている人はいつもどおりの作業をこなしているため、ミスをすることが極めて少ない状況にあります。しかし、その中で気づかずに損失を生んでしまったり、さらに効率化できる作業があったりする場合があります。このような状況を打開するためには、トップダウン活動・ボトムアップ活動が極めて重要になってきます。このような活動をすることで、関わる従業員全員が「やばい」を認識することができ、トランスフォーメーションすることが可能となります。また、日立製作所では、デジタルを活用して人間の行動を科学することを行っています。人間の行動を科学するためには、身体・動作、位置・移動、コミュニケーション状態など様々な情報が必要ですが、多くの情報を取ったとしてもそれを活用できるとは限りません。そこで、仮説を立てることが重要になってきます。スポーツ健康科学部に所属する1回生も今後、卒業論文を執筆するにあたって仮説を立てて研究を進めることは極めて重要になってきます。そのため、この考え方は大変勉強になりました。また、このようなDXには人間を中心としたデザイン思考が重要であるともおっしゃっていました。
最後に、well-beingと人間関係についてお話しいただきました。Well-beingとは心身ともに満たされた状態を表す概念です。このような状態を保つためには「三角形の関係性」を構築する必要があるとおっしゃっていました。縦のつながり、横のつながりだけではなく、斜めのつながりを構築することが重要です。斜めのつながりとは、後輩や先輩で、仕事以外のたわいもない話ができる人と関係を構築することです。これは、部活やサークルの活動でも応用することができ、大学生のwell-beingにも応用できるお話であると感じました。ご講演ありがとうございました。