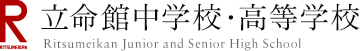国際科学交流と国際共同課題研究
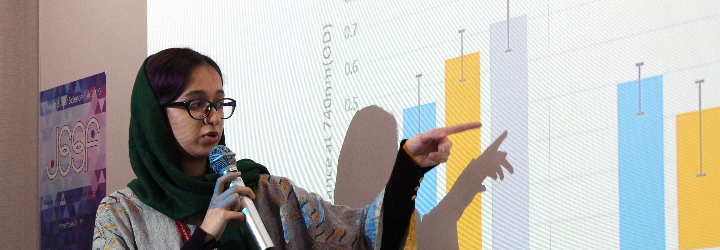
国際科学交流と国際共同課題研究
世界中の様々な国の理数教育重点校と交流するプログラムを積極的に開発してきました。年間10数回、海外科学研修への派遣プログラムを実施しています(2020年度はコロナ禍の影響で海外研修は不開催)。 海外校での授業に参加するプログラム、海外校での特別プログラムによる科学研修、数学や科学の課題解決を競うコンテスト等、様々な形態の科学研修を実施しています。 近年では、国際共同課題研究の取組を重視してきました。次のような力が得られると考えています。
- 幅広い視野と高い視点から、目的や方法を議論する
- 英語でコミュニケーションを取る
- お互いの役割を分担したり、意見の違いを共有したりする調整力
- 将来に向けて、国境を意識しない仲間作り
高校時代の国際科学教育のゴールは「国際共同課題研究の有意義な経験」であると言ってもよいのではないでしょうか。
第5期SSH研究開発においては、このような取り組みが日本中の高校生達に提供できる環境づくりを目指しています。
2019年度に立命館高校で実施した国際共同課題研究は以下の通りです。
| 相手校 | 国/地域 | 研究テーマ | 実施枠 |
|---|---|---|---|
| Korea Science Academy KAIST | 韓国 | 大気の暑さによる太陽スペクトルへの影響 | 基礎枠 |
| Mahidol Wittayanusorn School | タイ | 稲の塩害 | 基礎枠 |
| Mahidol Wittayanusorn School | タイ | 緑茶の抗酸化作用 | 基礎枠 |
| National Junior College | シンガポール | ヒートアイランド | 基礎枠 |
| National Junior College | シンガポール | 土壌と植物を用いた水質浄化 | 基礎枠 |
| Shawnigan Lake School | カナダ | カナダと日本における外来種と在来種の水草の比較 | 重点枠 |
| Chitralada School | タイ | 比色定量法によるアブラナ科の植物のイソチオシアネート含有量の比較 | 重点枠 |
| 高雄高級中学 | 台湾 | プラナリアの再生とその可能性 | 重点枠 |