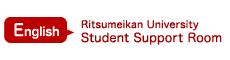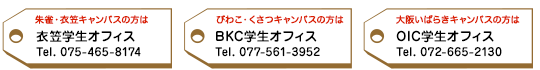2019.09.03
旅に出れば自分は見つかるか
みなさんは旅が好きですか?私は重度の出不精なので、旅ほど億劫なことはありません。それでもこの仕事をしていると研修等で遠出を強いられたり、会いたい知人が遠方に移住してしまったり、重い腰を上げざるを得ないこともあるのです。まあ一旦出かけてしまえば、そこまで嫌でもなかったりもするんですが。とくにひとりだと気楽ですしね。
旅、しかもひとり旅というのは、よく「自分探し」とセットで語られ、そこでは非日常に身をおいて、ひとり心静かに己を見つめることの効用がうたわれているように思います。
しかし、旅に出れば本当に自分は見つかるのでしょうか?
私の最近のひとり旅はアラスカでしたが、この極北の地域にまでも世界の均質化の波は押し寄せています。もちろん日本では考えられない風景(夜23時でも外はまだ明るいとか)や食べ物(トナカイ肉のホットドッグとか)も目にしましたが、都市部には大手チェーンの店舗が並び、アプリひとつでUberがさっと迎えに来てくれ、片田舎のスーパーマーケットにも日本メーカーのしょうゆが減塩バージョンまで並んでいます。そして大自然のなかで静かに己と対話をしようにも、一般旅行者が安全に足を踏み入れられるのはほんの一部であり、そこにはカップルや観光客グループが笑いさざめく、よくある日常が流れているのです。
「自分探しの旅」を求めるなら、もっとワイルドを追求せねばならないのか??バックパッカーとか?星野道夫とか?・・・そんなのは、動物には怖くて近寄れず、海外に行くときには各地のトイレ事情をネットでチェックするような性格の私にはとうてい無理なのです。
それでもひとりで滞在していると、同志と誤解されるのか本物のソロ・トラベラーに話しかけられてなんとなく地ビールを飲み交わしてみたり。また行く先々では、私の知人も含め米国内外から様々なきっかけでこの地に移住してきて、人生のある一時期をここで過ごし、またいずれ別の地に移り住んでいくのであろう人たちにもいろいろ遭遇しました。そして、地球の片隅に時を同じくして居合わせたという縁に、お互い「なぜ今ここにいるの?これからどこに行くの?」を問いかけ合う(その場で直接口に出す場合もあれば、心の中でそっとつぶやいたり、後からひとり考え続けるだけのこともあるのですが)なかで、私のなかの過去の様々な経験や信念、理想や願望といったものがいくつも撚り合わされていき、ああアラスカに自分がいるというこの出来事は、何も突飛なことではなくて、“これまでの自分”と“未来の自分”をつなぐ一条の線上に起きたことなんだなあ・・・としみじみ実感するのです。
いやー、旅っていいですね。あれ?そんな話でしたっけ。もとい、これが「自分探し」ですね!きっと。つまり、非日常に身を置くことそれ自体というよりも、「自分の芯に響くような問いを投げかけられる」チャンスが旅には潜在しているということが鍵で、またそのチャンスは「他者と語る」ことで手元に飛び込んできやすいようです。
そしてそのようなことは、私たちが学生さんのお話をうかがう時に感じることと同じです。学生の皆さんは、研究で行き詰まったとか、指導教員との関係が苦しいとか、友達や恋人との関係で悩んでいるとか、眠れないとか心の不調を感じるとか、さまざまな主訴でサポートルームにやって来られます。現在抱えているそれらの問題自体はとてもつらいことですが、それらは多くの場合、唐突に勃発したものではなく、あなたのこれまでと、ここから先のあなたをつなぐ一条の線上に起きたものなのです。そしてカウンセリングでは、当初の主訴のことだけに絞ってというよりは、それも含めた「丸ごとのあなた」の様々なことを語ってもらうことが多いです。そのやりとりのなかで、カウンセラーという他者の発する問いがふとあなたの芯に響くことがあり、それに伴って当初の主訴の見え方・感じ方が変わってきたり、糸口がおのずと見つかったりするようです。
皆さんのそんな自分さがしの旅に同伴させてもらうことを生業にしているということと、出不精の私が旅を嫌いになれない(というか結構好きなのかもしれない)理由とは、どこかつながっているのかもしれません。
2019.07.31
こころの時代
暑い季節です。外に出るのも気合が要ります。外での用事を済ませて家に戻ったら、ぐったりとなります。しなければならないことがたくさんあるのは分かっているのに、もう少し休みたい、もう少しだらだらしたい、と思っているうちに時間は過ぎていきます。そして随分と時間が経ってから、あぁ何もできなかった、と後悔しながら立ち上がる、そんな日々です。
平成の約30年は、いろいろな視点からまとめることができますが、「こころ」が注目された時代でもありました。それは、たびたび起きた自然災害や事故によってPTSD(心的外傷後ストレス障害)を患った方が多かったことや、経済の低迷による精神疾患の増加、価値観が多様化する中で様々な葛藤や軋轢が生じたこととも無縁ではありません。平成に生まれ、平成に育った学生の方々はご存じないかもしれませんが、それ以前の昭和の頃まで、ひとの「こころ」はあまり顧みてこられなかったのです。
ひとの「こころ」が注目されたのは、社会にとって大きな変化でした。「こころ」のパターンや傾向を捉えることで、ひとの複雑な行動を理解し、社会に活かそうという流れが大きくなりました。また、何かがうまくいかなくなって行き詰まり、困った時、それを「こころ」の在りようの行き詰まりだと捉え、それを扱うことで解決しよう、という流れができました。後者の流れの中で、悩みや様々な症状を専門家に相談して解決・改善を目指す、という選択肢が現れました。
しかしその反面、時に困ったことも生じます。本来は「こころ」の在りようが理由ではないことも、「こころ」の問題だ、とされることも出てきたように思います。カウンセラーは時々、相談に来られた方に生活リズムや食生活、課題の量等を尋ねることがあります。それは「こころ」の問題だけではなく、そもそも身体的、環境的な問題がないかを知りたいためです。「気分がふさいで仕方がない、うつかもしれない」という相談で来られ、病院で検査をしたら、身体疾患が明らかになったこともありました。「バイト先でうまく仕事をこなせない、自分の性格の問題だと言われた」という相談をよくよく聞くと、そもそも仕事の量がとても多い上に、それをサポートし合うシステムがバイト先にない、ということもありました。「こころ」の在りようだけが行き詰まりの理由になるのではなく、身体的な不調や社会が要求するものの矛盾、組織やシステムの不備といったものも、不調や症状の大きな要因となるのです。
(だからと言って身体的、環境的な問題と「こころ」の行き詰まりは関係ない、悩みや症状に対して専門家の援助は必要ない、と言いたいわけではありません。それでも社会で生きていくためにどうしたいか、どうなりたいかを伺った上で、解決のお手伝いを致します。)
つまり何が言いたいのかというと、こんなに暑い日は身体的な疲労が大きく、だるい気分になるのは私にやる気がないのではなく自然なことなので、身体を労わることを大切に、アイスでも食べながらぼちぼちやっていきましょう。
2019.06.07
ある舞台を観て思うこと
この場面を観ていて、犬が見聞きしている世界について考えていました。確かに人間の言葉をすべて分かっているわけではないかもしれません。舞台と同じように人間が耳から聞くのとは違う音として聞いているのでしょうか。それとも、理解できないだけで同じように聞こえているのでしょうか。犬は鼻の感度が人間よりずっといいそうですから、もしかしたら耳の聞こえ方も違っているのでしょうか。
カウンセリングでさまざまな人と会っていると、人の感覚の違いに気づくことがあります。同じ世界に生きていても、見ている世界が違う、感じている感覚が違うと。たとえば食感。どうしても肉を食べると、その食感が気持ち悪いと感じてしまい、子どもの時から出されたものを食べるのが苦痛だったという人がいます。肉好きな私からすると理解が難しいところです。実際、感覚から来る苦痛は、他人に理解してもらいづらく、好き嫌いとして、幼いころに矯正の対象となることが多かったようです。無理やり食べるように強いられる経験は、自分の感覚を否定されるようなつらい体験になることもあります。他にも、音にとても敏感すぎて細かな音まで拾ってしまう耳を持っている人もいます。外国語のリスニング能力が高かったり、音楽も一度聞くだけで正確に覚えられたり、場面によっては、才能として活かされる能力でも、大講義室など賑やかな人の多い場所では、授業を受けることに支障をきたすような場合もあります。これもまた、賑やかな場所でも、話している相手の声を聞くことを難なく出来ている人には、理解しがたい感覚かもしれません。
自分が感じている世界を、皆が同じように感じている訳ではないということを考えると、不思議な感覚に囚われることがあります。一方で、演劇や小説や映画などはそういった自分には感じ取れない世界を疑似体験できる面白さがあるように思います。犬と人のコミュニケーションとまでは行かなくても、誰かと話していてコミュニケーションがずれる感じや、うまく行かなさを感じることはあるかもしれません。相手の感覚は自分のそれとは違うかもしれない、という想像力が、相手を理解する上では大切なのかもしれないと舞台を見て感じたカウンセラーでした。
2019.06.04
音楽と心
みなさんの心の支えとなるものは、どんなものがありますか。読書や映画、詩や文学あるいは、スポーツ・・・そこにきっと個性が現れますよね。私にとっては音楽と言えそうです。私が幼少の頃は、音楽と言えば、テレビ、ビデオテープやカセットテープが主流で、CDを初めて手にしたときは、虹色の輝きに感激した記憶があります。一枚のCDを大切に味わい、一つの流行歌をみんなが共有している、そんな古き良き時代でした。今や音楽はデジタル化して大量消費時代となり大きく変化しましたが、人の心を惹きつけ、揺さぶる音楽の力というのは人が生きる世界がある以上、永遠であるように思います。
ところで、みなさんは、このときにこんな音楽にはまった!という経験はありませんか。私自身は、学生時代長らくオーケストラをしていたのでクラシック音楽に触れることが多かったのですが、時折ふと何かの音楽を耳にすることをきっかけに、昔の歌謡曲やJPOP、洋楽やクラシックの名曲などに一時的にはまる現象が起こります。
振り返ってみると、これは心の中で何かの喪失体験が起こっているときが多いのです。これまでの自分では立ち行かなくなって行き詰まりを感じているとき、自分の中にある基盤のようなものが揺らいでいるとき、過去の自分を脱ぎ捨てる必要が出てきます。その体験を心の中で統合し、新しい世界や自分に開かれようとしているときです。例えば、失恋や何かの挫折・・・それらもその中に入るかもしれません。そんなときに、偶然に出会った音楽にそのときの自分の心が共鳴し、活力を得ることができます。
社会人になって数年したあるとき、学生時代に親しんだベートーベンの第九の4楽章に心を奪われ、様々な演奏を聞き、あるいは聞いていない時にもふとした瞬間に心に鳴り響いていたことがありました。ちなみに、第九の4楽章の歌詞の冒頭の「おお友よ、このような旋律ではない もっと心地よいものを歌おうではないか そしてもっと喜びに満ちたものを」はベートーベンが作詞したと言われています。有名な話ですが、第九を作曲する時すでにベートーベンは聴力を失っており、当時としてはかなり型破りな交響曲を作曲しました。4楽章でこれまで美しく奏でられていた旋律が全て否定されるという驚く発想を用い、ベートーベンの苦悩、絶望・・・それらを突き破って希望、歓喜への希求を爆発させた、そんな名曲です。こういう曲の背景もあったのかもしれません。きっと、このときの私は、社会の厳しさの中で思うように力を発揮できないもどかしさや無力を感じながら、学生時代までの自分を脱ぎ捨てて、新たな自分像を構築せねばならない事態が起こっていたのでしょう。その心の中の大地震のような衝撃を受け止めてくれたのが音楽でした。
こんな風に、私にとっては、特に人生の転機において音楽は不可欠なもののようです。 様々な心の痛みや不安や絶望や・・・そういうものが音楽に抱えられて、そしてまた再構築されていく、そういうことがあるような気がします。音楽は、前に踏み出す力を与えてくれるものであると実感します。
何かに支えられて、心の痛みや絶望の中からまた歩き出すことができれば、それは幸運です。しかし、それだけではなかなか立ち行かない事態が起きることもあります。そんなときは、どうかサポートルームに足を運び、カウンセラーにあなたのお話をそっとお聞かせください。
2019.05.08
元号の変わり目~新しい時代の始まりにもの思う~
「令和」の時代が始まりました。
時代をまたいだだけでなく、その長さにおいても歴史的となった今年のゴールデンウィーク10連休。学生の皆さんは10連休とはいかなかったとは思いますが、どのような体験でしたでしょうか。TVをつければ、年末年始のカウントダウンに似た光景が映し出され、どこからともなく鐘の音が聞こえてきそうな深夜。しかしどこか新年を迎える雰囲気とは違う、昭和から平成に移り変わった時代の香りとも違う、なんとも形容しがたい初めての感覚を味わいました。平成生まれの皆さんの目には、この時代の変わり目はどのように映ったでしょう。
私にとっては休み前に仲間と誓い合った平成最後の大掃除が主なタスクでした。また、気軽な気持ちで始めた睡眠アプリに思いのほかハマったGWでした。新しいアプリや、便利なアプリは学生の皆さんの方が詳しいですね。実際学生さんから教えてもらうことも多いですし、学生さんから教えてもらったという同僚から教えてもらったりもします。今回お話しする睡眠アプリを知ったのもそのパターンでした。「朝、比較的すっきり起床ができるよ」という同僚からの勧めにより、私も早速ダウンロードをしてみました。
ご存知の方も多いと思いますが、枕元にスマホを置いておくことで、寝返りや振動をもとに睡眠の変化、サイクルを計測するというもの。ノンレム睡眠(浅い眠り)のところで目覚ましが機能し、起きやすくなるらしいのです。「寝ている時に枕元にスマホを置いて、電磁波とか大丈夫なんですか?」とか、「本当にちゃんと測れているんですか?」とか、「入眠までの時間をどうやって測っているんですか?」とか、担当者を質問攻めにしたくなる気持ちを抑え、使いだしてみると、なんだかんだ結構面白い。連休に入ったので早起きする必要がないことから、当初の目的は吹き飛び、寝言録音機能なるものに興味津々となりました。誰もが過去に、家族や友人から「昨日寝言で○○って言ってた」と勝手に大爆笑されたことは一度や二度ではないはず。聞いている方は誰かに言いたくなるくらい面白いのですが、当の本人は何も覚えてないものです。なので、「こんな手軽に自分の寝言をこっそり自分で聞ける時代が来たなんて!」と、感慨深い思いに浸っていました。一人遊びが加速するといえるのかもしれないけれど…。
そんな私は、寝言と夢との関連に興味がひかれているのでした。というのも、私自身は夢を記録する習慣があるのですが、このところ、記録しようと思いつつ、起きた瞬間に忘れていることが続いているのです。この「覚えていたくない、覚えていられない」という行為の無意識的な背景はいろいろあるのですが、ここではそれはさておき。寝言が夢を思い出すことに一役買ってくれそうだという思いと、また更に言えば、寝言と夢の関連から何か新しい発見があるのではないかという淡い期待があったのです。
さて、寝言録音機能とはどのようなものかというと、1回につき、短いものは8秒程で、長いものは40秒程の音が録音されています。多い時で、一晩で18回もの寝言(らしき音)が記録されています。最近はもっぱらこれらの録音にじっと耳を澄ますことが、起床後の密かな楽しみとなっているのです。
しかし、蓋を開けてみると、この機能で録音されている音は「ザザザザ、ガタガタ、ジジジ、バサバサ」という物音ばかり。時折、いびきと寝息の見事なハーモニーが奏でられています。これらの物音に耳を澄ませて聞き入り、寝ている自分自身に何が起こっているのかと想像を膨らますのもまた面白いのです。寝ることが楽しみになってきたアプリ使用開始4日目、ついに見事な寝言が録音されていました。
「うっ、うっ。○○としました!むす、むすされる…。あれですか…」
なんとも興味をそそる言葉。最近のスマホは音を拾う性能がかなり良いようで、相方の寝言をしっかり録音してくれていたのでした。寝ていても仕事をしている様子の、さらにその仕事が無視されているらしい相方への同情心が芽生えつつ、ここでまた疑問が湧いてしまいます。「私の睡眠だけではなく、相方の睡眠も計測しているのではないですか?」と。結局のところ、この1週間でちゃんと録音されていた寝言はこれ1つだけでした。
睡眠サイクルとは、レム睡眠とノンレム睡眠がきれいな波型になっているものと思い込んでいたのですが、浅い睡眠しか持ててない日もあったり、90分サイクルといえる日はほとんどなかったりしていました。これはつまり計測がきちんとできていないだけのことなのか、はたまた私の睡眠はかなり乱れているということが科学の進歩により初めて明らかになったということなのか、新学期で心と身体がざわついているだけなのか…。新しい時代の幕開けは、睡眠記録の謎に思いを馳せるところから始まりました。久しぶりに未知なるものに目を向ける体験をした高揚感といい表すこともできるのかもしれません。こうして文字に書いてみて改めて思いますが、「自分の寝言を聞くことができるって、やっぱり凄いことではないですか?!」。ただ、その日はいつ来るのかわかりません。寝言によって夢への手がかりがつかめる日は、寝言と夢に関する論文が書ける日は、一体いつ来るのだろうかと遠くを見ながら考えていたら、あっという間に連休は終わってしまいました。探求の日々はしばらく続くと思われます。
結局のところ何が言いたいかというと、いろいろな方法で客観的に自分を知ることができるのだなという驚きと、今まで見えなかったものに目が開かれることの喜び。そして、「夢に関心がある方、ぜひカウンセリングルームでお話ししてみませんか?」というお誘いでした。
2019.04.01
”Finding who you are”「自分との出会い」
Hello. I am a counsellor from the Student Support Room. Welcome to Ritsumeikan University!
For those who have just started college life this may be a very exciting time, as almost everything is new, or this may be a very stressful time, as nothing is familiar. If you are an international student, the excitement and anxiety can be doubled.
My first experience staying in a foreign country was a 3-month ESL program in the US. It was just a fun time with no pressure – learning English phrases in both classroom and social settings. The second and third times were different. I was majoring in Psychology, and it required much more work. Not only the theories I had to grasp, but also counselling skills in English I had to acquire, which was a struggle for me. It seems like when your vocabulary is limited, so is your intelligence. While other Canadian students were addressing their ideas and thoughts, and demonstrating wonderful skills of counselling in practicum, I felt so idiotic, and thought “Why on earth did I come here? What am I doing here all by myself?”
Thanks to the teachers, friends, and clients who continuously came to my counselling sessions, I started to realize “who I am.” Once I accepted who I was, although I was still struggling, I could appreciate what I had. If you would like to get the most out of their time here in Japan, and at Ritsumeikan University, please visit us at the Student Support Room. We are here to help you find “who you really are.”
皆さん、こんにちは。学生サポートルームのカウンセラーです。立命館大学にようこそ!
学生生活を始めたばかりの方にとっては、多くのことが新鮮で期待で胸がいっぱいかもしれません。一方で、初めてのことばかりでとまどっている方もいるかもしれません。留学生の皆さんは、わくわく感も不安も、日本人学生より多いのではないかと想像します。
私にとっての留学体験は、3ヶ月の語学留学が最初でした。このときは、ただ英語を身につけることだけが目的で、何のプレッシャーもない、楽しい期間でした。でも2度目、3度目は正規生として心理学を学んでいたこともあり、勉強はなかなか大変でした。机上の理論だけではなく、英語でカウンセリングの実習をしなければならず、苦戦しました。語彙が限られると、知性も限られてしまうように思えてきたものです。他のカナダ人学生が、自分の考えを積極的に発言したり、カウンセリングスキルを発揮したりしているのを見ると、自分が無能な気さえして、「なぜ留学なんてしたんだろう」と考えたものです。
しかし、先生や友人、そしてカウンセリングに来てくれるクライエントのおかげで、徐々に「自分らしさ」に気づくことができるようになりました。そしてその「自分らしさ」が受け入れられるようになると、まだまだ苦労はあったものの、何とかそれを生かしてのカウンセリングができるようになりました。日本での、そして立命館大学での学生生活をより充実させたいと思っている皆さん、どうぞ学生サポートルームにいらしてください。サポートルームが皆さんの「自分らしさ」発見の一助になれば幸いです。
学生サポートルームカウンセラー
2019.03.11
時間についてのいろいろ
もう3月・・別れと出会いの季節。一年の節目であり、一つの年が終ってまた新しい年がはじめる季節ですね・・。春夏秋冬と季節はめぐります。春には鮮やかに花々が色づき、まぶしく強い光の夏、秋風が吹いたと思ったら、雪がちらついて・・。そんなふうに、毎年同じように、季節は過ぎていきます。
そんな季節と同じように、自分は単に同じことを繰りかえしているだけなのではないかといった嘆きに、時々出会うことがあります。何かに出会い心ときめいて、でもしばらく経つとときめきも色褪せて、いつの間にか気持がうせて・・。あるいは、いつも同じようなことに傷ついて、同じような対応をして失敗して、同じような反省をして・・。そんな風に、気がつくと同じことを繰りかえしてばかりで全く成長していない、と。
かくいう私も、自分は小さいころと同じような心の物語を、いまだに繰りかえしながら生きているなぁ、とか感じることもあります。・・人生そんなものかもしれません。
でも同じようなことを繰りかえしているように見えて、それは単なる同じ円なのではなく、螺旋なんじゃないかと思います。真上から見ると同じ円周の周りをぐるぐると回っているだけ・・に見えて、実は横から見てみると1周回るたびに階を一段昇っている螺旋階段・・。そうやって見てみると励みになる気もします。
連想が少し飛びますが、以前ある本(出典忘れました、すみません)でこんな風に時間を直線ではなく円環として捉える考え方に出会いました(いやむしろ、私たち日本人にとっては、仏教の輪廻転生の考え方や、60年で一回りする十干十二支の方になじみが深く、時間は当然円環的なもの、なのかもしれませんが・・)。
時間を直線と捉えると、未来はまだ見ぬもの、未規定なものです。ゆえにまだ見ぬ未来に対する期待や希望があり、目標を設定し、その夢を実現して行くという生き方が自然なものとなります。その本ではこのような世界観や人生観を能動的能動と表現していました。
対照的に、時間を円環として考えると、未来とは過去にすでに起こったことの繰り返しであると捉えられます。ニーチェでいうところの永劫回帰です。そこには、時間は同じことの繰り返しでしかないという諦念を超えて、終わりのない円環とは即ちいつの時点もスタートラインにできるのだという実存的契機があります(直線的時間・・キリスト教的時間には始まりと終りがあります)。そこに立ち現れるのは、受動的能動という世界観、人生観です。そこでは、未来に向かって何かを実現していくということよりも、自分に訪れるものを引き受けて行くということが生き方となります。わかりやすい例としては、子どもを授かることや授かった子どもを育てていく行為があげられます。性別をはじめとしてどのような子どもを授かることになるか、能動的に選択することなど出来ませんが、人は授かった子どもを引き受け育てていきます。
そんな風に考えると、実は既に私たちは様々なものを、引き受けて生きているし、これからも様々なものが訪れて、それを引き受けていかないといけないということでしょう。けれども、時に、引き受けるには大きすぎる出来事、背負うには重すぎる宿命といったものも、ありますね。カウンセラーとはそういう辛さ、苦しさに対して、なにもできないかもしれないけど寄り添ってそばにいる、そんな側面もあるような気がします。
螺旋、直線、円環。どれも正しいような気もしますし、その時々に自分にフィットする時間観から生きるヒントを得られればと思います。もうすぐ年号が変わって一つの時代が終わります。新しい時代も皆さんにとっていい時代でありますように。
学生サポートルームカウンセラー
2019.02.14
苦手
2018年度の秋期試験期間も終わり、いかがお過ごしですか?
今回は「苦手なもの」について自分の経験を交えながら書いていこうと思います。
「苦手なもの」と聞いて、何を思い浮かべますか?私は真っ先に「椎茸」が浮かびます。何が苦手かというと、とにかくあの匂いと食感、そして味です。椎茸が好きな人からすると、「出汁にしみ込んだあの匂いと味がおいしいのに」とよく言われますが、「ちょっと何言ってるかよく分かんない」と常々思っています。家や給食、店で椎茸の入った料理が出たときは、「椎茸の匂いや味で終わりたくない」と真っ先に椎茸を口に詰め込んで、ほぼ噛まずに飲み込むことで対処(?)してきました。それまで食す機会もそこそこあった椎茸ですが、大学進学を機に一人暮らしをするようになるとほぼ口にすることがなくなりました。こうして椎茸は私の中で苦手なもののトップに君臨し続けていますが、これは椎茸にまつわる私自身が作り出したネガティヴなイメージや感情によって、苦手意識がますます大きくなった結果だということも分かっています。
ちなみに、小学4年生の姪も小さい頃から椎茸が苦手でした。どんな料理にしても、小さく切って混ぜ込んでも姪の椎茸センサーは抜群で、私の姉を困らせていました。そんな姪と去年の夏、実家に帰省した時期が重なり1年ぶりに会いました。夏に実家に帰省した際は、姉夫婦と一緒にBBQをすることが多いのですが、その時にも椎茸は私の気持ちも知らず、網の上で踊るように焼かれていました。なぜ椎茸を用意したのかと恨めしそうに思っていましたが、私と姪以外の家族や親戚は椎茸を割と好むので致し方ないと割り切り、椎茸の存在を見て見ぬフリしようと思っていました。と、その瞬間、かさが大きく開いた椎茸に姪が箸を伸ばし、私の知っている姪とはまるで別人かのようにおいしそうに食べているのです。勝手に椎茸苦手同盟を結んでいたつもりだった私は、「え?何で?」と思わず口にしていました。姪いわく、一昨年の秋に当時3歳になる別の姉の姪がさも当然のように椎茸を食べているのを見て、「年下なのに食べてる」「私の方がお姉ちゃんだもん」と思って食べてみたら、それまでの味も匂いも食感も違い、かつ姉をはじめ周りの人に大いに評価されたことを機に、食べられるようになったというのです。
姪の体験には、負けたくない、悔しい、恥ずかしいといった気持ちの他に、「自分も食べられるはず」という姪自身の有能感という肯定的な感情も含まれていたのでしょう。また、その肯定的な感情を受け止め、評価してくれる周りの人の存在も大きかったのでしょう。
アレルギーや病気でなければ、「苦手なもの」はあくまで自分が作り出し、半ば無駄に苦手だと思い続けることで本来自分が持っている肯定的な力をも抑えこんでしまっているということを、30歳近く年の離れた姪から教わった昨夏の出来事でした。
学生サポートルームカウンセラー
2019.01.08
はじめて出会う冬の世界・・・
“はじめて出会う冬の世界”ということを考えた時に、真っ先に『ムーミン谷の冬』という本を思い出したので、今日はこの本を紹介したいと思います。この本は、ある年ムーミンひとりだけが冬眠から目覚めてしまう・・・というところから物語りが始まります。起きているものは誰もいない、ムーミンパパやママを起こしてもだれも起きないのです。“世界じゅうが、どこかへ行っちゃった”とムーミンは急に怖くなってとても寂しくなってしまいます。ムーミンたちは毎年11月から4月頃まで冬眠をします。そう、ムーミンたちは未だ冬というものがどんなものかを知らないのです。幼少期、家族が誰も起きない家の中で、雪景色を前にしたときに不安になった気持ちと、ムーミンが急に恐くなって寂しくなった気持ちは、重なりあう部分がありました。冬の寒さと、雪という全てを覆いつくしてしまう感じになんだか圧倒されてしまう、そんなイメージがあります。
再び眠りにつけなくなったムーミンは、勇気を振り絞って外に出るのですが、冬というものが大嫌いになって、出会う生きものたちのことも“僕の気持ちはちっとも通じない“と拒絶してしまいます。ですが、水あび古屋で出会ったおしゃまさんに「雪ってつめたいと思うでしょ。だけど、雪小屋をこしらえてすむと、ずいぶんあったかいのよ。雪って白いと思うでしょ。ところが、ときにはピンク色に見えるし、また青い色になるときもあるわ。どんなものよりやわらかいかと思うと、石よりもかたくなるしさ、なにもかもたしかじゃないのね。」と、少し見方を変えるだけで世界が違って見えてくるんだよということを教えてもらいます。そこからムーミンは冬の生きものたちと出会い、助けたり助けられたりしながら、いつもとは違う冬の世界を体験していくのです。
ムーミンは知らなかった世界や試練を経験し、ついに”一年中を知っている最初のムーミントロールだぞ、ぼくは。”とまで言えるような自信をつけていき、強くなっていきます。ですが、それまでにムーミンも気持ちがしょげてしまって、たまに愚痴などもいってしまうのです。そんな時、またおしゃまさんから、「どんなことでも、自分で見つけださなきゃいけないものよ。そうして、自分ひとりで、それをのりこえるんだわ。」という言葉をかけてもらい、ムーミンはムーミン谷の冬について学んでいくのです。おしゃまさんの言葉は時に痛烈に心に響きます。時に厳しいことも言いますが、ムーミンが風邪をひきそうになったときには「あたたかいジュースよ。あたたかいものをのむのを、忘れないでね。」と労ってくれる優しい女の子なのです。
ムーミンの周りにいる生きものたちは皆、寒さを生き抜くための知恵と温かさを持っています。ムーミンがこれまで知らなかった冬の存在を、おしゃまさんをはじめとする生きものたちが教えてくれました。私はこの物語を読むと最初のちょっぴり恐かった、“はじめての冬の世界”がじわじわと温かく、そして冬の寒さを和らげてくれる感じがします。あたたかいジュースの存在も気になりいつか飲んでみたいなぁなんて思ってしまいます。どなたか飲んだことがあるという方は、こっそり感想を教えてほしいなぁ・・・。そんなことを考えながらこの本を紹介させて頂きました。
じきに春がきます。ムーミンたちも待ち望んでいた春です。みなさまもそれまで温かな飲み物を飲みながら、ゆっくりお過ごしくださいね。
2018.11.22
心に残る言葉
いつの間にか秋も深まり、気付けばもう12月です。
元来読書好きな私ですが、秋冬は特に本が読みたくなります。
今回は、私が大好きなある詩についてコラムを書かせていただくことにしました。
それは、吉野弘さんの“生命は”という詩です。
「生命は自分自身だけでは完結できないようにつくられているらしい
花も、めしべとおしべが揃っているだけでは不充分で
虫や風が訪れて、めしべとおしべを仲立ちする
生命はその中に欠如を抱き、それを他者から満たしてもらうのだ
世界は多分、他者との総和
しかし互いに欠如を満たすなどとは知りもせず、知らされもせず、
ばらまかれている者同士、無関心でいられる間柄
ときにうとましく思うことさえも許されている間柄
そのように世界がゆるやかに構成されているのはなぜ?
花が咲いているすぐ近くまで、虻の姿をした他者が光をまとって飛んできている
私もあるとき誰かのための虻だったろう、
あなたもあるとき私のための風だったかもしれない」
これを読んだとき、感動とともに心の中に浮かんだのは「あぁ、そうか」という思いです。まさにすとんと、腑に落ちたという表現がぴったりでした。
人と関わるということは、時に煩わしく、時にストレスの種でもあるでしょう。
自分がここにいる意味は?何のために勉強しているの?、と存在理由を見失うこともあるかもしれません。でも、「あなたは私のための風」であり、「私も誰かのための虻」になりうるのです。そう考えると、少し心が楽になりませんか?
自分を癒す言葉、助ける言葉をたくさん持っているということは、心の栄養になります。
どうか、皆さんも素敵な言葉と出会うことができますように。
学生サポートルーム カウンセラー