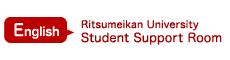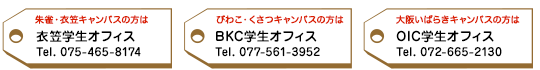2016.05.09
Supernova (スーパーノヴァ)
東日本大震災から5年の月日を感じつついたこの4月に、熊本で大きな地震がありました。今もまだ熊本や大分で、余震や家屋の倒壊で避難生活をされる方々が大勢おられます。
自然の脅威に対して人間はほんとうに無力で、この世界の多くの生き物のなかのひとつなのだと感じさせられます。
大きな地震がすぐ身近に起こるかもしれないこと、震災の報道から想像する被災者の体験を通して、最近はより命の儚さや生き方について考えさせられます。
自分自身も身近に大切な人を失ったとき、現実のこととは受け止められず、自分の心に集中するのは少しずつにしておこう・・と、日々の生活や仕事に埋没している時間も多かったのですが、たまたま耳にした曲に、その心に入る扉がふっと開きました。
若者に人気、BUMP OF CHIKEN (バンプオブチキン)の『supernova』です。
BUMP OF CHIKENの曲の歌詞はどれも、人の内面をよく表現していて、人と宇宙のつながりを感じたり、哲学的な感じもしてどれも好きだったのですが、特に好きな曲になりました。
あまり音楽に詳しくない私がいうのでもっといろいろあるのかもしれませんが、作詞をした藤原さんは、この曲で「Supernova (超新星)」を人との関係に例えているようです。
「超新星」または「超新星爆発」とは、大質量の恒星がその一生を終えるときに、大爆発を起こして太陽よりも明るい光を放つ現象だそうです。そしてその光が私たちのところに届くとき、もうすでにその星は存在しないのです。
そのことを知って、終わるときに初めてその存在を知るのはせつないと思った、でも私たちの身近によくあることです。身近な人を失ったとき、友達と遠く離れたとき、大切にしていた物がなくなったとき、それまであって普通だったものの存在がなくなったときに初めて、その大事さを知ります。
「終わる」ということは「生」そのもの、「終わり」があるから「生」なのだと強く気づかされる現象だなと思います。
『 熱が出たりすると気づくんだ 僕には体があるってこと
鼻が詰まったりするとわかるんだ 今まで呼吸をしていたこと
・・・
延べられた手を拒んだその時に 大きな地震が起こるかもしれない
延べられた手を守ったその時に 守りたかったのは自分かもしれない
・・・
人と話したりすると気づくんだ 伝えたい言葉がないってこと
適当に合わせたりするとわかるんだ 伝えたい気持ちだらけってこと
君の存在だって こうして伝え続けるけど
本当のありがとうは ありがとうじゃ届かなくて
・・・
君の存在だって いつでも思い出せるけど
本当に欲しいのは思い出じゃない今なんだ
君を忘れたあとで 思い出すんだ 君との歴史を持っていたこと
君を失くしたあとで 見つけ出すんだ 君との出会いがあったこと
誰の存在だって 世界では取るに足らないけど
誰かの世界は それがあって つくられる
君の存在だって 何度も確かめはするけど
本当の存在は 居なくなっても ここに居る・・・ 』(歌詞の一部)
他の曲の歌詞も、悲しみや傷つきだけでなく、後半には希望や「傷つきがあるからこその今」が上手に歌われているところが素敵だなと思います。
生まれたときが「新星」で、燃え尽きるときが「超新星」と考えると、全ての消える可能性のあるものは、「超新星が始まった」といえる。藤原さんは、そう考えるとみんなが、「今」大爆発しているように感じられた、といいます。
だから過ぎたことや思い出にとらわれたり、未来を心配して先のことばかり考えた「今」を過ごすより、この「今」を感じて生きていたい。終わりや限界があるからこそ、意味があり、この一瞬を大事にしたいと思えるのですね。
ただ物質の豊かさを求める時代が終わり、不安が漂う世の中ですが、どんなことを大事にして、どこに向かっていけばよいのか、これからの生き方に少しヒントをもらえるような気がしました。
自然の脅威に対して人間はほんとうに無力で、この世界の多くの生き物のなかのひとつなのだと感じさせられます。
大きな地震がすぐ身近に起こるかもしれないこと、震災の報道から想像する被災者の体験を通して、最近はより命の儚さや生き方について考えさせられます。
自分自身も身近に大切な人を失ったとき、現実のこととは受け止められず、自分の心に集中するのは少しずつにしておこう・・と、日々の生活や仕事に埋没している時間も多かったのですが、たまたま耳にした曲に、その心に入る扉がふっと開きました。
若者に人気、BUMP OF CHIKEN (バンプオブチキン)の『supernova』です。
BUMP OF CHIKENの曲の歌詞はどれも、人の内面をよく表現していて、人と宇宙のつながりを感じたり、哲学的な感じもしてどれも好きだったのですが、特に好きな曲になりました。
あまり音楽に詳しくない私がいうのでもっといろいろあるのかもしれませんが、作詞をした藤原さんは、この曲で「Supernova (超新星)」を人との関係に例えているようです。
「超新星」または「超新星爆発」とは、大質量の恒星がその一生を終えるときに、大爆発を起こして太陽よりも明るい光を放つ現象だそうです。そしてその光が私たちのところに届くとき、もうすでにその星は存在しないのです。
そのことを知って、終わるときに初めてその存在を知るのはせつないと思った、でも私たちの身近によくあることです。身近な人を失ったとき、友達と遠く離れたとき、大切にしていた物がなくなったとき、それまであって普通だったものの存在がなくなったときに初めて、その大事さを知ります。
「終わる」ということは「生」そのもの、「終わり」があるから「生」なのだと強く気づかされる現象だなと思います。
『 熱が出たりすると気づくんだ 僕には体があるってこと
鼻が詰まったりするとわかるんだ 今まで呼吸をしていたこと
・・・
延べられた手を拒んだその時に 大きな地震が起こるかもしれない
延べられた手を守ったその時に 守りたかったのは自分かもしれない
・・・
人と話したりすると気づくんだ 伝えたい言葉がないってこと
適当に合わせたりするとわかるんだ 伝えたい気持ちだらけってこと
君の存在だって こうして伝え続けるけど
本当のありがとうは ありがとうじゃ届かなくて
・・・
君の存在だって いつでも思い出せるけど
本当に欲しいのは思い出じゃない今なんだ
君を忘れたあとで 思い出すんだ 君との歴史を持っていたこと
君を失くしたあとで 見つけ出すんだ 君との出会いがあったこと
誰の存在だって 世界では取るに足らないけど
誰かの世界は それがあって つくられる
君の存在だって 何度も確かめはするけど
本当の存在は 居なくなっても ここに居る・・・ 』(歌詞の一部)
他の曲の歌詞も、悲しみや傷つきだけでなく、後半には希望や「傷つきがあるからこその今」が上手に歌われているところが素敵だなと思います。
生まれたときが「新星」で、燃え尽きるときが「超新星」と考えると、全ての消える可能性のあるものは、「超新星が始まった」といえる。藤原さんは、そう考えるとみんなが、「今」大爆発しているように感じられた、といいます。
だから過ぎたことや思い出にとらわれたり、未来を心配して先のことばかり考えた「今」を過ごすより、この「今」を感じて生きていたい。終わりや限界があるからこそ、意味があり、この一瞬を大事にしたいと思えるのですね。
ただ物質の豊かさを求める時代が終わり、不安が漂う世の中ですが、どんなことを大事にして、どこに向かっていけばよいのか、これからの生き方に少しヒントをもらえるような気がしました。
学生サポートルームカウンセラー
2016.04.05
実際のものに触れること
先日、“Mamma Mia!”という映画を見ました。スウェーデンの音楽グループのABBAの音楽を何曲も使っているミュージカル映画です。ご覧になったことがある方もいらっしゃるかもしれません。
私はABBAはなんとなく知っていて、“Mamma Mia!”というミュージカルや映画がよく知られているのは知っていましたが、実際に映画を見て、これABBAの曲だったんだ!というのがたくさんありました。ABBAが実際に活動していた時期に私はABBAを聞いていたわけではありませんが、これだけ今も耳にする曲があるとは、当時もとても人気だったのでしょう。
映画の中では主に俳優がABBAの曲を歌っているので、実際はどんな感じのグループなのだろうと思ってインターネットの動画でABBAの色んな曲の映像を見ました。外出しなくても、すぐ、ぱっと、見てみたい映像にアクセスできるとは、インターネットはすごい力を持っています。
映画は映画で面白かったのですが、動画を見続けているうちに、体が動き出す感じもあって、ABBAのライブを体験してみたかったな、何かライブに行ってみたいな、と思いました。見たインターネットの動画はメンバーを近くで撮っていたものだったので、メンバーの表情など細やかなところまで様子がわかりますし、実際にライブに行ったらそこまでわからないだろうと思います。他のアーティストについても動画で見るのも面白いですが、動画で見て聞くのとライブで見て聞くのとはかなり違いますよね。
ライブやコンサートに行くと、会場に入った時の空間の広がり、演奏される音楽が空間いっぱいに広がって体全身に響きが伝わってくる感じ、その音楽を聞きに来た他の人たちとその時間や空間を一緒にしている感じ、ライブやコンサート後は体の中に起きた高ぶりの余韻に浸る感じ、などがあり、映像を通して感じる音楽とは何か違うものがあると思います。音楽だけではなく、何かスポーツや展示などを見に行ってそれそのものを見るのは、実際に行って見るからこそ感じとれるエネルギーがそこにあるように思います。
普段はテレビやパソコンやスマートフォンなどで動画を見たり音楽を聴いたり、と視覚や聴覚を使うことが多いのではないでしょうか。そこで得られる情報は、聴覚以外の感覚(触覚や味覚、嗅覚など)が抜けた情報です。
春になって暖かくなり、冬で硬くこわばった体もゆるんできた頃かと思います。
映像を通して色んなことを知って世界を広げるのも面白いですが、普段の生活の中で感覚を広げ、実際のものに体を通して触れてみるのもいいのかもしれません。例えば外に出た時、自分が普段歩く道にどんな手触りの葉をつけた木が立ち、どんな匂いのする花が咲くのか、春の空気の中、少し意識してみてもいいのかもしれません。それは、自分に何かすぐに影響を与えることではないかもしれませんが、自分の体のどこかにゆっくりと蓄積されていくことなのではないかと思います。
私はABBAはなんとなく知っていて、“Mamma Mia!”というミュージカルや映画がよく知られているのは知っていましたが、実際に映画を見て、これABBAの曲だったんだ!というのがたくさんありました。ABBAが実際に活動していた時期に私はABBAを聞いていたわけではありませんが、これだけ今も耳にする曲があるとは、当時もとても人気だったのでしょう。
映画の中では主に俳優がABBAの曲を歌っているので、実際はどんな感じのグループなのだろうと思ってインターネットの動画でABBAの色んな曲の映像を見ました。外出しなくても、すぐ、ぱっと、見てみたい映像にアクセスできるとは、インターネットはすごい力を持っています。
映画は映画で面白かったのですが、動画を見続けているうちに、体が動き出す感じもあって、ABBAのライブを体験してみたかったな、何かライブに行ってみたいな、と思いました。見たインターネットの動画はメンバーを近くで撮っていたものだったので、メンバーの表情など細やかなところまで様子がわかりますし、実際にライブに行ったらそこまでわからないだろうと思います。他のアーティストについても動画で見るのも面白いですが、動画で見て聞くのとライブで見て聞くのとはかなり違いますよね。
ライブやコンサートに行くと、会場に入った時の空間の広がり、演奏される音楽が空間いっぱいに広がって体全身に響きが伝わってくる感じ、その音楽を聞きに来た他の人たちとその時間や空間を一緒にしている感じ、ライブやコンサート後は体の中に起きた高ぶりの余韻に浸る感じ、などがあり、映像を通して感じる音楽とは何か違うものがあると思います。音楽だけではなく、何かスポーツや展示などを見に行ってそれそのものを見るのは、実際に行って見るからこそ感じとれるエネルギーがそこにあるように思います。
普段はテレビやパソコンやスマートフォンなどで動画を見たり音楽を聴いたり、と視覚や聴覚を使うことが多いのではないでしょうか。そこで得られる情報は、聴覚以外の感覚(触覚や味覚、嗅覚など)が抜けた情報です。
春になって暖かくなり、冬で硬くこわばった体もゆるんできた頃かと思います。
映像を通して色んなことを知って世界を広げるのも面白いですが、普段の生活の中で感覚を広げ、実際のものに体を通して触れてみるのもいいのかもしれません。例えば外に出た時、自分が普段歩く道にどんな手触りの葉をつけた木が立ち、どんな匂いのする花が咲くのか、春の空気の中、少し意識してみてもいいのかもしれません。それは、自分に何かすぐに影響を与えることではないかもしれませんが、自分の体のどこかにゆっくりと蓄積されていくことなのではないかと思います。
学生サポートルームカウンセラー
2016.03.09
傷を育むこと
コラムで何を書こうかと思案している時、ある雑誌に“児童文学を読もう”という特集が組まれているのを見て、久しぶりに何か児童文学を読みたいなと思いました。手にとったのは何度か学生時代に読んだことのある、ファンタジー小説『裏庭』という梨木香歩さんの本です。
この小説は照美という少女が、ある出来事をきっかけに、洋館の秘密の「裏庭」へ入り込み冒険の旅に出るというお話です。”裏庭”という言葉は、なんだかワクワク、でもちょっぴり怖いような気がします。この裏庭に行けるのは、そこで庭師としての運命を背負った者だけが行くことが出来るのです。鏡を通って・・・。
この物語に出てくる照美の家族たちはそれぞれに理由があって、少し疲れていたり、時に感情を見失ってしまったり、悲しんでいたり、それでも毎日を生きながら暮らしています。しかし、照美の裏庭での体験に呼応する形で、照美の帰りを待つ家族も段々と変化してきます。照美は裏庭で祖母−母ともう一度関係を繋がりなおして、自分ともう一人の自分と繋がってこちらの世界に帰ってくるのです。
物語の中には裏庭の世界でも現実の世界でも”傷をもつもの“という言葉が出てきます。照美は三人の老婆から『傷を恐れるな』『傷に支配されるな』と言われますが、傷というものがまだよく分かりません。しかし最後に出会う老婆から『傷を大事に育んでいくことじゃ。そこからしか自分というものは生まれませんぞ』と言われ、少しずつ自分のもつ苦しみや葛藤、怒りや悲しみを感じ始めていきます。照美のそういった裏庭での体験に呼応する形で、現実の世界にいる照美の母も、老婦人から傷をもつことで鎧が必要な時期は誰にでもあるが、『薬を付けて、表面だけはきれいに見えても、中のダメージにはかえって悪いわ。傷をもっているということは飛躍のチャンスなの。だから充分傷ついている時間をとったらいいわ』と言われ、初めて照美の母は自分が鎧をつけて今まで自分の感情を見ないようにしていたことに気が付くのです。傷をもつことがどれだけ辛くしんどいのかということは勿論ですが、だからといって傷をもつことは悪いことではない、その傷は『多少姿形が変わったとしても自身の変化への準備というものにも変わり得るのだ』ということを教えてくれています。この物語は読み手にとっての大切な何かを教えてくれるような小説です。照美が無事帰還したことにほっとしながら本を閉じた後、きっとまたいつか読み返したくなるという気持ちになりました。それまで大切に心に留めておこうと思います。
この小説は照美という少女が、ある出来事をきっかけに、洋館の秘密の「裏庭」へ入り込み冒険の旅に出るというお話です。”裏庭”という言葉は、なんだかワクワク、でもちょっぴり怖いような気がします。この裏庭に行けるのは、そこで庭師としての運命を背負った者だけが行くことが出来るのです。鏡を通って・・・。
この物語に出てくる照美の家族たちはそれぞれに理由があって、少し疲れていたり、時に感情を見失ってしまったり、悲しんでいたり、それでも毎日を生きながら暮らしています。しかし、照美の裏庭での体験に呼応する形で、照美の帰りを待つ家族も段々と変化してきます。照美は裏庭で祖母−母ともう一度関係を繋がりなおして、自分ともう一人の自分と繋がってこちらの世界に帰ってくるのです。
物語の中には裏庭の世界でも現実の世界でも”傷をもつもの“という言葉が出てきます。照美は三人の老婆から『傷を恐れるな』『傷に支配されるな』と言われますが、傷というものがまだよく分かりません。しかし最後に出会う老婆から『傷を大事に育んでいくことじゃ。そこからしか自分というものは生まれませんぞ』と言われ、少しずつ自分のもつ苦しみや葛藤、怒りや悲しみを感じ始めていきます。照美のそういった裏庭での体験に呼応する形で、現実の世界にいる照美の母も、老婦人から傷をもつことで鎧が必要な時期は誰にでもあるが、『薬を付けて、表面だけはきれいに見えても、中のダメージにはかえって悪いわ。傷をもっているということは飛躍のチャンスなの。だから充分傷ついている時間をとったらいいわ』と言われ、初めて照美の母は自分が鎧をつけて今まで自分の感情を見ないようにしていたことに気が付くのです。傷をもつことがどれだけ辛くしんどいのかということは勿論ですが、だからといって傷をもつことは悪いことではない、その傷は『多少姿形が変わったとしても自身の変化への準備というものにも変わり得るのだ』ということを教えてくれています。この物語は読み手にとっての大切な何かを教えてくれるような小説です。照美が無事帰還したことにほっとしながら本を閉じた後、きっとまたいつか読み返したくなるという気持ちになりました。それまで大切に心に留めておこうと思います。
学生サポートルームカウンセラー
2016.02.03
Twitterにみる「もののあはれ」
Twitter(ツイッター)を始めてもう6年ほどになります。Twitterとは、ご存知の方も多いと思いますが、「ツイート」という140文字以内の「ひとりごと」の投稿を共有するウェブ上の情報サービス、コミュニケーションツールです。ユーザーは自分で「ひとりごと」をつぶやくとともに、他のユーザーを「フォロー」することによって彼らの「ひとりごと」を集め、それらが時間軸に沿って表示される様子(タイムライン)を眺めることができます。2015年の時点で、世界的なユーザーは3億人超、そのうち日本のユーザーは2000万人ほどで、諸外国よりも利用率が高い傾向にあるのだそうです。
古くから短歌や俳句などに親しんできた日本人にとって、短い文のなかにさまざまな思いを詰め込むという営みは馴染みのあるものなのかもしれません。実際に私も、面白い映画や音楽なんかと出会ったときに、反射的に『やばいまじで神』などと投稿していることがあります。昔の人が美しい風景に心動かされて思わず和歌を詠んでしまった、という「もののあはれ」の精神と、通じる部分があるような気がしないでもないです。
一方で、Twitterはコミュニケーションツールでもあり、そこには人との関係が存在します。現実の友人とフォローしあうのはもちろん、時には憧れの作家や芸能人から「リプライ(返信)」をもらえてしまうなど、このTwitter上での交流というのも楽しいものではあるのですが、そこには人間関係から生まれるさまざまな問題も浮上してきます。
たとえば「エアリプ」と呼ばれる現象があります。通常、誰かに「リプライ」を送る場合というのは、送る相手のユーザー名をあて先にしてツイートを投稿します。しかしこの「エアリプ」というものは、あて先をあえて不明にしたまま誰かに対しメッセージを発信する、という行為なのです。たとえば私が映画に関する感想を延々とつぶやいているときに、他のユーザーの誰かが『自分のことばっかり話す人って、どうなんだろう』などと投稿したとします。それを見た私は思わず肝を冷やし、「もしかして私の連続投稿、うっとうしかった…? でも、何か他にプライベートで嫌なことがあっての投稿なのかもしれないし…」などと疑心暗鬼に陥ります。「いとむつかし」な状況です。
学生さんのお話でも、「同じ部活の人がTwitterで、みんなからフォローされ見られていると知っていて、『どうせ私、嫌われてるし』などとつぶやいている。何かこちらから声をかけた方がいいのか」といった相談があります。こうした場合の対応はケースバイケースとしか言えませんが、Twitterを使ううえでは、他人の言葉の裏の意味を必要以上に想像しすぎないこと、曖昧なことを適宜曖昧なままにしておく能力というものが必要な気がしています。実際に「エアリプ」を含め、Twitter上で起こる微妙に気まずい対人トラブルというものは、結局は相手の真意を確かめることが出来ないまま、時間の経過とともに流れていってしまうことも多いようです。こうした儚さもまた、「もののあはれ」なのかもしれません。
ところでこのTwitter、近々投稿できる文字数が10000字まで増えるのだそうです。そんな、Facebookの真似をしなくても…あなたにはあなたの良さがあるのだから、もっと自信を持って…とTwitterに言ってあげたくなる今日この頃です。
古くから短歌や俳句などに親しんできた日本人にとって、短い文のなかにさまざまな思いを詰め込むという営みは馴染みのあるものなのかもしれません。実際に私も、面白い映画や音楽なんかと出会ったときに、反射的に『やばいまじで神』などと投稿していることがあります。昔の人が美しい風景に心動かされて思わず和歌を詠んでしまった、という「もののあはれ」の精神と、通じる部分があるような気がしないでもないです。
一方で、Twitterはコミュニケーションツールでもあり、そこには人との関係が存在します。現実の友人とフォローしあうのはもちろん、時には憧れの作家や芸能人から「リプライ(返信)」をもらえてしまうなど、このTwitter上での交流というのも楽しいものではあるのですが、そこには人間関係から生まれるさまざまな問題も浮上してきます。
たとえば「エアリプ」と呼ばれる現象があります。通常、誰かに「リプライ」を送る場合というのは、送る相手のユーザー名をあて先にしてツイートを投稿します。しかしこの「エアリプ」というものは、あて先をあえて不明にしたまま誰かに対しメッセージを発信する、という行為なのです。たとえば私が映画に関する感想を延々とつぶやいているときに、他のユーザーの誰かが『自分のことばっかり話す人って、どうなんだろう』などと投稿したとします。それを見た私は思わず肝を冷やし、「もしかして私の連続投稿、うっとうしかった…? でも、何か他にプライベートで嫌なことがあっての投稿なのかもしれないし…」などと疑心暗鬼に陥ります。「いとむつかし」な状況です。
学生さんのお話でも、「同じ部活の人がTwitterで、みんなからフォローされ見られていると知っていて、『どうせ私、嫌われてるし』などとつぶやいている。何かこちらから声をかけた方がいいのか」といった相談があります。こうした場合の対応はケースバイケースとしか言えませんが、Twitterを使ううえでは、他人の言葉の裏の意味を必要以上に想像しすぎないこと、曖昧なことを適宜曖昧なままにしておく能力というものが必要な気がしています。実際に「エアリプ」を含め、Twitter上で起こる微妙に気まずい対人トラブルというものは、結局は相手の真意を確かめることが出来ないまま、時間の経過とともに流れていってしまうことも多いようです。こうした儚さもまた、「もののあはれ」なのかもしれません。
ところでこのTwitter、近々投稿できる文字数が10000字まで増えるのだそうです。そんな、Facebookの真似をしなくても…あなたにはあなたの良さがあるのだから、もっと自信を持って…とTwitterに言ってあげたくなる今日この頃です。
学生サポートルームカウンセラー
2016.01.15
子育て雑感 ―魔法の言葉と2度目の誕生日―
我が家には一昨年に誕生しそろそろ1歳4ヶ月になろうという娘がいます。不肖ながら父親として日々成長を見守っているわけですが、心理学などを学んだ身として、時々色んなことを思い出させられたり感じさせられたりしています。
●魔法の言葉『パパ』
1歳になるしばらく前くらいから、娘も少しずつ単語を話すようになってきたのですが、ある時期、いろいろな場面で『パパ』という言葉を発するようになり、逆にそれ以外の言葉をあまり言わなくなってしまうということがありました。例えばこんな調子です・・。
(娘、足元にやってきて)
娘 「パパ・・」
ぼく 「はーい。抱っこね」(娘を抱っこする父親)
(娘、キッチンを指差して)
娘 「パパ・・」
ぼく 「はーい。キッチン行きたいんだね」(そのままキッチンへ移動)
(娘、食器棚にある自分のコップを指さして)
娘 「パパ・・」
ぼく 「はーい。コップね」(コップを手に取り渡してやる父親。)
「だっこ」とか「あっち」とか「取って」とか、いろいろと言葉を覚えたり発したりするチャンスはあるのに、どうもどこかの誰かさんが『パパ』の一声で動いてしまうものだから、娘は『パパ』と言えばなんでも叶うと思ってしまっているのです。一時はおっぱいを要求する時ですら『パパ』と言うようになり、さすがにこれには奥さんも閉口していました。それでもどこかの誰かさんは「父親なんていずれ娘に煙たがられるんだから・・」などとダメ親発言をするのでした。
ともあれ、このようなコミュニケーションから少しずつ、興味のあるものを一緒に見て名前を言ってみたり、一緒に驚いてみたりといった3項関係のコミュニケーションが広がってゆきます(上の例ではあまり広がっていませんが)。そこでは、世界を見て何かを感じている〈私〉と、それを共感という形で肯定したりあるいは名前を教えてくれたりする〈あなた〉という存在、そして私が感じている〈世界〉とが、同時に成立します。〈私〉がまずあって〈世界〉や他者(〈あなた〉)があるといったことなどではなく、3つ同時に成立するのです。これは『間主観性』という事態ですが、〈私〉の肯定感と〈あなた〉への信頼感と〈世界〉への安心感が同時に成立するという意味で、これは人がこの世に根を張っていく上でとても重要な現象です。もちろん赤ん坊時代だけの話ではなく、こうした他者と共に世界を見つめ、確かめ合う作業は一生続いていくものです。
あるいは〈私〉の成立には既に〈あなた〉や〈世界〉が含まれているという点で、青年期にありがちな、独我論的に1人でもの思いに耽って自分って何者なんだろう・・と煮詰めていってもやっぱり埒が明かないんだな、と若き日のぼくに知らしめてくれた契機のひとつとしても印象深い概念でした。
●2度目の誕生日
このように、少しずつ言葉を覚え、ぼくや奥さんと一緒に世界を眺めながら、この世に根を張りつつある娘ですが、そんな姿を見ながらもう一つ思うことがあります。それはある意味逆説的なのですが「早くこの子と出会いたい」という気持ちなのです。いやいやもうとっくの昔に出会っているじゃないか、と突っ込まれるかもしれませんが、案外そうとも限らないのです。こんな考え方があります。
人間の生命の出発点は、人間として自らが自らを生きたものと定めた日である。いわば2度目の誕生日がある。そしてそれ以前の生は、そこからの逆照射による気づきによって発生する。(中略)人間としての自覚の発生以前の精神生活、すなわち人間が人間としての自覚を持たずに赤ん坊として暮らしていた時代は、無意識となり、永遠に失われたものの範疇へと、追いやられるのである。エディプスが神話の中でスフィンクスの問いに答えて『それは人間だ』と言う瞬間は、この自覚の成立を物語る。
(作田啓一ほか編『人間学命題集』,新曜社,1998より)
言葉が飽和し、組織化され〈意識〉や〈自我〉という現象に至ったとき、このような第2の誕生日が訪れるのでしょう。そしてそれまでの姿は〈無意識〉として意識できない部分に追いやられる。中国の『荘子』には〈渾沌〉という神に7つの穴(感覚器)を穿ったら死んでしまったという話があるのですが、同じような話かもしれません。
そしてまた考えてみると、思春期、青年期、成人期・・とライフステージが変わるごとに、人間は第3第4の誕生日を重ねてゆくようにも思います。特に学生さんたちのような、青年期の人たちとお話をしていると、そういう生みの苦しみ(生まれる苦しみ)に立ち会っているように感じることも珍しくありませんし、先の「1人で考えてても埒が明かない」と気づかせてくれたというエピソードも、ぼく自身のそのような何度目かの誕生に関係していた話だったように思います。
いずれ第2の誕生日が訪れ再び生まれてくる娘、そしてその後も誕生を重ね、どんな風に成長してゆくのか・・・。将来、どこかのオジさんに「パパ・・」とか呟いてブランド物のバッグを買ってもらう、なんてことにならなければよいのですが・・。
●魔法の言葉『パパ』
1歳になるしばらく前くらいから、娘も少しずつ単語を話すようになってきたのですが、ある時期、いろいろな場面で『パパ』という言葉を発するようになり、逆にそれ以外の言葉をあまり言わなくなってしまうということがありました。例えばこんな調子です・・。
(娘、足元にやってきて)
娘 「パパ・・」
ぼく 「はーい。抱っこね」(娘を抱っこする父親)
(娘、キッチンを指差して)
娘 「パパ・・」
ぼく 「はーい。キッチン行きたいんだね」(そのままキッチンへ移動)
(娘、食器棚にある自分のコップを指さして)
娘 「パパ・・」
ぼく 「はーい。コップね」(コップを手に取り渡してやる父親。)
「だっこ」とか「あっち」とか「取って」とか、いろいろと言葉を覚えたり発したりするチャンスはあるのに、どうもどこかの誰かさんが『パパ』の一声で動いてしまうものだから、娘は『パパ』と言えばなんでも叶うと思ってしまっているのです。一時はおっぱいを要求する時ですら『パパ』と言うようになり、さすがにこれには奥さんも閉口していました。それでもどこかの誰かさんは「父親なんていずれ娘に煙たがられるんだから・・」などとダメ親発言をするのでした。
ともあれ、このようなコミュニケーションから少しずつ、興味のあるものを一緒に見て名前を言ってみたり、一緒に驚いてみたりといった3項関係のコミュニケーションが広がってゆきます(上の例ではあまり広がっていませんが)。そこでは、世界を見て何かを感じている〈私〉と、それを共感という形で肯定したりあるいは名前を教えてくれたりする〈あなた〉という存在、そして私が感じている〈世界〉とが、同時に成立します。〈私〉がまずあって〈世界〉や他者(〈あなた〉)があるといったことなどではなく、3つ同時に成立するのです。これは『間主観性』という事態ですが、〈私〉の肯定感と〈あなた〉への信頼感と〈世界〉への安心感が同時に成立するという意味で、これは人がこの世に根を張っていく上でとても重要な現象です。もちろん赤ん坊時代だけの話ではなく、こうした他者と共に世界を見つめ、確かめ合う作業は一生続いていくものです。
あるいは〈私〉の成立には既に〈あなた〉や〈世界〉が含まれているという点で、青年期にありがちな、独我論的に1人でもの思いに耽って自分って何者なんだろう・・と煮詰めていってもやっぱり埒が明かないんだな、と若き日のぼくに知らしめてくれた契機のひとつとしても印象深い概念でした。
●2度目の誕生日
このように、少しずつ言葉を覚え、ぼくや奥さんと一緒に世界を眺めながら、この世に根を張りつつある娘ですが、そんな姿を見ながらもう一つ思うことがあります。それはある意味逆説的なのですが「早くこの子と出会いたい」という気持ちなのです。いやいやもうとっくの昔に出会っているじゃないか、と突っ込まれるかもしれませんが、案外そうとも限らないのです。こんな考え方があります。
人間の生命の出発点は、人間として自らが自らを生きたものと定めた日である。いわば2度目の誕生日がある。そしてそれ以前の生は、そこからの逆照射による気づきによって発生する。(中略)人間としての自覚の発生以前の精神生活、すなわち人間が人間としての自覚を持たずに赤ん坊として暮らしていた時代は、無意識となり、永遠に失われたものの範疇へと、追いやられるのである。エディプスが神話の中でスフィンクスの問いに答えて『それは人間だ』と言う瞬間は、この自覚の成立を物語る。
(作田啓一ほか編『人間学命題集』,新曜社,1998より)
言葉が飽和し、組織化され〈意識〉や〈自我〉という現象に至ったとき、このような第2の誕生日が訪れるのでしょう。そしてそれまでの姿は〈無意識〉として意識できない部分に追いやられる。中国の『荘子』には〈渾沌〉という神に7つの穴(感覚器)を穿ったら死んでしまったという話があるのですが、同じような話かもしれません。
そしてまた考えてみると、思春期、青年期、成人期・・とライフステージが変わるごとに、人間は第3第4の誕生日を重ねてゆくようにも思います。特に学生さんたちのような、青年期の人たちとお話をしていると、そういう生みの苦しみ(生まれる苦しみ)に立ち会っているように感じることも珍しくありませんし、先の「1人で考えてても埒が明かない」と気づかせてくれたというエピソードも、ぼく自身のそのような何度目かの誕生に関係していた話だったように思います。
いずれ第2の誕生日が訪れ再び生まれてくる娘、そしてその後も誕生を重ね、どんな風に成長してゆくのか・・・。将来、どこかのオジさんに「パパ・・」とか呟いてブランド物のバッグを買ってもらう、なんてことにならなければよいのですが・・。
学生サポートルームカウンセラー
2015.12.03
強さの理由
パリで同時多発テロが発生して2週間、世界の情勢について連日メディアが伝える断片的な情報を、私たちは受け取っています。
みなさんは、どんなことを考えましたか?それぞれに、違う思いを抱いていることと思います。私は、またあらためて、世界の歴史、宗教や民族について、「知る」ことを続けなければいけないな、と強く思いました。
テロが起こる2週間前、ある学生さんから、一冊の本を借りました。『マララ~教育のために立ち上がり、世界を変えた少女~』(2014 岩崎書店)高等学校の課題図書にもなっていて、読んだ人もいるかもしれません。小学校高学年ぐらいからを対象に、字も大きく、やわらかい文章で読みやすい本になっています。
日本の私たちからすると、遠い異国の地に生まれたマララさんが、一人の女の子として、勉強をがんばったり、成績を気にしたり、友達関係で悩む、私たちと変わらない日常を生きる人だということが、とても新鮮に感じられます。そこから、彼女と一緒になって、その生い立ち~生活環境、周囲に起こる出来事、考えたこと~を追体験するかのように知ることができるところが素晴らしいと感じました。
貧困、紛争、難民問題が解決しない世界のしくみについて、それぞれがじっくりと考えていかなければいけないと思います。
さてここではカウンセラーとして、本から読み取れたマララさんの「心の強さ」が気になりました。タリバンから銃撃を受けたあと一命をとりとめ、その後も教育のために声を上げ続け史上最年少でノーベル平和賞を受賞したことは記憶に新しいですが、この本から、ここに至るまでのマララさんの生い立ちに、この勇気を生み出す土台と成長の過程を読み取ることができます。
彼女の母は字が読めませんが、父の夢を応援し、深い愛情でいつも家族を温かく支えています。父は、学校を経営しパキスタンの教育のために貢献している人で、自らに身の危険があっても反対勢力に声をあげていける強い信念の持ち主です。マララさんも、小さいときから学校になじみ、学校に特別な感情をもっています。
また父は、まだまだ女の子が教育を受けることが一般的でなく、男の子の誕生に比べて軽んじられる文化の残るパキスタンにおいて、マララさんの誕生を祝福し、教育を受ける権利、男の子と同じように外に出て活動をする権利を保障しています。そして、期待し、信頼しています。そのことによって、小さい頃から、女性が自由に生きられない社会について疑問を抱く感覚を身につけています。
そんな両親のもと、故郷のすばらしい自然環境のなか、幼少期をのびのびと過ごしていますが、小さいときから「頑固でのんきな性格」だそうです。「悪いことがあれば、必ずいいこともある」を信念に、周りの人の意見に流されず、どんな状況にも希望をみつけ、感謝する心が育っているようです。
また彼女が10歳のころ、タリバンが地域に侵攻を始め、政府軍との戦闘地域ともなり、昼夜の爆撃音、テロリズムの恐怖にさらされる生活を送っていますが、家族は生きることを、身に迫る危険を回避するだけでなく、可能性をみつけ、国のために行動する責任があると捉えています。
生まれたときから自然と心の内に宿っていくイスラムの精神も感じました。生活のなかに当たり前のようにあるものが、母親の「人と分け合うことを忘れてはだめよ」というような言葉や人を助ける行動に表れていると感じました。家庭や学校での学びに加えて、小さいときから神様に手紙を書くことによって、自分自身と対話しており、自分をより客観的にみる視点も養っているように感じました。
自分で考え、自分自身が信じる価値基準をもとに決断し、行動する。過酷な状況のなかでより強くなったこの「主体性」が、マララさんの心の強さなのだと感じました。そして行動するときには、尋常ではない「勇気」をもっていますが、自分を信じる強さ、また信仰する神様や家族に守られている「安心感」があってこそなのだと感じました。
この本から「心を強くする」ヒントをもらいながら、お会いする学生さんたちに強さをもって寄り添えるよう、自分自身も日々精進していきたい、と感じました。
※もっと詳しく知りたい人は、『わたしはマララ~教育のために立ち上がり、タリバンに撃たれた少女~』(2013 学研)もお勧めです。また感想は私見ですので違う見方もたくさんあると思います。
みなさんは、どんなことを考えましたか?それぞれに、違う思いを抱いていることと思います。私は、またあらためて、世界の歴史、宗教や民族について、「知る」ことを続けなければいけないな、と強く思いました。
テロが起こる2週間前、ある学生さんから、一冊の本を借りました。『マララ~教育のために立ち上がり、世界を変えた少女~』(2014 岩崎書店)高等学校の課題図書にもなっていて、読んだ人もいるかもしれません。小学校高学年ぐらいからを対象に、字も大きく、やわらかい文章で読みやすい本になっています。
日本の私たちからすると、遠い異国の地に生まれたマララさんが、一人の女の子として、勉強をがんばったり、成績を気にしたり、友達関係で悩む、私たちと変わらない日常を生きる人だということが、とても新鮮に感じられます。そこから、彼女と一緒になって、その生い立ち~生活環境、周囲に起こる出来事、考えたこと~を追体験するかのように知ることができるところが素晴らしいと感じました。
貧困、紛争、難民問題が解決しない世界のしくみについて、それぞれがじっくりと考えていかなければいけないと思います。
さてここではカウンセラーとして、本から読み取れたマララさんの「心の強さ」が気になりました。タリバンから銃撃を受けたあと一命をとりとめ、その後も教育のために声を上げ続け史上最年少でノーベル平和賞を受賞したことは記憶に新しいですが、この本から、ここに至るまでのマララさんの生い立ちに、この勇気を生み出す土台と成長の過程を読み取ることができます。
彼女の母は字が読めませんが、父の夢を応援し、深い愛情でいつも家族を温かく支えています。父は、学校を経営しパキスタンの教育のために貢献している人で、自らに身の危険があっても反対勢力に声をあげていける強い信念の持ち主です。マララさんも、小さいときから学校になじみ、学校に特別な感情をもっています。
また父は、まだまだ女の子が教育を受けることが一般的でなく、男の子の誕生に比べて軽んじられる文化の残るパキスタンにおいて、マララさんの誕生を祝福し、教育を受ける権利、男の子と同じように外に出て活動をする権利を保障しています。そして、期待し、信頼しています。そのことによって、小さい頃から、女性が自由に生きられない社会について疑問を抱く感覚を身につけています。
そんな両親のもと、故郷のすばらしい自然環境のなか、幼少期をのびのびと過ごしていますが、小さいときから「頑固でのんきな性格」だそうです。「悪いことがあれば、必ずいいこともある」を信念に、周りの人の意見に流されず、どんな状況にも希望をみつけ、感謝する心が育っているようです。
また彼女が10歳のころ、タリバンが地域に侵攻を始め、政府軍との戦闘地域ともなり、昼夜の爆撃音、テロリズムの恐怖にさらされる生活を送っていますが、家族は生きることを、身に迫る危険を回避するだけでなく、可能性をみつけ、国のために行動する責任があると捉えています。
生まれたときから自然と心の内に宿っていくイスラムの精神も感じました。生活のなかに当たり前のようにあるものが、母親の「人と分け合うことを忘れてはだめよ」というような言葉や人を助ける行動に表れていると感じました。家庭や学校での学びに加えて、小さいときから神様に手紙を書くことによって、自分自身と対話しており、自分をより客観的にみる視点も養っているように感じました。
自分で考え、自分自身が信じる価値基準をもとに決断し、行動する。過酷な状況のなかでより強くなったこの「主体性」が、マララさんの心の強さなのだと感じました。そして行動するときには、尋常ではない「勇気」をもっていますが、自分を信じる強さ、また信仰する神様や家族に守られている「安心感」があってこそなのだと感じました。
この本から「心を強くする」ヒントをもらいながら、お会いする学生さんたちに強さをもって寄り添えるよう、自分自身も日々精進していきたい、と感じました。
※もっと詳しく知りたい人は、『わたしはマララ~教育のために立ち上がり、タリバンに撃たれた少女~』(2013 学研)もお勧めです。また感想は私見ですので違う見方もたくさんあると思います。
学生サポートルームカウンセラー
2015.11.05
カウンセラーは何をしているのか?
皆さんもよくご存知のムーミン。最近はキャラクターグッズがたくさん店頭に並んでいますし、今年の夏には作者のトーベ・ヤンソン展が大阪で開かれていました。私も子どもの頃テレビでアニメを見ていましたが、主題歌だけが記憶に残っており、毎回のストーリーはあまり覚えていませんでした。最近になって、カウンセリングに来られた方からムーミンの話を聞き、興味が湧いて、『ムーミンパパの思い出』を読んでみました。このお話にはなかなか意味深いことがたくさん含まれていますが、読み手によってどう感じるかは異なると思いますので、ここで解説することは控えます。ムーミンパパがまだ「パパ」になる前の話ですので、青年期のみなさんが共感することがきっとあるだろうと思います。興味のあるかたは是非読んでみてください。
このお話の中で、「おお、これぞカウンセリング」と私が思った部分がありましたので、それをここではご紹介したいと思います。私たちがおこなっているカウンセリングは、守秘義務があるために、どんなことが起きているのかなかなか外からは見えません。みなさまの中には、カウンセラーっていったい何をしているのか?と疑問に思われる方もいることと思います。カウンセラーはそれぞれアプローチが異なりますので、これはあくまでも個人的な見解ですが、カウンセラーとして私が心がけていることは、相手の話に関心をもって聴くということです。苦しいこと、つらいこと、うれしいこと、来談者が話してくれるその場にいて、その語りを聴くことです。『ムーミンパパの思い出』で、ムーミンパパが友だちのフレドリクソンのことをこう書いています。「わたしがいつも感心したのは、かれが、人の気持ちをしずめてなっとくさせるのに、なにもとくべつ意味のあることをいったり、むずかしいことばをつかったりしないことでした。」フレドリクソンは、ムーミンパパの話に興味を持って熱心に聴きました。フレドリクソンのような熟練の域にはまだまだ達しませんが、そこに近づけるように日々聴いています。
このお話の中で、「おお、これぞカウンセリング」と私が思った部分がありましたので、それをここではご紹介したいと思います。私たちがおこなっているカウンセリングは、守秘義務があるために、どんなことが起きているのかなかなか外からは見えません。みなさまの中には、カウンセラーっていったい何をしているのか?と疑問に思われる方もいることと思います。カウンセラーはそれぞれアプローチが異なりますので、これはあくまでも個人的な見解ですが、カウンセラーとして私が心がけていることは、相手の話に関心をもって聴くということです。苦しいこと、つらいこと、うれしいこと、来談者が話してくれるその場にいて、その語りを聴くことです。『ムーミンパパの思い出』で、ムーミンパパが友だちのフレドリクソンのことをこう書いています。「わたしがいつも感心したのは、かれが、人の気持ちをしずめてなっとくさせるのに、なにもとくべつ意味のあることをいったり、むずかしいことばをつかったりしないことでした。」フレドリクソンは、ムーミンパパの話に興味を持って熱心に聴きました。フレドリクソンのような熟練の域にはまだまだ達しませんが、そこに近づけるように日々聴いています。
学生サポートルームカウンセラー
2015.10.7
秋の夜長に息を吸ってみませんか?
ようやく暑かった夏が過ぎ去り、夜風が涼しく秋めいてきましたね。
初めてコラムを書くにあたって何を書こうか迷いましたが、最近新しく始めたことについて少し書かせていただこうかなと思います。
最近ランニングを始めました。と、友人たちへ声高らかに宣言していると、周りからは“え?!運動デキルノ?!”というような反応をされます(笑)。それもそのはず、周囲から驚かれてもおかしくはない程、運動とかけ離れた生活をしていたので皆が驚くのも当然なのです。
働きだすようになってから、何か新しいことをするのが億劫だったり、時間やお金がかかることに、つい面倒くさくなっていました。ですが、暑い夏が終わり自分の中でムクムクと“何かチャレンジしたいな。身体を動かしたいな。”と思うようになりました。元々身体を動かしたいとは思っていたのですが、何がいいだろうかと思案している間に、友人の勧めでマラソン大会に応募する機会を得て、ランニンググッズを揃えてみたり・・・と、物事がトントン拍子に進み、まずは形から入ってみることになったのです。さすがに無鉄砲すぎる自分に驚きましたが、枠組みが揃ったことで後は身一つ鍛えるのみ。「よぉーし。いっちょやってみるか!」と私の熱い魂に火がついたのです。
ランニング初日の後、普段使わない筋肉がフル稼働されたことにより、翌日の筋肉痛は凄まじく痛かったのですが、翌朝はすっきりと目覚め清々しい気持ちになりました。全身の血液を巡らして身体中の毒素を出してくれるような感じにさせてくれるのです。また、夜に走っている最中、夜空や月が綺麗なときに思わず空を見上げることも増えました。そういえば・・・と、つい日々の忙しさに追われていると、顔をあげ空を見上げることも忘れてしまっていたように思います。
忘れてしまっていたなシリーズでいうと、普段生活している中で、息を吸うことって特別なことでもないですが、案外息を吸うことを忘れていませんか?走っていると、この息を吸って吐くことがとても大切な行為であることに気づかされます。「スッスッ、ハッハッ」と鼻から息を吸い、口で吐く。単純なことですが、そうしているうちに呼吸が整ってきて日々感じている様々な気持ちも、呼吸とともに整理されていくように思われます。私自身がいつもとは少し違う時間をもつことで、ちょっぴり日常の楽しみが増えたように思います。
学生の皆さまも、たまには電子機器を見る時間を減らして、まずは空を見上げて、息を大きく吸ってみるのもリラックスできるのではないでしょうか。ぜひお試しあれ。
初めてコラムを書くにあたって何を書こうか迷いましたが、最近新しく始めたことについて少し書かせていただこうかなと思います。
最近ランニングを始めました。と、友人たちへ声高らかに宣言していると、周りからは“え?!運動デキルノ?!”というような反応をされます(笑)。それもそのはず、周囲から驚かれてもおかしくはない程、運動とかけ離れた生活をしていたので皆が驚くのも当然なのです。
働きだすようになってから、何か新しいことをするのが億劫だったり、時間やお金がかかることに、つい面倒くさくなっていました。ですが、暑い夏が終わり自分の中でムクムクと“何かチャレンジしたいな。身体を動かしたいな。”と思うようになりました。元々身体を動かしたいとは思っていたのですが、何がいいだろうかと思案している間に、友人の勧めでマラソン大会に応募する機会を得て、ランニンググッズを揃えてみたり・・・と、物事がトントン拍子に進み、まずは形から入ってみることになったのです。さすがに無鉄砲すぎる自分に驚きましたが、枠組みが揃ったことで後は身一つ鍛えるのみ。「よぉーし。いっちょやってみるか!」と私の熱い魂に火がついたのです。
ランニング初日の後、普段使わない筋肉がフル稼働されたことにより、翌日の筋肉痛は凄まじく痛かったのですが、翌朝はすっきりと目覚め清々しい気持ちになりました。全身の血液を巡らして身体中の毒素を出してくれるような感じにさせてくれるのです。また、夜に走っている最中、夜空や月が綺麗なときに思わず空を見上げることも増えました。そういえば・・・と、つい日々の忙しさに追われていると、顔をあげ空を見上げることも忘れてしまっていたように思います。
忘れてしまっていたなシリーズでいうと、普段生活している中で、息を吸うことって特別なことでもないですが、案外息を吸うことを忘れていませんか?走っていると、この息を吸って吐くことがとても大切な行為であることに気づかされます。「スッスッ、ハッハッ」と鼻から息を吸い、口で吐く。単純なことですが、そうしているうちに呼吸が整ってきて日々感じている様々な気持ちも、呼吸とともに整理されていくように思われます。私自身がいつもとは少し違う時間をもつことで、ちょっぴり日常の楽しみが増えたように思います。
学生の皆さまも、たまには電子機器を見る時間を減らして、まずは空を見上げて、息を大きく吸ってみるのもリラックスできるのではないでしょうか。ぜひお試しあれ。
学生サポートルームカウンセラー
2015.08.19
つれづれ映画評第四回「お、お勧めできません…」
四回目を迎えたつれづれ映画評ですが、ここでは大々的に話題作になったわけではなく、しかし世代や男女の別に関わらず人の心を惹きつける作品を取り上げたいと思っています。が、中には扱われるテーマが重かったり描写が凄惨だったりして、紹介するのに躊躇してしまう作品もあるんですね。そもそも大々的な話題作からして重苦しい作品が昨今は多いと思います。
米国では国内外で不穏な要素を数多抱えている為か、アカデミー賞(の作品賞)にその手のものが数年続けて選ばれることも珍しくありません。何かしらダークで病んだ面が描かれないと却って受け入れられないと言うか。僕は少し前に劇場で「アメリカンスナイパー “American Sniper”(2014)」を観たんですが(2015年作品賞ノミネート)、その後味の悪さにエンドロールで早々に席を立ちたくなりました。米国では激賞されたそうです。俳優としてはもっぱら爽快感溢れるアクション映画で主演を張っていたイーストウッドが、メガホンを取るようになってから徹底して安易な映画的カタルシスに対し距離を置き続けているのは流石だなと思いました。ああ、またそう来るんですねと。でも… いくらなんでもあんな終わり方は…
とは言え人間の善い側面だけを扱う映画ってむしろ稀ですから、良作ではあるけどお勧めしにくい作品というのはやっぱりありますね。最近に限らず、昔から。例えば、そう、これがまた色々あるんですよ。
人には言えない遺伝子情報を隠しながらエリート集団の中で必死に生き残ろうとする主人公の苦闘がサスペンスフルな「ガタカ“GATTACA”(1997)」、軍の要請に応えて一線を越えた実験を行なう医師たちを描いた邦画「海と毒薬(1987)」、ありがちなB級モンスターパニック映画かと思いきや状況が刻一刻と過酷になっていき特にラストシーンで主人公が取る行動に激論必至の「ミスト“The Mist”(2007)」、9.11でテロに利用された(ものの土壇場で比類なき勇気を発揮した)旅客機の最期の状況を描く「ユナイテッド93 “United93”(2006)」、五十年以上前の作品とはいえ老いを扱う構造の深刻さが現代と変わらない「楢山節考(1958)」、と挙げていけばキリがありません。
これ、いずれも良作に違いないとは思うのですが、お勧めできるかと言えばかなり微妙です。いや、観てもらっても構わないんですよ、全然! ただ、どれもハッピーエンドにはほど遠く、ここぞという場面で安心して泣けるような救済措置が用意されているわけでもない。ことさら救いのなさを前面に押し出して製作者が悦に入るような暴力性はないものの、目(心)に優しいとはとても言えない作品たち。いや全くお勧めし難いです。
ついこないだは、「ヴィクとフロ、熊に会う“VIC+FLO ont vu un ours”(2013)」というマイナー作品を観ました。邦題からしてフィンランド映画だと思ったんですよ、ファンタジックでホロリと泣けるフィンランド映画だと! それがもう全然違う。だいたい熊なんか出てこない。
主人公のヴィクは還暦を過ぎた女性ですがどうやら長いあいだ刑務所にいたらしく、仮出所で故郷に戻ってもそこには体が不自由な叔父と彼が住む小さな小屋しか残っていない。ああ、じゃあこれは死と再生の物語なのか、悪事を働いたがゆえ相当な時間を無為に失った女性が故郷で再出発を果たす話なのか、と思ったんです。ヴィクは根っからの悪党には見えないし、二回りほど年若の恋人フロが訪ねてきた時は子供のようにはしゃいで生気を取り戻す。人の勧めで家庭菜園を始めたりもする。うん、死と再生の話やなと。
でも違いました。
フロは美しい女性で男性にもモテるので、あちこちで関係を持ってしまう。そういう自由奔放な恋愛をヴィクと出会う前から続けてきたようで、誰かの強い恨みを買うことも充分にあったのでしょう。ヴィクも内心苦々しく思っているのに、彼女を失えば自分にはもう何も残らないと感じるのか、フロに執着してしまう。その結果、いわば自業自得といった形で二人は熊のように恐ろしい災厄を招き寄せてしまうのです。
無味乾燥とした前半から中盤徐々に募っていくヴィクとフロの確執、そして目を覆いたくなるようなラストシーンへ一気に放り込まれる構成にはよくも悪くも胸を拍(う)つものがあり、この作品には学ぶべき怖さがあると思わされます。僕はトラブルメーカーのフロや上述した“災厄”よりも、ヴィクの狡さが怖いんですよ。その最後の災厄はヴィクにとっても予想外のものだった筈ですが、一瞬の差で彼女は回避することができたんじゃなかろうか。でもそうするとフロを助けねばならず、助ければフロは去っていくだろう。そこまで考えて、あえて二人一緒に絶望的な状況に身を置くことを咄嗟に選択したんじゃなかろうか。深読みかもしれませんが、だとしたら怖いですね。いやー全くお勧めできません。
・・・というわけで今回は、特にひとつの作品のみに言及することなく色々と書き連ねてみました。大学生活は日々様々な試練が降りかかりますから、このコラムでもできれば皆さんが少しでも前向きになれるような作品を紹介しようと心がけています。が、あまりそういうものばかりでも予定調和に過ぎて却って読んでもらえないかなと思い、こういう形にしてみました。自分としては大好きだけどお勧めはしにくい、そんな作品について友達と語り合ってみるのも楽しいかもしれませんね。
米国では国内外で不穏な要素を数多抱えている為か、アカデミー賞(の作品賞)にその手のものが数年続けて選ばれることも珍しくありません。何かしらダークで病んだ面が描かれないと却って受け入れられないと言うか。僕は少し前に劇場で「アメリカンスナイパー “American Sniper”(2014)」を観たんですが(2015年作品賞ノミネート)、その後味の悪さにエンドロールで早々に席を立ちたくなりました。米国では激賞されたそうです。俳優としてはもっぱら爽快感溢れるアクション映画で主演を張っていたイーストウッドが、メガホンを取るようになってから徹底して安易な映画的カタルシスに対し距離を置き続けているのは流石だなと思いました。ああ、またそう来るんですねと。でも… いくらなんでもあんな終わり方は…
とは言え人間の善い側面だけを扱う映画ってむしろ稀ですから、良作ではあるけどお勧めしにくい作品というのはやっぱりありますね。最近に限らず、昔から。例えば、そう、これがまた色々あるんですよ。
人には言えない遺伝子情報を隠しながらエリート集団の中で必死に生き残ろうとする主人公の苦闘がサスペンスフルな「ガタカ“GATTACA”(1997)」、軍の要請に応えて一線を越えた実験を行なう医師たちを描いた邦画「海と毒薬(1987)」、ありがちなB級モンスターパニック映画かと思いきや状況が刻一刻と過酷になっていき特にラストシーンで主人公が取る行動に激論必至の「ミスト“The Mist”(2007)」、9.11でテロに利用された(ものの土壇場で比類なき勇気を発揮した)旅客機の最期の状況を描く「ユナイテッド93 “United93”(2006)」、五十年以上前の作品とはいえ老いを扱う構造の深刻さが現代と変わらない「楢山節考(1958)」、と挙げていけばキリがありません。
これ、いずれも良作に違いないとは思うのですが、お勧めできるかと言えばかなり微妙です。いや、観てもらっても構わないんですよ、全然! ただ、どれもハッピーエンドにはほど遠く、ここぞという場面で安心して泣けるような救済措置が用意されているわけでもない。ことさら救いのなさを前面に押し出して製作者が悦に入るような暴力性はないものの、目(心)に優しいとはとても言えない作品たち。いや全くお勧めし難いです。
ついこないだは、「ヴィクとフロ、熊に会う“VIC+FLO ont vu un ours”(2013)」というマイナー作品を観ました。邦題からしてフィンランド映画だと思ったんですよ、ファンタジックでホロリと泣けるフィンランド映画だと! それがもう全然違う。だいたい熊なんか出てこない。
主人公のヴィクは還暦を過ぎた女性ですがどうやら長いあいだ刑務所にいたらしく、仮出所で故郷に戻ってもそこには体が不自由な叔父と彼が住む小さな小屋しか残っていない。ああ、じゃあこれは死と再生の物語なのか、悪事を働いたがゆえ相当な時間を無為に失った女性が故郷で再出発を果たす話なのか、と思ったんです。ヴィクは根っからの悪党には見えないし、二回りほど年若の恋人フロが訪ねてきた時は子供のようにはしゃいで生気を取り戻す。人の勧めで家庭菜園を始めたりもする。うん、死と再生の話やなと。
でも違いました。
フロは美しい女性で男性にもモテるので、あちこちで関係を持ってしまう。そういう自由奔放な恋愛をヴィクと出会う前から続けてきたようで、誰かの強い恨みを買うことも充分にあったのでしょう。ヴィクも内心苦々しく思っているのに、彼女を失えば自分にはもう何も残らないと感じるのか、フロに執着してしまう。その結果、いわば自業自得といった形で二人は熊のように恐ろしい災厄を招き寄せてしまうのです。
無味乾燥とした前半から中盤徐々に募っていくヴィクとフロの確執、そして目を覆いたくなるようなラストシーンへ一気に放り込まれる構成にはよくも悪くも胸を拍(う)つものがあり、この作品には学ぶべき怖さがあると思わされます。僕はトラブルメーカーのフロや上述した“災厄”よりも、ヴィクの狡さが怖いんですよ。その最後の災厄はヴィクにとっても予想外のものだった筈ですが、一瞬の差で彼女は回避することができたんじゃなかろうか。でもそうするとフロを助けねばならず、助ければフロは去っていくだろう。そこまで考えて、あえて二人一緒に絶望的な状況に身を置くことを咄嗟に選択したんじゃなかろうか。深読みかもしれませんが、だとしたら怖いですね。いやー全くお勧めできません。
・・・というわけで今回は、特にひとつの作品のみに言及することなく色々と書き連ねてみました。大学生活は日々様々な試練が降りかかりますから、このコラムでもできれば皆さんが少しでも前向きになれるような作品を紹介しようと心がけています。が、あまりそういうものばかりでも予定調和に過ぎて却って読んでもらえないかなと思い、こういう形にしてみました。自分としては大好きだけどお勧めはしにくい、そんな作品について友達と語り合ってみるのも楽しいかもしれませんね。
学生サポートルームカウンセラー
2015.05.08
新たな環境への期待と、どきどきと
この春から、大阪いばらきキャンパスが開学しました。まっさらでぴかぴかの校舎を歩いていると、新しい生活への期待に胸が膨らみます。一方で、“うまくやっていけるかなあ…”と、気後れのような、どきどきする気持ちもあります。新たな年度を迎え、同じように感じている学生さんもいらっしゃるのではないでしょうか。
このコラムにも、何を書くのがいいのか…と迷ったのですが、ひとまず自分の得意分野である現代サブカルチャーからひとつ、とりあげてみようと思います。
新しい環境に入っていく楽しみや不安について考えたとき、以前にやりこんでいたとあるゲームを連想しました(カウンセラーがゲームなんかするの!?と思われるかもしれませんが、する人はします)。「ペルソナ4」という作品で、アニメや舞台にもなっている人気シリーズなので、ご存知の方もおられるかもしれませんね。
高校生の主人公は、両親の仕事の都合で一年間、田舎町に住む親戚のもとで生活することになります。主人公は転校先の学校の友達や町の人々、はたまた動物とも交流し、さまざまな関係を築いていきます。さらには町で起こった事件の謎を解明するべく動きだすのですが、あるときから主人公は、“テレビのなかに入る”という力を手に入れます。
テレビのなかの世界には、“シャドウ”と呼ばれる化け物がいます。暴走し、襲いかかってくる“シャドウ”に対し、主人公は“ペルソナ”という力を使って応戦します。主人公は学校や家庭、部活やバイト先で交流を持った人々(と動物)の数と同じだけの“ペルソナ”を持っており、日々の生活で人々との関係が深まると、テレビのなかで用いる“ペルソナ”の力も強くなる、という仕組みになっています。さらには倒した“シャドウ”を受け入れることで、“ペルソナ”が生まれ変わったりもします。
“シャドウ”は心理学では「影」、すなわち「自分にとって受け入れたくない心の部分」とされます。一方の“ペルソナ”は「仮面」、すなわち「他者とのあいだで形作られる役割や態度」と言えるでしょう。人々や生き物と接し、そこで生まれた絆がさまざまなこころの問題に立ち向かう力をくれる、ととらえると、なかなか深いゲームだなと思いました。
まだよく知らない場所や人と関わるには、勇気がいります。どぎまぎしてしまって、つい萎縮してしまうこともあるかもしれません。しかしながら、新たな出会いが自分の可能性を広げてくれることもあるのだと思います。学生サポートルームも、学生のみなさんのこころの幅を広げる場のひとつとして機能していければ、と考えています。
ペルソナ4(persona4) 2008年 アトラス
このコラムにも、何を書くのがいいのか…と迷ったのですが、ひとまず自分の得意分野である現代サブカルチャーからひとつ、とりあげてみようと思います。
新しい環境に入っていく楽しみや不安について考えたとき、以前にやりこんでいたとあるゲームを連想しました(カウンセラーがゲームなんかするの!?と思われるかもしれませんが、する人はします)。「ペルソナ4」という作品で、アニメや舞台にもなっている人気シリーズなので、ご存知の方もおられるかもしれませんね。
高校生の主人公は、両親の仕事の都合で一年間、田舎町に住む親戚のもとで生活することになります。主人公は転校先の学校の友達や町の人々、はたまた動物とも交流し、さまざまな関係を築いていきます。さらには町で起こった事件の謎を解明するべく動きだすのですが、あるときから主人公は、“テレビのなかに入る”という力を手に入れます。
テレビのなかの世界には、“シャドウ”と呼ばれる化け物がいます。暴走し、襲いかかってくる“シャドウ”に対し、主人公は“ペルソナ”という力を使って応戦します。主人公は学校や家庭、部活やバイト先で交流を持った人々(と動物)の数と同じだけの“ペルソナ”を持っており、日々の生活で人々との関係が深まると、テレビのなかで用いる“ペルソナ”の力も強くなる、という仕組みになっています。さらには倒した“シャドウ”を受け入れることで、“ペルソナ”が生まれ変わったりもします。
“シャドウ”は心理学では「影」、すなわち「自分にとって受け入れたくない心の部分」とされます。一方の“ペルソナ”は「仮面」、すなわち「他者とのあいだで形作られる役割や態度」と言えるでしょう。人々や生き物と接し、そこで生まれた絆がさまざまなこころの問題に立ち向かう力をくれる、ととらえると、なかなか深いゲームだなと思いました。
まだよく知らない場所や人と関わるには、勇気がいります。どぎまぎしてしまって、つい萎縮してしまうこともあるかもしれません。しかしながら、新たな出会いが自分の可能性を広げてくれることもあるのだと思います。学生サポートルームも、学生のみなさんのこころの幅を広げる場のひとつとして機能していければ、と考えています。
ペルソナ4(persona4) 2008年 アトラス
学生サポートルームカウンセラー