TOPICS
2024年のTOPICS
2024.06.14



続きを読む
ゲスト講義実施報告(国際交流基金 日本研究部部長 原 秀樹様)
「プロフェッショナル・ワークショップ」(担当教員:石川幸子先生)の授業にて、国際交流基金 日本研究部部長の原 秀樹様をゲスト講師としてお招きし講義を行っていただきました。
今回の授業は、「自分だけの真実と新しいに本論」というテーマで講義を行っていただきました。まず初めに、国際交流基金の業務内容、及び国際協力における基金の役割について説明がありました。1972年に創設された国際交流基金は、芸術と文化の交流、海外における日本語教育の普及(日本語教師の派遣と共に各国の日本語教師の能力強化)、並びに日本研究と日本研究における知的交流(個人のフェローシップ及び各国の日本研究機関への支援)の3分野に特化しているとのことで、それぞれの分野における具体的な事業の説明がありました。
その後「自分だけの真実」についてGoogle Formを使用したワークショップに移行し、
学生たちに考えさせる授業を展開いただきました。「事実」と「真実」について学生たちに具体的な例を提示して質問した後、「事実の一側面が真実である」との結論に導びかれました。自らが時間をかけて観察した結果は「真実」であるが、それは物事の一側面でしかない、「事実」の全容解明には多くの人の協力が必要である、との説明がありました。
一人の研究者がたどり着けるのは、その人の真実のみであって、実態はあらゆる方面から見てみないと分からないものである。その観点から、海外の日本研究者の支援は、日本人が考えている「自分だけの真実」から、その全容に迫ろうとすることで「新しい日本論」(より多面的な理解、より共感しやすく、より比較可能で有用な)を導き出そうとする努力であることが説明されました。
学生たちからは、「文化相対主義と原さんの考え方はどのように違うのか」などの質問が出され、質の高いインタラクティヴな授業となりました。
2024.06.14



続きを読む
ゲスト講義実施報告(中央日報 東京特派員 大貫智子様)
「プロフェッショナルワークショップ」(担当教員:白戸圭一先生)の授業にて、中央日報 東京特派員として勤務されている大貫智子様をゲスト講師としてお招きし、講義を行っていただきました。
講演者の大貫様は、2000年に毎日新聞に入社し2024年3月まで25年間記者として勤務されました。
在勤中は政治部記者、外信部デスク、ソウル特派員、論説委員などを歴任され、30歳代半ばで会社の命で突然韓国語を勉強することになり、その後ソウルに特派員として5年間駐在し、朝鮮半島の取材に従事されました。
そして2024年3月、毎日新聞社を退職して韓国の大手新聞社の中央日報に入社し、日本人として史上初めて韓国紙の東京特派員となった異色の経歴を持たれています。
このほか、毎日新聞在勤中には新聞記事の執筆のみならず、韓国の著名な画家と日本人妻を題材にしたノンフィクションを単著として執筆され、小学館のノンフィクション賞を受賞される偉業も成し遂げられています。
今回の講演では、自身の記者としての歩みを振り返りながら、国境を越えて働くことの魅力や、会社から命じられた業務を自身のキャリア形成に巧みに利用していく生き方などについて学生たちに語っていただきました。
当時は女性記者の海外赴任が極めて稀であったにもかかわらず、当時5歳の息子を連れてソウルに赴任した体験についても講演し、将来働き続けることを望む女子学生たちにもエールを送ってくださいました。
2024.06.11




続きを読む
ゲスト講義実施報告(元:UNHCR駐日事務所代表 現:大学講師 Dirk Hebecker様)
「Introduction to the UN」(担当教員:石川幸子先生)の授業にて、前UNHCR駐日事務所代表で現在は大学講師をされているDirk Hebecker様をゲスト講師としてお招きし講義を行っていただきました。
前UNHCR駐日事務所代表で、現在はUNHCRを定年退職し日本国内で複数の大学の講師として活動しているMr. Dirk Hebeckerをゲスト講師として招聘し、Global Displacementを中心に講義をしていただいきました。
学生とのインタラクションを重視するDirk Hebecker様の授業では、まず、現在の世界における大きな課題は何かについて、学生に質問を投げかけられました。学生から様々な回答が出された後、それらをsecurity, climate, inequality, and healthの4つに分類しながら話を進められました。
特にDisplacementについては、戦争、国内紛争、自然災害、環境破壊、貧困など、様々な要因によって引き起こされることが説明され、現在、難民と国内避難民(IDP)を併せて前代未聞の数の人間が、これらの理由から自分の住んでいた土地から離れなければならない状況に追い込まれているとの指摘がありました。
特に、現在、ウクライナ、スーダン、ガザ、シリア、DRC(コンゴ)等から難民になる人々と共に、国内にとどまって避難民になる数が多いが、シリア難民については、庇護国のレバノンの情勢悪化に伴って、スケープゴートにされるケースが多くなっているとの説明がありました。
難民・IDPの現状については、Crisis Groupの地図、IRC Humanitarian Watch Listなどが常に最新の情報を提供しているので、それらを参照するのが良いとのアドバイスがありました。2021年には8400万人だった難民の数は、2023年10月には1億1400万人までに膨らんでおり、今後も増加していくことが予想され、難民・国内避難民を含めて、その40%が子供たちであるとの説明がありました。
講義後、学生たちからは、ミャンマー情勢についての質問や、国連で働くための方法等についての質問がありました。
2024.06.07



続きを読む
ゲスト講義実施報告(UUUM(ウーム)株式会社 Lee PUI YIU様)
「プロフェッショナルワークショップ メディア」(担当教員:白戸圭一先生)の授業にて、UUUM(ウーム)株式会社に勤務されているLEE Pui Yiuさんをゲスト講師としてお招きし講義を行っていただきました。
香港出身のリさんは2023年3月の本学卒業後、ユーチューバーのマネジメント企業であるUUUM社に就職し、海外企業等に対してユーチューブ番組への広告出稿についての営業をされています。
中国語、日本語、英語を堪能に操るリさんは、自身の能力を存分に生かして海外を相手に仕事をされており、講義の内容は自身の特性を活かすことの重要性を学生に理解させるものでありました。
また、ユーチューバーの人々との間でどのような仕事が行われるかについての話は、ユーチューブを視聴が一般化している学生たちにとっては特に興味深いものであり、受講生たちは身を乗り出してリさんの話を聞いていました。
リさんは学生たちと歳の近い社会人2年目でもあることから、在学時の就職活動の経緯や社会人として働いた1年間を振り返った話は受講生たちの関心を引いていました。
本授業はこれまで、マスメディアへの就職に関心を持つ学生を対象に、新聞、テレビなどのジャーナリズムの世界で働くゲストを中心に招聘し、学生に向けて話をしていただいています。エンターテインメント分野の企業への関心が高まっている中で、そういった学生のニーズに応えるものでもあり、今後もエンターテイメント分野からのゲストの招聘を行っていきたいと思います。
2024.06.07

続きを読む
ゲスト講義実施報告(国連レジデント・コーディネーター事務所:JOP ウォルシュ佑衣様)
「プロフェッショナルワークショップ」(担当教員:石川幸子先生)の授業にて、国連レジデント・コーディネーター事務所に勤務されているウォルシュ佑衣さんにゲスト講師としてオンラインにて講義を行っていただきました。
Walsh結依(旧姓 田中)さんは、立命館大学 国際関係学部の卒業生で、現在、バンコクの国連駐在調整官事務所でJPOとして活躍されています。
講義は、Walshさんご自身がどのような経歴を辿って国連に就職したのかというお話と共に、現在の仕事の内容、並びに今後、国際協力の道に進みたいと考えている後輩たちへのアドバイスなど、盛沢山のお話を伺う機会となりました。
Walshさんの原点は、慶祥高校時代に尋ねたベトナムで物乞いをする子供たちを目の当たりにしたことだということでしたが、これがまさに人生を変える「るつぼ体験」であったそうです。JPOの試験を受けるまでには10年以上の歳月がありましたが、その間に、民間セクター、NGO、政府機関勤務を経験し、この多彩な経験とそこから生まれる柔軟な考え方が、JPO試験でも生かされたようです。現在の業務は、SDGsの進捗を可視化するためのUNINFOの立ち上げやGender equality and Women’s empowerment(平等推進ビジネスと女性の社会進出支援)だということですが、フィールド業務ではない代わりに、ハイレベルな会合にも参加できるという立場、及び育児との両立ができるポジションとのことで充実した毎日を送ってらっしゃるとのことです。他にも、国際協力に携わる方法についても具体的なポジションについて言及があり、国際機関に応募する方法についてはJPOが王道である等、適格なアドバイスをくださいました。
学生たちからは、多くの鋭い質問が投げかけられ、インタラクションで盛り上がった授業となりました。質問の一例として、UN内で赴任地が数年ごとに変わることをどう受け止めるのか、JPOの年齢制限ギリギリで受験したのは何故か、大学時代に休学してどのような経路でインターンのポジションを得たのか等、多岐にわたっていました。大学の先輩ということもあり、Walshさんの活躍の話は学生たちを大いに鼓舞したようです。
2024.06.07
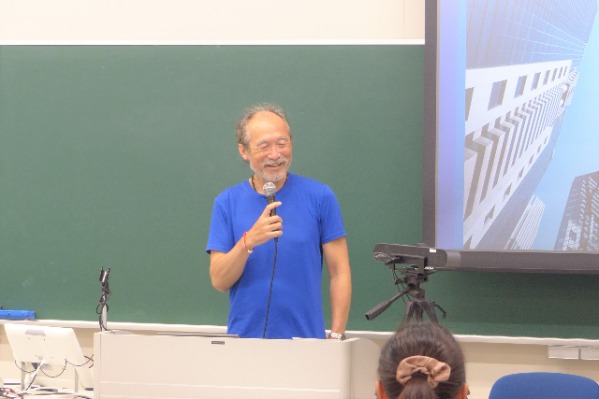


続きを読む
ゲスト講義実施報告(立命館アジア太平洋大学 アジア太平洋学部教授:前学部長 佐藤洋一郎様)
「プロフェッショナル・ワークショップ(英語)」(担当:チャダ・アスタ先生)の授業にて、立命館アジア太平洋大学 アジア太平洋学部教授(前学部長)の佐藤洋一郎先生をゲストスピーカーとしてお招きいたしました。佐藤先生はこれまで、関西外国語大学ハワイカレッジ、オークランド大学、アジア太平洋安全保障研究センター(米国国防総省、2001~2009年)で勤務し、ユソフ・イシャク東南アジア研究所の上級客員研究員(2023年)を務められました。
佐藤先生は学生たちに、米国、ニュージーランド、日本の名門大学における研究キャリアについてお話しされました。また、講義ではインド太平洋の安全保障問題について、主に次のテーマに関してお話しいただきました。
1. 日米関係
2. マラッカ海峡の安全保障
3. 日本の対南太平洋政策
4. インド太平洋における海洋安全保障問題
学生たちは、卒業後の進路選択や大学院で研究を続けるという選択肢について、ゲストスピーカーの佐藤先生と話し合いました。佐藤先生は、就職市場での競争力を維持できるよう自身のスキルを常に最新の状態に保つことがいかに重要であるかについてお話しされていました。
2024.5.31

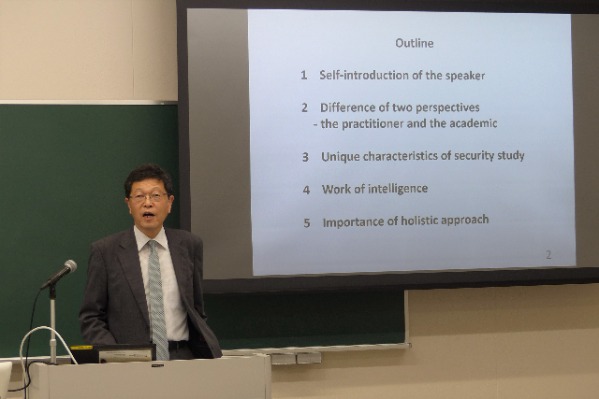

続きを読む
ゲスト講義実施報告(一般財団法人 平和・安全保障研究所(RIPS)理事長 德地秀士様)
2024年5月31日、「プロフェッショナル・ワークショップ(英語)」(担当:チャダ・アスタ先生)のゲストスピーカーとして、一般財団法人 平和・安全保障研究所(RIPS)の理事長・德地秀士様をお招きいたしました。德地様は東京大学法学部を卒業し、フレッチャー・スクール修士課程(M.A.L.D.)を修了ののち、防衛省運用企画局長、人事教育局長、経理装備局長、防衛政策局長、防衛審議官等を経て、2017年に平和・安全保障研究所理事に就任されました。
今回の講義で德地様は、安全保障という概念を、学術的および実務家としての観点からお話しされていました。主なテーマは下記の3つでした。
1. 米国、日本およびその他の国における、安全保障研究の特徴
2. 情報収集という仕事
3. 国際関係における包括的なアプローチの重要性
学生たちからは、政府における業務や研究についていくつもの質問が挙がりました。德地様からは他にも、卒業後の就職機会や政府の安全保障分野で働くために必要なスキル、国際関係分野におけるキャリア形成などについてアドバイスをいただきました。
2024.05.30




続きを読む
ゲスト講義実施報告(サイバーエージェント アベマTVプロデューサー 池田克彦様)
大山真司先生の「専門演習」の授業にて、サイバーエージェント アベマTVプロデューサーとして活躍されている池田克彦様をゲストスピーカーとしてお招きし講義を行っていただきました。
現在はサイバーエージェントのアベマTVでプロデューサーとして幅広いコンテンツ制作に関わっておられる池田様の就職活動の話から始まり、国内一と言われるTBSドラマ部から、AbemaTVでのキャリア、そして並行して自身の制作会社を立ち上げるまでの豊富な実務経験と、メディア産業、コンテンツ制作に関する洞察を共有して頂きました。
特に、地上波全盛の時代からネットTV、ストリーミング配信に至るまで、メディア環境が劇的に変化する中で、国内メディア企業のビジネスモデルや制作スタイルがどのように進化してきたかについて詳しくお話しいただきました。
また同時に、こうした早い変化の中でどのようにキャリアを築いてきたのか、その具体的な経験や洞察を交えながらの説明には大きな気付きがありました。
講演中、学生からは活発に質問が寄せられ、特にキャリアに関する質問に対して親身に受け答えをしてくださいました。
その結果、学生たちはメディア業界の現状や将来について深く理解し、自身のキャリア形成についても多くの学びを得ることができました。
全体を通し、大変有意義な時間となり、学生にとっても貴重な学びの場となりました。
2024.05.24
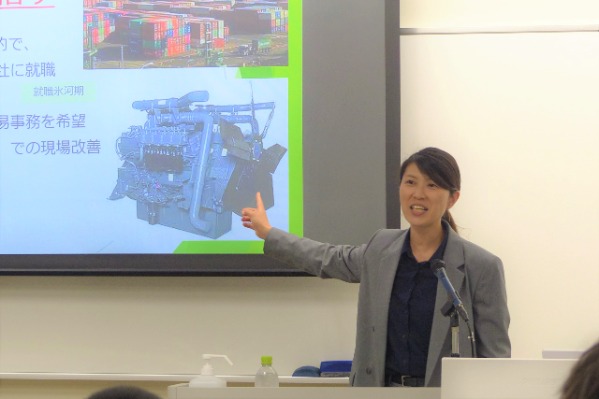
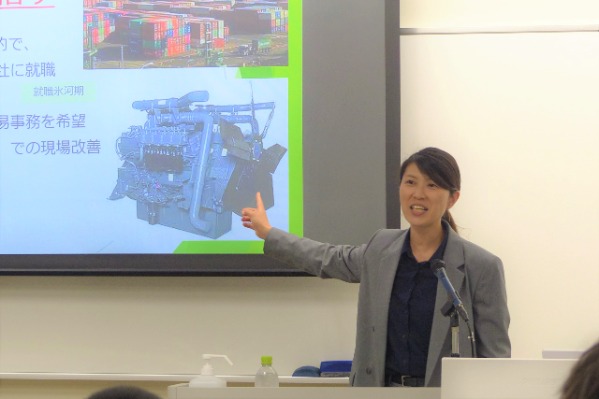


続きを読む
ゲスト講義実施報告(和歌山eかんぱにぃ:理事 中嶋悦子様)
「プロフェッショナルワークショップ」(担当教員:石川幸子先生)の授業にて、和歌山eかんぱにぃにて理事をされている中嶋悦子様をゲスト講師としてお招きし講義を行っていただきました。
本授業では、国際的に活躍するためには「るつぼ体験」(自分の価値観・人生観を再構築する経験)が必要であるとの認識に基づいて、毎年、「るつぼ体験」の一例である青年海外協力隊(JOCV)の経験者をお招きして講義を行って頂いています。
今年も本学の国際関係学部を卒業されてJOCVとしてネパールで活動された中嶋悦子様をお招きしました。
中嶋様は、まず、どのような経緯でJOCVに応募するに至ったかについて説明されました。学部生の時に行ったJICAのインターンで刺激を受け、将来はJOCVとして途上国で仕事をしたいという夢をあきらめることなく、27歳の時にJOCVに応募されました。彼女の職種は「コミュニティ開発」。これは特に専門分野を持たない人がJOCVに応募できる分野ですが、派遣された先で“誰と何をするのかを決めるところから日ごとを始めなければならない”というハードルがあります。
派遣先はネパールのシャンジャ郡という田舎でした。派遣前の2か月間の特訓で学んだネパール語を駆使して、何とか現地の人々とコミュニケーションを図りながら何を自分の仕事とするかを決めるまでのお話は大変興味深かったです。
学生たちに考えさせる授業を目指すということで、授業では「2年間という限られた時間の中で、どのように活動計画を作ったら良いか」というトピックでグループディスカッションを行いました。
授業の最後に中嶋様は「学び続ける姿勢、明日やろうは馬鹿野郎、人間力を磨こう」というメッセージを後輩たちに贈ってくださり、授業は締めくくられました。
授業終了後には、質問の長い列ができ全ての質問への回答が終わるまで30分ほどかかりました。
2024.5.24
 続きを読む
続きを読む
ゲスト講義実施報告(DTS株式会社:シニアマネージャー 岩山洋様)
2024年5月24日のプロフェッショナル・ワークショップのゲストスピーカーとして日本のDTS株式会社シニアマネージャーでらっしゃる岩山洋様に講義いただきました。
講義では、IT業界、日本の銀行、および合併・買収取引後の新しい子会社の管理など、ゲストスピーカーの経験をもとに、関連する4つのテーマについて講義いただきました。
1. 日本と海外、特に米国のITシステム部門の歴史的文化の違い。
2. 日本の IT および銀行部門における DX (デジタル化、DX へのステップを含む)。
3. 日本のIT企業や銀行企業でのキャリア選択の課題と海外で働くことの難しさ。
4. 経済危機、自然災害、パンデミックがキャリアの成長と雇用の機会に与える影響。
学生たちからは、新しいデジタル技術、企業買収の複雑さ、日本の銀行での勤務経験、海外の日系企業での勤務経験などについて質問があり、岩山様は、希望するキャリア選択と必要なスキルを一致させ、大学在学中にどのように技術スキルを伸ばすかについて、ご自身の見識を述べてくださいました。
講義の最後には、岩山様とチャダ先生とでグループワークが行われ、学生たちは自分の希望するキャリアや目標を達成するために必要なスキルについて考える良い機会となりました。