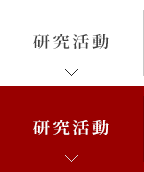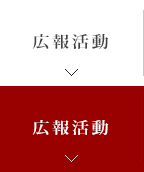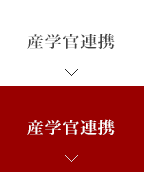2025.03.18
受賞実績
2024.12.24
前田 大光プロジェクトリーダーの日本化学会第42回学術賞受賞が決定しました
この賞は、化学の基礎または応用のそれぞれの分野において先導的・開拓的な研究業績をあげた研究者に授与される賞です。
なお、前田教授は同学会において、2008年度に第58回進歩賞を受賞しています。
2024.11.21
長谷川知子グループリーダーが令和6年度「京都府あけぼの賞」を受賞
R-GIRO 第4期研究プログラム「気候変動に対応する生命圏科学の基盤創生」プロジェクトのグループリーダー長谷川 知子教授(総合科学技術研究機構)が2024年9月27日に京都府より発表された令和6年度「京都府あけぼの賞」を受賞し、11月2日に京都テルサ(京都市南区)で開催された「第36回KYOのあけぼのフェスティバル2024」にて執り行われた表彰式に出席しました。
「京都府あけぼの賞」は、男女共同参画による豊かな地域社会の創造を目指して、女性の一層の能力発揮を図るため、各分野での功績の著しい、京都にゆかりのある女性やグループに京都府知事が授与する賞で、今年度は、長谷川教授を含め個人4名が表彰されました。
表彰式では、受賞者の紹介ののち、西脇隆俊 京都府知事より表彰状と副賞が贈呈されました。
長谷川教授は、世界各国の農業・土地利用分野における気候変動政策立案や食料問題への影響に関する独創的な解析を行い、顕著な成果を挙げており、これまでにも、JST第5回「輝く女性研究者賞(ジュンアシダ賞)」、文部科学大臣表彰科学技術分野科学技術賞(研究部門)、内閣府女性のチャレンジ賞 特別部門賞など、多数の賞を受賞しています。
2024.11.15
立命館グローバル・イノベーション研究機構・井上真男助教が「2024年度極限環境生物学会研究奨励賞」を受賞
R-GIRO 第4期研究プログラム「気候変動に対応する生命圏科学の基盤創生」プロジェクトのメンバー井上真男助教(立命館グローバル・イノベーション研究機構 (R-GIRO))が、「極限環境微生物における多様な代謝タンパク質の機能進化に関する研究」という研究題目で「2024年度極限環境生物学会研究奨励賞」を受賞し、2024年11月3日 (日) に東京大学・弥生講堂・一条ホールにて受賞講演を行いました。
井上助教は、極限環境微生物をターゲットとして、生命の起源や進化・多様性といった生命科学の根源的な問いに分子・原子・情報のレベルで迫るべく、最先端の実験科学と情報科学を組み合わせた二刀流のアプローチで研究を進めています。極限環境微生物は、我々ヒトを含む動植物が生存できないような極限環境に適応した生命圏を構築しています。人々の生活に大きく関わっているPCRや一部の産業酵素・医薬品といったバイオテクノロジー、タンパク質立体構造予測AIなどの最新の情報テクノロジーは極限環境微生物の研究から生まれたものです。井上助教は、このような技術シーズと生物多様性の宝庫ともいえる極限環境微生物がもつ代謝タンパク質の機能進化について、次々と画期的な研究成果を挙げており、歴代の受賞者の中でも高い評価を受け、この度の受賞となりました。
「極限環境生物学会研究奨励賞」について
極限環境生物学会は、世界に先駆け日本で学問的に体系化されてきた極限環境微生物学の推進を図り、広い分野の多くの研究者達の参加を得て、多面的な研究対象と多様なアプローチを総合的に議論することを目的として、1999年に設立された学術団体です。研究奨励賞は、優れた研究を行った学会員に対する顕彰と学会指導者となることが期待される若手学会員の発掘・育成を目的とした賞になります。
2024年度は厳正な審査選考の結果、2名が受賞となっています。
井上真男助教のコメント
この度はこのような栄誉ある賞を賜り、誠にありがとうございます。ご指導いただいた先生方, 共同研究者の皆様に深く感謝申し上げます。小さな生命の無限の可能性に夢を馳せて、今後も超オモロイ微生物の超オモロイ遺伝子・タンパク質について研究を進めていきたいと考えております。
・生命科学部・応用分子微生物学研究室
・井上真男 助教|立命館大学 研究者学術情報データベース
・立命館グローバル・イノベーション研究機構
-
井上助教による受賞講演(東京大学 弥生講堂 一条ホール)
-
受賞式の様子
-
井上 真男助教
-
2024.10.25
本学博士後期課程学生等が国際学会(IEEE)にてBest Paper Awardを受賞
2024年10月6日(日)~10日(木)にかけてマレーシアのクチンで開催された2024 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (IEEE SMC2024)において、本学情報理工学研究科卒業生の中川光さんと同研究科博士課程後期課程3回生の長谷川翔一さんの共著論文が「Franklin V. Taylor Memorial Award (Franklin Taylor Best Paper Award Winner)」を受賞しました。
「Franklin V. Taylor Memorial Award」、同国際会議で最も優れた論文を表彰するものです。
この研究は、「内閣府ムーンショット型研究開発制度(ムーンショット目標1)『誰もが自在に活躍できるアバター共生社会の実現』」(代表:石黒浩・大阪大学大学院基礎工学研究科 教授)、「R-GIRO研究拠点『記号創発システム科学創成:実世界人工知能と次世代共生社会の学術融合研究拠点』」(代表:サトウタツヤ・立命館大学総合心理学部 教授)、「立命館先進研究アカデミー (RARA) 学生フェロー」、「立命館科学技術振興会」の成果でもあります。
長谷川翔一さんコメント
今回受賞した論文は、人の指差しフレームを推定するために、複数のニューラルネットワークで音声と画像の時系列データを処理し、生活支援ロボットの実際の利用シーンで評価したものになります。
受賞した賞は、共著者である中川光さん、萩原良信先生 (総合科学技術研究機構 客員研究准教授 / 創価大学 准教授)、谷口彰先生 (情報理工学部 講師)、谷口忠大先生 (総合科学技術研究機構 客員教授 / 京都大学 教授)、創発システム研究室メンバーの支援で得たものだと思います。今後は、今回の研究で明らかになった研究課題に取り組み、家庭用ロボットに関する研究を推進していきます。
受賞した論文の概要は以下の通りです。
Title: Pointing Frame Estimation with Audio-Visuai Time Series Data for Daily Life Service Robots
Project page: https://emergentsystemlabstudent.github.io/PointingImgEst/
2024.09.24
前田大光プロジェクトリーダー、羽毛田 洋平准教授らが日本液晶学会論文賞(C部門)を受賞しました
R-GIRO 第4期研究プログラム「物質の時空間制御を実現する有機資源の有効活用」|プロジェクトリーダー前田 大光教授(生命科学部応用化学科)、プロジェクトメンバー羽毛田 洋平准教授(立命館グローバル・イノベーション研究機構)が、2024年9月12日、日本液晶学会討論会にて論文賞(C部門)を授与されました。
この賞は、液晶関連学会および学術雑誌、書籍等において発表された優秀なレビュー、総説論文等(ただし、日本液晶学会誌に掲載されたものは除く)の著者に与えらえる賞です。
前田教授らは受賞対象となった総説論文で、π電子系(二重結合などを持つ分子)への電荷の導入により得られる荷電π電子系に焦点を当て、ペアリング・集合化挙動に関してまとめました。荷電π電子系の間には静電力と分散力が相互作用としてはたらき、カチオンとアニオンの組み合わせによって、結晶や液晶などにおいて多様な規則配列構造の構築が実現します。
荷電π電子系イオンペアの探索は端緒についたばかりであるものの、液晶化学にも多大に貢献し、将来、新たな材料・デバイスの開発などへと応用展開されることが期待されます。
受賞対象総説論文
・総説論文名: π-Electronic ion pairs: building blocks for supramolecular nanoarchitectonics viaiπ-iπ interactions
・著者: Yohei Haketa†, Kazuhisa Yamasumi†, Hiromitsu Maeda (†equally contributed)
・発表雑誌: Chemical Society Reviews 2023, 52, 7170-7196
・DOI: https://doi.org/10.1039/D3CS00581J
関連リンク
日本液晶学会ウェブサイト
2024.09.06
半導体材料科学研究室 土田 海渡さんが「Best Poster Award」を受賞|カーボンニュートラル実現へ向けた高効率エネルギー利用技術創成拠点
R-GIRO 第4期研究プログラム「カーボンニュートラル実現へ向けた高効率エネルギー利用技術創成拠点」プロジェクト(プロジェクトリーダー:折笠 有基教授)のグループリーダー荒木 努教授(理工学部 電気電子工学科)らの研究チームの研究成果について、2024年 6月24日(月)~6月27日(木)に韓国チェジュ島で開催されたThe 9th Asian Conference on Crystal Growth and Crystal Technology (CGCT-9)にてポスター発表がなされ、土田 海渡さん(理工学研究科電子システム系 博士課程前期課程1年/半導体材料科学研究室)が「Best Poster Award」を受賞しました。
学会について
The 9th Asian Conference on Crystal Growth and Crystal Technology(CGCT-9)は、半導体をはじめとする様々な結晶材料の成長技術と応用技術を議論する会議です。3年ごとに日本、韓国、中国で開催され、今年第9回が韓国チェジュ島で開催されました。
発表研究内容
青色発光ダイオードやスマホ充電器に用いられている窒化物半導体を結晶成長するための基板材料として、ScAlMgO4基板が注目されています。今回の発表では、ScAlMgO4基板上に分子線エピタキシー法を用いて成長した窒化インジウムガリウム(InGaN)の物性評価結果について報告しました。
・ポスタータイトル:”Molecular beam epitaxy growth
and properties of InGaN on ScAlMgO4substrates”
・ポスター著者:K. Tsuchida, Y. Kubo, Y. Yamada, H
Watanabe, T. Yagura, M. Deura, T. Fujii, and T. Araki (Ritsumeikan University)
受賞コメント
この度は「The 9th Asian Conference on Crystal
Growth and Crystal Technology」にてBest Poster Awardを賜り,大変光栄に存じます.今回の受賞に際しまして、ご指導いただいた荒木先生,藤井先生,出浦先生、共同研究企業をはじめ、共に研究に取り組んできた研究室メンバーに深く感謝いたします.賞を頂いたことを励みに、今後も精進したいと思います。
(土田 海渡さん(理工学研究科電子システム系 博士課程前期課程1年/半導体材料科学研究室))
「ワイドギャップ半導体による高効率エネルギー利用基板技術開発」グループ(荒木グループリーダー)では、窒化物半導体の革新的結晶成長技術開発を進めています。ScAlMgO4基板上への窒化物半導体成長は、結晶高品質化、基板コスト、プロセス効率化などの課題を解決する技術として注目されており、R-GIROプロジェクト研究の主要テーマとして進めており、すでに4報の関連学術論文が発表されています。
今回の受賞されてたポスターの共著者である、出浦 桃子准教授(立命館グローバル・イノベーション研究機構)、藤井 高志教授(総合科学技術研究機構機構)はともに本R-GIROプロジェクトのメンバーとして参画しています。
2024.03.07
島田 伸敬チームリーダーが「2023年度日本機械学会賞(論文)」を受賞
R-GIRO 第4期研究プログラム「記号創発システム科学創成:実世界人工知能と次世代共生社会の学術融合研究拠点」プロジェクトのG2-T2チームリーダー島田 伸敬教授(情報理工学部情報理工学科)らの研究チームが、2023年度日本機械学会賞(論文)を受賞しました。
受賞論文の第一著者である眞田 慎氏は、立命館大学グローバル・イノベーション研究機構研究員(論文掲載時。のち博士学位を取得後PD研究員を経て現在ヤマハ発動機に勤務)として当該研究拠点プロジェクトに参画しました。
論文情報
・論文名:「観察に基づく学習における類似物体との自動的な動作共有による未知の操作方法の想起」
・著 者:眞田 慎(立命館グローバル・イノベーション研究機構(論文掲載時))、松尾 直志(立命館大学(現 一関工業高等専門学校))、島田 伸敬(立命館大学 情報理工学部情報理工学科)、白井 良明(立命館大学
総合科学技術研究機構)
・発表誌:日本機械学会論文集89 巻
(2023) 920 号
・掲載URL:https://doi.org/10.1299/transjsme.22-00274
日本機械学会HP
https://www.jsme.or.jp/20240305/
人の行動観察から獲得した知識に基づいて想起した初見物体に対する操作方法の例(受賞論文Fig.11より引用)
2023.12.27
長谷川知子グループリーダーが「輝く女性研究者賞(ジュン アシダ賞)」「高被引用論文著者」の受賞を報告
2023.12.26
山末 英嗣PLが「日本LCA学会功績賞」の受賞内定|資源パラドックス問題の解決に 向けたマルチバリュー循環研究拠点
2023.09.19
R-GIRO田原 緑助教が「2023年度日本植物学会若手奨励賞」を受賞
2023.06.13
R-GIRO光斎 翔貴准教授がベストプレゼンテーション賞を受賞
2023.06.08
山末研究室の研究チームが「廃棄物資源循環学会令和4年度論文賞」を受賞しました
2023.05.31
創発システム研究室が「RoboCup Japan Open 2023」において複数受賞
R-GIRO 第4期研究プログラム「記号創発システム科学創成:実世界人工知能と次世代共生社会の学術融合研究拠点」プロジェクトのプロジェクトリーダー 谷口 忠大 教授(情報理工学部)の創発システム研究室が、2023年5月3日(水)〜7日(日)にかけて滋賀ダイハツアリーナで開催された「RoboCup Japan Open 2023」において複数の賞を受賞しました。
詳細はこちら(LINK:https://www.ritsumei.ac.jp/news/detail/?id=3166)