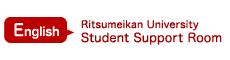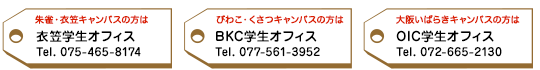2013.10.17
ある清掃員画家の話
この夏をこえて、また新しい体験ができました。人生のいいとき、悪いとき、どちらも大切だと思うのは、順調でない時に目にするもの、読んだもの、会った人に、心を動かされ、自分がまた一歩成長し、その積み重ねに今があると感じるからです。
先日、ぼうっとテレビを見ていたら、何だか引き寄せられて、途中からでしたが釘付けになって見入りました。NHKの再放送番組「ガタロさんが描く町~清掃員画家のヒロシマ」、今年の春の放送が話題を呼び、この夏2度の再放送があったので見たという人もいるかもしれません。
広島市のとある町の商店街に、モップや雑巾などの掃除道具と、使いかけのクレヨンや筆などの画材が置かれる倉庫のような一室があります。商店街を30年間1人で掃除してきた清掃員の作業場兼、アトリエで、画家名をガタロと名乗っています。夏の暑い日も冬の凍える日も、朝4時からゴミを集め、トイレを磨き、アーケードを掃くのが仕事です。合間に、拾ってきた画材で絵を描きます。多くはモップや雑巾などの掃除道具を、自分の相棒として親しみと敬意の気持ちで描くそうです。 その仕事につくまでに数々の苦難があり、自分を拾ってくれた商店街だと感謝の念で掃除している気持ちが伝わってくるようでした。「仕事をする」ということはこういうこと、何かに一生懸命に取り組んでみることで、その狭い隙間からも世界のいろいろなものが見えてくるのだと思いました。
私が最も心に残ったのは、あるホームレスが商店街の片隅に住むようになり、ある日自分を描いてほしいとガタロさんに話しかけてきました。ガタロさんは疑問に感じながら彼を描くうち、これは徹底的に描こうと、そして彼はガタロさんのアトリエを繰り返し訪れるようになり、寝たり、ご飯を食べたり、そしてガタロさんは夢中になって描き続けました。寡黙だった彼は次第に身の上を語るようになり、知的障害があること、仕事は長続きせず、ホームレス生活を長年続けていること。いじめられたこと、追いかけられて虐待されたことを語るとき、優しいけど目が鋭いのを感じて、描いても描ききれなかったといいます。それは「生」そのもので。 ある日ガタロさんは思い切って聞きました。「あんたは、ワシのことをどう思うか?」そしたら、「馬鹿じゃ思う(馬鹿だと思う)」と言いました。一瞬誰のことを言っているのかなと後ろを振り返ったそうです。 あの言葉はどういう意味だったのか、彼が突然町から姿を消して何年もたつ今も考え続けているそうです。
ガタロさんにとってまさに描くこととは理解しようとすること、何も語らない物からもたくさんのものを読みとろうとすること、自分の感じたこと、思いを表現することだと感じました。彼をただ理解しようと描き続けたことが、ホームレスの彼の心にどのようなことを残したのか、誰も分からないのですが、一生のうちに自分のことを真剣に理解しようとしてくれた人がいたことは本当のことでした。 私もいつか、「馬鹿じゃ思う」と言われるような、そんな仕事ができるような人になりたいと、心から思いました。
先日、ぼうっとテレビを見ていたら、何だか引き寄せられて、途中からでしたが釘付けになって見入りました。NHKの再放送番組「ガタロさんが描く町~清掃員画家のヒロシマ」、今年の春の放送が話題を呼び、この夏2度の再放送があったので見たという人もいるかもしれません。
広島市のとある町の商店街に、モップや雑巾などの掃除道具と、使いかけのクレヨンや筆などの画材が置かれる倉庫のような一室があります。商店街を30年間1人で掃除してきた清掃員の作業場兼、アトリエで、画家名をガタロと名乗っています。夏の暑い日も冬の凍える日も、朝4時からゴミを集め、トイレを磨き、アーケードを掃くのが仕事です。合間に、拾ってきた画材で絵を描きます。多くはモップや雑巾などの掃除道具を、自分の相棒として親しみと敬意の気持ちで描くそうです。 その仕事につくまでに数々の苦難があり、自分を拾ってくれた商店街だと感謝の念で掃除している気持ちが伝わってくるようでした。「仕事をする」ということはこういうこと、何かに一生懸命に取り組んでみることで、その狭い隙間からも世界のいろいろなものが見えてくるのだと思いました。
私が最も心に残ったのは、あるホームレスが商店街の片隅に住むようになり、ある日自分を描いてほしいとガタロさんに話しかけてきました。ガタロさんは疑問に感じながら彼を描くうち、これは徹底的に描こうと、そして彼はガタロさんのアトリエを繰り返し訪れるようになり、寝たり、ご飯を食べたり、そしてガタロさんは夢中になって描き続けました。寡黙だった彼は次第に身の上を語るようになり、知的障害があること、仕事は長続きせず、ホームレス生活を長年続けていること。いじめられたこと、追いかけられて虐待されたことを語るとき、優しいけど目が鋭いのを感じて、描いても描ききれなかったといいます。それは「生」そのもので。 ある日ガタロさんは思い切って聞きました。「あんたは、ワシのことをどう思うか?」そしたら、「馬鹿じゃ思う(馬鹿だと思う)」と言いました。一瞬誰のことを言っているのかなと後ろを振り返ったそうです。 あの言葉はどういう意味だったのか、彼が突然町から姿を消して何年もたつ今も考え続けているそうです。
ガタロさんにとってまさに描くこととは理解しようとすること、何も語らない物からもたくさんのものを読みとろうとすること、自分の感じたこと、思いを表現することだと感じました。彼をただ理解しようと描き続けたことが、ホームレスの彼の心にどのようなことを残したのか、誰も分からないのですが、一生のうちに自分のことを真剣に理解しようとしてくれた人がいたことは本当のことでした。 私もいつか、「馬鹿じゃ思う」と言われるような、そんな仕事ができるような人になりたいと、心から思いました。
学生サポートルームカウンセラー
2013.08.07
夏休みになると
夏休みになると、NHKラジオ第1で、『夏休み子ども科学電話相談』というラジオ番組が午前中にあります。今年で30周年になる番組で、本にもなっています。私は数年前、たまたまこの番組を知って、とても面白くて、聞ける時はなるべく聞いています。
主に3・4歳から10歳を過ぎた頃の子どもが電話で専門家の先生に質問します。ジャンルは、野鳥、昆虫、植物、天文・宇宙、魚・動物などがあります。私が聞いた時は、「ツバメは渡り鳥だけど、同じ巣に戻ってくるの?」、「カマキリの上手な飼い方は?」、「どうして苦い野菜がある?」、「惑星は最後はどうなるの?」、「魚はどうやって寝ているの?」といった内容の質問がありました。
聞いていて、知ってる知ってると思う質問もあれば、そんなこと考えたこともなかった!という質問もあります。知ってる知ってると思っていても、専門家の先生のお話を聞くと、詳しくはそうなってたんだ、と新たな発見もあります。
でも私がもっと面白いのは、子どもと専門家の先生のやりとりです。「苦い野菜は何があるかな?」と専門家の先生に尋ねられて、「ピーマン…」と答えられる子どももいますが、ぱっとは出てこない子どももいます。「惑星って、どういうのがあるかな?」と尋ねられて、「うーん…わからない…」となる子どももいます。
子どもの質問にどう答えるかというのは、年齢に応じた理解の仕方がありますし、その子の体験している世界に沿って答えないと子どもは納得してくれません。例えば、3・4歳の子どもに「慣性の法則がね…」と言っても多分ちんぷんかんぷんです。でも、どうしてもそういう法則を持ち出してこないと答えられないこともあるし、大人が完璧に答えられないこともあります。大人の側が「わからないんだ」となることもありますし、「もっと大きくなったら習うよ」等、少し、今後の道筋を子どもに示すこともあります。
次々電話はかかってきて次の質問に移っていかないといけないし、大概の子どもはわからなくても、「わかったかな?」と大人に尋ねられたら「…わかった」と答えているように聞こえるのですが、それまでのやりとりの感じが、子どもも大人も苦心していて、聞いていてほほえましくなります。
30年も番組が続いていると、これまでの番組の中で内容としては似たような質問はたくさんあっただろうと思います。けれども、その子どもがその時に疑問に思ったというのはかけがえのないことですし、これまでと同じように答えたからといって、電話の先のたった一人のその子どもが理解してくれるかはわかりません。
電話なので、直接会っているのではなく、相手の様子はわからないし、質問に答える側も大変だと思うのですが、電話でのやりとりを聞いているだけでも、子どもがとても可愛いらしいです。
大学生の皆さんは、普段子どもと接する機会はあまりないかもしれませんが、夏休み中に、例えばこの番組を通して、子どもの体験している世界を垣間見るのも新鮮かもしれません。
主に3・4歳から10歳を過ぎた頃の子どもが電話で専門家の先生に質問します。ジャンルは、野鳥、昆虫、植物、天文・宇宙、魚・動物などがあります。私が聞いた時は、「ツバメは渡り鳥だけど、同じ巣に戻ってくるの?」、「カマキリの上手な飼い方は?」、「どうして苦い野菜がある?」、「惑星は最後はどうなるの?」、「魚はどうやって寝ているの?」といった内容の質問がありました。
聞いていて、知ってる知ってると思う質問もあれば、そんなこと考えたこともなかった!という質問もあります。知ってる知ってると思っていても、専門家の先生のお話を聞くと、詳しくはそうなってたんだ、と新たな発見もあります。
でも私がもっと面白いのは、子どもと専門家の先生のやりとりです。「苦い野菜は何があるかな?」と専門家の先生に尋ねられて、「ピーマン…」と答えられる子どももいますが、ぱっとは出てこない子どももいます。「惑星って、どういうのがあるかな?」と尋ねられて、「うーん…わからない…」となる子どももいます。
子どもの質問にどう答えるかというのは、年齢に応じた理解の仕方がありますし、その子の体験している世界に沿って答えないと子どもは納得してくれません。例えば、3・4歳の子どもに「慣性の法則がね…」と言っても多分ちんぷんかんぷんです。でも、どうしてもそういう法則を持ち出してこないと答えられないこともあるし、大人が完璧に答えられないこともあります。大人の側が「わからないんだ」となることもありますし、「もっと大きくなったら習うよ」等、少し、今後の道筋を子どもに示すこともあります。
次々電話はかかってきて次の質問に移っていかないといけないし、大概の子どもはわからなくても、「わかったかな?」と大人に尋ねられたら「…わかった」と答えているように聞こえるのですが、それまでのやりとりの感じが、子どもも大人も苦心していて、聞いていてほほえましくなります。
30年も番組が続いていると、これまでの番組の中で内容としては似たような質問はたくさんあっただろうと思います。けれども、その子どもがその時に疑問に思ったというのはかけがえのないことですし、これまでと同じように答えたからといって、電話の先のたった一人のその子どもが理解してくれるかはわかりません。
電話なので、直接会っているのではなく、相手の様子はわからないし、質問に答える側も大変だと思うのですが、電話でのやりとりを聞いているだけでも、子どもがとても可愛いらしいです。
大学生の皆さんは、普段子どもと接する機会はあまりないかもしれませんが、夏休み中に、例えばこの番組を通して、子どもの体験している世界を垣間見るのも新鮮かもしれません。
学生サポートルームカウンセラー
2013.07.19
つれづれ映画評
第二回「ダウン・バイ・ロー」
就活についての話は時々耳にしますが、本当に大変そうですね。
数をこなさなければならないのも辛そうですが、自己アピールするだとか自分の長所や強みについて述べるだとか、文化的にあまり馴染みのない行為を強いられるのがまたしんどそうです。
僕自身の育ってきた環境(昭和世代・地方出身)のせいでそう思うんでしょうか。とにかく小中高と「自分のことを良いふうになど言うな」という文脈に身を置いてやってきましたから、仮に今いきなり自己アピールしてとか言われても、その場で固まっちゃうと思います。短所を五つ六つ並べて「それでも何とかやってます」ぐらいしか言いようがないというか。だいたい長所なんて人様から言ってもらう類いのもので、自らの内省によって得られるのは専ら短所だけなんじゃないかと思うんですが、どうなんでしょう。
まあとにかく、就活は本当に大変そうです。
そんなわけで今回ご紹介するのは、就活の「しゅ」の字もかぶってないような三人に男のダメッダメな有り様を描いた「ダウン・バイ・ロー」という作品です。1986年のもので皆さん生まれてもないですよね。古いです、すみません。しかも白黒。ストーリーは平坦で盛り上がりも特になく、アクション性も皆無。ロマンスもないです。シリアスでもないし、コメディに寄ってるわけでもない。
じゃあ見所は何なの、と言うとその何もなさと、それでも何とかやってますという有り様が淡々と、しかし自虐的にでなく、温かみのある感じで描かれているところでしょうか。言わば就活や仕事、人間関係に疲れた人のための、風変わりなおとぎ話といった作品です。
三人のうちのひとりが恋人と揉めるシーンから映画が始まるのですが、とにかく皆、何か失うばかりの寄る辺ない世界に生きている。家族も出てこないし親身になってくれる友人もいない。ひとりは外国人という設定で、コミュニケーションもままなりません。仕事とも呼べないような仕事をして、それがまた更なるトラブルを運んでくる。そんな具合です。
妙な巡り合わせから三人は一緒になりますが、うちふたりが意地っ張りでプライドも高く、全っ然仲良くなろうとしません。「オイオイこの映画は会話すらないんか」と逆にその辺りから面白くなってきます。普段、懸命に気を遣って身の回りのコミュニティを良好に維持しようと神経をすり減らしている人ほど、彼ら三人のやり取りがじんわり染みる清涼剤のように感じられるかもしれません。意固地、狭量、場の空気の読めなさ。そういった、一見短所と見なされる側面が生き生きと描かれ各々の場面を小気味よく繋いでいくさまは、おとぎ話的ではありますが、この作品の最大の醍醐味といえるでしょう。
というわけで最初の就活の話と繋がっているのか割と不安ですが、まあ誰だって長所だけで出来てるわけでもないですし。いずれにしても、長所はもちろん短所も隠さずにいられる誰かと巡り合えることは、本当に素晴らしいことだと思います。
「ダウン・バイ・ロー」 ”Down By Law”
監督:ジム・ジャームッシュ
キャスト:トム・ウェイツ、ジョン・ルーリー、ロベルト・ベニーニ
数をこなさなければならないのも辛そうですが、自己アピールするだとか自分の長所や強みについて述べるだとか、文化的にあまり馴染みのない行為を強いられるのがまたしんどそうです。
僕自身の育ってきた環境(昭和世代・地方出身)のせいでそう思うんでしょうか。とにかく小中高と「自分のことを良いふうになど言うな」という文脈に身を置いてやってきましたから、仮に今いきなり自己アピールしてとか言われても、その場で固まっちゃうと思います。短所を五つ六つ並べて「それでも何とかやってます」ぐらいしか言いようがないというか。だいたい長所なんて人様から言ってもらう類いのもので、自らの内省によって得られるのは専ら短所だけなんじゃないかと思うんですが、どうなんでしょう。
まあとにかく、就活は本当に大変そうです。
そんなわけで今回ご紹介するのは、就活の「しゅ」の字もかぶってないような三人に男のダメッダメな有り様を描いた「ダウン・バイ・ロー」という作品です。1986年のもので皆さん生まれてもないですよね。古いです、すみません。しかも白黒。ストーリーは平坦で盛り上がりも特になく、アクション性も皆無。ロマンスもないです。シリアスでもないし、コメディに寄ってるわけでもない。
じゃあ見所は何なの、と言うとその何もなさと、それでも何とかやってますという有り様が淡々と、しかし自虐的にでなく、温かみのある感じで描かれているところでしょうか。言わば就活や仕事、人間関係に疲れた人のための、風変わりなおとぎ話といった作品です。
三人のうちのひとりが恋人と揉めるシーンから映画が始まるのですが、とにかく皆、何か失うばかりの寄る辺ない世界に生きている。家族も出てこないし親身になってくれる友人もいない。ひとりは外国人という設定で、コミュニケーションもままなりません。仕事とも呼べないような仕事をして、それがまた更なるトラブルを運んでくる。そんな具合です。
妙な巡り合わせから三人は一緒になりますが、うちふたりが意地っ張りでプライドも高く、全っ然仲良くなろうとしません。「オイオイこの映画は会話すらないんか」と逆にその辺りから面白くなってきます。普段、懸命に気を遣って身の回りのコミュニティを良好に維持しようと神経をすり減らしている人ほど、彼ら三人のやり取りがじんわり染みる清涼剤のように感じられるかもしれません。意固地、狭量、場の空気の読めなさ。そういった、一見短所と見なされる側面が生き生きと描かれ各々の場面を小気味よく繋いでいくさまは、おとぎ話的ではありますが、この作品の最大の醍醐味といえるでしょう。
というわけで最初の就活の話と繋がっているのか割と不安ですが、まあ誰だって長所だけで出来てるわけでもないですし。いずれにしても、長所はもちろん短所も隠さずにいられる誰かと巡り合えることは、本当に素晴らしいことだと思います。
「ダウン・バイ・ロー」 ”Down By Law”
監督:ジム・ジャームッシュ
キャスト:トム・ウェイツ、ジョン・ルーリー、ロベルト・ベニーニ
2013.05.31
大学は何をするところなのだろうか
大学のキャンパスには様々な意識の学生が通っています。明確な目標を持って目標に向かって行動している学生もいれば、なんとなく毎日を過ごしている学生もいます。明確な目標を持っていても、どうやって目標に向かって行動して良いのか悩んでいる学生もいれば、目標以外まったく見えず過ごしている学生もいます。では、大学とはそもそも何をするところで、何をすればよいのでしょうか?
私は、大学は自分の意思で「様々な経験を積むところ」だと考えています。高校生であれば、「○○をしなさい」と先生が明確に道を教えてくれたかもしれません。一方大学では、何をするかは自分自身で決めなければなりません。皆さんには学ぶ「自由」が与えられています。この「自由」は時には残酷です。ある人は悩み、ある人はサボり、ある人は一歩も動けなくなります。でも、学ぶ「自由」を通じて皆さんは飛躍的に成長します。
他人の助け、書籍の助け、メディアの助け、ネットの助けなど自身の意思決定のための様々なツールがあります。このツールを自発的に使いこなすことで皆さんは無意識のうちに、他人に相談する力(コミュニケーション力)、書籍を読み理解する力(論理的思考力)、メディアから必要な情報を抽出する力(問題発見能力)、ネットを使いこなす力(情報リテラシー)など大学生として必要な能力を身につけることができます。
しかし、これらの能力は受動的でパターン化された日常では容易に身につきません。つまり、大学在学中にどれだけ多くの「自発的な経験を積めたか」がポイントとなります。
講義で教授の話を聞く“だけ”、サークルで友達と話す“だけ”、図書館で本を読む“だけ”では、経験が偏り限定的な成長しか期待できません。つまり、目標を達成するために必要だと思うこと“だけ”を頑張っても、大学生としては十分な評価を得ることができないのです。余り興味がないと思うことも、進んでやってみよう!体験してみよう!という知的好奇心が様々な経験へと皆さんを誘い、大きな成長へとつながります。友達との遊びの中にも成長への鍵は潜んでいます。たまには違う友達と違う遊びを楽しむことも「様々な経験」という意味では大学生には有益だと思いますよ。
自発的に様々なツールを使いこなし、遠回りと思えることや、一見関係がないと思えることも積極的に経験をすることで、新しい目標が見つかったり、届かないと思っていた目標に思いの外近づいていたりします。
一度考えてみてください。自分は大学生としてどれだけの経験をつめたのでしょうか。
私は、大学は自分の意思で「様々な経験を積むところ」だと考えています。高校生であれば、「○○をしなさい」と先生が明確に道を教えてくれたかもしれません。一方大学では、何をするかは自分自身で決めなければなりません。皆さんには学ぶ「自由」が与えられています。この「自由」は時には残酷です。ある人は悩み、ある人はサボり、ある人は一歩も動けなくなります。でも、学ぶ「自由」を通じて皆さんは飛躍的に成長します。
他人の助け、書籍の助け、メディアの助け、ネットの助けなど自身の意思決定のための様々なツールがあります。このツールを自発的に使いこなすことで皆さんは無意識のうちに、他人に相談する力(コミュニケーション力)、書籍を読み理解する力(論理的思考力)、メディアから必要な情報を抽出する力(問題発見能力)、ネットを使いこなす力(情報リテラシー)など大学生として必要な能力を身につけることができます。
しかし、これらの能力は受動的でパターン化された日常では容易に身につきません。つまり、大学在学中にどれだけ多くの「自発的な経験を積めたか」がポイントとなります。
講義で教授の話を聞く“だけ”、サークルで友達と話す“だけ”、図書館で本を読む“だけ”では、経験が偏り限定的な成長しか期待できません。つまり、目標を達成するために必要だと思うこと“だけ”を頑張っても、大学生としては十分な評価を得ることができないのです。余り興味がないと思うことも、進んでやってみよう!体験してみよう!という知的好奇心が様々な経験へと皆さんを誘い、大きな成長へとつながります。友達との遊びの中にも成長への鍵は潜んでいます。たまには違う友達と違う遊びを楽しむことも「様々な経験」という意味では大学生には有益だと思いますよ。
自発的に様々なツールを使いこなし、遠回りと思えることや、一見関係がないと思えることも積極的に経験をすることで、新しい目標が見つかったり、届かないと思っていた目標に思いの外近づいていたりします。
一度考えてみてください。自分は大学生としてどれだけの経験をつめたのでしょうか。
学生部副部長
情報理工学部准教授
西浦 敬信
情報理工学部准教授
西浦 敬信
2013.02.27
シベリア鉄道の夜
「シベリア鉄道の夜」
ある日、友人とシベリア鉄道に乗って旅をしていたときのことです。列車の中は、2段ベッドが2組あり、4人1室のコンパートメントになっていました。そろそろ眠りに就こうかとしていた午後11時ころ、列車はある駅に到着し、私たちのコンパートメントに夫婦らしき40代くらいの男女が入ってきました。その夫婦はやたらフレンドリーで、寝ようとしていた私たちに、スーツケースから取り出した食料を勧めました。ちょっと怪しげな二人だなと思いつつも、せっかく勧めてくれるのだからと、出されたパンや豚肉をいただきました。夜もふけて、私と友人が熟睡している間に、この夫婦は列車から下車したようでした。
翌朝、ベッドから降りてみると、私たちの履きなれたスニーカーが2足とも見つからない!あちこち探しましたが、就寝まではあり、朝一番でなくなっている、しかもコンパートメントは、鍵はかかってはいませんが、ドアが閉まっていますので、たぶん夜中に乗車して下車したあの夫婦が持って行ってしまったのだろう、という結論になりました。そのままあきらめることもできたのですが、「このことを誰かに言いたい!(怒)」と思ったのでしょうか、私と友人は、車掌さんに事情を説明しに行きました。と言っても、私たちはロシア語は話せませんし、車掌さんも英語は話せません。身振り手振りで、説明しているうちに、他の乗客も混じって、昔テレビ番組でやっていた「ジェスチャーゲーム」さながらのシーンとなりました。やっと話がわかってもらえたときには、乗客から拍手がおこり、笑いがおこり、私と友人は妙な達成感を抱き、とんだハプニングからスタートしたこの話も、いつの間にか、ほんわか笑い話になっていました。その後、私は上履きにしていたカンフーシューズを、友人は、身丈150cmほどの小柄な美人車掌さんから同情とともにいただいたかわいい靴をはいて、無事シベリア鉄道の旅を終えたのでした。その後、列車の中で知り合った通訳ガイドのロシア人青年から、ロシアでは多くの人が給料だけでは食べていけないので、闇市で輸入製品などを売ってその収入で暮らしていることを教えてもらいました。私たちの、履きつぶした安物のスニーカーが、闇市で売られ、そのお金であの夫婦は食料を買い、売られたスニーカーはどこかで誰かに履かれて、ロシアの地を歩いているのだなと、盗まれたスニーカーから夢とロマンが広がりました。
異国の地で、旅の重要アイテムである靴を盗まれ、はじめは困惑と怒りでいっぱいでしたが、後にそれは人とのつながり、笑い、そして夢とロマンまでもたらしたのでした。今こうして、心理の仕事をしていて、あのネガティブな感情が、後にほんわか温かい、ポジティブな感情に変わったのは、どうしてかなと考えると、いろいろと興味深いものです。
ある日、友人とシベリア鉄道に乗って旅をしていたときのことです。列車の中は、2段ベッドが2組あり、4人1室のコンパートメントになっていました。そろそろ眠りに就こうかとしていた午後11時ころ、列車はある駅に到着し、私たちのコンパートメントに夫婦らしき40代くらいの男女が入ってきました。その夫婦はやたらフレンドリーで、寝ようとしていた私たちに、スーツケースから取り出した食料を勧めました。ちょっと怪しげな二人だなと思いつつも、せっかく勧めてくれるのだからと、出されたパンや豚肉をいただきました。夜もふけて、私と友人が熟睡している間に、この夫婦は列車から下車したようでした。
翌朝、ベッドから降りてみると、私たちの履きなれたスニーカーが2足とも見つからない!あちこち探しましたが、就寝まではあり、朝一番でなくなっている、しかもコンパートメントは、鍵はかかってはいませんが、ドアが閉まっていますので、たぶん夜中に乗車して下車したあの夫婦が持って行ってしまったのだろう、という結論になりました。そのままあきらめることもできたのですが、「このことを誰かに言いたい!(怒)」と思ったのでしょうか、私と友人は、車掌さんに事情を説明しに行きました。と言っても、私たちはロシア語は話せませんし、車掌さんも英語は話せません。身振り手振りで、説明しているうちに、他の乗客も混じって、昔テレビ番組でやっていた「ジェスチャーゲーム」さながらのシーンとなりました。やっと話がわかってもらえたときには、乗客から拍手がおこり、笑いがおこり、私と友人は妙な達成感を抱き、とんだハプニングからスタートしたこの話も、いつの間にか、ほんわか笑い話になっていました。その後、私は上履きにしていたカンフーシューズを、友人は、身丈150cmほどの小柄な美人車掌さんから同情とともにいただいたかわいい靴をはいて、無事シベリア鉄道の旅を終えたのでした。その後、列車の中で知り合った通訳ガイドのロシア人青年から、ロシアでは多くの人が給料だけでは食べていけないので、闇市で輸入製品などを売ってその収入で暮らしていることを教えてもらいました。私たちの、履きつぶした安物のスニーカーが、闇市で売られ、そのお金であの夫婦は食料を買い、売られたスニーカーはどこかで誰かに履かれて、ロシアの地を歩いているのだなと、盗まれたスニーカーから夢とロマンが広がりました。
異国の地で、旅の重要アイテムである靴を盗まれ、はじめは困惑と怒りでいっぱいでしたが、後にそれは人とのつながり、笑い、そして夢とロマンまでもたらしたのでした。今こうして、心理の仕事をしていて、あのネガティブな感情が、後にほんわか温かい、ポジティブな感情に変わったのは、どうしてかなと考えると、いろいろと興味深いものです。
学生サポートルームカウンセラー
2013.01.21
たべる、ねる、そしてリラクゼーション
80年代の終わりごろ、バブル期の終わりごろに、ある車の広告で「くうねるあそぶ。」というコピーが使われました。井上陽水が、ゆる~い感じで「みなさ~んお元気ですか~?」と問いかけるようなCMが流れていたように記憶しています。日常生活、もっとリラックスして楽しみましょうというコンセプトが背景にはあったかと思います。
実は、この「くうねるあそぶ」は、日常生活でとても大切なことなのです。
サポートルームでは、さまざまな問題を抱えて学生さんがやってきますが、主な問題をじっくり聴いた後に、「睡眠・食事・運動」の状況をうかがうことがあります。一人暮らしの学生さんが多いですし、自宅生だったとしても、日常生活がどのぐらいしっかり送れているかは、メンタル面と関わる重要なことなのです。
睡眠に関しては、試験や就職活動など、緊張の続くときには、寝つきがわるくなることもあるかと思います。質のよい睡眠をとるには、日中の適度な運動、カフェインを控えめにする、睡眠の1~2時間前にはPC作業やネット操作・ゲームをやめる、ぬるめのお風呂にゆっくり入ってからだをほぐすなどがポイントです。
食事に関しては、3食しっかりとる、栄養が偏らないようにする(生協の赤・緑・黄の表示などを参考に)、旬のものを食べるようにするなど気をつけるとよいでしょう。試験やレポートで忙しい時には、野菜とお肉かベーコンの煮込みをたっぷり作り、毎日煮込んで食べたり(煮込むと味が濃くなっていくので、塩味を薄くするのがポイント)、小さな鍋に取り分けて、めんつゆ、カレー味、トマト風味など味に変化をつけて頂くとよいでしょう。
運動では、心も身体もほどよくほぐれるようなことが望ましいです。家で過ごす時間が多い場合には、お買い物のついでに、遠回りしてお散歩したり、室内でストレッチや体操などできるといいですね。忙しいとき、緊張のつづくときには、ついつい身体も心も縮こまってしまいますので、眠る前にお腹に手をあてて、ゆっくり深い呼吸を10回ほどするのもお勧めです(腹式呼吸)。サポートルームでは、時々ヨガ企画をしておりますので、一度参加して、日常生活にとりいれるとよいかもしれません。また、おもしろTシャツを着て運動というのも、楽しいかもしれませんよ。(前回のエッセイをご参照ください。)私は、TRFのダンス用DVDに合わせて、踊ったりしています。
なんだか「くうねるあそぶ。」のバランスがよくないなあ、自分でどうしていいかわからないなあというときには、いつでもサポートルームにいらしてくださいね。スタッフ一同、みなさんの充実した学生生活を応援しています。
実は、この「くうねるあそぶ」は、日常生活でとても大切なことなのです。
サポートルームでは、さまざまな問題を抱えて学生さんがやってきますが、主な問題をじっくり聴いた後に、「睡眠・食事・運動」の状況をうかがうことがあります。一人暮らしの学生さんが多いですし、自宅生だったとしても、日常生活がどのぐらいしっかり送れているかは、メンタル面と関わる重要なことなのです。
睡眠に関しては、試験や就職活動など、緊張の続くときには、寝つきがわるくなることもあるかと思います。質のよい睡眠をとるには、日中の適度な運動、カフェインを控えめにする、睡眠の1~2時間前にはPC作業やネット操作・ゲームをやめる、ぬるめのお風呂にゆっくり入ってからだをほぐすなどがポイントです。
食事に関しては、3食しっかりとる、栄養が偏らないようにする(生協の赤・緑・黄の表示などを参考に)、旬のものを食べるようにするなど気をつけるとよいでしょう。試験やレポートで忙しい時には、野菜とお肉かベーコンの煮込みをたっぷり作り、毎日煮込んで食べたり(煮込むと味が濃くなっていくので、塩味を薄くするのがポイント)、小さな鍋に取り分けて、めんつゆ、カレー味、トマト風味など味に変化をつけて頂くとよいでしょう。
運動では、心も身体もほどよくほぐれるようなことが望ましいです。家で過ごす時間が多い場合には、お買い物のついでに、遠回りしてお散歩したり、室内でストレッチや体操などできるといいですね。忙しいとき、緊張のつづくときには、ついつい身体も心も縮こまってしまいますので、眠る前にお腹に手をあてて、ゆっくり深い呼吸を10回ほどするのもお勧めです(腹式呼吸)。サポートルームでは、時々ヨガ企画をしておりますので、一度参加して、日常生活にとりいれるとよいかもしれません。また、おもしろTシャツを着て運動というのも、楽しいかもしれませんよ。(前回のエッセイをご参照ください。)私は、TRFのダンス用DVDに合わせて、踊ったりしています。
なんだか「くうねるあそぶ。」のバランスがよくないなあ、自分でどうしていいかわからないなあというときには、いつでもサポートルームにいらしてくださいね。スタッフ一同、みなさんの充実した学生生活を応援しています。
学生サポートルームカウンセラー
2012.12.25
遊びごころ
今年最後の学生サポートルームのコラムです。
「何について書こうかな」
「どういうテーマなら読む人のこころに届くだろう」
と思いながらネタ探しをしていたのですが、
なかなかこれ、というのに出会えません。
時事ネタについてはコラムを書けるほど詳しくないですし、
季節にまつわるエピソードは巷にあふれているので
ここでとりあげることもなさそうです。
うーん、と考え込んでしまったそんな時、ある漫画の登場人物が、
より正しい(正しそうに思える)選択を求めて悩む友人に伝えた
アドバイスを思い出しました。
正確な文言は忘れましたが、
「“どうすべきか”を考えて迷ったら、“どうしたら面白いか”で決めること」
というような内容だったと思います。
どうするのが正解か、何を求められているのか、を考えすぎて
凝り固まった思考では柔軟な発想は浮かばない。
むしろ、面白いかどうかと感じるこころを大事にして、
それを手がかりにすることで見えてくるものがある、
その様な意味が込められているのだと思います。
“Don't think. FEEL!(考えるな、感じるんだ!)”
という名言もあるくらいですから、人は考えすぎると身動きが取れなくなり、
頭を使うのに一生懸命になりすぎると本質から逸れていく、
その様な側面があるともいえそうです。
真剣になにかに向き合うとき、持てるかぎりの経験や知識、
情報をよりどころにして考えることも大切な作業です。
けれどももし、考えすぎて袋小路に陥ったならば、
ふっと肩の力を抜いて、こころの声に耳を澄ませてみることで、
新たな展開や可能性に開かれていくこともあるのではないでしょうか。
ところで、肩の力を抜く、こころの声に耳を澄ます、と書いたものの、
誰もが今すぐに、自由自在にできることでもなさそうです。
日ごろから、こころを柔らかくする工夫が必要になってくるでしょう。
映画を観たり、身体を動かしたり、音楽を聴いたり、
小説を読んだり、おしゃべりしたり、工夫は人それぞれで、
自分に合うものを試すのが一番だと思いますが、
ここでちょっとした工夫を披露(白状?)して、
このコラムをしめくくろうと思います。
それは、落ち着いた装いの下に、面白モチーフのTシャツを秘かに着込み、
何くわぬ顔で過ごすこと。
時々やってみるのですが、けっこう効果的なのです。
先が見えなくて不安なときや疲れて何もかもが嫌なとき、
困難の中にあるときにも、遊びごころを忘れずに。
「何について書こうかな」
「どういうテーマなら読む人のこころに届くだろう」
と思いながらネタ探しをしていたのですが、
なかなかこれ、というのに出会えません。
時事ネタについてはコラムを書けるほど詳しくないですし、
季節にまつわるエピソードは巷にあふれているので
ここでとりあげることもなさそうです。
うーん、と考え込んでしまったそんな時、ある漫画の登場人物が、
より正しい(正しそうに思える)選択を求めて悩む友人に伝えた
アドバイスを思い出しました。
正確な文言は忘れましたが、
「“どうすべきか”を考えて迷ったら、“どうしたら面白いか”で決めること」
というような内容だったと思います。
どうするのが正解か、何を求められているのか、を考えすぎて
凝り固まった思考では柔軟な発想は浮かばない。
むしろ、面白いかどうかと感じるこころを大事にして、
それを手がかりにすることで見えてくるものがある、
その様な意味が込められているのだと思います。
“Don't think. FEEL!(考えるな、感じるんだ!)”
という名言もあるくらいですから、人は考えすぎると身動きが取れなくなり、
頭を使うのに一生懸命になりすぎると本質から逸れていく、
その様な側面があるともいえそうです。
真剣になにかに向き合うとき、持てるかぎりの経験や知識、
情報をよりどころにして考えることも大切な作業です。
けれどももし、考えすぎて袋小路に陥ったならば、
ふっと肩の力を抜いて、こころの声に耳を澄ませてみることで、
新たな展開や可能性に開かれていくこともあるのではないでしょうか。
ところで、肩の力を抜く、こころの声に耳を澄ます、と書いたものの、
誰もが今すぐに、自由自在にできることでもなさそうです。
日ごろから、こころを柔らかくする工夫が必要になってくるでしょう。
映画を観たり、身体を動かしたり、音楽を聴いたり、
小説を読んだり、おしゃべりしたり、工夫は人それぞれで、
自分に合うものを試すのが一番だと思いますが、
ここでちょっとした工夫を披露(白状?)して、
このコラムをしめくくろうと思います。
それは、落ち着いた装いの下に、面白モチーフのTシャツを秘かに着込み、
何くわぬ顔で過ごすこと。
時々やってみるのですが、けっこう効果的なのです。
先が見えなくて不安なときや疲れて何もかもが嫌なとき、
困難の中にあるときにも、遊びごころを忘れずに。
学生サポートルームカウンセラー
2012.11.30
大学の授業の思い出
「大学の授業の思い出」
大学生の頃、一般教養の生物学の授業で聞いた話が今も記憶に残っています。それは、鳥の抱卵についての話でした。先生によると、産卵した鳥は胸の辺りが腫れて熱を持ち、羽毛が抜け落ちるそうです。鳥は腫れた胸を冷やそうとして、冷たい卵に熱心に押し当て、結果的に卵が温まるということでした。
それよりも前、高校生ぐらいのとき、一羽の鳥が空き缶を温めている写真を見たことがあります。いつか缶から雛が孵ると信じて、一生懸命温めているんだな……と、哀れを誘われたものでした。でも、先生の話から考えると、その鳥は缶を温めていたのではなくて、缶で自分を冷やしていたのかもしれません。
先生の専門は、原始的な猿の研究でした。ジャングルに長期間寝泊りしながら、個体を識別し、行動観察をするそうです。そんな先生が、鳥の話の中で、「我が子への愛情とか、そういった人間の感情をそのまま投影して、動物の行動を分かったつもりになるのはよくない」と言ったのは印象に残りました。
同じようなことは身の回りでも、よくあるような気がします。
動物の話ばかりで恐縮ですが、小型犬に服を着せている飼い主を、ブログ等で時々見かけます。おしゃれということなのでしょうか、飼い主の楽しみのために、犬もたいへんだなあと思ったりしていました。でも、チワワなんかの小さい犬、特に短毛種は、気温が低い日に外出させる時には、服を着せる必要があるんだそうです。飼い犬に服を着せるという人間の行動には、犬の低体温を防ぐという動機があったのかもしれないというわけです。
他人が表に出している行動が、どんな動機によっているのか、微妙に勘違いしていたり、想像もつかない理由があったりして、日々驚かされます。
野生動物相手の場合、行動を繰り返し観察し、もしかしたらこうじゃないかという仮説を立てて、検証していくという接近法を人間は持っています。
相手も人間の場合、できることはもっとあります。なんといっても言葉を使えますから(使えない場合もありますが)。私たちはお互いに、質問をすることによって、相手のことを直接、本人から教えてもらえます。
もちろん、聞いたら答えてもらえるとは限りません。「あなたはなぜそんな服を着ているのですか? 自分ではかっこいいと思っているのですか?」と尋ねたら、たいてい怒られるでしょう。嘘をつかれることもあります。 答えようのない質問、本人にも分からない質問だってありますよね。サポートルームのカウンセリングでも、きっと、いろんな思い込みや謎が交錯しているのだと思います。ふとした会話から、目の前の学生さんが、それまでとは違った風に見えたりしつつ、カウンセリングは徐々に進んでいきます。「えっ、そうなの!」と驚くカウンセラーを、学生さんもまた観察しているかもしれませんね。
学生サポートルームカウンセラー
大学生の頃、一般教養の生物学の授業で聞いた話が今も記憶に残っています。それは、鳥の抱卵についての話でした。先生によると、産卵した鳥は胸の辺りが腫れて熱を持ち、羽毛が抜け落ちるそうです。鳥は腫れた胸を冷やそうとして、冷たい卵に熱心に押し当て、結果的に卵が温まるということでした。
それよりも前、高校生ぐらいのとき、一羽の鳥が空き缶を温めている写真を見たことがあります。いつか缶から雛が孵ると信じて、一生懸命温めているんだな……と、哀れを誘われたものでした。でも、先生の話から考えると、その鳥は缶を温めていたのではなくて、缶で自分を冷やしていたのかもしれません。
先生の専門は、原始的な猿の研究でした。ジャングルに長期間寝泊りしながら、個体を識別し、行動観察をするそうです。そんな先生が、鳥の話の中で、「我が子への愛情とか、そういった人間の感情をそのまま投影して、動物の行動を分かったつもりになるのはよくない」と言ったのは印象に残りました。
同じようなことは身の回りでも、よくあるような気がします。
動物の話ばかりで恐縮ですが、小型犬に服を着せている飼い主を、ブログ等で時々見かけます。おしゃれということなのでしょうか、飼い主の楽しみのために、犬もたいへんだなあと思ったりしていました。でも、チワワなんかの小さい犬、特に短毛種は、気温が低い日に外出させる時には、服を着せる必要があるんだそうです。飼い犬に服を着せるという人間の行動には、犬の低体温を防ぐという動機があったのかもしれないというわけです。
他人が表に出している行動が、どんな動機によっているのか、微妙に勘違いしていたり、想像もつかない理由があったりして、日々驚かされます。
野生動物相手の場合、行動を繰り返し観察し、もしかしたらこうじゃないかという仮説を立てて、検証していくという接近法を人間は持っています。
相手も人間の場合、できることはもっとあります。なんといっても言葉を使えますから(使えない場合もありますが)。私たちはお互いに、質問をすることによって、相手のことを直接、本人から教えてもらえます。
もちろん、聞いたら答えてもらえるとは限りません。「あなたはなぜそんな服を着ているのですか? 自分ではかっこいいと思っているのですか?」と尋ねたら、たいてい怒られるでしょう。嘘をつかれることもあります。 答えようのない質問、本人にも分からない質問だってありますよね。サポートルームのカウンセリングでも、きっと、いろんな思い込みや謎が交錯しているのだと思います。ふとした会話から、目の前の学生さんが、それまでとは違った風に見えたりしつつ、カウンセリングは徐々に進んでいきます。「えっ、そうなの!」と驚くカウンセラーを、学生さんもまた観察しているかもしれませんね。
2012.10.31
久しぶりの運動会でのこと
私の住んでいる地域では、この季節になると毎年、町別対抗の運動会が催されます。その地域に住んでいる人全員が参加できるもので、あらゆる年代の人が楽しめるようなプログラムになっています。
学校の運動会であれば、リレーで一番になるとか、赤組白組の勝敗をかけて戦うとか、本気モードの競争が想定されるわけですが、地域の運動会なんて楽しめればいいじゃないと考える人も多いと思います。ところが、意外に「本気」になる大人が続出するのです。本気で競っているのは、大人(と小さい子ども)だけと言ってもいいくらい、リレーはもちろんのこと、玉入れだって事前に戦略を打ち合わせたりして真剣そのものです。
今年は私も久しぶりに参加したのですが、いつの間にかうちの町が三連覇をかけて戦っているということになっていました。連覇して特に何があるわけでもないのですが、優勝という名誉!?のためにわりと本気で競争せざるをえない状況でした。私もエントリーされた競技で、町内の皆さんの健闘ぶりに応えなくてはと、数年ぶりに全速力で(ほんの少し)走ってみました。「全力で走るって、いったい何をどのように・・?」と頭の中で??がたくさん飛び交うなか、とにかく一生懸命走ってみると、結果はどうあれ、なんだかとても清々しく、愉快ではないですか。久しぶりに味わった感覚でした。そして、これは大人にとっては本気の競争ごっこなのだろうと思い当たりました。
ふり返ってみると、子どもの頃に学校の運動会をこれほど心置きなく楽しめていたかというと、私の場合そうでもありませんでした。一番でなくていいのは百も承知でも、全力を出して競走すること自体をどこか恐れていたし、そういう恐れに圧倒されていた気がします。大人にしてみれば「たかが」徒競走でも、子どもにとっては「たかが」と言い切れない、自分全部が賭かってしまう競争のように感じられていたのでしょう。
これまで小学校の運動会で「世界に一つだけの花」が流れているのを聞くと、なぜ今ここで「ナンバーワンにならなくてもいい~♪」と唱えなくてはならないのか・・と不思議に思っていました。でも、これは「負けてもどうってことないよ、」「だから力いっぱい走ってごらん」という、競争に尻込みする子どもたちの背中を押してくれる応援歌なのかもしれませんね。
ほんものの、ここ一番の勝負で、一流のアスリートのごとく「楽しみたい」「自分との闘いに勝つ」などと言うにはまだまだ修行が足りないとしたら、せめて遊びの競争で恐れずに全力を出す感覚を愉しむのも悪くないなあと感じた一日でした。
学校の運動会であれば、リレーで一番になるとか、赤組白組の勝敗をかけて戦うとか、本気モードの競争が想定されるわけですが、地域の運動会なんて楽しめればいいじゃないと考える人も多いと思います。ところが、意外に「本気」になる大人が続出するのです。本気で競っているのは、大人(と小さい子ども)だけと言ってもいいくらい、リレーはもちろんのこと、玉入れだって事前に戦略を打ち合わせたりして真剣そのものです。
今年は私も久しぶりに参加したのですが、いつの間にかうちの町が三連覇をかけて戦っているということになっていました。連覇して特に何があるわけでもないのですが、優勝という名誉!?のためにわりと本気で競争せざるをえない状況でした。私もエントリーされた競技で、町内の皆さんの健闘ぶりに応えなくてはと、数年ぶりに全速力で(ほんの少し)走ってみました。「全力で走るって、いったい何をどのように・・?」と頭の中で??がたくさん飛び交うなか、とにかく一生懸命走ってみると、結果はどうあれ、なんだかとても清々しく、愉快ではないですか。久しぶりに味わった感覚でした。そして、これは大人にとっては本気の競争ごっこなのだろうと思い当たりました。
ふり返ってみると、子どもの頃に学校の運動会をこれほど心置きなく楽しめていたかというと、私の場合そうでもありませんでした。一番でなくていいのは百も承知でも、全力を出して競走すること自体をどこか恐れていたし、そういう恐れに圧倒されていた気がします。大人にしてみれば「たかが」徒競走でも、子どもにとっては「たかが」と言い切れない、自分全部が賭かってしまう競争のように感じられていたのでしょう。
これまで小学校の運動会で「世界に一つだけの花」が流れているのを聞くと、なぜ今ここで「ナンバーワンにならなくてもいい~♪」と唱えなくてはならないのか・・と不思議に思っていました。でも、これは「負けてもどうってことないよ、」「だから力いっぱい走ってごらん」という、競争に尻込みする子どもたちの背中を押してくれる応援歌なのかもしれませんね。
ほんものの、ここ一番の勝負で、一流のアスリートのごとく「楽しみたい」「自分との闘いに勝つ」などと言うにはまだまだ修行が足りないとしたら、せめて遊びの競争で恐れずに全力を出す感覚を愉しむのも悪くないなあと感じた一日でした。
学生サポートルームカウンセラー
2012.09.30
歩きだしてみませんか
先日、友人と話していたら、幼いころ読んだ本の話になりました。グリム兄弟の「ブレーメンの音楽隊」です。年老いて役に立たなくなり、人間から捨てられそうになったロバが一念発起し、音楽隊にでも入ろうと思い立ち、ブレーメンに向かって歩きはじめるお話です。道中で、同じく処分されそうになった年老いた犬、猫、ニワトリに出会います。ロバに誘われて、動物たちは一緒に歩きだします。本場のドイツ語圏では、ロバがニワトリを誘った言葉、「一緒に来ませんか! 死ぬよりましなことは、どこにでもみつかるさ」はとても有名だそうです。
実はこのお話は、小さいころの私にとっては、あまり印象に残らない話でした。記憶が定かでなかったので、再読してみることにしました。4匹の動物たちは、ブレーメンに行く途中で明かりがともっている家を見つけます。のぞいてみると泥棒たちが食事をしていました。お腹がすいた動物たちは、泥棒たちを脅かそうと独特の体制をとり、鳴き声の音楽で騒ぐことを思いつきます。それを実行したところ、泥棒たちはびっくりして家から逃げていきました。ご馳走を食べ、夜になり、動物たちが家で休んでいると泥棒が様子を見に戻ってきました。今度はそれぞれがひっかいたり、かみついたり、蹴ったり、騒いだりして泥棒を追い出しました。それから、動物たちはその家がとても気に入り、ずっとそこに住みました。
子供のころは、え、ここで終わり、泥棒とはいえ、人をだましていいの、そして、いったいブレーメンに行くという目標はどうなってしまったのと、もやもやした気持ちになりました。よくわからない変な話だと思ったものです。でも、最近、読んだ時はいい話だと感じました。どん底にいる動物が、ともかく行動を起こしてみる。そして、途中で同じ思いを持った動物たちと出会って、道連れになり、一緒に知恵を出し合う。目標には届いていないけれども、そもそもちょっと前の状況より、ましなことを見つけるという目的は達成したのだからいいじゃないかと思えたのです。ブレーメンに行って音楽隊に入ることは、ロバが思いついた途方もないアイデアでした。目標とは、もしかしたら、何かはじめていくうちに、最初とは少し違う形で自然と目の前に現れてくるものなのかもしれませんね。
物の見方は変わるものだなと大発見をした気持ちになりました。ふとそう思ったのは私だけかなと、インターネットで検索してみたら・・・なんと同じように思った人が結構いるではありませんか。私の大発見は一瞬でな~んだとしぼんでしまいました。でも・・・私にとって発見は発見、まあいいかと思いなおしました。
実はこのお話は、小さいころの私にとっては、あまり印象に残らない話でした。記憶が定かでなかったので、再読してみることにしました。4匹の動物たちは、ブレーメンに行く途中で明かりがともっている家を見つけます。のぞいてみると泥棒たちが食事をしていました。お腹がすいた動物たちは、泥棒たちを脅かそうと独特の体制をとり、鳴き声の音楽で騒ぐことを思いつきます。それを実行したところ、泥棒たちはびっくりして家から逃げていきました。ご馳走を食べ、夜になり、動物たちが家で休んでいると泥棒が様子を見に戻ってきました。今度はそれぞれがひっかいたり、かみついたり、蹴ったり、騒いだりして泥棒を追い出しました。それから、動物たちはその家がとても気に入り、ずっとそこに住みました。
子供のころは、え、ここで終わり、泥棒とはいえ、人をだましていいの、そして、いったいブレーメンに行くという目標はどうなってしまったのと、もやもやした気持ちになりました。よくわからない変な話だと思ったものです。でも、最近、読んだ時はいい話だと感じました。どん底にいる動物が、ともかく行動を起こしてみる。そして、途中で同じ思いを持った動物たちと出会って、道連れになり、一緒に知恵を出し合う。目標には届いていないけれども、そもそもちょっと前の状況より、ましなことを見つけるという目的は達成したのだからいいじゃないかと思えたのです。ブレーメンに行って音楽隊に入ることは、ロバが思いついた途方もないアイデアでした。目標とは、もしかしたら、何かはじめていくうちに、最初とは少し違う形で自然と目の前に現れてくるものなのかもしれませんね。
物の見方は変わるものだなと大発見をした気持ちになりました。ふとそう思ったのは私だけかなと、インターネットで検索してみたら・・・なんと同じように思った人が結構いるではありませんか。私の大発見は一瞬でな~んだとしぼんでしまいました。でも・・・私にとって発見は発見、まあいいかと思いなおしました。
学生サポートルームカウンセラー