TOPICS
2024年のTOPICS
2024.12.13



また、中央アジア5か国(カザフスタン、トルクメニスタン、ウズベキスタン、タジキスタン、キルギスタン)の魅力についてわかりやすく紹介していただき、この地域への新たな関心が高まった様子でした。

続きを読む
ゲスト講義実施報告(国連開発計画(UNDP) 駐日事務所 二瓶 直樹 様)
11月28日の「国際連合入門」(担当教員:織田靖子先生)の授業にて、国連開発計画(UNDP)駐日事務所の二瓶直樹様をお招きし、講義を行って頂きました。講義のテーマは「国連の現場での活動ーウクライナ及び中央アジアの事例より」。
二瓶直樹さんは急遽決まった2週間ほどのウクライナ出張から帰国したその足で立命館大学に立ち寄ってくださいました。
内容は、①ウクライナ(紛争・危機の中での支援)、②l日ソ連の国々(中央アジアを例に)、③国際機関で働く(どんなことが肝要か)の三部構成。各テーマ毎に受講生からの様々な質問に丁寧に誠実に答えていただきました。
特筆すべきは、空港が使えないため陸路でモルドバから入国したという経緯に続き、空爆最中の 11月現在のウクライナの生々しい状況でした。UNDPの活動に関する具体的な情報に加え、美しいキーフの街並み、対照的なインフラ破壊と援助活動の写真と実体験を交えて説明していただきました。紛争下で生きる人々の感情面の変遷など、メディアや文献などからはなかなか得ることのできない現実を垣間見ることができ、貴重な経験ができたという感想が多くの受講生から寄せられました。
また、中央アジア5か国(カザフスタン、トルクメニスタン、ウズベキスタン、タジキスタン、キルギスタン)の魅力についてわかりやすく紹介していただき、この地域への新たな関心が高まった様子でした。
講義の最後に国際機関でのキャリアについて二瓶さん自身の心構え、JICAなどの様々な国際機関、国連などの契約体系など細かな点までをお話していただきました。
終了後のアンケートからは、現役の国連職員に会い、自分自身の将来を考えるきっかけになったというコメントが多く寄せられました。
2024.12.11

国際関係学部での学びは、アフリカの民間セクター開発分野でのこれまでのキャリア、そしてUNDPへの入職を決意するに至った強い動機づけの基盤となりました(卒業生 原 祥子さん:国連開発計画(UNDP))
2024.12.02

I undoubtedly have gained comprehension from different fields of studies under the realm of International Relations studies at Ritsumeikan.(Diva Fristika Lordya)
2024.11.29




また、講演会の前の時間に、外務省や国家公務員を目指す学生を対象とした「キャリア・トークセッション」を開催しました(こちらの企画は日本語で実施)。


続きを読む
元外務事務次官 薮中 三十二客員教授による特別講演「Turbulent World and Japan」と外務省を目指す学生へ向けた「キャリア・トークセッション」を開催しました
11月28日、薮中三十二客員教授による特別講演を実施しました。
薮中先生は、外務省入省後、日米構造協議や、アジア大洋州局長として6カ国協議の日本代表を務め、北朝鮮の核や拉致問題をめぐる交渉に臨む等、数々の国際交渉を担当し、2008年には外務事務次官を務められた日本外交のエキスパートです。
2010年に外務省退官後、客員教授として立命館大学 国際関係学部・研究科の授業をご担当いただいています。
2010年に外務省退官後、客員教授として立命館大学 国際関係学部・研究科の授業をご担当いただいています。
講演のテーマは「Turbulent World and Japan—US Presidential Election, Middle East, and Asian Theater」。
英語で実施いただき、多くの国際関係学部・研究科の学生が参加しました。
薮中先生から最新の国際情勢と今後の日本外交の課題について直接お話を伺うことができる、国際関係学部生にとって大変貴重な機会となりました。
国際関係学部の学生はもちろん、他学部からも多くの学生が参加し、外務省・国家公務員を目指す上での貴重なアドバイスを薮中先生よりいただくことができました。
2024.11.26
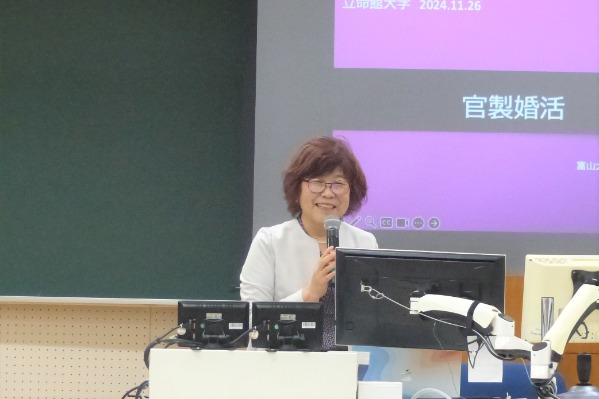


続きを読む
ゲスト講義実施報告(富山大学 非常勤講師:社会学者 斉藤正美様)
「比較家族論」(担当教員:山口智美先生)の授業にて、社会学者の斉藤正美様をゲスト講師としてお招きし、講義を行っていただきました。
斉藤先生はフェミニストの社会学者として、「官製婚活」政策について調査研究をされてこられたこのテーマの第一人者です。
講義は、「官製婚活」とは何かという説明から始まりました。国が少子化対策の一環として自治体に取り組ませている結婚支援策で、結婚に向けた機運の醸成、マッチングアプリの開発、婚活パーティーや出会いイベントの開催、婚活セミナーやライフデザイン教育、
プレコンセプションケアなど多岐にわたるものです。こうした「官製婚活」政策の流れと現状を概観した後で、京都府が進める「官製婚活」政策についても具体的に紹介し、考察していきました。
さらに、学生たちの世代がターゲットになっており、新たに最近政府によって推進されているという「プレコンセプションケア」の取り組みについて、京都府や東京都などの具体的な事例を挙げつつその問題点について論じました。
授業途中では、「官製婚活」政策についてどう思うか話し合うグループワークの時間ももち、斉藤先生は教室を周りつつ、いくつかのグループの学生たちと対話の機会を持ってくださいました。
グループワークの後、政策と婚活業界の繋がりの深さについて批判的検討を行い講義は終わりました。
「官製婚活」という言葉は初めて聞いたという学生も多く、授業後の学生たちの感想では、少子化対策のために有効とする意見も、役に立たないのではないかとする意見もあり、さまざまな反応がありました。結婚すべきという特定の価値観の押し付けになったり、「官製婚活」政策は多様な結婚や家族のあり方と齟齬があるのではないかとする意見や、LGBTQ+や外国籍の人たちを排除する政策になっていることの問題を指摘する意見もあり、「官製婚活」政策の是非や日本の少子化問題についてどう対応していくべきなのかについても学生たちが考える貴重なきっかけとなった講演でした。
2024.11.21
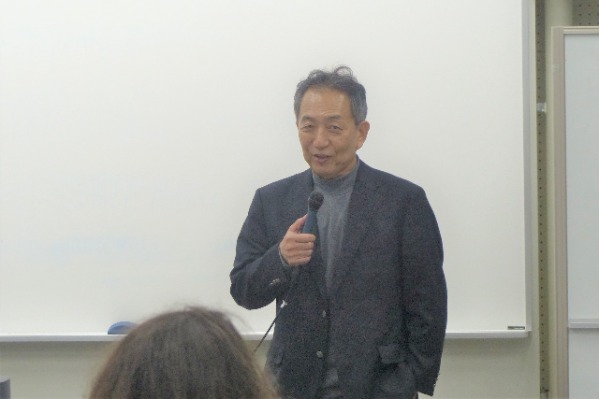


続きを読む
ゲスト講義実施報告(JICA国際協力専門員、元国連食糧農業機関(FAO)事務局長補佐 三次啓都様)
「Introduction to the United Nations」(担当教員:石川幸子先生)の授業にて、2020年12月まで4年半に渡り国連食糧農業機関(FAO)事務局長補佐(No.2)としてローマの本部で勤務されていた三次啓都様をゲスト講師としてお招きし、FAOのミッションと活動について講義を行っていただきました。
まず、授業の冒頭でFAOの話を始める前に、学生たちに国連システムに対して持っている印象や考えを問いただし、国連が多岐にわたって困難に直面している現実を共通認識として確認しました。FAOに関しては、半世紀を経て森林減少が進んでいく様子をYou-tubeの動画で確認し、環境破壊が考えている以上のスピードで進行している現実が紹介されました。地球上の陸地の3分の1が森林ですが、統計上、アフリカと南米で森林減少が顕著であるとのことです。アジアでは森林増加の傾向が示されているものの、これは、中国のみが造林を行っている結果であるとのことです。
また、カカオ、コーヒー、ゴム、パームオイル等の生産量が増加するに従って、生産に要する土地の確保のため、森林が伐採されている現状が紹介されました。
次に、FAOのミッションと活動について説明がありました。世界の食糧と農業にかかるデータを分析し、グローバル・スタンダードを基盤とした規範を作成してモニターをします。そして技術協力や能力強化のプロジェクトを実施するといった活動が紹介されました。現在、世界中で深刻となっている食糧危機については、その原因が紛争、貧困、並びに気候変動にあるという研究結果について詳細な説明がありました。ウクライナ・ロシア戦争による食糧危機はピークを越えたものの、ウクライナ国土に撒かれた地雷によって農地が奪われているとのことです。
最後に、FAOが提唱するHealthy dietについて考えました。バランスの良い食事や、安全な食について理解はできているものの、世界中の多くの人たちがhealthy dietを実行できない原因について学生たちの意見を聞きました。健康に良い食品は高価であることが多く、経済的に購入する余裕がないことが大きな原因であるなど、多くの意見が出されました。
今回の講義では、専門機関であるFAOの業務内容について理解が深まったともに、食糧に関連する課題を考える良い機会となりました。