TOPICS
2022年のTOPICS
2022.06.24
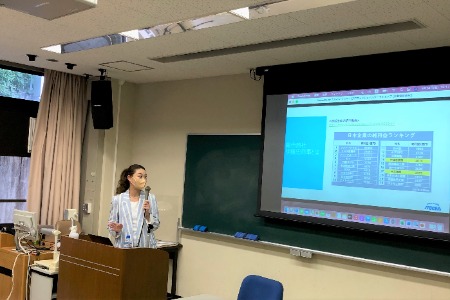
ゲスト講義実施報告(伊藤忠商事株式会社:山根のこ様)
プロフェッショナル・ワークショップ(ビジネスクラス:星野郁先生担当)にて、伊藤忠商事株式会社の山根のこ様をゲスト講師としてお招きしました。
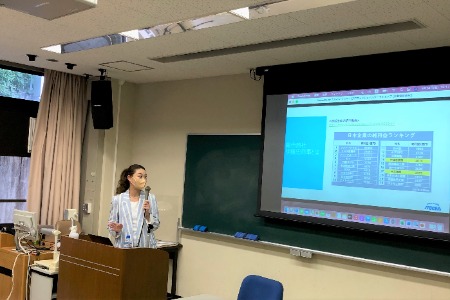

続きを読む
山根氏は、受講生の詳細な総合商社業界並びに伊藤忠商事に関する報告を受けて、主に伊藤忠商事におけるご自身の仕事について話されました。
入社以来の食料カンパニー部門に属し、当初は小麦や大麦といった原料調達・販売部門で働かれた後、現在は国内コンビニエンスストアに関する業務を担当されておられることや、総合商社の業務に関しては、取引相手の企業だけでなく、会社内の様々部門とのコラボレーションが非常に重要であり、総合商社は「ひと」が財産というだけあって、対人交渉能力やコミュニケーション能力が欠かせないことなどをお話されました。
続いて、総合商社業界企業研究担当班から出された、就活や学生時代の過ごし方、入社後の働き方、仕事のやりがい、女性社員の処遇、海外勤務等に関する質問に対して、ご自身の体験をもとに、詳しく丁寧に回答されました。
講演終了後も、就活の相談に受講生が列をなし、気軽にメールアドレスの交換に応じられるなど、盛況のうちに授業は終了しました。
2022.07.08

ゲスト講義実施報告(岩谷産業株式会社:佐伯雄大様)
プロフェッショナル・ワークショップ(ビジネスクラス:星野郁先生担当)にて、岩谷産業株式会社:佐伯雄大様をゲスト講師としてお招きしました。


続きを読む
佐伯雄大氏は、岩谷産業で3年にわたり人事部採用担当として2000人を超える学生と接してきた経験を元に、企業側から見た欲しい人材像や自身の経験を踏まえた学生時代の過ごし方、就職活動に臨むにあたって、まず自分の人生の目的や軸の確立の重要性を強調され、その上で業界・企業選びの軸、自己分析の重要性、面接への臨み方について話されました。
採用・面接に際しては、人とのコミュニケーション能力が最も重視されることや、内定獲得は通過点に過ぎず、入社して以降の働き方が何よりも重要であることを強調されました。
また、自らの10年にわたる社会人経験を踏まえ、仕事と私生活は、巷のワーク・ライフ・バランス論で言われているような、お互いに対立し合うものではなく、相互に深く結びついているものであり、うまく両立させることが重要であることを強調されました。
熱意溢れる講演に対して、受講生からも活発な質問が出されました。
2022.06.17

ゲスト講義実施報告(元青年海外協力隊:中嶋 悦子様)
プロフェッショナル・ワークショップ(国際公務クラス:石川幸子先生担当)にて、元青年海外協力隊の中嶋 悦子様をゲスト講師としてお招きしました。


続きを読む
本授業は、将来、国際機関や外交官等の職業を目指したいと考えている学部生を対象として開講されていますが、まず、国際的に活躍するためには「るつぼ体験」(自分の価値観・人生観を再構築する経験)が必要であるとの認識に基づいて、「るつぼ体験」の一例である青年海外協力隊(JOCV)の活動を紹介することにしました。
本学部卒業生の中嶋さんから、大学卒業後の就職、JOCVとしてネパールで従事した村落開発とその後の展開について時間一杯お話を伺いました。
「人のためだと思って行った活動が、結局、人生観を転換させる自分育ての活動であった」という結論が、まさに中嶋さんのるつぼ体験を物語っています。
ネパール派遣前研修では、70日間のネパール語集中講義があり、そこで身につけたネパール語を駆使して現地の人々に語り掛けている動画は圧巻でした。女性支援を中心として現地に溶け込んで仕事をする姿は「共感力」をよく表現していました。
2022.06.17

ゲスト講義実施報告(森永製菓株式会社:高草木勇人様)
プロフェッショナル・ワークショップ(ビジネスクラス:星野郁先生担当)にて、森永製菓株式会社の高草木勇人様をゲスト講師としてお招きしました。

続きを読む
高草木氏は、日本の食品業界の事情について話され、食品業界大手企業の売上高ランキングや収益率、系列などのデータを示されました。
就活に際しては、自分の入りたい会社の事情だけでなく、当該企業の属する業界、さらには、メーカーの場合、営業取引先の多くがイーオンをはじめとする大手スーパー・小売店であることから関連業界の事情についても研究しておく重要性を強調されました。
続いて、森永製菓の経営理念や業務内容、主力商品についての詳しい説明がなされ、営業で担当していた冷菓販売業務の仕事内容や、現在担当している新規事業開発部での業務について、それぞれやりがいや課題も含めて話されました。
最後に、森永製菓の今後の経営戦略やその中での自分がやりたいことなどを述べられ、受講生から寄せられた質問についても、丁寧に回答されました。
2022.06.20

ゲスト講義実施報告(多文化共生センターひょうご・代表:北村広美様)
専門演習(園田節子先生担当)にて、「多文化共生センターひょうご」の北村広美代表をゲスト講師としてお招きしました。


続きを読む
同センターは神戸市東灘区で長年、外国人住民の多様な生活支援に取り組み、2021年3月に神戸新聞主催の地域再生大賞優秀賞、同年7月に第16回国際ソロプチミスト神戸東クローバー賞を受賞されました。
北村代表の講義は、ダイナミックな語りと論理的な構成であり、日々の経験を要所に交えつつ、在日外国人の社会保障と保健医療の権利に焦点を当て、日本の法整備や制度の現状と具体的な問題、NGOによる支援の取り組みから見えてきた課題、といったトピックを学びました。
日本にはそもそも外国人を保証の対象とした法そのものが存在しないという実態があり、外国人住民が向き合う困難には現行法の運用や準用を継ぎ接ぎしながら乗り切っている現状があります。
そうした歪みに加えて、日本社会には、外国人が日本の医療保険予算を圧迫している、あるいは医療費の未払いが増えるので受診をさせたくないなど、外国人住民の社会保障に関していくつかの誤解があります。講義では、こうした歪みや誤解も紹介され、丁寧な反証がおこなわれました。
授業の最後には、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジや「平等equalityではなく公平equityを」などのグローバル基準からの有効な考え方が提示されました。
2022.06.07
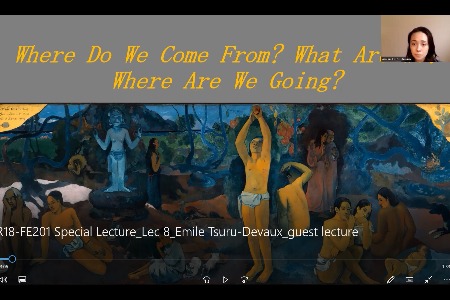
ゲスト講義実施報告(京都芸術大学准教授:都留恵美里様)
Special Lectureにて、京都芸術大学准教授の都留恵美里様をゲスト講師としてお招きしました。

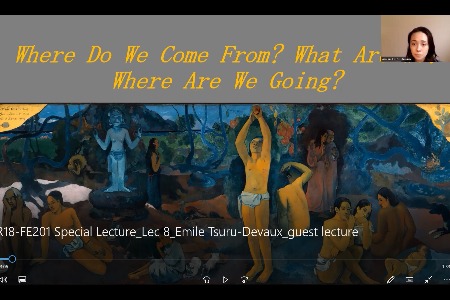
続きを読む
本授業では、エドワード・サイードの『オリエンタリズム』を読み進めることで、「他者化」の力学とその過程を考察しています。
都留先生に登壇を依頼したのは、第8回目の講義で、“Cultural Filters: Where did we come from, where we are, and where are we going?”と題した講演を行ってもらった後で、学生からのコメントや質問に応じるディスカッションを行いました。
講演では、西洋美術史におけるオリエンタリズムの潮流について紹介がなされたうえで、それが「西洋」のアイデンティティー形成に及ぼした影響と、「西洋」による「東洋」の他者化によって顕著になった課題、そして今日の国際社会が多様化する中で顕在化している「他者との共生」という課題についてお話ししていただきました。
都留先生が取り組んおられる西洋美術史研究やブラジルにおける日系人芸術家の研究から見えてきた学術的な洞察と、ご自身の日本とフランスの両国を跨いだ生い立ちや多民族国家であるブラジルでの生活経験などから得られた個人的な洞察を、バランス良く織り交ぜてお話ししていただいたので、学生にとって分かりやすく且つ多くの気付きを与えた内容になりました。
2022.06.15

続きを読む
ゲスト講義実施報告(第一生命経済研究所 主席エコノミスト:田中 理様)
国際金融論Ⅱにて、第一生命経済研究所 主席エコノミストの田中 理様をゲスト講師としてお招きしました。
今回は「国際金融論Ⅱ」10回目の講義で「欧州経済・金融」について取り扱う予定であり、それに合わせて田中氏を招聘しました。
タイトルは「ウクライナ危機にみる欧州統合の課題」。非常に時機を得たものでした。
内容は非常に豊富で、EUの起源から始まり、欧州統合の歴史、2008-12年のユーロ危機の背景及びその後の状況、さらに最近のウクライナ・ロシア及び旧東欧諸国の歴史的関係、EU加盟の問題、EUにおけるドイツの地位・役割、ロシアへのエネルギー依存状況、ウクライナ侵攻に際して加盟国の対応の相違と課題、欧州統合の今後の課題などを取り扱ったものであり、「3,4回分の講義内容を1回に凝縮した」 (田中氏) ともいえる内容となりました。
2022.07.01
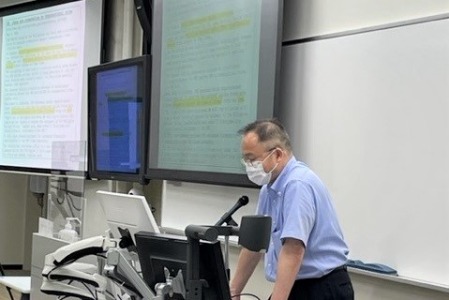
ゲスト講義実施報告(前警察庁東北管区警察局長(退官):世取山茂様)
プロフェッショナル・ワークショップ(国際公務クラス:石川幸子先生担当)にて、前警察庁東北管区警察局長(退官)の世取山茂様をゲスト講師としてお招きしました。
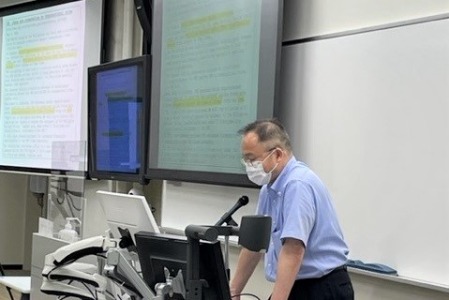

続きを読む
今回の授業では、世取山茂先生に「国際犯罪と警察の国際協力」と題する講義を行っていただきました。世取山先生は、警察庁に入庁されて以来、国内業務の他に、東ティモールにおける国連PKO活動に従事されるとともに、インターポールの呼びかけで模造・違法医薬品の広告・販売を取り締まるオペレーション・パンゲアなど数々の国際捜査のオペレーションに携われて来られた警察庁内での国際派でもあります。
講義では、まず、日本の警察による国際業務について、暴力団やその他犯罪組織の海外進出への対応、フィリピン航空434便爆破事件、拳銃や覚せい剤の密輸入等の例を挙げながら海外のカウンターパート機関と協力の上行われる捜査についての説明がありました。
次に、警察による国際協力として、東ティモールでの活動を中心に国連平和維持活動(PKO)及び、政府開発援助として実施されたフィリピン国家警察犯罪対応能力向上プログラムについて、多くの写真を共有されながら臨場感の籠ったお話がありました。
普段、警察による国際業務、及び国際協力については、お話を伺う機会に恵まれることが殆ど無い中で、今回の世取山先生の講義は、日本の国際協力について視野を広げる一助となるとともにその重要性について改めて認識する機会となりました。