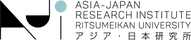所長室から
2025年も、よろしくお願い申し上げます
明けましておめでとうございます。本年も、どうぞよろしくお願い申し上げます。
昨2024年も、皆さまから、温かい応援やご支援をたくさんいただき、所員が力を合わせて1年間の活動を展開してきました。ご声援やご鞭撻に、厚く御礼申し上げます。
新しい年には、本大学における研究高度化第4期中期計画の最終年度がやってきます。4月からの新年度によって、R2030チャレンジデザインがめざしている次世代研究大学へ向かって進む10年間のちょうど半分が終わるわけで、立命館アジア・日本研究機構も、その傘下の本研究所も、第4期中期計画を有意義に完了して、その先に進むべく、研究活動、成果発信、国際連携に力を入れていきたいと思います。
この1年間をふりかえって見ると、1月にはまず、多言語国際フォーラムMeridian180のワークショップとして、「超高齢社会の新しい地域ガバナンスの構築」が実施されました。ここでの多言語は、具体的には、4言語5文字、つまり、日本語、英語、中国語(簡体字と繁体字)、韓国語を用いての報告と討議を意味しています。2011年にスタートしたMeridian180は、そこで活動展開を終えることとなりましたが、このフォーラムは非常に先進的な試みをいくつも実施し、大きな資産を私たちに遺してくれました。
本大学では、その活動を通じて広がった国際的なネットワークを発展させるために、「アジア・日本研究グローバルフォーラム」を今年から展開していきます。その初回として、2月12日に多言語フォーラム「アジアで医を語り、言葉を創出する:越境的人文研究の地平へ」を実施いたします(近日中にイベント情報をHP上で告知します)。
また、昨年2月には、年次シンポジウムを「AJIグローバル・シンポジウム」と改名して、「立命館発 これからの価値創造と私たちの羅針盤:アジア・日本研究からの発信」を開催しました。今年は、1月25日に今年の主題を「立命館発 これからの平和創出と私たちの羅針盤」として、基調報告「中東・西アジアと世界の戦乱がやむ日:平和をめざす3つの視点」と、パネル・ディスカッション「急増するアジアの移民と寛容な社会創出の課題」の2本立てでおこないます。オンライン配信いたしますので、是非、ご覧下さい(英語の同時通訳も付いています)。
言うまでもありませんが、どこの研究所でも、研究機関としての重要な役割として、学術誌を刊行して、研究成果発信の場として国内外の学術界に貢献する仕事があります。本研究所では、そのために英文学術誌2誌、和文学術誌1誌を毎年刊行してきました。
3誌それぞれの特徴については、投稿者向けのご案内をご覧下さい。
3誌それぞれの特色がありますが、日本や世界の各地でアジア・日本研究にたずさわっている皆さまから、これらの学術3誌が研究成果の発信媒体として認知いただいて、嬉しい限りです。3誌とも厳格な査読システムを採用して、J-STAGEにも登録されており、成果発信の役割をしっかりと果たせているかと存じます。このことは、編集委員会、編集部にとって、おおいに励みとなっています。
さらに、新しい成果発信の媒体として、『アジア・マップ:アジア・日本研究Webマガジン』を2023年に創刊し、昨年は、国会図書館から、定期刊行物として認知され、ISSN(国際標準逐次刊行物番号)をいただくことができました。
「アジア・マップ」という、地図をクリックしてコンテンツにつながる新しいスタイルは、学術的な発信としては斬新な形でしたが、原稿を執筆いただくアジアの専門家の皆さまからも、このスタイルが気に入っていただけたようで、それも嬉しいことです。
新しいスタイルと言えば、研究者エッセイ・シリーズも、「アジアと日本:ことばの旅」シリーズが開始され、また「学術エッセイ」シリーズも、新たなシリーズとして創刊されました。是非、ご覧ください。
国際連携も、2024年には、新しい展開がありました。中国の浙大城市学院、ベトナムのノンラム大学、インドネシアのブラヴィジャヤ大学、インドネシア国際イスラーム大学、マレーシア国民大学、オーストラリア国立大学などと緊密な研究連携、共同研究が展開されました。
コロナ禍で海外との交流が3年間も制限されていた間は、大変つらい時期でしたが、その間にもDX(デジタルトランスフォーメーション)を活用した国際連携を続けることができました。国際人流の制限がなくなった現在、いっそう多角的で広域的な学術交流を展開していきたいと思います。
昨年度の国際連携の中で特筆すべきは、11月にジョホール・バル(マレーシア)で開催された第2回「イスラーム/ハラール経済研究国際会議」において、「イスラーム/ハラール経済研究国際コンソーシアム」が設立され、本大学もそれに加わって、幹事校の1つとなったことです。このコンソーシアムはアジアから、ヨーロッパ、アフリカなどへとネットワークを拡大中で、新しい国際的な研究連携を実のある形で展開したいと願っています。
若手研究者育成では、「大学院連携・次世代研究者育成プログラム」も4年目に入り、昨年は、そのプログラム・メンバーをはじめとして、いく人も、若手が専任ポストを得て、巣立っていきました。
そのような朗報をお知らせするために、ホームページ内に、朗報コーナーを設けましたので、どうぞ、ご覧ください。
本大学では、教学と研究の拡大的再結合ということで、研究の成果を大学院に還元する仕組みを強めています。今年は、それがいっそう強化されることが見込まれますので、研究所としても、おおいに貢献すべく、いろいろな構想を練っています。乞うご期待、というところでしょうか。
そのほかにも、本研究所のいっそうの発展をめざして、さまざまな活動を企画しています。皆さまにも、順次、お知らせいたしますので、研究所ホームページをご愛読ください。
本年も、どうぞご支援・ご鞭撻をよろしくお願い申し上げます。
(2025年1月1日)