「第86回:日々の学びで出会いの準備を整える」西谷 順平先生(経営学部)
インタビュー:学生ライブラリースタッフ 石上・北村・渡邉・中北
2022.06.08

――西谷先生の研究テーマである、会計基準設定の経済分析について教えてください。
会計とは、“説明する学問”です。会計は英語でaccountingと書くのですが、accountとは、account forで「説明する」という意味です。したがって、説明責任全般が会計に入ります。今だと、環境会計という環境基準に関する会計や、人材に対してコンプライアンスを守り、労働者に対してきちんと優しい企業経営をしているという説明責任などについても会計の範疇に入ってきます。しかし、企業には様々なタイプがあるため、放っておくと基本的には説明が足りない状態になるのです。どうしても情報が足りない。したがって、基準や規制を作り、企業に会計情報や、環境に関するデータを出すこと、説明することを求めなければ社会が回らないです。社会をきちんと回していくためには、そのような情報を社会に出させなければならない。その説明責任に対する基準を経済的にどのように決めていけばいいのか、あるいは、もちろん経済と政治は裏表一体ですので、政治の問題があるとするとどのようなことが問題なのかということを研究しています。
――どのような経緯でこの研究テーマに取り組もうと思われたのか、その関心をもたれたきっかけを教えてください。
実は大学での専攻は国際経済学で、1年生の時から国際経済に関係するサークルにも入っていました。国際経済学の難しい本を大学院の先輩と読んだり、国連の人を呼んでイベントをしたり、NGOから情報をもらったりしました。実際の現場では、貧しい人がいるからこそ儲かる商売など、より複雑な世界を目の当たりにしました。リアルな国際経済は美しい理論だけではないことを間近に見せられた経験が大きく、やればやる程、理論でする国際経済論よりは何か自分自身が力をつけられるような勉強をしたいと強く思ったのです。そこで、大学院に入ってから少しずつ会計学の授業にも出るようになり、出会いがありました。私の3歳上で趣味趣向も似ている先輩が、「迷ってないで会計学に来いよ、なんでも教えてやる」と言ってくれたのです。22、3歳が25、6歳に「ついていこう」とは、今考えたら「どうなの?」という感じがします。しかし、その人と話す度に目が開かれるような思いがし、この人についていこうと思い、会計学に大学院の途中で切り替えました。
――そのような中で西谷先生ご自身が影響を受けられた本について教えてください。
若い時に読んだ本がやはり一番強烈に残っており、作者をあげると一番影響が大きかったのは村上春樹です。私が芦屋に住んでいた頃、本屋に居たらとあるおじさんが来て、「息子が今こういうエッセイ書いてるから読んでみて」と言われました。それが村上春樹のお父さんだったのです。それから彼の本を読み始めたのですが、『ノルウェイの森』は高校生の時に読み、涙が出ました。他には三浦綾子の『道ありき』という本です。三浦さんがどのように自分の道を見つけたのかという内容です。また、「尊敬する人は誰ですか」と言われたら「勝海舟」とよく言うのですが、子母澤寛の『勝海舟』もよく読んでいました。
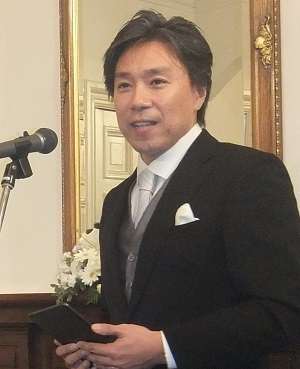
――学生時代、先生はどのように図書館を利用されていましたか。
私が大学生の頃はインターネットが無かったため、図書館はたまり場でもあり、勉強する場所でもありました。大学院の試験や卒論の試験のための勉強をする時は、映画のように周りに本を並べて図書館に籠っていました。大学の図書館にはありとあらゆる本があり、巡るだけでもとても楽しかったです。大学院に入ると、学部時代に通っていた総合図書館ではなく、学部ごとの専門の図書館を利用するようになりました。そこでは、100年前の本や雑誌を渉猟するような日々を送っていたのですが、誰も手をつけていない本であるため、開くたびに埃が出てくるのです。そんなことを繰り返し、途中からはマスクをするようにはなったのですが、肺を悪くしました。しかし、それもいい思い出ですね。
――大学生におすすめしたい本を教えてください。
一般的に言うと、大学生にとって決定的に足りなくなるものは小説です。専門の勉強というのは知識です。整理されたものであり、なおかつロジカルです。けれど、皆さんのような若い時に一番読んでいて刺さるのは感性に訴えるものだと思います。小説を読んでいないと、創造性や心の遊びの部分が無くなったり思い詰めてしまったり、将来的なダメージが大きいと思います。小説はかなりフリーハンドであり、結論はあるものの解釈や思いはそれぞれ読者に任されています。そのような想像力を膨らませることにきちんと若い時から慣れていないと、視野の狭い大人になってしまいます。小説を読んでいない人が増えると、社会は堅苦しくなるため、社会のためにも小説を読んで欲しいと思います。おすすめするとすれば、サリンジャーの『ライ麦畑でつかまえて』です。『キャッチャー・イン・ザ・ライ』のタイトルで村上春樹訳も出ています。主人公がかっこよくないのですがそういうものを読んで欲しいと思います。あとは、小説というよりも半分リアルなのですが、三浦綾子の『塩狩峠』。軽く読むのであれば、村上春樹の『風の歌を聴け』は本当にすぐ読めます。自分のことを幼いと思っている人はボブ・グリーンの『十七歳』という本もおすすめです。専門的な本はすぐに廃れてしまうため、むしろ専門性を高めるためには、小説を読むべきだと思います。

――先生のゼミではどのような活動を行っていますか。
西谷ゼミでは、基本的にはアメリカの公認会計士をめざすような勉強、あるいは企業に入り国際的な財務や会計ができるような人材を育てており、その一環として3回生の時にはシンガポールに連れて行きます。ビジネスの世界観を実地で学んでもらうのです。シンガポールにも立命館大学のOB会があり、世界を相手にしながら働いている先輩から実際の苦労や楽しいことを聞かせてもらいます。学生に夢を掴みとるためのきっかけにしてほしいと思っています。4回生の時は、また違う世界ということで北京に連れて行きます。ところが、それがコロナで全部ダメになりました。本当にショックです。
――今はオンラインで開催されているのでしょうか?今のゼミ活動を教えてください。
オンラインというものに私が早く対応できたということもあり、反転授業を導入することができました。反転授業というのは、学生が家で勉強してきて、教室に来たら勉強してきたことで議論したり、質問しあったりする形態の授業です。私が、家で勉強する素材をYouTubeなどの動画で撮っていたため、それを利用できるようになりました。そのようなスタイルによって、今の3回生の新しいゼミの子たちというのはとても集中度の高い、強度の高い勉強をしていると思います。
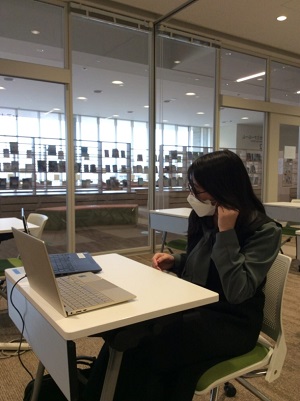
――最後に学生に向けてメッセージをお願いします。
人との関わり方の本かな。誰かから教わることはあまりないと思うので。クラブ活動やアルバイトをしている場合は、こういう話し方が良いよとか、いろいろと教えてもらえるかもしれないけど、それはわずかな話だと思います。だから、ビジネスにおける礼儀やマナーについて書かれた本の内容を知っておくと、役に立つかもしれませんね。どんなお仕事をするにしても大切だと思うので。人との関わりの中で、何か物事を作ったり、進めていったりするのであれば、コミュニケーションスキルを身に付けておいて損はないと思います。誰かにお願いしたいときや逆にお願いを断りたい場面でも、コミュニケーションスキルを活用して相手に嫌な思いをさせず上手に断れたら、とてもハッピーだと思いませんか? 相手が不快に思わず「忙しいなら違う人に頼むね」と言ってくれた方が場はスムーズになるでしょう。きっと皆さんが働き出したらそんな経験がでてくると思います。
今回の対談で紹介した本
『キャッチャー・イン・ザ・ライ』、J.D.サリンジャー [著] ; 村上春樹訳、白水社 、2003
『塩狩峠』、三浦綾子、新潮社 、1987
『風の歌を聴け ; 1973年のピンボール』、村上春樹、講談社 、1990
『十七歳』、ボブ・グリーン著 ; 井上一馬訳、文藝春秋 、1994
