TOPICS
最新のTOPICS
2025.06.27

ゲスト講義実施報告(テレビ東京 芳賀 愛麗様)
「プロフェッショナル・ワークショップ」(担当教員:星野 郁先生)の授業にてテレビ東京の芳賀 愛麗様をお招きし、講義をしていただきました。


講演を受けて、受講生からは活発な質問が出され、テレビ業界、なかでもテレビ東京を選んだ理由は何か、学生時代の経験は現在の仕事に活かされているか、入社前と入社後でギャップはないか、といった質問が寄せられ、盛況のうちに講演は終了しました。
続きを読む
今回ゲスト講師にお呼びした芳賀 愛麗さんは、2017年3月に国際関係学部を卒業し、テレビ東京に入社、アニメ販売部門を経て、現在ビジネス・ニュース制作・配信部門(ワールド・ビジネス・サテライト)担当のディレクターとして活躍しておられます。
当日は、まず受講生によって、マスコミ業界、続いてテレビ業界の紹介が行われ、テレビ東京と、フジテレビや日テレ、テレビ朝日、TBSといった同業者との経営比較がなされた後、芳賀氏のご講演に移りました。
講演はテレビ東京へ入社以来、ご担当された業務の内容についてお話いただきました。
入社当初は、Narutoをはじめとするテレビ東京のアニメを海外に販売する業務をご担当され、世界の色々な国々向けの営業に飛び回られたご経験をお話いただきました。
本年4月より、テレビ東京の番組制作部門(ワールド・ビジネス・サテライト)に移られ、ディレクターとして、番組のニュース作成・配信業務に携わっておられ、同業他社の大手テレビ局に比べて、新人でも責任のある仕事を任され、日々多様な業界への取材や、大手企業・内外の公的機関のトップへのインタビューなど、大変ではあるものの、刺激に満ちた環境で働いておられることをお話いただきました。
最後に、ご自身の就活についてもお話いただき、中国やイギリスなどへの留学のため、同期と比べやや就活開始時期が遅れたものの、テレビ局や総合商社など、比較的業界を絞って活動されたことや、決められたルーティンの仕事をこなすのではなく、幅広く色々な仕事ができるという観点から、テレビ東京を就職先に選び、多忙ではあるものの、現在の仕事には満足している旨が語られました。
2025.06.26
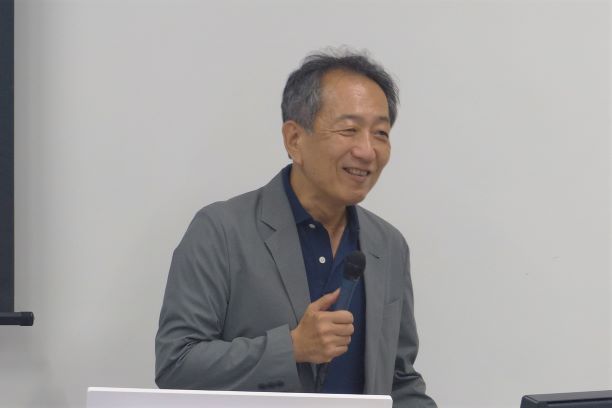
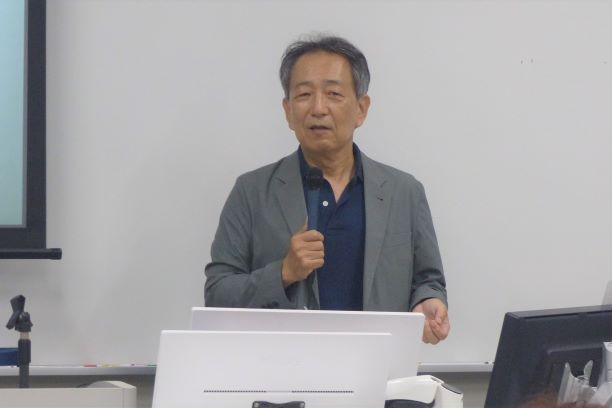

次に、森林破壊をテーマとして取り上げた。半世紀を経て森林減少が進んでいく様子をYou-tubeの動画で確認し、環境破壊が考えている以上のスピードで進行している現実が紹介された。地球上の陸地の3分の1が森林であるが、統計上、アフリカと南米で森林減少が顕著である。アジアでは森林増加の傾向が示されているものの、これは、中国のみが造林を行っている結果であるとのこと。また、カカオ、コーヒー、ゴム、パームオイル等の生産量が増加するに従って、生産に要する土地の確保のため、森林が伐採されている現状が紹介された。
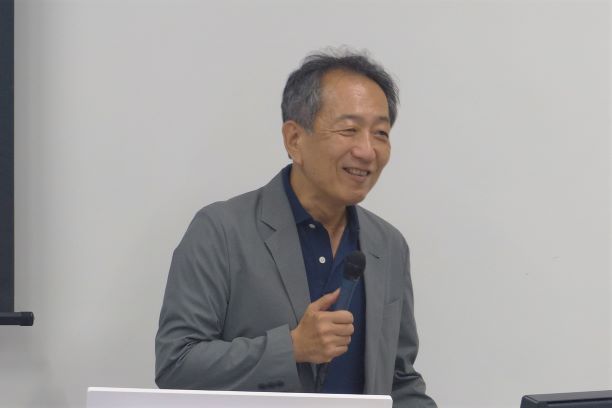
続きを読む
ゲスト講義実施報告「FAOのミッションと活動」(JICA国際協力専門員、元国連食糧農業機関 事務局長補佐 三次 啓都様)
「国際連合入門」、「Introduction to United Nations」(担当教員:石川 幸子)の授業にて、2020年12月まで4年半に渡り国連食糧農業機関(FAO)事務局長補佐(No.2)としてローマの本部で勤務されていた三次啓都氏をお招きして、FAOのミッションと活動について講義を行って頂いた。
まず、授業の冒頭でFAOの話を始める前に、国連システムについて簡単におさらいした後、国連が多岐にわたって困難に直面している現実(特に平和と安全保障分野)を共通認識として確認した。
FAOについては、戦略枠組みとして“Four Betters”(better environment, better life, better production, and better nutrition)を掲げて活動している旨の説明があった。FAOは、毎年、Food Security and Nutrition in the Worldというレポートを発行しているが、その中でもfood accessibility が問題になっている。これは、食料と購入する現金がないという側面と、所謂healthy dietを実現できないという側面を持っており、栄養失調は、栄養不足、肥満、微量栄養素不足という3つの課題を抱えている。
また、世界の食糧危機は、環境問題、経済危機、並びに紛争が3大原因となっているとのこと。紛争については、ウクライナとロシアの戦争を例に挙げ、2大農業国間の戦争が、どの程度世界の食糧危機にネガティヴな意味で貢献しているかについて説明があった。
最後に、healthy dietについてグループディスカッションを行った。学生たちの回答にはユニークなものが多く、例えば、“レポートや試験で自炊する時間がないので、ファストフードで済ませているが、これはacademically healthy dietだ”というものや、“自分が食べたい物を食べることでmental healthを保つことができる”といった意見が挙げられた。
今回の講義は、FAOの機能を理解すると共に、食糧危機や環境破壊という関連の課題について理解を深める、大変良い機会となった。
2025.06.24


続きを読む
2025年度「グローバル・シミュレーション・ゲーミング」本番を6月21日に実施しました。
GSGは、受講生が「国家」「国際機関」「NGO」「メディア」などの国際社会に実在する主体に扮し、実際の国際問題を解決するために擬似的に国際交渉を体験する科目です。2025年度のテーマは「安全保障」であり、受講生はこのテーマに基づいて交渉を行いました。
当日は、354名の2回生が58のアクターに分かれ、GSGをスタートしました。日本語基準の国際関係学専攻(IR専攻)と英語基準のグローバル・スタディーズ専攻(GS専攻)の学生が合同で英語で実施し、専攻を超えた学びや学生間の繋がりが深まりました。
受講生は、4月から6月にかけてクラスごとの授業と受講生全体での授業を組み合わせる形で事前学習を行いました。1つのアクターは5~8人で構成され、アクター内で役職(大統領、外務大臣など)を決めるなど役割分担を行い、他アクターとの国際交渉に備えました。
本番では、1セッションを現実社会の1年とみなし、1日で2セッションを行いました。学生たちは国連総会をはじめとする多様な国際会議を開催し、課題解決に向けて積極的な国際交渉を進めました。また、メディアアクターがニュースで報道するなど、各アクターがそれぞれの特長を活かした活動を行いました。
GSGを通じて、学生たちはTVやニュース等で見ているだけでは学ぶことができない「国際交渉」の難しさやリアルを実体験することができました。この経験は、現実世界で起きている国際関係の事象が何故起きているのかを複眼的な視点から考える力を身につけると共に、3回生以降の自身の学びやキャリアの方向性を考えるきっかけとなりました。
2025.06.23



続きを読む
ゲスト講義実施報告(弁護士 上瀧 浩子様)
「専門演習」(担当教員:山口 智美)では、日本社会・文化に関する多様な課題を取り上げています。本ゼミ初めてのゲストスピーカーとして、京都弁護士会所属の上瀧浩子弁護士をお招きし、「ヘイトと闘う」をテーマにお話しいただきました。
講義ではまず、上瀧先生がこれまで弁護士として関わってこられた「京都朝鮮学校襲撃事件」「徳島県教職員組合襲撃事件」「李信恵氏複合差別事件」などの事件について、その経緯についてお話しいただきました。そして、これらの事件において、具体的にどのようなヘイト攻撃が行われたのか、また裁判闘争にどのような社会的意義があったのかについて詳しい解説がありました。
特に上瀧先生が強調されたのは、レイシズムとセクシズムの交錯という問題であり、在日女性をはじめとするマイノリティ女性がヘイトの標的とされやすい構造についてです。また、ヘイトに対する抗議行動であるカウンター運動の経緯やその意義についても解説がありました。
「ウトロ放火事件」や「コリア国際学園放火事件」など、近年の深刻なヘイトクライムについて、さらには選挙を利用したヘイトスピーチやSNS上での差別的言動の広がりや、現在広がっている「日本人ファースト」といった排外主義的言説の問題への言及もありました。
学生たちにとっては、京都朝鮮学校襲撃事件やウトロ放火事件のような近隣の地域で起きた出来事であっても、今回初めて知る内容も多かったという声が多く聞かれ、マイノリティへのヘイトに対する闘いについて学び、考えることができた貴重な機会となりました。
排外主義が強まる現在の日本において、レイシズムやセクシズムをめぐる歴史や現状について学び、差別に反対していくことの重要性を再認識することができました。
2025.06.20


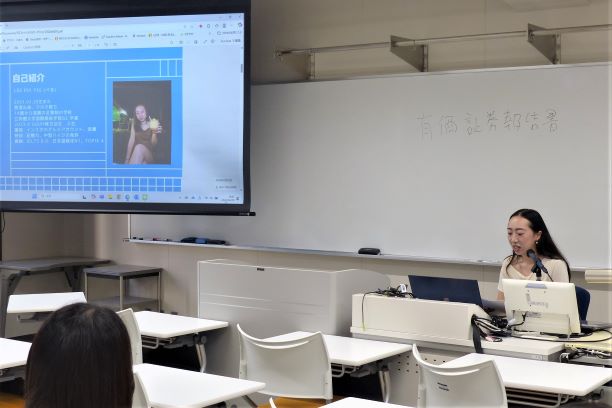
大学のキャリア教育はこれまで「良い会社」に多数の学生を就職させることを第一目標として設計されていたので、ゲスト講師の方々には、学生時代の就職活動の振り返りや、入社後の仕事の魅力などについて話してもらうことを中心としてきましたが、多くの若者が就職後に短期間で転職に踏み切ることが「当たり前」となった現在、学生が就職後の転職まで見据えて人生設計できる力を養成することが重要になっています。
続きを読む
ゲスト講義実施報告(UUUM株式会社 Lee PUI YIU様)
「プロフェッショナル・ワークショップ(メディア)」(担当教員:白戸 圭一先生)の授業にてUUUM株式会社 Lee PUI YIU様をお招きし、講義をしていただきました。
香港出身のLeeさんは2023年3月の本学卒業後、ユーチューバーのマネジメント企業であるUUUm社に就職し、海外企業等に対してユーチューブ番組に広告を出すよう売り込む業務等を担当してきました。
学生たちと歳の近い社会人であることから、在学時の就職活動の経緯や現在の日常についてパワーポイントを使った説明は、受講生の学生たちに強い関心を引きました。また、ユーチューバーの人々との間でどのような仕事が行われるかについての話は、テレビよりもユーチューブを視聴しながら日々を暮らしている現在の学生たちには殊更に興味深いものであり、受講生たちは身を乗り出してLeeさんの話を聞いていました。
大学のキャリア教育はこれまで「良い会社」に多数の学生を就職させることを第一目標として設計されていたので、ゲスト講師の方々には、学生時代の就職活動の振り返りや、入社後の仕事の魅力などについて話してもらうことを中心としてきましたが、多くの若者が就職後に短期間で転職に踏み切ることが「当たり前」となった現在、学生が就職後の転職まで見据えて人生設計できる力を養成することが重要になっています。
そこで、今回の授業では、実験的試みとして、講師に退職・転職についての経験も話していただきました。
2025.06.20



続きを読む
ゲスト講義実施報告「国際犯罪と警察の国際協力」(元警察庁:世取山 茂様)
「プロフェッショナル・ワークショップ」(担当教員:石川 幸子)にて、「国際犯罪と警察の国際協力」について、元警察庁で国際犯罪業務及び国際協力に携わってこられた、世取山茂氏をお招きし、講義を依頼した。
まず、恒例の質問として、警視庁と警察庁の違いについて学生たちに尋ねた。今回は完璧に両者の違いを説明できる学生がいたことに世取山氏も驚いた様子であった。
「警視庁」は、東京都の警察業務を行う一方で、「警察庁」は国の機関であり、国家公務員となる。警察庁による国際業務は、外国捜査機関との連絡・調整・交渉と、国際協力の2分野に分類されるとのこと。世取山氏からは、自らが関与した国際業務について具体的かつ丁寧に説明があったので、普段、報道だけでは分からない細部の情報と共に、警察がどのように動くのかについても理解が促進した講義であった。
外国捜査機関との連絡・調整・交渉の分野では、リビア政府によるパンアメリカン航空103便爆破事件について触れ、日本人も同乗していたことから国際共助要請を出したという話から、天皇在位60周年記念金貨偽造事件についても、各国の調査機関との連携を行った。
それに続き、フィリピン航空434便爆破事件、拳銃密輸入事件、インターポールと協力して行ったオペレーション・パンゲア(模造・違法医薬品の取り締まり)、並びに覚醒剤密輸入事件など、多くの事例が紹介された。
国際協力の分野では、東チモールでの国連PKO(UNMIT)に参加した際には、助言・指導・監視が業務であったため(日本のみがこのような特殊なマンデートを有しているとのこと)、PKOのトップや東チモール政府関係者への助言が主な業務であったとのこと。
政府開発援助でフィリピン国家警察犯罪対応能力向上プログラムでは、指紋による調査技術の向上等について携わってきたとの説明があった。
授業内ではグループディスカッションも行い、トピックは「日本の警察の国際協力の特徴は何か?(優れた展、及び改善すべき点は何か?)。日本に求められている国際協力とはどのようなものであるか?」であった。
学生からは、何故、キャリアとして警察庁を選んだのか?というプライベートな質問から、国外犯の処罰について、サイバー攻撃への対応など、数多くの質問が出され、1つ1つ丁寧に対応いただいた。
2025.06.20


まず、国連の基礎的な内容についてクイズ形式の質問があり、授業のアイスブレイクとなった。また、UNHCRと国連人権高等弁務官(UNHHR)の2名のみが使用を許されている“高等弁務官”は、緊急時などに独自に決断を下すことが出来るという特殊な地位にあることが説明された。

続きを読む
ゲスト講義実施報告「UNHCRの活動:現場の事例を中心に」(元UNHCR 中央アジア地域事務所所長:織田 靖子様)
「国際連合入門」(担当教員:石川幸子)にて、2年前に国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)を早期退職された織田靖子さんをゲスト講師にお迎えして、「UNHCRの活動:現場の事例を中心に」というタイトルで講義を行って頂いた。
UNHCRの必要予算は年間106億ドルであるが、これは「この金額まで集めて良い」という意味であり、実際に各国の拠出金で集まるのは、毎年その半分程度であり、慢性的な予算不足の中で業務を行っているとのこと。実際に、2024年には45%しか集まらなかった。
最大のドナー国であった米国が国際協力予算を大幅に削減している現在、今後の見通しは暗いとの説明があった。UNHCRが保護の対象とするのは、庇護申請者、難民、無国籍者、国内避難民、並びに自主帰還で自国に戻った人たちであり、現在その数は、1億2000万人に迫っている。パレスチナ難民の救援活動には国連パレスチナ難民救済機関(UNRWA)が当たっており、活動地域は、ヨルダン、レバノン、シリア、ガザ、ヨルダン川西岸に限定されている。職員数2万8000人の内、99%はパレスチナ人である。
奇しくも6月20日は世界難民の日となっている。現在、多くの難民を輩出している国は、ベネズエラ、シリア、パレスチナ、アフガニスタン、ウクライナの順である。2024年12月にアサド政権が崩壊したシリアでは、復興の時期になったが、国連には支援する予算がないのが現状であるとのこと。
講義の最後には、織田さんが実際に勤務されていた南スーダンやウガンダの写真を見せながら、臨場感あふれた話が展開された。南スーダンの洪水発生時には、難民のみならず、現地の村人たちも含めた支援を行ったとのこと。また、新型コロナ肺炎が蔓延していた当時、ウガンダの奥地の村までWHOのワクチンが届けられ、国際機関の存在意義を再認識したとの話があった。
2025.06.20



続きを読む
ゲスト講義実施報告(NEC株式会社:水間ゆり様)
「プロフェッショナル・ワークショップ」(担当教員:星野 郁先生)の授業にてNEC株式会社の水間ゆり様をお招きし、講義をしていただきました。今回ゲスト講師にお呼びした水間ゆり氏は、2022年9月に国際関係学部を卒業し、現在NECの通信部門に所属・勤務しています。
当日は、まず受講生によって、日本の総合電機メーカー業界の状況、NECの概要、NTTや富士通などライバル企業との経営比較に関する報告が行われました。
続いて、水間様の自己紹介に始まり、現在のNECでのお仕事の内容、就活への取り組み、NECを就職先に選んだ理由、後輩への助言等について話されました。
自己紹介では、立命館大学での学びや課外会活動(ボランティア・サークル)および、叶わなかったロシアへの留学等について語られました。次に、NECの会社概要と現在の業務の説明に移り、NECの経営の中心が、既にモノづくりから、IT・通信分野、防衛・宇宙へシフトし、ご自身はNTT西日本向けの通信機器の納入業務を担当されていることや、現在開催中の大阪万博に出展していて、毎週通われていることなどを話されました。
ご自身の就活については、ロシアへの留学をコロナ禍によって断念せざるを得ない中での就活で、必ずしも十分な準備ができない中で、幅広く業界研究もできなかったが、社風や業務内容、面接時の応対等で最終的に決められたとのことでした。また、十分に就活できなかったご自身の体験を踏まえて、受講生にはなるべく早めに業界・企業研究を始めることを勧められました。
受講生からは活発な質問が出され、企業の社風、社員の雰囲気を知るにはどうしたら良いのか、ワーク&ライフ・バランスは取れているか、1日の勤務スケジュール、セクハラなどハラスメントはないのかといった質問が寄せられました。
最後に個別の相談の機会が設けられ、盛況のうちに講演は終了しました。