TOPICS
2023年のTOPICS
2023.6.30
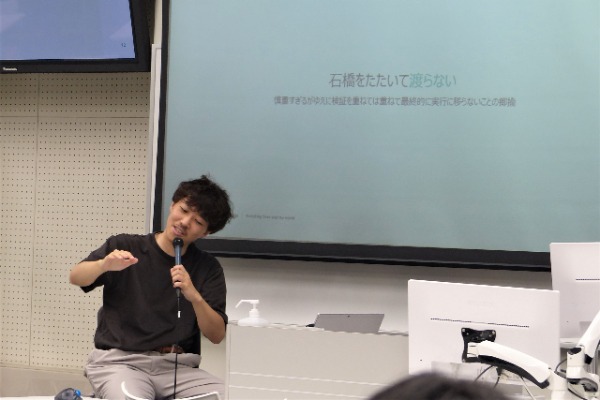


続きを読む
ゲスト講義実施報告(住友商事 建機販売事業第2部 加藤稚日志様)
「プロフェッショナル・ワークショップ(ビジネス編)」第3回目のゲスト講師講演は、
2020年3月に国際関係学部を卒業し、現在住友商事、建機販売事業第2部で働かれている加藤稚日志氏をお招きしました。
ご講演に先立ち、総合商社の就職を志望する受講生から、業界企業研究の成果報告として、いわゆる5大総合商社の中で中堅に位置する、住友商事の業務概要や、社員の処遇や働き方、同業他社との違い等について説明がありました。また、報告班からは、加藤氏に対して、住友商事を就職先に選んだ理由や総合商社が求める人材像、業務内容や入社前と入社後の印象の違い、就活への取り組み等に関する質問が出ました。
受講生による業界企業研究報告に対しては、加藤氏からは、社会人4年目に入った先輩の立場から、ネットで得られる情報だけでなく、数字やデータに基づくより深い分析の必要性が指摘されました。
続く講演では、住友商事で現在担当している建設機械販売に関する業務内容の解説や大学時代の過ごし方、就活への取り組み方、内定獲得に至る経緯と現在の仕事のやりがい、他の総合商社との違い、そして後輩たちの就活へのアドバイス等について話されました。講演の後、質疑応答に移りましたが、フロアからは、学生に人気だが狭き門である総合商社で内定を得るためにやっておくべきことや、必要な英語力の水準、海外赴任の機会や頻度などについての質問が出ました。
加藤氏は、それらの質問に丁寧に答えると共に、総合商社に限らず、民間企業では具体的な数字で成果が求められることや、国際関係学部生であっても簿記や財務など一定の専門知識を身につけておいた方が良いこと、自分はそうではなかったが、就職活動は早く始めた方が良いこと、面接にあたっては、面接官との会話のキャッチボールや話の一貫性が重要であり、キャリアセンターの模擬面接など大学の
サポートを積極的に利用すべきことなどを語られました。受講生は、加藤氏の率直な語りに魅せられると同時に、面接をはじめ就活への取り組みに貴重な示唆を得ることができたように思われます。
2023.06.30



続きを読む
ゲスト講義実施報告(わかやまeかんぱにい理事 中嶋悦子様)
「プロフェッショナル・ワークショップ」(担当教員:石川幸子先生)の授業にて、わかやまeかんぱにいにて理事をされている中嶋悦子様をゲスト講師としてお招きしました。
本授業は、将来、国際協力や外交官等の職業を目指したいと考えている学部生を対象として開講されていますが、まず、国際的に活躍するためには「るつぼ体験」(自分の価値観・人生観を再構築する経験)が必要であるとの認識に基づいて、昨年に引き続き「るつぼ体験」の一例である青年海外協力隊(JOCV)の活動を紹介する目的で、本学部の卒業生である中嶋さんをお招きし、大学卒業後JOCVに応募するまでの経歴、JOCVとしてネパールで従事した村落開発、並びにその後の展開についてお話を伺いました。
「人のためだと思って行った活動が、結局、人生観を転換させる自分育ての活動であった」という結論が、まさに中嶋さんのるつぼ体験を物語っていました。ネパール派遣前研修で身に着けたネパール語を駆使して現地の女性たちに語り掛けている動画は、それを観ている学生たちに「自分たちの可能性を開花させることに自信を持て」と言わんばかりの説得力を持っていました。中嶋さんはJOCVの活動を契機として、帰国後も積極的に地元での国際協力、SDGs促進活動に取り組んでおり、若い時の「るつぼ体験」の効果を体現している講義でした。
本授業のTAである研究科2回生の学生は、この秋からJOCVの訓練を経てアフリカの認知に派遣されることが決まっています。他のゼミ生も応募を検討しており、若者の「るつぼ体験」願望が広がりつつあること を感じています。授業後、応募を検討して書類の準備を進めているゼミ生に対しても、個別に中嶋さんからアドバイスを頂戴する機会もあり、同窓の先輩JOCV体験談は、学生たちに親近感をもって受け止められ、履修生に自分たちの可能性を信じさせるのに大きな効果があったと考えます。
2023.6.30



続きを読む
ゲスト講義実施報告(UNFAO顧問 兼 独立行政法人国際協力機構(JICA)国際協力専門員 三次啓都様)
「国際連合入門」(担当教員:石川幸子先生)の授業にて、2020年12月まで4年半にわたり国連食糧農業機関(UNFAO)の事務局長補としてローマの本部に勤務され、現在は、UNFAOの顧問兼、独立行政法人国際協力機構(JICA)の国際協力専門員として活躍されている三次啓都氏をゲスト講師としてお招きしてUNFAOの仕事について講義を行っていただきました。
まず、国連システム内のFAOの位置づけと、専門機関の役割と機能について説明があった後、FAOが担当する業務について講義が行われました。
FAOはSDGsのナンバー2,5,6,12,14並びに15を重点的に担当しており、”ゼロ・ハンガー“と”ゼロ森林破壊“を掲げて環境・社会・経済の循環を重視しながらプロジェクトを実施しているとのことでした。
次に、喫緊の課題である食糧安全保障については、どれだけ食糧があるか、それにアクセスできるのか、加工できるのか、安定的に供給できるのかの4点が重要であり、特に、COVID-19で物理的、経済的に食糧にアクセスすることが困難になったとともに、現在では世界の紛争が食量危機の最大の原因になっているとの説明がありました。
最後に、森林伐採について、アジアやヨーロッパでは森林面積が増えているのに対し、アフリカと南米では劇的に減少しているとの説明があり、その80%の原因は農業であるとの指摘がありました。
授業終了後には、多数の学生が質問の列に並びました。彼らの質問は森林伐採の現状、食料危機の現場での国連職員の役割と心構え、FAOの職員になるための準備等、学生の質問の内容は多岐に渡っていました。
FAOの内部で仕事をした経験に裏付けられた講義は大変興味深く、学生たちの好奇心と学習意欲を刺激するものでありました。
2023.06.26

続きを読む
ゲスト講義実施報告(日本社会事業大学 非常勤講師 橋本恭子様)
「東アジア研究A」(担当教員:園田節子先生)の授業にて、橋本恭子先生をゲスト講師としてお招きし、台湾のフェミニズムとレズビアン・フェミニズムを地域研究の視点から講義を行って頂きました。
比較文学、台湾文学を専門とされる橋本先生は、フランスと台湾、日本で研究し、代表的著書『《華麗島文学志》とその時代』(三元社、2012年)のほか、張小虹や李玟萱の著作を精力的に翻訳されるとともに、首都圏で男女平等推進委員を多く務められています。
講義は、台湾のフェミニズム運動史を概観する内容でした。
まず導入部で台湾と日本のジェンダーギャップ比較を数値で確認し、日本統治から現在までの台湾におけるフェミニズム運動の中でどのような事件や進展があったか、さらにその特徴や具体的な活動を明確にしながら、最後に日本社会について問う、重厚な構成でした。
講義中、中央-地方・社会階層・学歴へのまなざし、運動を一気に推し進める象徴的な死、民主化や中台関係、他の社会運動とのかかわりが運動に間接的・直接的に与えた影響などの重要な議論が示されました。
授業後の学生フィードバックには、台湾との比較を通して日本のジェンダー平等に向けた教育などの動向に対するコメントが集中しました。特に日本は1990年代末に男女共同参画社会基本法の制定に続く一連の法律や制度がしっかりと確立・整備されているにも拘わらず、2000年前半のバックラッシュによってそれらが市民に降りてこず機能しない状況にある、という点への関心の高さが表われました。
2023.6.23



続きを読む
ゲスト講義実施報告(筑摩書房 取締役編集局長 伊藤大五郎様)
「プロフェッショナルワークショップ(メディア)」(担当教員:白戸圭一先生)の授業にて、筑摩書房 取締役編集局長の伊藤大五郎様をお招きし講義を行って頂きました。
ゲスト講義の前の授業にて白戸先生から受講生に対し、ゲストの伊藤氏がこれまでに白戸先生が執筆した書籍の編集を3度にわたって担当してくださった優れた書籍編集者であることを紹介しました。
また、伊藤氏の講演に先立ち、白戸先生より出版業界の概況について説明しました。
伊藤氏は、出版社はテレビ局や新聞社に比べて規模が小さく、新卒者の採用が少ないことから、就職産業や大学のキャリアセンターを利用した一般的な就職活動では不十分であり、個人的人脈の開拓や中途入社を前提とした人生設計が需要なことなどについても話してくださりました。
また、著者と編集者の間でやり取りした書籍ゲラの実物を見せながら、編集の仕事内容について詳細に説明し、学生たちに編集や校閲の仕事の魅力を伝えてくださいました。
学生たちは、伊藤氏が編集者と著者の間の意思疎通など書籍出版に至るプロセスを詳細に説明したことなどに関心を示し、売れる本の作り方やテーマ設定の方法などに関する質問が相次ぎました。
また、出版社への就職の方法について、伊藤氏が自身の大学卒業後の経験を基に「中途入社が一般的である」「表向きは新卒募集していなくても、新卒者が応募してくれば、その学生の熱意を買って選考対象とすることもある」などと業界の実態について本音を語ってくれたことで、講師と学生との心理的距離が縮まり、授業時間が終了した後もカジュアルな形での意見交換が続きました。
2023.6.23



続きを読む
ゲスト講義実施報告(資生堂 プレミアブランド事業本部 赤木万由香様)
「プロフェッショナルワークショップ(ビジネス編)」(担当教員:星野郁先生)の授業にて、資生堂 プレミアブランド事業本部の赤木万由香様を第2回目のゲスト講師としてお招きし講義を行って頂きました。
赤木万由香氏は、2018年3月に国際関係学部を卒業し、現在資生堂のプレミアブランド事業本部で働かれています。
ご講演に先立ち、化粧品業界ならびに資生堂への就職を志望する受講生から、業界企業研究の成果報告として、資生堂の業務概要や、女性が活躍する日本の企業として日経ウーマン(日本経済新聞)の調査で2年連続トップとなった社員の処遇や働き方、同業他社との違い等についての説明がされました。
また、学生の報告班からは、赤木氏に対して、資生堂を選んだ理由や資生堂の求める人材像、具体的な業務内容や入社前との印象の違い、コロナ禍の影響等に関する質問が出されました。
それを受けた赤木氏の講演では、資生堂で現在担当している業務の内容、部活とゼミが中心であった大学時代の過ごし方、就活への臨み方、資生堂を志望した理由と最終的に同社を選んだ理由、そして入社後のこれまでのキャリア等について話されました。
ご講演の後、質疑応答に移ったが、フロアからは、就活の際の困難とその克服方法、以前の業務と現在の業務の違いや今の業務の働きがい、課題についての質問が出されていました。
赤木氏は、それらの質問に丁寧に答えると共に、世界の化粧品会社の売り上げの第5位に位置する資生堂での仕事は、一見華やかに見えるかもしれないが、実際の現場での仕事は、泥臭く地味で、自身も、入社6年目で、然るべき成果を求められる、現在の営業本部の仕事の苦労についても語られました。受講生は、率直に心情を吐露する赤木氏の熱い語りを通じて、就活に向けた取り組みや心構えについてだけでなく、入社の後、働くことの厳しさについても理解を深めることができたように思われます。
2023.6.19



続きを読む
ゲスト講義実施報告(同志社大学グローバル地域文化学部・教授 和泉真澄先生)
「専門演習」(担当教員:園田節子先生)の授業にて、日系アメリカ人研究で多数の著作を持ち、メディアでも活躍されている同志社大学 グローバル地域文化学部・教授の
和泉真澄先生をゲストスピーカーとしてお招きしました。
招聘講義の内容は、新型コロナ以後のアメリカ社会におけるアジア系住民を標的とするヘイト・クライムの状況を確認し、アジア系住民自身の差別への対抗活動である情報プラットフォーム「STOP AAPI HATE」の活動、バイデン政権の対策法の設置や国際的に活躍するK-popグループ「BTS」と同政権の会談に表れた様々な意味、アメリカ社会におけるアジア人移民とアジア系住民の歴史、社会的イメージ、そしてトランプ政権のアジア人攻撃とコロナ対策の失敗、といった構成でした。
こうした豊富なトピックを通して、アメリカにおけるアジア人差別の構造を考えました。
招聘講義の前、ゼミでは『現代ビジネス』『毎日新聞』に掲載された和泉先生の論説記事を読み、全員で質問を出し合って準備しました。
講義当日は、アメリカの事例を通して、日本における「アジア」を、より深く考察する時間となりました。質疑の時間には、アメリカには「BTS」をはじめアジア文化に好感を持つ世代が育つ一方、アジア系を人種化し蔑視を向ける人々もいる中で、世代間のギャップやアジア人の人種化や異化はどうなっていくのか、日本人の“名誉白人”的な自意識の根源には西欧やアジア諸国との関係性から発生した一種の達成感や歴史的な優越感があるのか、日本で見られる差別はアメリカの人種化されたものと異なり、人権意識そのものへの薄さがその性質を考える鍵なのではないか、といった活発なやり取りとなりました。
2023.6.16



続きを読む
ゲスト講義実施報告(株式会社リクルート 中川誉也様)
「プロフェッショナル・ワーク(ビジネス編)」(担当教員:星野郁先生)の授業にて、第一回目となるゲスト講師による今回の講演は、2019年3月に国際関係学部を卒業し、株式会社リクルートの人材領域事業企画で働かれている中川誉也をお招きしました。
講演に先立ち、IT人材業界を志望する受講生により、業界企業研究の成果報告として、リクルートの業務内容やビジネス・モデル、社員の働き方、同業他社との違い、人材業界事情についての概要説明を行いました。それを受けて、中川氏の講演では、今の業務の内容と働きがい、大学生活の過ごし方、自身の生い立ちと絡めた自分の性格や志向と、今の仕事との繋がり等について話してくださいました。
講演の後、質疑応答に移りましたが、受講生からは、ワーク&ライフバランスのあり方や、長期雇用とリクルートのような若年層を中心とした短期雇用の是非などに関する質問が出ました。
また、講演に先立ち、中川氏には、上記のIT人材業界志望の受講生による、リクルートの社風や社員の働き方、求められるスキルや研修のあり方等に関する質問表を送っていましたが、それらの質問にも丁寧に答えてくださいました。
中川氏によれば、結局のところ、就活ならびに企業で働くということは、単なる会社や仕事選びではなくて、自分がどう生きるか、どう生きたいかという人生選択の問題であり、その意味で、自己分析の重要性を強調されていました。
そうした中川氏の熱い語りに受講生は感銘を受けた様子で、授業終了後の個別相談セクションでも、活発なやり取りが行われ、今回の中川氏の講演を通じて、受講生は、就活に向けた取り組みや心構えについて、沢山の示唆を得たと思われます。
2023.06.16



続きを読む
ゲスト講義実施報告(株式会社AFRICA DOGS 代表取締役社長 中須俊治様)
「アフリカ研究Ⅰ」(担当教員:白戸圭一先生)の授業にて、株式会社AFRICA DOGS 代表取締役社長の中須 俊治様をお招きし講義を行って頂きました。
ゲストの中須さんは1990年生まれの京都府出身でいらっしゃいます。滋賀大学在学中に大手企業への就職が内定していたにもかかわらず、インターネット上で見つけた西アフリカのトーゴ共和国におけるラジオDJ募集の情報に興味を抱き、トーゴへ渡航して半年間、ラジオ局で働く体験をされました。
就職内定を断り、1年留年して大学を卒業したあと、京都信用金庫で働き始められましたが、アフリカに関する仕事をやりたい思いをあきらめきれず、28歳の時に退職されました。その後、2018年にAFRICA DOGSを創業されました。
同社はトーゴで織られた布を買い付け、京都の染色業者の手で染め上げ、洋服を仕立てて販売するビジネスを展開されています。現在はそれ以外にも、様々なアフリカ布の輸入販売や、トーゴでの暮らしを経験したい日本の若者向けのスタディーツアーの斡旋なども手掛けており、日本とアフリカを結ぶ各種事業を積極的に展開されています。
中須さんは、学生時代から現在に至る時間を振り返りながら、アフリカを相手に仕事することの魅力や起業の体験などについて、熱のこもった講義を実施してくださりました。
普段出席してこない学生もこの日は多数登校し、教室は超満員となり、学生からは起業に関する質問などが相次ぎました。
「就活関連情報」に振り回されがちな学生にとって、生き方を考え直す良い機会になったと思われます。
2023.6.9

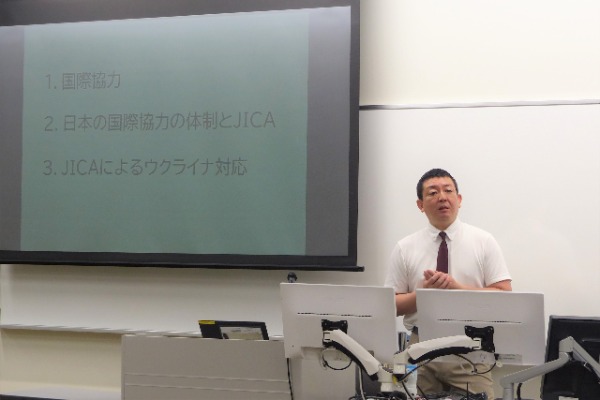

続きを読む
ゲスト講義実施報告(独立行政法人国際協力機構 安全管理部 今井 健様)
「プロフェッショナルワークショップ」(担当教員:石川幸子先生)の授業にて、JICA安全管理部次長の今井健様をお招きし、政府開発援助(ODA)を含む国際協力のあり方について講義を行って頂きました。
毎年、この講義は学生から好評を得ており、その理由として、JICAが実施しているODAの内容にとどまらず、「なぜ国際協力は必要なのか」について学生に考えさせる講義内容となっていることが挙げられます。
今回の講義では、まず、世界の80%の国々がOECDの開発援助委員会(DAC)が定義する開発途上国であり、これらの国々は先進国にとっては“商売相手”(援助の対象)なのだというショッキングな言い回しで始まりました。
日本は、貧困、紛争、環境問題、感染症等の複合的な危機に対してODAによって対応しているが、それは人道的な配慮のみならず、パートナー国が不安定であると、日本も不安定な状況に置かれるという相互依存関係が進んでいるからであり、国際協力といえども、ODAの場合は国益を無視したものではないことを強調されました。また、国際協力はODAのみで実施するものではなく、ODAから始まった協力も、ゆくゆくは民間連携事業に繋げていくことが肝要であるとの視点について言及がありました。
現在、企業はSDGsを視野に入れたESG投資を行う傾向にあり、国際協力の在り方は多様化しているとの見解が示されました。