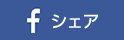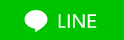関係者がひも解く熱い挑戦の軌跡 Learning Infinity Hall誕生ストーリー
2024年4月、立命館大学大阪いばらきキャンパス(OIC)に新棟、H棟が誕生した。中でも目玉の一つが「Learning Infinity Hall」。視線を教壇に集められる階段教室の良さとグループワーク仕様を両立させ、リアルとバーチャルを縦横無尽に行き来できる他に類を見ない新型教室だ。誕生の背景にあるのは、2015年のOIC誕生以来10年の間に蓄積された知見。「Learning Infinity Hall」はなぜ生まれたのか、成し遂げようとしているものとは何なのか。
今回は、OIC開設に力を注いだ及川清昭教授(総合科学技術研究機構)と服部利幸教授(政策科学部)、新棟開設をはじめOICの新展開を推進する三宅雅人教授(社会共創推進本部 本部長)と豊田幸平さん(社会共創推進課)、各キャンパスの情報基盤設備を整備してきた倉科健吾さん(情報基盤課)、H棟の設計を担当された竹中工務店本店設計部の永井務さんと堀良平さんとバラエティに富んだ方々にお集まりいただき、この教室の存在価値と創造する未来について語ってもらった。
つながりが「インフィニティ」に広がる教室
――まずは、「Learning Infinity Hall」とはどういう施設なのかから、お話を伺っていきましょう。
豊田 そもそもの構想は、2020年のコロナ禍の最中に生まれました。近年の学びとコミュニティの変化を整理すると、伝統的な1対nの講義形式や学内の閉じていた世界から、アクティブラーニングや学習者同士の対話を重視する学びによって地域や企業など学外への広がりが見えてきました。2015年に開設したOICは、まさにこの変化を意識してつくられたキャンパスです。今回のOIC新展開ではさらに、先端技術を基盤としてリアルとバーチャルを融合させ、学びとコミュニティの拡張をめざしました。そういうわれわれの思いを具現化した設備として竹中工務店さんが提案されたのが、「Learning Infinity Hall」の原型です。
堀 目標は今までにないグループワーク主体の新しい教室でしたが、設計の前に延々と私や永井も含め、関係者で議論したのを覚えています。当時はコロナ禍の真っ只中で「オンラインで十分」といった論調もあり、大学に来る意味が問われていたんです。そんな中で湧いてきたのが、ライブ会場やスタジアムのイメージです。個々の学びや考えが独立してあり、そのバラバラのものを同時多発的に味わうことで今までにない刺激や一体感が生まれる教室。能動でも受動でもない、一方向でもなくマンツーマンでもない、それら全部のいいとこ取りみたいなことはできないかというところで出てきたアイデアです。
三宅 「Learning Infinity Hall」がどういう教室なのか、特徴を紹介しましょう。豊田さんの言った学びやコミュニティの拡張ということで、グループワークをさらに発展させ、社会とつながる、地域とつながる、市民とつながる機能を付加しました。6人掛けの各ブースには、タッチパネルモニター、カメラ、マイク、スピーカー、パソコン接続ケーブルを設置。ブースは38個あり、各グループが全く違う相手とつながることができます。つながりが無限に広がっていくことから「インフィニティ」という名前が付きました。
倉科 全ブースのリモートセッションを同時に成立させ、38ブースの映像を自由に瞬間的に切り替えるにはかなり高い技術が必要で、各メーカーさんとコラボしてようやく実現しました。先生の手元で各ブースの動きが把握でき、講義内容やグループの発表内容の共有・切り替え、個別ブースの指導なども瞬時に行うことが可能です。こうした複雑なことをどこまで簡単に操作できるようにするか、ずいぶん悩み抜きましたね。
10年で築いた「うちんとこの大学」という基盤
――それでは、「Learning Infinity Hall」が生まれる背景へとお話を進めていきましょう。OICはそれまでの大学での学びやコミュニティの概念をどう超えていったのか、当時を振り返っていただければと思います。
服部 計画は2015年に開設する3年半ぐらい前から進めましたが、地域の方々が新キャンパス建設を非常に好意的に受け止めてくださっていましてね。「学生さんと一緒にやりたい」「こんなお祭りがあるのだが…」などのお話を早くからうかがい、心待ちにしておられる様子が伝わってきました。そんな中で生まれたのが、地域と密接なかかわりを持つ「塀のないキャンパス」というコンセプトです。キャンパスのセキュリティの問題で反対もありましたが、結果的に塀がなくてもうまくいっているのは地域の方の理解によるところが大きいと思います。
及川 OICには公園との境がありません。茨木市をはじめ、さまざまな人たちのご協力で、キャンパスと公園の一体化が実現しました。公園は立命館のものではないのにキャンパスマップに描かれ、それを誰も不思議に思わないほどなじんでいるんです。
永井 東京では、フラッパーゲートやセキュリティカードといった設備を設置する大学もありますが、OICは人力でセキュリティを守っていますよね。
及川 装置の導入で、せっかくつくってきた地域との関係を壊したくありませんでした。大変なのはわかっているけれど、まずは人の目とコミュニケーションでセキュリティを維持しようと考えました。それが現在まで10年続いているのは、現場の方々の力と服部先生のおっしゃる地域の方々の理解のおかげです。
服部 茨木商工会議所に入居いただくなどしたことも、産学公がつながる素地になりました。
永井 2015年頃といえば全国的にPBL(課題解決型学習)が盛んになってきて、学生が外に出て地域や企業と連携し、ともに課題解決を図るような学びが取り入れられるようになりました。OICではキャンパス自体に課題を持った市民を集めることでPBLをやろうみたいなユニークな発想だったように思います。塀のないキャンパスは単に地域に開くということだけでなく新しい学びのための工夫でもあったんですね。結果として学びのフィールドが広がり、まちづくりに大学が関与するなど地域への発信の場にもなっていったといえそうです。
堀 キャンパスが大学生だけのものでなく地域のフィールドであることが、目に見えて実感できるようになったんですね。
永井 地域の方々にとっては、「うちんとこの大学」みたいな感じになっているのでしょう。わずか10年でここまで密接につながれるようになったのは、OICの発想がすごかったんだなと感じます。
服部 発想を固めるまでの過程がそれなりにありましたからね。キャンパスをつくるにあたっての会議の数が膨大で、分野ごとにいろんな人が集まる会議が数百ぐらいあったんじゃなかったかな。議論して、議論して、議論して。徹底的な議論の中から一番いい上澄みを取ってきたことが強みになったのだと思います。
倉科 結果的に、学内に「OICでは新しいことがあるみたい」という雰囲気が醸成されたような気がします。学外の人が感じるキャンパスカラーが、学内にも浸透してきた感じがします。
ラーニングシアターで向き合った「自由」
――「Learning Infinity Hall」は、これまでの知見の集大成とも言える設備だとうかがっています。中でも影響を与えたと思われるこれまでの取り組みについてお聞かせください。
永井 まずは、OICのラーニングシアターではないでしょうか。当時、アクティブラーニングが注目され始めインターネットが進化してきました。先生方からも市民を招いていろんな授業をやりたいとか、googleマップを使った街づくりの授業がしたいといった、さまざまな要望も出てきていました。そこで、二層吹き抜けで300人収容できる階段教室をつくる予定を変更し、グループワークに適したIT機器を取り入れた教室を提案しました。
倉科 グループワーク用に12のテーブルを設け、教室周囲の壁面にはスクリーンを設置。さらにホワイトボードを置きました。そこに自由に書き込んだり、画像をスクリーンやホワイトボードに映し出したりすることができます。パソコンの画像を映し出すだけでなく、アナログワークをカメラで写してすぐ共有することも可能。グループワークやワークショップ、またその報告や発表をみんなで行うなど幅広い用途に使うことができます。当時考えていたのは、先生がどこに座るかを決められ、自分のやりたいスタイルの授業ができるよう、教室の自由度を高めることでした。先生がセルフプロデュースできるという意味でラーニングシアターの意義は大きかったし、「Learning Infinity Hall」に受け継がれている精神の一つです。
服部 ラーニングシアターでは、卒業生を呼んで在校生の進路相談をしてもらったことが印象に残っています。各テーブルに卒業生についてもらって、最後はみんなで発表を聞いたりしました。倉科さんがおっしゃるように、自由度が高くていろんなことができた。面白いのは、どこかのテーブルが盛り上がると、連鎖的に盛り上がっていく現象が起こったことですね。
堀 本当に、ライブしているみたいな感じ。こういう雰囲気が、「Learning Infinity Hall」の発想の根源にあるような気がします。
豊田 ラーニングシアターをイベントで使ったことがあったのですが、テープル・椅子やカメラを好きな場所に移動できるのがすごくいいんですよ。話者がどこにいてもそれに合わせてカメラを動かし、話者の顔をとらえて臨場感のある映像を見せることで、会場内もリモートでつながっている人も一つになれるんです。
倉科 コロナ禍の経験も大きかったですね。ちょうどその渦中にAPUのグリーンコモンズ新設に向けた企画を行っていましたが、念頭に置いたのは、対面の人とオンラインの人が混在した時にオンライン参加者も取りこぼさない、ということでした。先生の映像だけでなく教室全体を引きで撮った映像を送り、オンライン参加者にも教室の空気を伝え一体感を感じてもらいたいと思いました。発言した人を自動でカメラが追いかけるAIカメラの導入も、もともとはオンライン参加者に教室の進行状況をきちんと伝えられると考えたのがきっかけです。徐々にAIカメラのレベルアップとコストダウンが実現してきたので、先生が動くのを自動で常においかけるカメラのプロトタイプを入れることにしました。そうした積み重ねをベースに、「Learning Infinity Hall」では本格的に実装しています。
教室の挑戦が紡ぎ出す教育・学びの未来
――「Learning Infinity Hall」は、これからの大学教育や教室の在り方に、どんな視点や可能性を提供するのでしょうか。未来への展望をお聞かせください。
永井 私は、OICⅠ期の中で先生方からオープンエンドの思想を学んだと思っています。作り込まず、作りすぎず、できあがってから使いながら少しずつ作っていく部分があってもいいという姿勢が、OIC以降の設備の特長の一つとして継承されていますよね。
倉科 それは、選択肢を広げたいからでもあります。使ううちに出てくる要望に応えた機能はもちろん、こちらからも新機能を提供できればと思っています。それらを押し付けるのでなく、機能を自由に組み合わせて使ってもらえればいいなと。使い方が決められていない分、われわれの想像を超えた使い方をしてほしいと思いますね。
三宅 OICにあるフレキシビリティや作り込まない姿勢は変化を生みます。教える内容や学生の感覚は変化し技術もものすごいスピードで進化する今、常に最先端に近づけた形で使っていけるという気がします。
堀 立命館さんは、教室じゃないものを常に作っていこうという意識が高いのかなとちょっと思っているのですが。
倉科 大学として最低限必要な設備はすごく丁寧に作りながら、一方で新たな挑戦やリノベーションを大胆に進めていくというところですかね。OICでは、チャンスに恵まれて大きな挑戦ができている実感があります。
三宅 5月に開かれた「いばらき×立命館DAY 2024」で「Learning Infinity Hall」のデモンストレーションをしました。学生がブースからインド、北京、アメリカとつないでディスカッションをしているのを、小学生や中学生が周りで歓声を上げながら見守るみたいな光景が展開されました。今まで縛られていた時間や空間や人などすべての要素から自由になって、いろんな人が出会いつながることができるという環境に、改めてすごく期待させられました。
服部 そう、問題は何を学ぶのか、教えるのかですよね。教育現場の最新動向や技術の変化を知っている人たちが作った教室が、教員と学生の前に「使えるものなら使ってみぃ」と差し出されているわけです。この挑戦に対して、われわれ教員も新しい教育の挑戦で返していかないといけない。教室の主役であり責任者は教員ですから。「学生たちの知的好奇心を掻き立てられるような講義をしたい」と、教員のモチベーションを上げる教室だと思います。
堀 そうなんですよね。TEDみたいなことができたらなと思っていました。
服部 それから「Learning Infinity Hall」を含め、非常に多種類の教室が存在していて、その中から教員や学生が選べることが価値かなとも思います。学生が授業を、教材と教員と教室の掛け合わせで選ぶようになったら、すごく面白いですよ。
倉科 毎年担当される授業を今年から新しいスタイルに変えていく挑戦をされている先生がいらっしゃいます。搭載された機能を使ってどんな授業ができるのか、ご要望をお聞きしながら私も新しいやり方を一緒に模索中で小さな改善を実装したりしていますが、今後もそういう取り組みをいろいろとしていきたいですね。技術革新のスピードは速いですが、コストを低く抑える観点から設備をより長く大切に使いつつ、さまざまな人の新たなニーズに応えていけるような整備をいかに続けていけるか突き詰めていきたいと思います。
三宅 この教室では社会と簡単につながることができるので、誰でも、たとえば専門家の人や地域の子ども、併設校の生徒たちも呼んできて先生になってもらったり学ぶ仲間になってもらったりできます。今までない、いろんな形の学びが提供できるはずなんですね。また、授業を受ける側にも変化がありそう。普通、教室の後ろには授業への参加意識が低い学生がいることが多いですが、ここだと一番後ろの端にいても授業の進行に積極的に関わろうとする姿が見られました。後ろほど教室空間の全体が見られるので、仲間意識がより高まるのかもしれません。「教える」のも「学ぶ」のも従来とはその意味が変わってくる、そんな取り組みに期待しています。