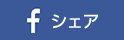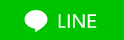【知の拠点を訪ねて】「障老病異」を抱えて生きる身体と社会の関わりを探究する 生存学研究所
私たちは、一人ひとり異なる身体をもって生きている。生きるということは加齢や病気などで変化してゆく身体と付き合ってゆくことであり、身体をとおして社会と関わってゆくこととも言える。
立命館大学生存学研究所は、さまざまに異なった身体を生きる人々の経験を集積し、社会との関わりを問う『生存学』の研究拠点である。これまで見過ごされてきた身体をめぐるさまざまな問いに迫る研究活動について、所長の立岩真也先生(大学院先端総合学術研究科 教授)に伺った。
多様な生のありかたを記録し、身体と社会の間で起こる問題を考える
生存学研究所は、文部科学省グローバルCOEプログラム「生存学」創生拠点の採択を受けて2007年に設立された生存学研究センターを前身としている。2019年度に立命館大学の恒常的な研究所に改組され、現在に至っている。その立ち上げを主導し、現在まで所長を務めている立岩先生は、設立の経緯をこう振り返る。
「私が教員を務める先端総合学術研究科には、生命や身体といったテーマを扱う教員のほか、本人が障害をもつ当事者であったり、当事者と関わりをもって研究に取り組んでいる研究員や学生が当時から多く所属していました。研究科内でグローバルCOEに応募する話が出たときに、せっかくならば多様な身体に関わる研究や活動を集約した拠点をつくりたいと考えたのです。
応募に際して『生存学』という名称を使いました。生きている限り、人間は一生自分の身体と付き合っていかなければなりません。そして身体を持っている限りは『普通』ということはありえず、一人ひとりが老化や病気、さまざまな変化を経験することになります。そうした身体という環境、あるいは出来事のなかで、人々はこれまでどう生きてきたのか、今どう生きているのかを記録し、身体と社会の間で起こっている問題を考えていくこと――こうした営みを生存学という言葉に込めました。
もちろん、既存の学問のなかでこうした身体の問題に取り組む分野もありますが、依然としてその中で見落とされている問題は多いように思います。生存学研究所ではこうした社会や時代、人々の要請に応えるべく、あえて守備範囲を定めず、できることなら何でもやるという姿勢で研究活動に取り組んでいます」
生存学研究所が理念として掲げているのが「障老病異」という四字熟語。仏教における四苦「生老病死」をもじって、「老いること」、「病気になること」、「障害をもつこと」、「それぞれが異なった身体をもって生きること」の4つをあらわす造語だ。障老病異をめぐる問いを考えるには、真っ先に考えてしまいがちな医療や福祉といった視点から一歩引いた視点をもつことが大切なのだそうだ。
「たとえば、病気というものは医学の視点で見ると治さなければいけない対象ですが、もう少し手前で考えると、そもそも本当に治さなければならないのか、人はどうして病気を治したいと思うのか……という問いも成り立ちます。当たり前と思われていることの手前に立ち戻って考えることはとても大切なことです。歴史を振り返ると、誤った『治療』のためにたくさんの人が亡くなったり、傷つけられたりした例はいくらでもあります。それは現在も同じですし、そのまま放っておけば未来も変わりません」
俯瞰した視点をもちつつ、今起こっていることにクローズアップする視点をもつことも大切だと立岩先生は言う。生存学研究所では、社会の中で暮らす人々や、社会を変えるために前線で活動する人々と密接に関わりあいながら研究に取り組んでいるという。つぎに具体的な研究内容について伺った。
唯一無二のアーカイブをはじめとする研究活動
幅広い研究テーマを擁する生存学研究所だが、現在は「生存学アーカイヴィング」「東アジアにおける生存学拠点」「支援テクノロジー開発」の3本柱に重点を置いているという。このうち立岩先生が担当するのが「生存学アーカイヴィング」だ。
「ここでは多様な身体を生きる当事者の声や運動に関する資料を収集して、誰もが必要なときに参照できるように保管・公開しています。一般に流通している書籍であれば原則的に国立国会図書館に収蔵されることになっていますが、ここで収集しているのは一般流通していない書籍や活動団体の機関紙、あるいは書籍としてまとまっていない原稿やビラなど多岐にわたります。たとえば、日本では1970年代に公害や薬害が大きな問題になり、被害にあった方々が運動を起こして国や社会に実態を訴えてきました。それから50年の歳月が経ちますから、当時活動されていた方がお亡くなりになって、お持ちだった資料をご遺族から寄付いただくことが多くなっています」
アーカイブ活動をとおして前線で活動する人を支える後衛、あるいは貯蔵庫の役割を果たしたいという立岩先生。他の研究機関がもつアーカイブとも連携することで、人々の要請に応えたいという。さらに、アーカイブするのは紙の資料だけではない。
「障害当事者の方や運動に関わって来られた方などさまざまな人を訪ねてお話を伺い、障老病異に関わってどんな人生を生き、社会に主張してきたのかを記録する活動も行っています。どなたも人に伝えたいことをたくさん抱えておられるのですが、多くの人はそれをまとまった形で書き残すという習慣がありません。けれども、こちらからお伺いして聞けば答えてくれます。私自身としてはこの聞き取りが一番大きな活動ですし、今お聞きしておかないと間に合わないという危機感も常にあります。
さらに、現在進行形の言論を記録する上ではウェブサイトやSNSに残された言葉を収集することも重要になってきます。ネット上の情報をどのように収集すべきかを現在検討しています。この取り組みはグローバルな視点でも意味があります。他国で言論の規制が厳しくなってネット上の投稿が大規模に削除されてしまうような場合も、日本でデータを保管しておけば言論が消えてなくなるのを防ぐことができます」
膨大な資料目録やインタビューは、「生を辿り途を探す 身体×社会アーカイブの構築」と題してウェブ上でも公開されている。年間のアクセス数は3000万件にものぼるというから、アーカイブがどれだけ多くの人々に必要とされているのかが窺える。また、サイトとは別に、教員や学生、卒業生、客員研究員など関係者数百名が参加するメーリングリストでも頻繁に情報交換が行われているそうだ。
このほか、「東アジアにおける生存学拠点形成」では、中国、韓国、台湾の研究機関と連携し、10年以上にわたって毎年「障害学国際セミナー」を開催している。それぞれの地域で共通する身体を巡る課題について情報交換を行い、連携を深める場となっている。2020年以降はコロナ禍でオンライン開催となっていたが、来年は韓国で現地開催が予定されている。
「支援テクノロジー開発」では、ダイバーシティ社会を実現するテクノロジーの社会実装をめざして、当事者の視点を取り入れた社会調査や支援のありかたをハード面からソフト面まで幅広く探究している。2020年度からは、自身が車いすを常用する当事者でもある大谷いづみ教授のもと、障害者や高齢者の移動や情報アクセスの課題に取り組むアクセシビリティ・プロジェクトを展開しているという。
15年間の蓄積で見えてきた身体をめぐるテーマを書籍にまとめる
ここまでは現在進行中の活動をお聞きしたが、新たな取り組みとして、生存学研究所設立以来15年分の蓄積を書籍にまとめる計画が進んでいるという。
「15年間の活動をとおして私たちが考えてきた身体をめぐる問題を、いくつかのテーマで整理して書籍として出版したいと考えています。本日お話ししたようなアーカイブについての話から、薬やワクチンについて、病気や障害をもちながら働くということについてなど、すでにいくつかのテーマを考えて動き始めています。研究員や院生にも編集に入ってもらい、年に数冊ずつ7年ほどかけてシリーズで刊行していく予定です。
これまでウェブサイトを中心に際限なく知見を蓄積してきましたから、そろそろまとめるという作業に着手するタイミングかなと思うんです。たとえば『ダイバーシティ』という言葉は世間でよく耳にする割に、実態が伴っていないことが多いように感じます。私たちはダイバーシティについて15年間考え続けてきたので、書籍という形にまとめることでその外縁を提示できるかもしれません」
書籍にまとめることで全体の輪郭が浮き上がってくるようなテーマがある一方、簡単に結論を出せないテーマもある。
「障老病異の『異』の話になりますが、相貌や挙動といった『姿かたち』が他人とは異なるために偏見の目にさらされるなど困りごとを抱えている人々がいます。当然ながらご本人に問題があるわけではないですし、視力の弱い人がメガネを掛けるように何かで補えば解決するという問題でもありません。
逆に、外からは見えづらいがゆえの苦しみもあります。それが『痛み』です。人と身体的な痛みを共有することはできないので、苦痛を訴えても嘘と疑われたり、障害や病気として認められなかったりすることもあります。それがときには年金がもらえないとか、学校や職場で配慮を受けられないという制度の問題にも発展します」
「姿かたち」や「痛み」といった問題は、社会ではほとんど取り上げられることはなく、当事者自身が抱え込むしかないのが現状だ。だからこそ、書籍という形でテーマを可視化することに意味があると立岩先生は言う。
「世の中には、バリアフリーのように理屈として解決策はわかっているけれども実際の対応がなかなか進まないという問題もあれば、『姿かたち』や『痛み』のようにそもそも解決策すら分かっていないような問題もあります。書籍を作ることでどんな結論が出るのかもまだわかりませんが、そうした問題こそ文字化する必要があることは確実です。答えが出ないからと投げ出すのではなく、可能なところまで迫っていって、今ある問題の一部であっても解決していくのが私たちの仕事だと思っています」
書籍のシリーズ刊行という大きな計画を進めながらも、立岩先生の軸足はアーカイブにある。そのために、資料の収集や聞き取りを途切れることなく続けていくことが永遠の課題だ。
「英語、中国語、韓国語といった多言語発信にも力を入れていきたいのですが、予算やマンパワーには限度があるので、今は資料の収集・整理や聞き取りが最優先です。今残せるものを残しておかなければ、後から翻訳することもできませんから。大学の大切な社会的使命として、学生や研究者、そして市民の誰もが必要なときに参照できるアーカイブを維持し、さらに拡大していきたいです」