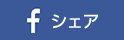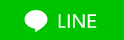【知の拠点を訪ねて】社会問題に食科学で力を尽くす 食総合研究センター
「食」はあまりに身近でありふれているために、なかなか学問の対象としてとらえにくいかもしれない。しかし考えてみると、食糧危機、食のSDGsや食の安全保障、食文化、食の生産やビジネス、健康と栄養など、今や食に関わる社会問題は多様な形で存在し多くの人々の関心を集めるようになっている。立命館大学食総合研究センターは、食の研究組織の中でも珍しい、食を総合的に研究するセンターである。その設立の目的や経緯、研究活動の内容について、センター長の阿良田麻里子(食マネジメント学部教授)にお話を伺った。
学際的・総合的なアプローチで食科学を推進
食総合研究センターは、2014年4月に開設された国際食文化研究センターを前身とする。生産、流通システム、食文化など幅広い分野で加速する食のグローバル化に対応して、食に関わる活動の情報の集積と、異文化理解やフードビジネスのイノベーションにつながる食研究の拠点をめざして発展。2018年4月、食マネジメント学部の開設にあたり、食総合研究センターとして新たなスタートを切った。
本センターの目的の一つは、総合的な学問としての食科学の確立・推進である。現代社会が直面する「食」にかかわる様々な問題の本質をとらえ解決に導くためには、人文科学、社会科学、自然科学の枠を超えた学際的・文理総合的な研究が必要という考えのもと、本センターでは食マネジメント、食文化、食テクノロジーといった多様な領域を総合的に研究し、新しい学問である食科学を確立しようとしている。
各領域は具体的にどのような研究分野を含むのか、阿良田先生が概略を説明してくれた。
「食マネジメントは、食の生産から消費まであらゆる局面で必要となるマネジメントを含み、たとえば食に関わる政策や経営戦略などがテーマとなります。マーケティング、行動経済学、資源循環、アグリビジネスなどの幅広いテーマがあります。食文化は、歴史学、社会学、文化人類学、民族学、地理学などの視点で食文化のこれまでとこれからを研究します。食テクノロジーは、官能評価や認知科学、栄養学、調理科学などの側面から新しい食の可能性を探求します」。
世界の研究者が出会い影響し合う場
本センターは、総合的、学際的な研究拠点として、食科学の先進的な研究を行う国内外の研究者や機関、行政や企業と広く連携を図っている。こうした特長を象徴するのが、これまで数度にわたり開催してきた国際シンポジウムと言えるだろう。
たとえば、食マネジメント学部開設前、前身時代の2016年、2017年と2年連続で大規模な国際シンポジウムを開催している。2016年に行ったのは国立民族学博物館と連携した「食文化の交流―過去・現在 ・ 未来」という2日間にわたるシンポジウム。中国を中心とする国際的食研究組織、亜洲食学論壇(アジアフードスタディーズカンファレンス)の研究大会をびわこ・くさつキャンパスに招き、アジアを中心に多数の発表者を迎えて盛況を博した。2017年は「世界の食研究と高等教育」と題して、食科学の先駆者であるイタリア食科学大学、アメリカのコーネル大学から講演者を招き、日本と世界の食科学研究、教育のあり方を議論した。
「これらの国際シンポジウムは、食科学という総合的な学問の必要性を社会に認知してもらうとともに、本センターが世界的な食研究拠点としての存在価値をアピールする場にもなりました」と阿良田先生は振り返る。また、国内外の研究者や組織との研究ネットワークの礎を築くという意味でも「創生期のエポックメーキングなイベント」だとも評価する。
近年では、新型コロナウイルスの世界的に流行で食ビジネスが大打撃を受けたことを受け、2021年、「ビヨンドコロナ時代の食と農」と題した国際シンポジウムをオンラインで開催している。コロナ禍で食ビジネスが直面した問題やその対応についての情報を広く共有し、持続可能な食マネジメントシステムの構築に向けた提言、研究の方向性、人材育成法などについて議論。朝9時半から夕方5時半という長丁場で様々なセッションを開催し、多くの講演者、参加者を迎えた。「ローカルな知恵のようなものを国境を越えて分かち合う貴重な機会になった」と阿良田先生は話す。
これらの国際シンポジウムからは、多様な研究者が出会い、互いに影響し合いながら、様々な成果を社会に発信・実装する場としての本センターの姿が浮かび上がってくる。
「伝統食」を軸に食文化の継承を考える
研究者の幅広いネットワークだけでなく、地域との密な連携も本センターの特色と言っていい。研究会や研究プロジェクトの形で進める研究活動にも産官学の垣根を越えて多様なメンバーが集まっており、その研究成果は地域活性化などの取り組みとして社会実装されている。
なかでも「伝統食」は、前身時代から様々な観点から研究が継続されてきた、本センターにとって重要なテーマといえる。たとえば、古代から都に運ばれ食文化を支えてきた「御食国(みつけくに)」もキーワードの一つになった。若狭の代表的特産品である若狭小浜小鯛ささ漬けを軸に御食国の成り立ちや食品加工技術の変遷を調査し地域ブランディングを考えるプロジェクトでは、小浜市や京都の錦市場などと連携し、地域活性化や伝統技術の継承を目的に研究を続けている。
また、琵琶湖の淡水魚、湖魚食の伝統を継承・発展させることをめざしたプロジェクトも活発に活動中である。海水魚と比較して知名度の低い淡水魚食について、琵琶湖漁業の収益拡大、販路・市場拡大の取り組み、アジアの食文化を取り入れた消費拡大策など、総合的なアプローチを行っている。
伝統食をテーマにした研究について、阿良田先生はその方向性について次のように話す。
「食文化と言うと、昔から守られてきた伝統の文化というイメージを持たれがちですが、伝統だからずっと変わらない、ということではないと思っているんです。食文化に限らず文化というものは、歴史の中で様々に組み合わさりながら発展したり洗練したり、変化していくものです。現在の和食文化も、そうした流れの中の一通過点と言えるでしょう。伝統食の研究においても、昔ながらの何かを守るというより、これからどのように発展をさせていくのかというところに重きを置いています。産官学、いろんなところとつながることで、発展の可能性はより大きく広がっていくと思っています」。
充実の動画コンテンツで研究成果を発信
研究成果の発信を重視している点も、本センターの特色であると言ってよさそうだ。公式ウェブサイトを見ると、研究成果を動画にまとめたコンテンツが数多く並んでいる。少し前から映像学部の教員・学生とコラボレーションし、プロジェクトの調査風景を映像として記録・編集してもらったり、撮影・編集技法の研修をしてもらったりしているという。一般の人に研究内容を分かりやすく伝えたり、興味のきっかけをつくったりするのに、動画の威力はやはり大きいと阿良田先生。今後も、さらに映像による発信を充実させていくという。
また、興味深いのは、ICTを活用した新たな食科学教育のあり方を、多くの動画コンテンツによって提案していることだ。エッセンスを抽出してテンポよく表現された動画を観ていると、食科学教育の将来性の大きさにわくわくさせられる。
たとえば「GAstroEdu」は、大学の持つ食の世界的なネットワークと最先端の技術を活用して、海外と直接つながるライブ感あふれる体験を通して学ぶプログラムで、系列校の児童・生徒に提供されている。食は身近であるがゆえに、多くの社会問題がそこに含まれ、それらが複雑に絡み合って存在していることが理解しやすく、問題を自分事としてとらえやすいともいえる。本プログラムでは、トマト、ポテト、牛など身近な食材を通じて、自分で解決策をつくり出していく体験から、サイエンス、テクノロジーのみならず文化や歴史などの多くの視点から問題の本質をとらえることのできる人材を育成することをめざしている。また、食マネジメント学部の実習授業やフィールドワークにおいて、ICTを活用して現地に行くよりも豊かで深い体験の可能性を探る研究成果も公開されている。
「コロナ禍の間に、ICTの様々な技術を使って、どういうことができるのか、いろいろと挑戦してきました。今後、フィールドワークにもリモート技術を活用することで、全員が入れないような場所でも代表者が入って全員に共有できたり、現地に行かなくてもライブ映像を見ながら気軽に質問ができたりするでしょう。書物などによる間接的な学習に加え、直接つながる経験によって深く発展的な学習ができるようになるのがメリットです。学習だけでなく研究でも同様。フィールドワーク後に追加の調査をやりたいと思っても、リモートならすぐに現地とつながれます」と阿良田先生はICT技術の活用による教育・研究の深化を強調し、今後もICT活用を発展させていきたいと話す。
本センターの研究活動には、食マネジメント学部の学生や大学院生を中心に多くの学生たちが参加している。「社会で食科学の成果を実践していく人材を育てることが、将来の食科学発展につながり、産官学連携の輪を広げることにもつながる」という思いがあるからだ。
「本センターは、それぞれの地域の色を生かした食ビジネスや食文化をどうつくっていくのか、そのベースとなる研究をするセンターだと考えています。今から30年後、50年後、100年後の未来を考えた時、食マネジメント学部や本センターができたことで、私たちの今のすばらしい食生活があるんだね、と振り返ってもらえるような活動をしていきたいと思います」と阿良田先生は大きな夢を語る。
一人一人の健康や嗜好から、地域活性化や第一次産業、さらには国際関係まで、改めて考えると食がカバーするレンジは本当に広い。食を総合的に研究する意義は高まり、それにつれて本センターの活動への期待も大きくなるだろう。社会の問題にどんな解を与えるのか、どんな発信で社会を変えていくのか、今後の動きから目が離せない。