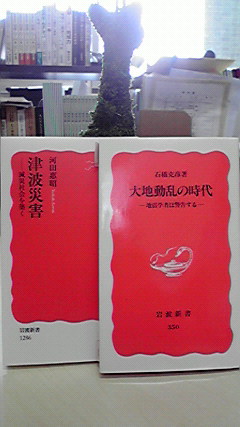最近とある友人と「応用科学であるスポーツ(体育)科学・健康科学の分野で、本当にスポーツ、健康に関連しているテーマがどれだけあるか?!」に関して意見を交わすことがありました。「"スポーツ"や"健康"を謳いながらやっていることは親学問の"生理学""生化学""神経科学"etcになっていないか?!」との問いかけです。
あくまで私の個人的な意見ですが、スポーツ健康科学という分野を独自色を出して囲い込む、一種の独立した領域、としていくことには危機感を持っています。そうなると、分野の発展や、サイエンスとしての面白さには限界がくるのではないかと思っています。
むしろ、"生理学""生化学""神経科学"との垣根があってないような、そんな同等のレベルでの研究が進行していくのがいいとさえ思っております。
そのため、それこそ"生理学""生化学""神経科学"の専門家がこの領域に積極的に入り込み、一種の融合があるべきではないかと思っております。
そして、スポーツ健康科学者は各自、融合して新たな色を解き放つための自分色(それは応用科学であったり基礎科学であったり多様だと思いますが)に磨きをかけることが重要なのではないかと思うと応えました。
それに対し友人からは、各領域の専門家が進出し、様々な側面・観点から事象を捉えるのが応用学問としてのスポーツ科学・健康科学であるとの認識は共通しており、そのうえで自分の研究が"スポーツ""体育""健康"等の分野でどこに居るのか、どこを目指しているのか、を常々意識しておく必要があると思うとの返答がありました。
研究としては、個人的な興味やサイエンスとしての面白さ、それらの追求でいいが、"スポーツ健康科学部"等に所属している意義、そこで研究する意義を意識することが重要であるとの意見です。
そんな折、私の恩師から、その師である故猪飼道夫東京大学教授の「体育・スポーツを科学する心」と題したエッセーを頂きました。すーっと差し出されたそのエッセーは、原点に立ち返らせてくれるものでした。そこには、寺田寅彦博士「物質と言葉」における「頭のいい人は批評家には適するが行為の人にはなりにくい。凡ての行為には危険が伴うからである。怪我を恐れる人は大工にはなれない。失敗を怖がる人は科学者にはなれない。」逆に、「怪我を恐れぬ者は、科学をやってみよ」の示唆に、窮地に光を見出した気持ちになったことが書かれてありました。そして、自身、「科学する心」とは何かを考えてみても、どこにもその姿はみあたらない、ただ現象の分析が面白く、手当たり次第にやってきたにすぎない、つまり、「科学する心」とは本能のようなものであり、やりたくてしかたがないというだけのことであると述べておられます。最後に、「今後どのように発展するか」ということは、科学することが止められない研究者という人種と、方向付けを性格にする能力をもつ教育者という人種とが、退けあうことなく、理解し合って、創造に協力することの成否如何によるであろう、と述べられております。
研究の意義を明確にし、研究費を獲得していくことは大事なことですが、一方で「純粋に研究が面白い!だからやるんだ」というシンプルな気持ちが基本的な原動力であるはずです。自分が面白いと思える自身の研究が学術的に大きな意義を持てるような、そうした「心」の方向性が重要であると感じました。 [Hassy]