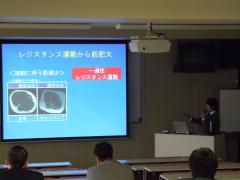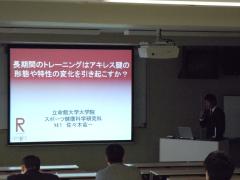2月24日に、草津市スポーツ少年団の指導者研修会に招かれ、お話をさせてもらう機会を得ました。
ご存じのように、日本スポーツ少年団は、1962年に「ドイツ・スポーツ・ユーゲント」をモチーフに、青少年の健全育成、特に「一人でも多くの青少年に、スポーツの歓びを!」という理念に基づき、青少年の心と身体を地域が一体となって育てるという目的で設立されました。
現在では、全国に36,000以上もの団体数を誇り、その団員数は88万人にも上ります。
ウインタースポーツでは、ジャンプ競技で金メダリストの原田さんや、スピードスケートのメダリスト清水さんや岡崎さんなどは、スポーツ少年団がスポーツを始めるきっかけとなったようです。
話は、戻って、その日本スポーツ少年団の傘下にある草津市スポーツ少年団の指導者講習会で、「子どもから"スポーツ大好き!"という言葉があふれ出るための大人のかかわり方」という演題で、講演をさせていただきました。
3つのポイントに基づいて、お話をしました...
①"スポーツマンシップ"について考える
②"スポーツ大好き!"を応援する大人のかかわり方
③スポーツ少年団・単位団(各チーム)の社会的存続意義について考える
左の画像は、2つめの「"スポーツ大好き!"を応援する大人のかかわり方」に用いたスライドの一部です。
子どもがスポーツに社会化されるにあたって、親や兄弟姉妹、また友達、教員、指導者といった「重要なる他者」と、学校や地域社会、またマスメディアや所属チームといった「社会文化力」の2つが、子どもとスポーツをつなぐエージェント(仲介役)になるいうことが示されたものです。
つまり、子どもたちのスポーツへの参加・不参加のみならず、スポーツそのものに対する価値観にも、スポーツ少年団という組織と、その指導者は、強い影響力をもたらしているということです。
講演では、我々大人は、スポーツをする子どもたちの言葉や声に、どれほど耳を傾けてきたのかという問いかけをし、「変えよう、わからせようと...」といった大人のエゴによるアプローチによって、子どもたちの主体性を阻害してきたのではないかというお話や、「褒めない...叱らない」子どもを勇気づけ、子どもの存在を認めるには、どのようなかかわり方をすればいいのか、また子どもの言葉に耳を傾け、心理的事実に目を向けるためには、「アクティブ・リスニング(積極的傾聴)」が重要であるといったお話をしました。
残念ながら、私自身がお話をしたため、講演の様子などの画像はないのですが、19時から1時間20分ほどの講演で、お仕事や家事などを終えられた後にもかかわらず、たった一人も寝ることもなく、最後まで、熱心に私のお話に耳を傾けてくださいました。
また80名ぐらいの参加者の8割以上は、なんと!女性の方...
概ねスポーツ少年団に登録されている指導者の9割近くが男性なのに、何で?と思ったのですが、後で、講演に参加された【忠】先生の秘書の方にお聞きしたところ、「単位団のチーム代表者に対する事務連絡会議と重なっていたためです」と...。
???
現場の指導者は男性で、チームの事務担当などは女性が...とのことでした...。
子どもたちの活動を支える「育成母集団(保護者の方々の集まり)」の方々にも、もちろん、お聞きいただきたいお話をしたのですが、さらにいえば、活動場面で"強い...(笑)"影響力を持つ、指導者自身に、より聞いていただきたかった内容なのですが...(笑)。
今日は、岐阜県のクラブマネジャー研修会、明日は、守山市のスポーツ指導者研修会にお呼びいただき、お話をさせていただく機会を得ています。
講演をさせていただくたびに、上にある私が勝手につくった(笑)ロゴをパワーポイントのスライドの中に組み込み、スポーツ少年団の理念と同様、我々立命館大学でも全ての人々とスポーツとの結びつきを強めたいというメッセージを送っています。
そのような機会をたくさんいただき、本当にありがたい限りです...。