この「社会」という言葉には、いろんなものがこめられています。
2012.05.22
最近のこと
この「社会」という言葉には、いろんなものがこめられています。
[ ] の記事一覧
2012.05.22
2012.05.21
先週のスポーツ健康科学セミナーⅡのゲスト講師に、医療法人 康生会クリニック 今井 優氏をお招きしました。今井さんは、体育系学部を卒業後された後に、医療関係の職場に着かれました。健康運動指導士ならびに心臓リハビリテーション指導士の資格をお持ちで、現在の所属先のクリニックで患者さんの運動療法に携わったり、後進の指導にあたったり、この分野の専門書を執筆したりされています。
健康運動指導士の養成は、1988年から始まり、現在まで24年経過しています。今井さんはその初期の頃に取得されました。ご存じのように、2006年に健康づくりのための運動基準2006、運動指針2006が出され(田畑学部長が深く関わっています)、「運動」というキーワードが国民の健康にかかせないものとして示されました。その後、「メタボ」という言葉が流行するように生活習慣病の概念が広まり、2008年から特定健診・保健指導が導入されるようになりました。
このような中、健康運動指導士の役割と認識も高まりつつあります。ただし、今後、医療機関を含め、民間の運動指導施設などで、さらに需要を高めるためには、「健康運動指導士」の認知と期待を高める必要があり、そのためには従来以上の能力を持った若い人材が求められる、と今井さんは強調され、「健康運動指導士」養成認定校である本学部の学生に大いに期待を語ってもらいました。
また、今後の健康運動指導士への期待として、①コミュニケーション能力、②楽しませる、③地域の特性の配慮、④学術面でのスキルアップが求められる。スポーツ健康科学部の強みは、「運動」指導が適切にかつ楽しくさせられること、ということも質疑応答でお話し頂きました。今井さんありがとうございました。
本学部からこのような能力を備えて、社会、国民の健康に貢献する「健康運動指導士」が巣立つことを楽しみにしております。
<<今週のちょっと、もっと、ほっとな話>>
今朝は「金環日食」が観られました!
【本日】真田先生NHKに生出演! 「Rの法則」 18:55~19:25
是非、ご覧下さい。
【忠】
2012.05.20
日常的に経験する色々なことがらからフーッと浮かび上がってくる、仕事としての思考に関して、ここ2回くらいは書いています。
私は家から百メートル位に田園が広がる所に住んでいます。先週前半から夜間の様相が急に変わってきました。玄関前の側溝には「シャーッ、ポチャッ、シャーッ」と、速くて不規則な水流の音が起こっています。田圃への水の引き入れと田植えとが始まったのです。それと同じ頃、「ゲロ、ケロ、ゲロ、ケロ」と蛙の鳴き声が一斉に響き渡ります。前の準備期間とは全く異なった田圃風景(昼間)と音声情況(夜間)にガラリと相が移行しました。
運動の学習や練習と関連してすぐ頭に浮かんできたのが、「期分け」という言葉です。「鍛練期→移行期→準備期→第1試合期→移行期→第2試合期→・・・」あるいは「導入期→反復・固定化期→応用・洗練期→・・・」などと、前の段階がつぎの段階に移行、あるいは相を転換していくことです。
今の状態をもたらしている要因の相互の働きが落ち着いたままでは、次の段階には移行しません。いつ、どの様な要因を、いかに(既存のものにとって代わるのか、それとも既存のものと結びつくのか等々)働かせるかが主要な問題です。学習や練習をサポートしコントロールする「スポーツ教育」の分野にとって、これら1つひとつが重要な議論の対象ですし、それらを内包する「期分け」という語は、この分野の基本概念の1つと言えます。
「期分け」という語や考え方に私が初めて触れたのは、45年ぐらい前の高校1~2年の頃、陸上競技マガジンという雑誌を通してでした(ずいぶん古い話で、恐縮です)。当時のソビエト連邦のN.G.オゾーリン(モスクワ体育大学教授)とA.O.ロマノフ(IOC委員)が編著者となって編纂された『スポーツマン教科書』(後に、岡本正巳訳、加藤橘夫・広田公一・平田久雄校閲、講談社、1966.5として刊行)が、同誌に分割翻訳で連載されました。当時クラブ活動で少し齧った程度ですが、自分達が行っていることを理論的に考えることができる参考書だ、という強い気持ちをもったことを覚えています。
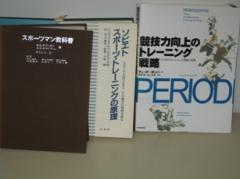 1964年の東京以後、68年のメキシコ・オリンピックに向けてスポーツ科学研究が急激に胎動する状況で、本書は纏められました。編著者は、日本語版への序文で次のように言っています。「競技者諸君は自分が何を、何の目的で、なぜ行うのかを十分に知り、理解し、自分のトレーニング計画の作成、運用に積極的に参加する必要がある。」「今日ではコーチ、医師、学者と協力して、スポーツマンが自分自身や強化方式に意識的に、合理的に対処することがスポーツにおいて大成しうる唯一の道である。」
1964年の東京以後、68年のメキシコ・オリンピックに向けてスポーツ科学研究が急激に胎動する状況で、本書は纏められました。編著者は、日本語版への序文で次のように言っています。「競技者諸君は自分が何を、何の目的で、なぜ行うのかを十分に知り、理解し、自分のトレーニング計画の作成、運用に積極的に参加する必要がある。」「今日ではコーチ、医師、学者と協力して、スポーツマンが自分自身や強化方式に意識的に、合理的に対処することがスポーツにおいて大成しうる唯一の道である。」
同書のなかでは自然科学の知識はもちろん、大小の組織に関わる行動指針などが教示・解説され、
要するに文理融合の具体的方策が多く議論されています。
これと同じ趣旨で、上記教科書の執筆者として参加していた、マトヴェイエフが下記のテキストを刊行します。自然科学の研究者と同じぐらいの規模で社会学や心理学、教育学の研究者が参画して、より一層緻密に仕上がっていると言えます。
L.P.マトヴェイエフ著、江上修代訳、川村毅監修『ソビエトスポーツ・トレーニングの原理』白帝社、1985.
さらに、「期分け」を正面にすえ、トレーニング科学の知見を総合的にまとめたテキストが、次に示すものです。
T.O.ボンパ著、尾縣貢・青山清英監訳『競技力向上のトレーニング戦略ーピリオダイゼーションの理論と実際』大修館書店、2006.
これは、様々な競技、欧米のトレーニングに関する実験的知見をあてはめても、十分耐える議論の枠組みを理論的に提供していると言えます。
大雑把に20年ごとに、「期分け」を内に含む、理論的テキストに出会ってきたと私は感じています。従って、システムの目的・目標とそれに加わる要因の働き方・働かせ方、システムの状態とその様相が転移していくプロセスの記述の仕方が、大きな共通の課題だと感じます。スポーツ教育は、様々なスポーツ健康科学の各論の成果や知見に支えられ、かつそれらを統合、総合する実践的理論を築いていく分野だと思います。スポーツ健康科学部の学生の皆さんやこれからこの分野に進出しようと考えている高校時代の皆さんには、機会があれば、現在では古典とも言うべき最初の2冊には、ざっと目を通して欲しいと願っています。
【善】
2012.05.19
2012.05.18
「心理的な時間の長さは、これまで生きてきた年数の逆数に比例する。すなわち年齢に反比例する」(P.ジャネ)と言われているように、1日1日が何と短いこと!そして1週間の速いこと!このブログの金曜日担当となってから早1月が経ちました。いろいろな形や手段があると思いますが、記録は記憶につながり記憶はまた人生を豊かにするのかもしれないと思っています。それでは個人的ことで恐縮ですがこの1週間の中でのことを2つほど。
ある資格研修会で「東日本大震災の中・長期的支援のあり方」(本郷一夫東北大学大学院教育学研究科長)の講演で、時間軸、文化、人間関係を考慮した支援といった観点からサイコロジカル・ファーストエイドの必要性とその紹介がありました。時間軸ではアニバーサル反応の例や、特に子供たちにとっては震災体験の意味は成長と共に違ってくること、また抱える問題も異なり、保護者のとの関係性も変わって行くことなどの認識の上に立った支援が求められているとのこと。
 テクターをつけているせいか非常に雄々しく、普段の教室での姿とは別人のように思えます。試合前のミーティングでは各自のやるべきことの確認、監督とコーチからのアドバイスの後、狭いミーティングルームの壁を突き破るような大きな声で応援歌を歌い(アイスホッケーは氷上の格闘技で心理学的には重要な儀式です)いざリンクへ。第1ピリオッドは互角。しかし第2ピリオッドでは流れが急に変わった感じで、攻めきれず、守りきれず、課題を残す結果となりました。「課題はやるべき次の目標」と選手の勇姿を讃え、次に期待!(老ブロガー・ハル)
テクターをつけているせいか非常に雄々しく、普段の教室での姿とは別人のように思えます。試合前のミーティングでは各自のやるべきことの確認、監督とコーチからのアドバイスの後、狭いミーティングルームの壁を突き破るような大きな声で応援歌を歌い(アイスホッケーは氷上の格闘技で心理学的には重要な儀式です)いざリンクへ。第1ピリオッドは互角。しかし第2ピリオッドでは流れが急に変わった感じで、攻めきれず、守りきれず、課題を残す結果となりました。「課題はやるべき次の目標」と選手の勇姿を讃え、次に期待!(老ブロガー・ハル)
2012.05.17

2012.05.16
2012.05.15
2012.05.14
先週末は、少し肌寒く感じられるほど気温が下がりました。皆さん、体調などは大丈夫だったでしょうか?これから一気に暑くなることも予想されます。くれぐれもご注意下さい。
大学のリサーチオフィースから、下記の写真にある特許証のコピーを頂きました。理工学部ロボティクス学科に所属していたときに、同僚の先生方、院生たちとアイデアメイクして、実験機をつくり、実験を進めてきた研究の成果が、「特許」という形で認められました。世の中に、「発明」という形で貢献できたことは凄く嬉しいですね。
大学・研究機関で、研究開発された成果は、「学会発表」「論文発表」の形式で公開されることになります。そのような成果の一つとして「特許」があります。特許は、著作権、意匠、商標などの知的財産権のひとつです。現物としてみることのできないアイデアでも、今までにない新規性が認められると特許として認定されることがあります。特許として認定されるまでには、①出願(自分の発明が、世の中にない新しいものであると特許庁へ申請する)、②公開(出願後一定期間をおいて公開されます。大抵はこのあたりで留まることが多いです)、③審査請求(特許発明として認められるかどうか特許庁に審査を依頼する)、④審査をパスすれば特許権として認証。
「人類の叡智は人類の財産」という発想ですので、特許として独占的にその権利を保有できるのは出願から20年となっています。それ以降は、誰が使っても構わないことになっています。つまり、世の中の発展のために、特に産業の発展のために貢献することになります。当然のことですが、既に「公知」(誰もが知っている)」ことは発明にはあたりません。ですので、論文・学会発表を済ませてしまうと特許にならないことになります。特に競争の激しい、生命科学分野などでは、アカデミックに発表するインパクトと同時に特許としておさえておくことが求められ、よりスピーディに発明として出願することが求めあらます。もちろん、同様な内容が世界中で行われているので、先に出した方に優先権が与えられます。
立命館大学スポーツ健康科学部、立命館大学大学院スポーツ健康科学研究科からも今後、多くの「発明(特許)」が誕生し、世の中に新しい智恵とアイデアで貢献することを確信しています。
先週のスポーツ健康科学セミナーⅡは、6班に分かれてのグループワークでした。キャリアセンターの方々にファシリテーターをお願いしました。各自が①何に取り組むのか、②何をもくひょうにするのか、③どのように取り組むのか、をまとめて発表していました。しっかりとできていましたとキャリアセンターのスタッフから聞かされ、さすがスポーツ健康科学部の学生!と嬉しくなりました。
【忠】
2012.05.13
京都市の西部,K市から毎日、自動車で通っています。片道45kmで約50~60分、その半分以上が高速道路です。数年前にBKCに隣接して新名神道路への草津ジャンクションと田上(Tanakami)インターが設置され、ものすごく便利になりました。学外から来られる人たち、特にバス等でのアクセスは東西どちらからも、かつてとは雲泥の差です。
通勤は無駄な時間ですが、それでも趣味と実益を兼ねて、物事を考える材料を提供してくれることがしばしばです。
通勤時間帯は毎日運転するドライバーが多く、老若男女さまざまですが、みんなそれなりに運転スキルがまずまず、ルートをよく知りあらかじめ決めた人たちが圧倒的に多いと思われます。ほとんどの人が時間内に目的地に着こうと急いでいますが、車が多い割には不思議にかなりの速さでスムーズに流れていることが多いと思います。
先日のような連休になると、日頃通勤に使われていない車も、人びとの速く、遠くへ移動する手段として高速道路に出ていくことになります。同じ道路に多くの車が一挙に出てくるのだから、渋滞があちこちで発生することは理解できますが、原因はそれだけではなさそうです。
通勤時間帯は混んでいるのですが、スピードと車間距離は多くの車の間で、相対的に安定しています。けれども連休中などは、それらが非常に不安定になっていることにすぐ気付きます。
前車との距離を極端に詰めているところと大幅に空けているところ、その中間距離もバラバラで、前方のあちこちでギクシャクした車の動きが目立ちます。そのようなときはしばらく走った後、車が短時間完全に止まってしまうことが多くあります。
前方のどこかで事故が起こったのかなと注意してしばらく走っても、前方にそのような形跡は見られません。車は自然と流れているのに、先ほどは何故急に止まってしまったのか、このように不思議に思えることに何回も出くわします。
誰もが危険への注意喚起を余儀なくさせられる個所では、トンネルの出入り口付近、合流地点、登り下り坂などがあります。アクセル戻してブレーキ準備、それだけでなく実際にブレーキングしたり、その合図を後続車に送ってしまう場合もあります。後続のドライバーもそれに「反応する時間」と「強さの程度」に「ずれ」があり、そのことがランダムにあちこちで起こっていることになります。けれども、流れの速さと流量によって、少しずつのずれが「協同」し、先ほどの渋滞と流れの相が生じ、その相転換の現れ方も異なるのです。ドライバーの側から言えば、流れに乗る、流れをよむ、ということになります。
これらの研究は、自動車安全工学での車作りや道路設計・建設等に関する多くの学会・研究所等から論文・記事が発行されています。また、ドライバーや人間因子に関することは、人間工学や心理学に関するいくつかの学会・研究所から豊富な情報を得ることが可能です。
車の運転に関する運動スキルの習得という狭くて限定した課題を設定する場合には、一方の極に初心者ドライバーの運転動作習得、他方の極にF1のエキスパート・ドライバーの運転技術が、具体的研究対象として取り上げられそうです。
でも、人びとは運転の初歩的スキルを習得してから長期間、何回も免許証を更新して車の運転を日常的に行っています。その間、運転のスキルは、その人が生活、レジャー、仕事等で車を有意義に使いこなすという大きな枠組みの中の下位要素に組み入れられています。様々な新規の場面で、常日頃と異なった車種や地形ルート、交通流状態で運転することへの適応能力は、10年間というスパンでとらえれば、一体どのような進歩あるいは停滞を示しているのでしょうか。初歩的な運転スキルの学習から始めて、その人がいかに社会的ドライバーとして成長したのか、という問題と同じだろうと思います。
運動学習は、具体的対象分野がどのようなものであれ、初心者が対象になる場合が圧倒的に多く、それに対する指導内容・方法が対応的に取り上げられることが主になっています。スポーツに関しても同じことが言えると感じます。高校や大学時代に競技スポーツの世界に関与する度合を弱めてしまい、「もう技術的に習得する課題はなくなりました」あるいは「もう、○○を練習しても仕方ありません」と言う人は、かなり多いと思われます。けれどもそれから後長く、野球やテニス、サッカー、バスケ等々に関わり、楽しむ人は、これから益々多くなると思われます。
文理の枠を超えて、運動学習の分野の研究や教育の課題は、このような人たちのもつ問題意識に応えることを取り上げていく必要があると思います。そして対象把握をする場合にも、時間軸を従来よりも相対的に長く取ってものごとを論議した方が良いと、私は最近感じています。
【善】