[ Fri ] の記事一覧
前回のブログに引き続き、沢木耕太郎さんの「
深夜特急2」を読みました。舞台はまずマカオからバンコクに移ります。旅行のテーマが「インドのデリーからロンドンまで路線バスで旅する」という事なので、依然として寄り道状態ですが少しスタート地点のデリーに近づいています。ここでもローカル電車を使い、地元のタクシーの運転手と懸命な値切り交渉を行い、土地の空気を存分に味わいながら旅を続けて行きます。行く先々で友人が出来、楽しい思いをしたり刺激を貰ったりしていて羨ましくも思いました。とはいっても筆者にはタイでの旅はあまりしっくりこなかったとの事で、タイをどんどん南下し、マレーシアを突っ切ってシンガポールに進んでいきます。
私はタイとマレーシアはいつか行ってみたいと思いつつまだ訪れた事がありません。特に近年はマレーシア(クアラルンプール)で学会等が開催される事も増えているので、いつか機会を見つけられればと思っています。
シンガポールは2010年に
World Congress of Biomechanics が開催された際に訪れる事が出来ました。学会には勿論学術的な発表や情報収集をしたり、人的なネットワークを作るために参加するのですが、世界各地を見て回れるというのも大きな楽しみです。学会では1週間くらい一つの土地に滞在する事も少なくありません。行動半径は大きくは出来ないですがその地区については歩いて回ることが出来ます。シンガポールに行った際は学会のセッション終了後の夕方から夜に掛けて様々な名所に行きました。丁度真夏の時期に行ったのですが、猛暑の日本よりも涼しかったのも印象的でした。大学院生の方々は国際会議で発表することも楽しみの一つにして研究に励むと良いと思います。
深夜特急の話に戻ります。シンガポールでも様々な人に出会い、多くを考え、筆者は次にカルカッタを目指します。デリーとカルカッタ、勿論同じインドの中にありますが地理的には結構離れています。ここでも大きな寄り道になるわけです。私の場合は海外旅行というと目的地と日程が決まっている事がほぼ 100% ですので、ここまで来ると珍しいお話し、という感じですね。
この本に触発されたわけではありませんが、先日神戸に旅行に行って来ました。立命館に着任するまで6年半程神戸に住んでいたので、家族で久しぶりに行ってみました。神戸在住時はしなかったことをという事で、六甲山の上のホテルに宿泊してみました。素晴らしい眺めでした。お値段もリーズナブルでした!他にも神戸牛のお店とか洋食屋さんとか、色々とお勧めの所があるので神戸に行く機会のある方は是非お問い合わせください。

今月で旅行や学会も一段落、9月はBKCに落ち着いて実験を進めたいと思っています。何事にもメリハリが大切ですね。
沢木耕太郎さんの「
深夜特急1」を読みました。この本は「
新潮文庫の100冊2015」に選ばれています。私の良く行く書店でも大々的にディスプレイがされており、中身をパラパラ見たところ面白そうだったので買ってみました。
沢木耕太郎さんの著書は以前にも「
敗れざる者たち」等を読んでおり、スポーツライターという印象を持っていました。「敗れざる者たち」の中ではマラソン、野球、ボクシング等様々な分野の選手にスポットライトを当て、その光と影を描いています。現在 Number 等の雑誌で見られるスポーツエッセイのジャンルの傑作と言える一冊だと思います。是非一度手にとって見て下さい。
「深夜特急」はそれとは異なり、紀行文のジャンルの作品です。インドのデリーから出発し(デリーまでは飛行機で行く)、乗り合いバスだけを使ってロンドンまで行く、というテーマだそうです。地球の広さを身体で実感するために、飛行機も鉄道も高速バスも使わない、とのこと。自分にはこの様な旅をした経験はありませんので(今後も無いだろうと思います、、、)珍しさもありのめり込むように読み進めて行きました。
文庫本としては6冊のシリーズで、私は現在2冊目を読んでいる所です。1冊目は何とデリーに行く途中に立ち寄った香港とマカオで数週間ブラブラしてしまった、という話。2冊目では次に立ち寄ったバンコクで同じ様な日々が始まります。流石の観察眼と文章力で、香港の喧噪やマカオのカジノの張り詰めた空気感までもが伝わって来る様です。この作品、以前から知っては居たのですが6冊の大部ということで読むのを躊躇していました。ですが今回読み始めて良かった、面白い作品に出会えたと嬉しく思っています。皆さんもまずは出だしだけでも読んでみてください。
そして読み始めると自分も旅に出たくなるでしょう。学生の皆さん、時間の沢山あるうちに世界を歩いてみてください。
楽しみながら英語のリスニング力を高めるやり方の一つとして、映画鑑賞をお勧めします。字幕無しで見られれば一番ですが、英語の字幕付きでも良いトレーニングになると思います。「リスニング」の練習をしようとする時に、何はともあれ量をインプットする必要があります。書店に行くとリスニング用のテキスト+CDのセット等が多数売られていますが、それらを1部または数部購入しても量的には十分では無いと思います。最初の導入の際は役立つでしょうが、ある段階以降は経済的かつ楽しく続けられるやり方で継続的にトレーニングするのが良いでしょう。
リスニングがそれほど得意でない方でも、映画を字幕無しで見てみると意外とストーリーが掴める事に気づくと思います。映画は2~3時間の間に起承転結の流れがあります。また実際には言語だけではなく、登場人物の表情、効果音、カメラワーク等、様々な手掛かりによって視聴者にメッセージを伝えてくれています。それらをキャッチして頭の中で咀嚼して、意味の流れを掴む事は非常に良いトレーニングになります。最初は英語の字幕を表示しても良いでしょう。リアルタイムに字幕を読んで内容理解の手助けにする事自体、実は結構英語力を要求されます。まずはこのレベルを目指して取り組んでみるのが良いかも知れません。
アメリカに住んでいた頃、近所の映画館では学割で4ドルくらいで映画を見ることが出来ました。元々映画が好きだったことも有り毎週のように観に行っていました。アメリカに行って一番最初に観た映画は「リーサル・ウェポン4」です。シンプルなストーリーのアクション映画ですので非常に解り易く楽しむことが出来ました。全般的にアクション映画は解りやすいですね。逆に当初比較的解りにくいなと思ったのはサスペンス物とか裁判物の映画でした。
DVD とかケーブルテレビとかで是非試して見てください。週に1本、1年間続けることが出来たらまずまずのレベルアップが出来ると思います。「そんな暇は無い」と思うかも知れませんが継続は力なりです。語学の力は一朝一夕には付きませんので、1年後のためと思ってトレーニングしてください。
毎年この時期になると思い出す事があります。初めてアメリカに住んだ時の事です。
20代の半ば頃、私は博士号を取るためにアメリカに留学する事を決意しました。当時はインターネットを通して情報を得ることも出来ず、何もかも手探り状態で進めて行きました。幸いにして出願する大学については、先週のブログでも触れた国際学会(International Society of Biomechanics)を東京で開催した際に色々な先生方に相談に乗って頂く事ができました。その結果幾つかの候補を絞ることが出来ました。
修士2年目の7月~11月に掛けてTOEFLやGREといった試験を受け、書類を用意し、お世話になった先生方に推薦状を書いて頂き、、、といった手続きを経て出願をしました。12月にはやるべき事は済んでいて、後は次の連絡が来るのを待つばかりとなりました。その間修士論文を作成したり公聴会があったりし、連絡を受けたのは3月頃だったと思います。メールで「電話で面接をするので○日の○時に取ってくれ」と言った内容で、ついに来たか、と思いました。
当時私は留学どころか海外に行ったことも無い(パスポートすら持っていませんでした)状態で、リスニングのテストの練習はしていましたが「ネイティブの方と電話で会話」というのは初体験だったと思います。通常の対面の会話では想像以上にボディーランゲージに助けられています。ここが勝負時と前日は一睡もせず朝の電話を待ちました。面接は上手く行き、財政支援(3年間TAをやりました)の話もまとまり、第一志望だった
アリゾナ州立大学へ行くことになりました。
アリゾナ州立大学の新学期は8月から始まります。1年以上全力で準備をし、待ちに待った大学院での生活を始めた時の事を、毎年夏の暑さと共に思い出します。とは言えアリゾナの暑さは日本のそれとは異質でした。
西部劇の舞台になった砂漠の大地、強烈な日差し、
サボテンだらけの乾いた土地、という所なので日本の基準で想像するのは難しいです。サングラスなどは日本から持って行った物では用を為さず早速買い換える事になりました。着いて1~2週間で大分日焼けしました。
今までの人生の中で、アリゾナ州立大学での出会い、学んだことはかけがえの無い物となっています。日々の生活も勉強も研究も、何もかもが大変でしたが全身全霊で取り組みました。本当に素晴らしい時間を過ごすことが出来、大学や先生方は勿論の事、友人、一緒に格闘技をした仲間、大学のある街、そしてアリゾナ州に今でも感謝しています。またいつの日か、必ず訪れようと思っています。関連分野の学会等見つけられた方は是非教えてください!
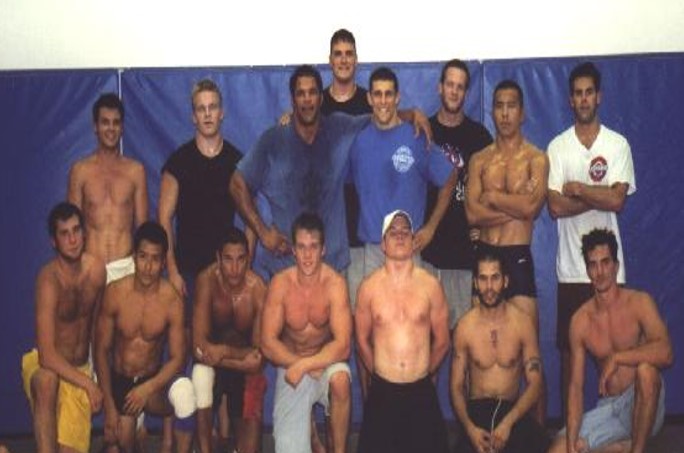
【忠】先生の以前の記事でもご紹介頂きましたが、International Society of Biomechanics に参加して来ました。場所はスコットランドのグラスゴーです。大規模な学会で、 Scottish Exhibition and Convention Center という会議場で開催されました。
学会HPはこちら会場HPはこちらこの学会は2年に一回開催されます。20年近く前、私が修士2年の時に、私の恩師が事務局長となって東京で開催した事があります。私自身も発表をし、また会場係として業務の担当もし、非常に強い印象を受けたことを今でも良く覚えています。それ以来私にとって最も大切な学会の一つとなりました。

今回立命館からは当研究室の学生さん2名、【忠】先生の研究室の学生さん1名、ポスドクの fktn さん、私が発表をしました。皆良く練られた内容で、立命館大学としても日本の研究者としてもプレゼンスを示せたと思います。
当研究室の学生さん2名については、初の国際会議ということで4月から準備をして来ました。4月・5月は2週間に一回、6月は週一回のペースで発表練習をしました。その課程で見違えるほど良い出来になったと思います。練習におつきあいくださった fjmt 先生、どうも有難う御座いました。
当日の発表も堂々としたもので嬉しく思いました。
帰国してから聞いたところ、「自分達の今居る位置が解った」「質疑応答が思い通りに行かず悔しかった」との事。自らを客観評価出来るのは良いことです。今回得た刺激を活かして研鑽を重ねてください。必ず今よりもレベルアップして行けるでしょう。
今回は所謂「ホテル」ではなく Bed & Breakfast という、日本でいえばペンションとか民宿の様な宿に宿泊しました。非常にアットホームな感じの綺麗な宿で大変くつろがせて頂きました。
オーナーの方は絵本作家でもあり、私の子供達にと言って絵本を2冊と朗読 CD をプレゼントしてくれました。有難う御座いました!
↓は宿の入口の写真です。

長い間訪れたいと思っていたスコットランドに行くことが出来、また発表も上手く行き、非常に良い旅となりました。この International Society of Biomechanics、2年後はオーストラリア・ブリスベンで開催されます。2年後を楽しみにしつつ、良い研究成果を出して行こうと思います。
「社会学」ではなく「社会人学」です。大学を卒業して就職をしたり、大学院に進学する際に大いに参考になる一冊と思い紹介します。もともとは東大で行われた講義内容に基づいて、人が実社会の中で生きていくために必要な基礎知識をまとめたテキストです。
私自身は27歳で博士号を取得した後、幾つかの期限付きのポストを経て来ました。幸いにも自分の仕事(研究)の継続性は確保できていましたが、ポストとしては何度も異動をしてきました。博士課程に進んだ学生さんは多かれ少なかれ同様の経験をされるのではないかと思います。企業や官公庁に就職する方もこの先50年位の内に何があるかは予測できません。そうした時に「社会人として働くとはどういうことか」という道標があると良いと思います。この一冊はその助けになると思います。
章立てを以下に書き出します。内容の概略をお解り頂けるのではないでしょうか。
第 1 章:働くことの意味と就職
抜粋:なぜ働くのか、就職する前に、大企業か中小企業か
第 2 章:会社というもの
抜粋:会社の選び方、会社の本質、成功する技術者
第 3 章:サラリーマンとして生きる
抜粋:年齢と年収、所得と税金、企業理念の変質と崩壊
第 4 章:転職と企業
抜粋:転職の心得、起業・独立の心得、親分と子分
第 5 章:個人として生きる
抜粋:結婚と家庭生活、子供と教育、人生とお金
第 6 章:人生の後半に備える
抜粋:老後、介護、保険
大学を卒業した後、就職(または起業)するなり大学院に進学するなり、自覚としては「社会人」の認識をはっきり持つことが求められると思います。既にご存じの事項もあるでしょうが、初めて目にして「そうだったのか!」と気付く事も多いと思います。
是非早い段階で読んでみてください。
2015.07.10
JMOOC 出張講義@立宇治
立命館宇治高校にお邪魔して来ました。段取りをして下さった tngc 先生、どうも有難う御座いました。
ただいま JMOOC で開講中の「ランニングのスポーツ健康科学」に関し、反転授業という形で2コマ講義させて頂きました。学生さんは事前にオンラインの講座を受講して事前レポートを作って来てくれています。10ページ以上のボリュームで書いてきてくれた学生さんもいて感心しました。講義開始の際に感想や疑問点を話してもらい、それに答えられる様に進めて行きました。
オンライン講座、事前に色々と考え検討を重ねて準備をしたのですが、矢張り受講者の方からのフィードバックを得る前に完成させなくてはならないという難しさがあります。通常の授業では学生さんの反応を見ながら繰り返し説明をしたり、別の角度からの考え方を紹介したり色々と工夫しています。一回の授業の中でもしばしば方向修正しますし、もちろん次週の準備の際にはその週の講義の際のインタラクティブシート等を大いに参考にします。それが出来ないオンライン講座というのは難しいな、と改めて実感しています。現在「ランニングのスポーツ健康科学」は 4000 名以上の方々が受講くださっているとの事。掲示板に頂くコメントを見て「これも講座の中で説明しておけば良かったな」と思うことが多々あります。
本日の講義は多くの学生さんが熱心に参加してくれていたと思いますが、バイオメカニクスの講義は物理や数学の要素が多く入るため「難しい」「何となくピンと来ない」というイメージもあるようです。常々思うのですが、この分野は実験から入った方が親しみ易いのです。微分とか積分とかの計算にしても、カメラで撮影した動画からボールのスピードを計算する、等の処理をやってみると意外と解りやすいし本当の理解につながると思います。今日の学生さん達にはまたインテグレーションコアにもお越し頂く予定ですので、その時に改めてスポーツ科学・バイオメカニクスの面白さに触れて頂ければ、と思います。
近頃我々の研究室で行った実験の紹介をします。
7月半ばにスコットランドで開催される International Society of Biomechanics で発表する内容で、タイトルは Impact of boxing punches assessed with wearable inertia sensor and motion capturing です。ボクシングのパンチの衝撃力を測ろう、という研究です。被験者・験者としてご協力下さった皆さん、有難う御座いました!
私は大学生の頃ボクシング部に所属していました。部としての合同練習が週5日、自主的なロードワークも入れて週8回位練習していたと思います。推薦入学の無い大学としてはまずまずのところに位置しており、国体や全日本選手権に出場する選手も多数いました。私の2年後輩が全日本選手権で3位に入賞したのが部としては歴代最高位ではないかと思います。私自身は減量が厳しすぎたこと、大学院の入試日程とバッティングしていた事が理由で、国体予選を勝ち抜いたのち本戦を辞退して部活動を引退しました。
ボクシングでは練習でも試合でも頭部に衝撃を受けます。その衝撃力はどの程度の大きさなのか?と思い、加速度センサを使って計測をしてみました。小型・軽量・無線のセンサで、断線や故障の心配も無く実験をデザインすることが出来ました。加速度センサはサンドバッグに取付けます。サンドバッグの質量は 15kg と解っていますので、Newton の第2法則
力=質量×加速度
を用いるとパンチによってサンドバッグに与えられる衝撃力が計算できます。
結果として、左ストレートの衝撃力は 1700 N 位、右ストレートの衝撃力は 2700 N 位というデータが得られました。kg 重の単位で言うとそれぞれ約 170kg 重、270kg 重程度です。ただし今回の実験は予備動作無しのパンチですのでフットワークに乗せたパンチ、或いはワン・ツーを打った際の右ストレートの場合には更に大きな衝撃力になるのではないかと思います。
今回使用した様なセンサはヘッドギアに装着しても殆ど邪魔にはなりませんので、練習や試合の際の安全管理に使えるのではないか、と考えています。ボクシングは素晴らしいスポーツだと思いますが実施に伴うリスクは軽視できません。ボクシングを含め、格闘技全般をより安全に行う事に研究を通して貢献出来れば幸いと思います。
2015.06.26
100のモノが語る世界の歴史
先日東京に行った折に、東京都美術館で開催中の「大英博物館 - 100のモノが語る世界の歴史」を見に行きました。東京都美術館は上野公園の中、公園の奥の方の上野動物園の近くにあります。私は通っていた高校が近くのエリアだったので上野には良く行きました。教室にテレビを置こうという事になって皆でアメ横に買い物に行ったりしていました。そういう事を黙って見ていてくれる大らかな高校でした。
東京都美術館のHPさて展覧会ですが、大英博物館の展示物から選りすぐりの100件が来ています。大変な混雑との話を聞いていましたが、時間が遅めだったせいか比較的空いていたのだと思います。それぞれの展示物をゆっくり見ることが出来ました。そのためあっという間に2時間程が経っていました。多少心残りではありましたが新幹線の時間が決まっていたため、丁度一通り見終わったところで美術館を後にしました。
特に印象に残った展示は以下の3点です。
・オルドヴァイ渓谷の握り斧
約140万年前の物だそうです。石同士を打ち合わせて作った石器ですが、どこからどう見ても「切るための道具」でした。機能美を感じさせる形をしていました。それほどの太古に明らかな意図を持った道具が存在していたという事に驚きを感じました。
・ロゼッタ・ストーン(レプリカ)
紀元前196年に出された勅令が刻まれた石碑の一部です。同一内容の文章が三つの表記法(古代エジプトの神聖文字、同民衆文字、ギリシア文字)で刻まれています。この石碑が発見されたのが1799年。それまでは神聖文字の解読はされていなかったのですが、三つの表記を比べ合わせることで神聖文字の解読が出来る様になったという、文字通りの記念碑です。
・バカラの水差し
1878年の製品、パリ万博のために製作されたそうです。シンプルな「美しさ」という意味で今回の展示物の中でも際立っていました。色々な角度から見易い位置に展示され、多くの人々が見とれていました。人間にこんな物が作れるのか、、、と私も感動しました。
この展覧会、上野公園では今週末で終了しますが関西にも来る予定です。一旦九州国立博物館に行った後、神戸市立博物館で今年9月から来年1月に掛けての開催です。
皆さんも是非足を運んでみて下さい。
展覧会のHP
我々の研究室では毎週水曜日に研究ミーティングを行っています。学部生の場合は専門演習、院生の場合は合同ゼミ等の場でも研究のディスカッションは行っていますが、この水曜ミーティングはそれらとは異なる場と考えています。一言でいえば「学会や論文発表のための準備をする場」です。「準備」とは広い意味の準備で、研究構想や実験計画の立案も含みます。要するに自分達の成果を外に出し厳しい評価にさらされた時、それでも戦えるクオリティを達成するための場と考えています。
2014年度に立ち上げた当研究室ですが、学部生に加え今年4月に大学院生2名が入学したのを機にこの研究ミーティングを始めました。現時点でのルールはただ一つ(時間厳守とか研究倫理を守るとか協力し合うとかは当然の事として)、毎週必ず研究を前進させること、です。皆日々の生活の中で様々な事情があり、体調にも気分にも波があるので毎週コンスタントに研究を進捗させるのは容易ではないと思います。ですが「少しでも良いから必ず進める」と決めて、それが習慣化すれば却って進捗のない時が居心地悪くなるものです。
ミーティングのスタート当初から fjmt 先生も毎回ご参加下さり大変助かっています。いつも有益で productive なご助言を頂きありがとう御座います!
izi君:着実にレベルアップして来ています。自ら調べて勉強する姿勢、解らないことは素直に認めて学ぶ姿勢に感心しています。
wkmyさん:コツコツ続けて来た成果が蓄積されて来ていると思います。もう実験も始められると思うのでますます面白くなってくると思いますよ。
akgm君:ここ暫くの伸び率が素晴らしいです。お世辞ではなく何度も驚かされました。細かい緻密な作業も覚えて行きましょう。
kdu君:学会の準備も完成度高く仕上がって来ました。超一流の方が沢山集まる会ですので、良い刺激を受けて今後の糧としてください。
nkmr君:就職活動もそろそろ落ち着いて来たでしょうか?卒業前に学会発表することを目標に進めて行きましょう。
努力に勝る才能無し、継続は力なりです。Good Luck!







