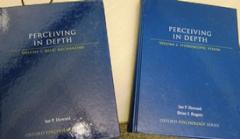まずは復習です。
間接的エネルギー源とは、「糖質」、「脂質」、「タンパク質」です。
日常的な有酸素運動では間接的エネルギー源のうちタンパク質(アミノ酸)は
運動中の脂質と糖質の利用割合は、主に3つの要因で決まります。
つまり運動時間、運動の強さ(強度)、およびトレーニング状態が関係します。
ちなみに、体重70kgの男性の場合、体内の糖質貯蔵量は2,000~2,500kcal
(筋肉内グリコーゲン300~400g、肝臓内グリコーゲン100g、細胞外液グルコース20g)程度です。
体脂肪率15%とすると、脂肪が10㎏程度ありますからその脂肪としての貯蔵エネルギーは
70,000kcalつまり30倍程度となります。
運動強度(最大酸素摂取量に対する割合)およびトレーニング状態と脂質および糖質の利用割合を
図2に示します。
横軸は運動強度、縦軸は脂質と糖質の利用割合が示されています。
グラフには幅(黒い帯状の部分)がありますが、帯の上の方はあまり運動トレーニングを
していない人、下の方はよくトレーニングしている人のデータです。
この図から分かることは、身体活動強度が低い(家事やゆっくりした歩行など)
うちは脂質と糖質が共に50%程度使われ、中等度~高強度の運動
(ジョギングやサッカーの試合など)になると糖質が多く使われ、もうそれ以上
できなくなる強度ではほとんど糖質のみが使われるということです。
また、よくトレーニングをしていると運動強度が高くなっても脂質を
ある程度使うことができることも分かります。
【今日の1 shot!!】
金星の太陽面通過!
滋賀大学の江﨑先生から提供いただきました。
画像の倍率を上げていただくと分かるかと思いますが
黒点やコロナが見えます。
【Hama】