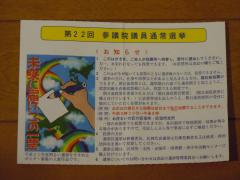先週は日本全国猛烈な雨でした。ゲリラ豪雨とよばれるぐらい亜熱帯のスコールを彷彿とさせる激しい雨でした。多分にもれず、先週の水曜日に広島へ出張した際には大雨でした。新幹線も大幅に遅れてしまい、山陽新幹線も広島止まりとなってしまいました。
同行していた【敦】先生からは、「先生の雨男パワーにはかないませんわ~!」とお褒め!?の言葉を賜りました。いずれにしましても約束時間から1時間遅れで到着しましたが、Dr.Will Jonen と無事会うことができ、インターンシップの打ち合わせをすることができました。話をしている折に、Dr.Jonenが乳酸の研究をしていて、うちの【Hassy】先生とUCバークレーで会ったことがあるとのこと。【Hassy】先生も記憶にあり、「ああ、Willは覚えていますよ!気の良い研究者ですよ!」とのこと。世の中狭いものですね。私もDr.Will Jonenは、オハイオ在住の友人の紹介でした。いずれにしてもネットワークも巡り巡ってつながっていることを感じます。
7/17(土)は、NS研究会がありました。この研究会発足には色々な経緯がありますが、そのうちの一つはMR導入に伴っての勉強会をしながら、世界的な研究を目指そう!というものでした。隣の滋賀医科大学には、MRの世界で非常に高名な犬伏先生がおられます。お顔だけは知っておりましたが、直接お話しをしたことはなかったのですが、無謀にも直接電話して、経緯をお話しして参加要請をさせて頂きました。犬伏先生からは二つ返事でOKを頂きました。以来、毎回ご参加頂いて、有益なコメントもらっています。今回は、ワールドカップでの日本の活躍を例にしながら、「個別の研究者が頑張るだけでなく、スポーツ健康科学部のみなさんは、チーム力、総合力で世界的な研究をして欲しい」と激励を頂きました。総合的・学際的な本学部の特徴を生かして、『チーム力』で世界のトップ・ジャーナルに載るような研究成果をだしていきたいと参加教員一同、再確認いたしました。


 7/18(日)は、第5回Athletic研究会があり、午前中は学生向けのセッションで、湯浅さん(トレーニング指導者)、陰田さん(アスレティックトレーナー)からスポーツ現場に関わる仕事(キャリア)についての紹介がありました(お二人とも水曜朝8時の『チームゼロ』に参加してもらっていますので、詳しいことは直接尋ねて下さい)。午後は、後藤一成先生の講演と本学スポーツ強化オフィース所属のアスレティックトレーナー、ストレングスコーチからの現場報告がありました。スポーツ健康科学部の一期生も多数参加して、熱心に質問をしており、この分野への強い関心を感じました。実は、この研究会のはじまりは、ストレングスコーチとして本学の卒業生である山田佳奈さんが着任してきて、私の研究室に勉強会に参加するようになったのがきっかけでした。勉強熱心な彼女に、「本学のスポーツ強化オフィースには、アスレティックトレーナー、ストレングスコーチが、衣笠、BKCのそれぞれのキャンパスに配置されているから、年に何回か全体集まっての研究会でもつくってみたら?」と勧めたところ、持ち前の組織力で、年2回の研究会を定期開催するようになりました。スポーツ健康科学部の学生、院生とも馴染みの研究会ですので、今後ともサポートしていきたいと考えています。先生方にもご協力をお願いすると思います(ちなみに昨年は【聡】先生に講演をお願いしました)。
7/18(日)は、第5回Athletic研究会があり、午前中は学生向けのセッションで、湯浅さん(トレーニング指導者)、陰田さん(アスレティックトレーナー)からスポーツ現場に関わる仕事(キャリア)についての紹介がありました(お二人とも水曜朝8時の『チームゼロ』に参加してもらっていますので、詳しいことは直接尋ねて下さい)。午後は、後藤一成先生の講演と本学スポーツ強化オフィース所属のアスレティックトレーナー、ストレングスコーチからの現場報告がありました。スポーツ健康科学部の一期生も多数参加して、熱心に質問をしており、この分野への強い関心を感じました。実は、この研究会のはじまりは、ストレングスコーチとして本学の卒業生である山田佳奈さんが着任してきて、私の研究室に勉強会に参加するようになったのがきっかけでした。勉強熱心な彼女に、「本学のスポーツ強化オフィースには、アスレティックトレーナー、ストレングスコーチが、衣笠、BKCのそれぞれのキャンパスに配置されているから、年に何回か全体集まっての研究会でもつくってみたら?」と勧めたところ、持ち前の組織力で、年2回の研究会を定期開催するようになりました。スポーツ健康科学部の学生、院生とも馴染みの研究会ですので、今後ともサポートしていきたいと考えています。先生方にもご協力をお願いすると思います(ちなみに昨年は【聡】先生に講演をお願いしました)。
先週は「つながり」を感じることの多い一週間でした。
【忠】