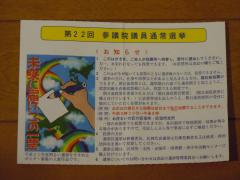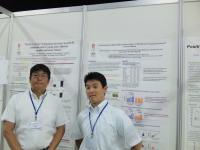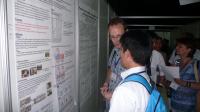W杯サッカーも準々決勝が始まり、ディフェンスからシンプルかつ素早い攻撃で得点を重ね、今大会優勝候補の本命中の本命といわれたブラジルが、鉄壁といわれるオランダディフェンスを完全に崩しきれず、敗退してしまいました。今日は、"因縁の対決"といわれるドイツ対アルゼンチン戦など、W杯サッカーからまだまだ目が離せず、睡眠不足の日々が続きそうです...(笑)。
我が"侍ジャパン"の歴史に残る戦いぶりに、日本列島が沸き返り、ビデオリサーチの調べによれば、23時にキックオフした日本対パラグアイ戦の関西地区における平均視聴率は54.1%で、瞬間最高視聴率も62.3%に上りました。結果は、ご承知の通り、120分間の死闘後に、残念ながら、PK戦で惜しくも勝利を逃しました。
スポーツが、我々の心をつかんで離さないのは、プレイヤーのみならず、彼らを陰で支える人たちも、声援を送り続ける我々国民も、みんなが"感動"を共有するからに他なりません。スポーツシーンの切り取り方や感じ方は、まちまちなのかもしれませんが、いずれにしても我々は、懸命に戦う選手の姿に目を奪われて、心が動かされます。
"スポーツは、筋書きのないドラマだ!"とよく言われますが、今回のW杯を戦った"岡田ジャパン"の戦士たちに我々が強い共感や感動を覚えたのは、"チーム一丸"や"チームワーク"だけでなく、厳しい戦いに臨む選手たちの"懸命でひたむきな姿"に感情移入しているからでしょう。
これとよく似た感情を抱くのが、これから戦いが始まる高校野球...。特に普段、野球をみない人までもが、汗と泥と涙にまみれる高校球児に心を奪われます。
それは、我々がチーム一丸、チームワーク、懸命さ、ひたむきさということを好む国民性を持ち備えているということであり、また少し穿った見方をすれば、我々自身がそのような体験から遠ざかっており、自らの心を揺れ動かされるような出来事に出くわしていないという感情の裏返しなのかもしれません。
とにかく、選手のみならず、監督やコーチを始めとした数多くのスタッフを含め、岡田ジャパンにかかわる全ての人たちに惜しみない賛辞を送りたいと思います。
"惜しみない賛辞"といえば...
PK戦で、日本が敗れ去った後に起こった出来事に、私は心を奪われました。それが、今回のテーマである"スポーツマンシップ"にかかわる出来事です...。

前置きが長い...とまた叱られそう...
日本対パラグアイ戦は、120分の死闘の末、PK戦に突入し、日本チームの3番目のキッカーとして登場した駒野選手の蹴ったボールが、ゴール上部のクロスバーに阻まれ、全員のキッカーがゴールを決めたパラグアイチームが勝利を収めました。当然、パラグアイチームは勝利に歓喜し、紙一重の差で敗れた日本チームは、どの選手もうなだれ、崩れ落ち、涙を流していました。
PK戦とは、本当に過酷な手段です。
1994年のW杯アメリカ大会の決勝戦のことです。決勝へと駒を進めたのはブラジルとイタリアで、今回と同様に試合はPK戦にまでもつれ込みました。イタリアチームは、守りの要であったバレージ選手と、チームのエースであったバッジョ選手がPKを外し、ブラジルが優勝しました。
その後、バッジョ選手が残した名言があります。
「PKを外すことができるのは、PKを蹴る勇気を持った者だけだ。そしてPKを決めても誰も覚えていないが、外したら誰もが忘れない...」
勝敗が決した後、責任感の強い駒野選手は、ピッチでなかなか立ち上がることができませんでした。彼は、"PKのスペシャリスト"と言われるぐらいの選手で、話によれば、彼は、中学時代からPKを一度も外したことがなかったようです。
控え選手を始め、ディフェンスの要であった中澤選手が駒野選手を抱擁したり、自分自身を責めようとする駒野選手を多くの選手が労いの言葉をかけたり、慰めたりするシーンなどがテレビなどで多く報道されました。特にケガや選手起用の方針などにより、チャンスに恵まれず、苦労人と呼ばれる駒野選手のことをよく知る同級生の松井選手が彼の肩を抱き、目を真っ赤にしながら、ずっと寄り添っているシーンなどは、多くの人にとっても印象的だったことでしょう。
そこで、私が心を奪われたシーンです!
テレビやインターネットなどの報道で、いくつか取り上げられていたので、ご存じの人もいるかもしれませんが...
画像には、著作権があり、無断転用などができないため、以下のURLを見てほしいのですが...。
http://cache.daylife.com/imageserve/0baI29xgA29e9/610x.jpg
これは、パラグアイチームの5人目のキッカーで、最終的にパラグアイを勝利に導くPKを決めたバルデス選手が、うなだれる駒野選手に駆け寄り、額を当てて何かを伝えているシーンです。
報道によれば、彼は、駒野選手に対して、「お前が外したゴールは、必ずオレがスペインゴールにぶち込んでやる」と伝えたとのことです。涙で言葉にならなかった駒野選手に代わって、同級生であり、親友の阿部選手が"Thank you"とバルデス選手に言ったようです。
バルデス選手のみならず、幾人かのパラグアイチームの選手が駒野選手に駆け寄り、労いの言葉を駆けている様子が、報道で伝えられました。
私は、これぞ"スポーツマンシップ"だと思いました。
スポーツには勝敗がつきものです。一時、運動会で順位や勝敗を決めないという、ある意味、歪なことが学校教育機関の中で行っていましたが、競争や勝敗は、それが全てではないにしても、スポーツにおける醍醐味であり、多くの人たちは、この勝敗から多くのことを学んできました。
"Be a brave fighter and a good loser"
"果敢なる闘志で相手に立ち向かう戦士であるとともに、潔き敗者であれ"...こんな意味でしょうか...。
私の心が奪われたシーンは、"潔き敗者"よりも、"誇り高き勝者"に焦点が当たられたものかもしれませんが、勝敗が決し、ノーサイドの後は、勝者は勝ちにおごることなく、敗者は潔く、ともに両者の健闘を称え合い、相手をリスペクトする...、そのような気持ちが"スポーツマンシップ"という言葉に込められた意味だと私は理解しています。
W杯サッカーは、オリンピックと同様に、国を動かす、一大イベントです。
勝敗に一喜一憂するばかりか、かつては、敗戦チームの選手が帰国後に射殺されるという事件も起こったことがあります(1994年に起こったコロンビアチームのエスコバル選手の悲劇)。
今回も"世紀の大誤審"と言われるようなシーンによって、様々な物議を醸し出していますが、ビデオ判定の導入ばかりか、ゴールにセンサーをつけろなど、試合後の監督や選手の"拙走のない"コメントにはうんざりし、いくらW杯とはいえ、今回のテーマにあるような"good loser"とはほど遠いようにも思えます。
そのようなレフリーの苦悩を描いた映画が現在、上映されています。
"レフリー 知られざるサッカーの舞台裏"
http://www.webdice.jp/referee/
また知っているようで、知られていない"スポーツマンシップ"については、広瀬一郎先生が素晴らしい本をお書きになっています。
広瀬一郎(2002)「スポーツマンシップを考える」ベースボール・マガジン社.
スポーツ健康科学部の学生は、スポーツマンシップについて語ることができるとともに、それをスポーツシーンのみならず、社会の様々な場面で、行動に示すことができる人になってほしいと思います。
スポーツとは何か?スポーツマンシップとは何か?
この学部で、しっかりと学んでほしいと思います。