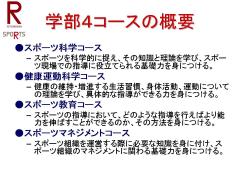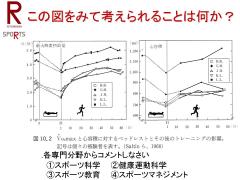スポーツ健康科学部の学生は、スポーツの実技と直接関わる科目として、スポーツ方法実習とスポーツ指導実習を受講する。これらの違いを簡単に言うと、スポーツ方法実習は、自分が行うものとしてスポーツを位置づけており、スポーツ指導実習は他者に指導するものとしてスポーツを位置づけている。詳しく知りたい方は、以下を参照してください。
★スポーツ方法実習
1 基礎科目
(1)教養科目
(ア)総合学術科目A
(イ)総合学術科目B
(A)各スポーツ方法実習科目
★スポーツ指導実習
3 専門科目
(3)実習科目
(ア)コーチング実習
(A)各スポーツ指導実習科目
同じようにスポーツに関わるのであるが、その科目の性質は異なっている。これらの区分を学生は理解して受講してもらいたい。
同様に、教員もその区分を踏まえて指導する。
今年の4月に開設された学部であるので、スポーツ健康科学部では、この区分を明確にして、指導ができるように、月1回程度の割合で、担当者を中心とした会議が行われている。
そして、教員の担当者の会議では、模擬的な指導を学部生が行うとよいのではないか、ということになった。
ここから先である。
通常は、「それでは、次年度から取り組みましょう」というのが、ほぼ通例である。
ところが、である。それを直ぐに試してみようという先生がおられた。スポーツ健康科学部のm先生である。
「良い」と思ったことは、とにかくやってみよう、ということである。
このような進取の精神は、本当に素晴らしいと思う。
上手くいかなければ、やり直してみよう。自分がいいと思ったことは、まずやってみよう。
実は、このように考えている先生は、我がスポ健の先生には、とても多いのである。
スポ健の先生は、本当に素晴らしい先生が多いと思う。
私たちも、続いていきたいものである。
学部生には、これらの授業を受けて、優れたスポーツ指導・体育指導の能力を獲得して欲しいと切に願う。
【 智 】(201001 m先生からの写真)