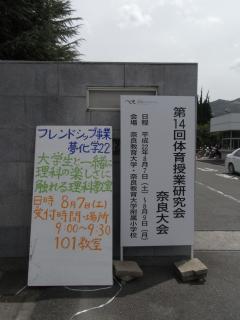先週お伝えしたように、名桜大学(沖縄県名護市)に訪問調査に出かけてきました。
皆さんのご期待通り!? ときおり雨が降りました。訪問調査の時には、下の写真の
ように雨雲から海面をたたきつけるような大雨が接近するのが見えました。最終日の
出発時には、突如のゲリラ豪雨に見送られるようにホテルを後にすることになりました。
さて、今回のFD活動は、木曜日の【ippo】先生まで連続4回に分けて報告します。
1回目の私からは全体の概要を報告します。名桜大学が文部科学省からGP(Good
Practice、優れた取り組み)に採択されている学生支援プログラム「先輩・後輩コミュ
ニティを 基本とする学習支援センターの構築」につきまして、国際学群教授の木村
先生に詳しく話を伺いました。
下の写真(左が木村先生、右がウエルナビの学生さん)

学生の力を活用した学生目線で正課学習の支援(ウエ
ルナビ),サポート
(言語学習センターのチューター、数理学習支援センターのチュー
ター)ならびに就職サポート(S-CUBE)まで、幅広くシステム化されていて学生自身が
大学の教育に参画し、ならびに後輩支援に取り組むことで,大学により愛着をもち、
卒業後も後輩を含めて大学を愛する気持ちを醸成させる大きなシステムとなっています。
本学にもオリタ-、就職支援のジュニアアドバイザーのような制度があります。
システムは安定するとかえってメンテナンスをおろそかにするところがあります。永続的
に上手く機能するためには、定期的なメンテナンスのための「面倒をみる」「相談にのる」
というあまり目に見えない地道な支えが必要であることも学ばせてもらいました。そして、
学生の自主的な活動に対して、教職員が理解し「ほめる」「激励する」「認める」ということ
をさりげなく行っているところも参考になりました。
今回の訪問調査では、学部の各コースから1名の先生に出張してもらいました。今回の
FD活動の目的は、学部の人材育成目標である『リーダーシップを備えた人材』に育てる
ために、リーダーシップをカリキュラムマップに落とし込むことです。2泊3日の出張期間中、
訪問調査のみならず、朝食を食べながら、移動中、夕食を囲みながら、四六時中このこと
を中心に学生育成のためのディスカッションができました。同じ、空間、時間を共有し、
ひとつの目標に向けて教員仲間と協働できていることを実感したことも大きな成果のひとつ
です。
今後も学部全体としてFD活動を推進するとともに、三間(時間、空間、仲間)を共有しながら
教育・研究に大きな成果があげられると確信しています。
【忠】