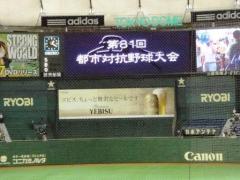草津市では、現在、スポーツ振興計画の策定に向けて様々な準備や取り組みが行われています。
国や地方自治体が様々な事業を執り行う上で、政策がスポーツ振興にとって心臓部に当たるということは、「スポーツ立国戦略」が策定されたときに、すでにブログでお伝えしたとおりです。つまり、1961年に公布されたスポーツ振興法に準じれば、国のスポーツ振興に対する方向性を示したものが「スポーツ立国戦略」であり、都道府県や市区町村といった各地方自治体は、この国の方針を参酌しながら、地域性を加味し、スポーツ振興の方向性を定めるためにスポーツ振興計画を策定しなければなりません。
草津市教育委員会では、まさに草津市のスポーツ振興の顔となる計画の策定に乗り出しています。この政策の策定に際して鍵を握るのが「スポーツ振興審議会」という組織ですが、審議会は、草津市教育委員会から委嘱されたスポーツ関係団体、学識経験者、市民からの一般公募といった方々から構成されており、振興計画の策定に向けて様々な角度から意見を述べます。我が立命館大学からは、佐藤副学部長が委員長として振興審議会をとりまとめていらっしゃいます。
草津市と立命館大学は、官学の包括協定を結んでおり、スポーツ健康科学部の数名の教員が、スポーツ振興審議会の運営やスポーツ振興計画の策定にかかわるサポートをしています。そのサポートの1つとして、現在、草津市内で進めているのが、「草津市民の運動・スポーツ活動と地域生活に関する実態調査」です。スポーツマネジメント論の授業で、「マーケティングのはじめの一歩は、"顧客"の声をキャッチすること」とメッセージしましたが、まさにその作業を現在行っています。
この調査は、草津市民の20歳以上の男女を対象に、層化多段階無作為抽出法(年齢や性別、また居住地域といった草津市民の地域特性や比率に応じて、調査対象者を無作為に抽出する方法)によって、2,992名をサンプリングし、アンケートを実施しています。調査は、草津市民の日頃の運動・スポーツ活動の様子やスポーツ振興に対する意見を伺い、その調査から拾い集めた声を草津市の政策に活かそうというものです。ただ調査は、草津市民を代表する2,992名の方々から一人でも多くの声を集めることが重要となります。つまり、調査の回収率が10%では、草津市民の1割の意見しか反映されないことになってしまいます。市民の方々にも、様々な事情があることなので、100%の回収というのは、無理としても、一人でも多くの市民の方々の声を拾い集めたいので、このブログをご覧になった草津市民の方々で、お手元に調査票が届いた方は、ぜひ調査にご協力いただければと思います。
以前、国のスポーツ振興の柱となる存在が「総合型地域スポーツクラブ」であるということをブログで書きましたが、全国各地では、このクラブを育成するために様々な取り組みが行われています。その1つとして、クラブをマネジメントするための専門的知識とスキルを要した「クラブマネジャーの養成」があげられますが、いま富山県の養成講習会の講師として招かれ、サンダーバードに乗車しています...。テーマは、「総合型クラブのマーケティング:魅力あるプログラムづくりと住民の啓発」...。一人でも多くの方々にクラブマネジメントを進める上でのきっかけづくりができればと思っています。
明日は、鳥取県、来週は京都府で同様の講習会が開催され、講師として招かれます...。地域の方々とふれあうことができるだけでなく、立命館大学でスポーツマネジメントについて学ぶことができるということも知ってもらうチャンスとなり、本当にありがたい限りです。