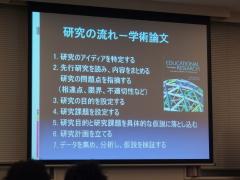22日から25日まで、埼玉大学で開催された日本行動計量学会に参加しました。
スポーツマネジメント研究も他の社会科学領域と同様に、人間の行動や組織の行動、またその測定尺度や統計的な分析手法の開発に余念がありません。さらには、スポーツマネジメント研究は、それらの結果をマーケティングや経営戦略にどのように活かすのかというインプリケーション(実践的示唆)が研究で重要な鍵を握ります。
今回は、ippo先生から紹介いただき、初めてこの学会に参加することにしました。ippo先生から提供していただいた情報で興味を引いたのは、「ソーシャル・キャピタルのマルチレベル分析」でした。
"ソーシャル・キャピタル"って何?と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、この概念は、私がもっとも関心を寄せているスポーツ振興とまちづくりの研究を進める上でも重要なキーワードです。
ソーシャル・キャピタルとは、この研究の第一人者であるPutnam先生によれは...
「協調的な行動を促進することにより、社会的な効率を改善しうる信頼・規範・ネットワークといった社会的組織または仕組みの特徴」
と定義づけられるものです。
もちろん、ピンとこないと思います(笑)。
Putnam先生が2000年に発表した"Bowling Alone(孤独なボウリング)"の事例を使って、簡単に説明しましょう!
アメリカ人に愛されてやまないボウリングですが、1980年から1993年までにボウリング人口は約10%増加しているのですが、リーグボウラー(クラブやチームに所属し、リーグ戦に参加する人たち)の人口は約40%も減少しています。Putnam先生は、このような現象がどのような意味をもたらすのかをデータを添えて論じています。
「リーグボーラーの減少は、ボウリング場の経営者にダメージをもたらす...」
これを裏づけるものとして、クラブやチームに所属し、仲間と一緒にボウリングを楽しむリーグボーラーは、一人でボウリングをする人よりも、ビールやピザの消費金額が3倍違うというデータが提示されています。
考えてもらえればわかると思いますが、居酒屋に行って、一人でグラスを傾けるよりも、気の合う仲間とワイワイしながら、お酒を飲んだ方がきっとお酒も進むことでしょう。私の上司で沈着冷静な行動をとる【忠】先生も、学部のメンバーと一緒に宴会に出かけると、翌日、「ちょっと飲み過ぎたわぁ~」といつもおっしゃっています(笑)。
つまり、協調的な行動が促進されると、消費や経済活性化にも影響をもたらすということです。
また経済的な影響だけでなく、協調的な行動が促進されるということは、組織内においても、また地域内においてもコミュニケーションが図られ、意思の疎通や他者への理解、規範意識や秩序を保つことにも大きく貢献することが予想されます。他者とのつながりが希薄化すれば、入手したい情報も手に入りにくくなることでしょうし、他者とのつながりが希薄化すれば、周りの人たちを信頼するというチャンスも失うため、さらに孤立化を助長するという悪循環につながります。
Putnam先生の研究は、アメリカの社会で定着してきた古き良き時代、つまり、デモクラシーの衰退が社会の衰退を招くと結論づけたものです。
このソーシャル・キャピタルという概念を使って、現在では、政治学、社会学、経済学、経営学のみならず、ヘルスプロモーションなどの健康政策にも関わる問題まで論じられています。
それで...
話を行動計量学会の発表に戻すと、このソーシャル・キャピタルという概念の定義、操作化、測定尺度、また分析レベルで検討を加えるべき点についてディスカッションされました。
このセッションの登壇者は、日本でもソーシャル・キャピタル研究の第一人者といわれる日本大学の稲葉先生やこの分野の実証的研究を数多く進められている三菱UFJリサーチ&コンサルティングの市田さん、また地域でヘルスプロモーションの実践とソーシャル・キャピタルの研究に手がけている島根大学の濱野先生でした。
ソーシャル・キャピタルは、個人のものか、集団や地域の特性か、測定尺度は単一項目ではなく、複数項目で測定されるべきではないか、また分析レベルは、相関や回帰ではなく、多変量や階層レベルを考慮したマルチレベル分析を進めるべきではないか...などなど、刺激的な情報を入手することができました。
ついつい、研究を進めていると、視野が狭まり、大切なきっかけを見過ごしがちになります。
我々スポーツマネジメント領域のメンバーには、体育科教育やスポーツ教育学に手がける【智】先生、基礎科学としての経営学やマーケティングに手がける【道】先生、そして社会心理学や組織心理学に手がける【ippo】先生など、ユニークかつ多彩な研究業績を持つメンバーがスクラムを組んで学生の指導に当たっています。
我々教員も互いに学びあうように、学生諸君も他の学生から刺激を受けてほしいと思いますし、視野を広く持って、研究の可能性を探究してほしいと思います。
今回の学会参加は、そんな気づきを得るものでした!ippo先生、多謝!