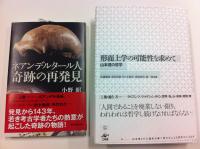Hamaです。
先週、本を2冊紹介しましたが、実はもう1冊注文していました。「化石の分子生物学 -生命進化の謎を解く-」
更科 功 講談社現代新書この本は、先週の本「ネアンデルタール人」と同様なジャンルの本です。
「ネアンデルタール人」も少し始めの方は読んだのですが、ちょっと置き忘れてしまい、先にこちらの本から読むことにしました。
この本の中で、とても興味深いのは、ジュラシック・パークの夢をほんとうに実現できるかどうか、という第5章です。
「ジュラシック・パーク」は、蚊が閉じ込められた化石から、蚊が吸った恐竜の血を見つけ、そこから恐竜のDNAを採取して、バイオテクノロジーを使って、恐竜を現代によみがえらせるとういう物語です。映画にもなりましたから、みなさんも見られているかもしれませんね。
恐竜は、6500万年前に絶滅したとされていますから、それよりも古い地層を掘らなければ、恐竜のDNAは入手することができないわけです。でも、1994年には、8000万年前の恐竜の化石からDNAが抽出されたということです。しかし、読みすすめていくうちに、実はこのDNAは、人間のミトコンドリアDNAに一番近いことが判ったということでした。残念ながら、恐竜のDNAではなかったようです。
ちなみに、先週から取りかかっていた研究費の計画書は、無事に、大学内の担当部所に提出しました!!あとは審査待ちです・・・。
【Hama】