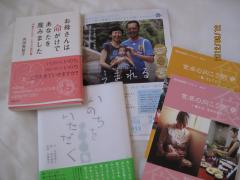2012.09.15
岐阜に来ています(日本体力医学会)
昨年に引き続き、今年も立命館からは多数の教員、大学院生、学部生が参加しています(約40名??)。はい、チーム立命館よく目立っています!私の研究室からも大学院生5名(うち2名が発表)、学部生1名の6名が参加しています。私自身は大学院の博士課程に進学した25歳の時に初めて学会に参加しました。一方、今は、修士課程や何と学部の学生も積極的に参加しています。立派の一言です。
今日のお昼はランチョンセミナーを立命館大学が主催しました。「スポーツ健康科学分野の展望」というテーマで、本学部における研究施策や「スポーツ健康科学研究センター」での研究プロジェクトの取り組みを学部長のizumi先生が紹介され、その後、hassy先生の研究室でポストドクトラルフェローをされているH田先生が【脂肪分解の分子メカニズムに関する研究】というテーマで、現在取り組まれている最新の知見を披露されました。その後私は、【代謝、内分泌応答を手がかりにしたトレーニング科学研究〜トレーニング、栄養、休養からのアプローチ〜】というテーマで話をさせていただきました。運動後のリカバリー中におけるコンプレッションウェア着用の効果や、運動に伴う食欲の変化に関する最新の研究結果を報告しました。特に後者については、先週データが揃ったばかりで、運動をすると食欲を促進させるホルモンである【グレリン】が低下し、それに伴い空腹感が軽減されるという内容です。これからまだ幾つかの研究が必要ですが、1日の中で適切なタイミングで適切な運動を実施することで、1日を通して食欲を抑えることができないか。。。。かなり大胆な発想をもっています。もし、これが現実になればぜひ私自身積極的に取り入れたいと思います(特に私は食欲旺盛で、我が家のエンゲル係数は凄いものがありますので・・・・)。
さて、学会も明日で最終日です。明日の午前中もスポ健からは大学院生や学部生が発表をします。特に、若手研究奨励賞にノミネートされている2名の学生の発表は楽しみです!
GOTO