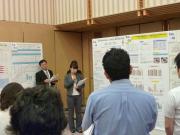先週末に行われた体力医学会大会(山口県下関)では,本学部の先生方,院生,学部生を会わせると総勢37名の参加がありました.この詳細は,今週の【香】先生,【Hassy】先生のブログで紹介されるはずでので,そちらを楽しみにしてください.
また,本日は修士2回生の修士論文構想発表会が行われます.全員15分の持ち時間を使って,自らの修士論文を最終的にどこまで達成するのか,その具体的なこれまでの進捗と残り4ヶ月間の計画を発表します.はじめでの修士論文を出す教員にとっても緊張します.
さて,9月11日から14日までの期間,シンガポールに【聡】先生と出張してきました. 今回の出張は,アジアでの教育交流の可能性,ならびに研究ネットワークを構築するためのものです.訪問先は,National Institute of Education,Nanyang Technology University, Singapore Sports Institute の3カ所です.まず感じたのは,いずれの教育,研究機関でも雇用されているスタッフは世界中から集まってきていることです.シンガポールの人口は約600万人で,中国系約70%,マレー系20%,インド系10%,その他,という比率です.英語は公用語になっており,全ての国民が英語を話します.ですので,もちろん大学の講義は英語です.現在の大学進学率は,20%であり非常に競争が激しいと聞きました.
3つの教育・研究機関ともに,研究に力を入れていました.そのために海外から優秀な人材を集めています.シンガポールには日本人研究者が100名ほどいるようで非常に著名な先生から若手の優秀な研究者までいます.今回,コーディネイトしてもらった増田先生もそのような若手研究者の一人です.客員教授である田口先生のおられた京都大学で博士号を取得して,その後シンガポールで研究をして現在2年目です.増田先生は,学部をでたあと一度仕事に就いた後,「どうしても研究したい」ということで30歳前に博士課程に入ったそうです.その分,意欲高く,現在の研究に集中して研究成果をあげるべく頑張っておられます.
このような意欲的な人材を集め,そのための環境を十分に整えています.スポーツにおいても同様な「勢い」を感じました.Singapore Sports Instituteは,日本の体育協会,国立スポーツ科学センター,国立トレーニングセンターを兼ねたような組織です.対象のスポーツ種目は少数に特化して,その分,集中して強化を図っています.施設整備についても,2025年までの構想ができており,巨大スポーツ施設(競技場,スポーツ科学施設,トレーニング,スポーツ医学施設など)が建設されます.おそらく,今後も世界中から関連の人材を集めるでしょう.本学部・研究科の卒業生の進路の一つになってほしいと願っています.今回の訪問で,日本の大学で修士をでてそのあとオーストラリアで博士号と取った日本人の研究スタッフにも会いました.彼に続いてほしいものです.
このSingapore Sports Instituteのミッションは,「参加」「競技力向上」「スポーツ産業」の3つです.「参加」「競技力」は他の国でも共通にみられます.「スポーツ産業」をミッションに入れているのは新鮮に感じました.産業の少ないシンガポールにあって,スポーツ産業の振興を掲げているのは興味深いです.この産業振興のために,スポーツ科学の研究スタッフは,経営,テクノジーの分野の人々との交流が求められます.やはり「学際的な力」が必要になってきます.本学部の強みである学際性,総合性は,異分野交流にとっても産業振興にとっても強みになることを感じさせてくれました.
【忠】
今週『ちょっと,もっと,ほっと話』
 今回のシンガポール滞在で宿泊先にしたのは,Furama City Center です.ここにサービスマネジメントインスティチュートを卒業した,竹田健二朗君が働いています.彼は在学中からホテルマンになることを固く決意し,卒業後にホテル業の専門学校へ行った後,このホテルで国際的なホテルマンの修行をしています.にこやかに,巧みな英語で接客している彼をみて頼もしく,嬉しくなりました.ホテルマンとしてさらに磨きをかけることを念頭において修行するようです.シンガポールに行く際には是非,彼のつとめるホテルをご利用してください.
今回のシンガポール滞在で宿泊先にしたのは,Furama City Center です.ここにサービスマネジメントインスティチュートを卒業した,竹田健二朗君が働いています.彼は在学中からホテルマンになることを固く決意し,卒業後にホテル業の専門学校へ行った後,このホテルで国際的なホテルマンの修行をしています.にこやかに,巧みな英語で接客している彼をみて頼もしく,嬉しくなりました.ホテルマンとしてさらに磨きをかけることを念頭において修行するようです.シンガポールに行く際には是非,彼のつとめるホテルをご利用してください.