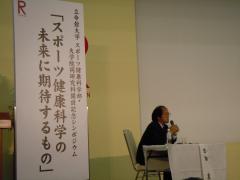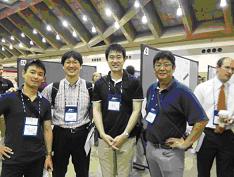立命館大学にスポーツ健康科学部と大学院同研究科が開設されて、2ヶ月あまりが経ちました。
今日は、学部と研究科の開設を記念した式典及びシンポジウムがBKCのプリズムホールにて開催されました。産官学の様々な分野からお招きした来賓の方々だけでなく、第一期生となる学部生・大学院生など、約300名が出席し、会は盛大に執り行われました。
まず、記念式典においては、川口総長が新学部及び研究科の開設に当たって4つの願いと期待を述べられました。
それは、「スポーツ分野における最先端の研究と新しい時代に求められる人材の養成」「立命館がめざす新しい教育システムの機能化」「課外活動分野におけるチーム及びアスリートの飛躍的なパフォーマンスの発揮」「人々に感動を与える州スポーツの輪を地域社会に広げるというものでした。
 次に、スポーツ健康科学部長ならびに大学院同研究科長の田畑先生が挨拶され、最先端の設備とスタッフのもので、第一期生は、大いに学んでもらいたいという学生に対する期待が述べられました。
次に、スポーツ健康科学部長ならびに大学院同研究科長の田畑先生が挨拶され、最先端の設備とスタッフのもので、第一期生は、大いに学んでもらいたいという学生に対する期待が述べられました。
また学生のキャリア形成に力を注ぎ、保健体育教員の免許状、健康運動指導士の養成を始め、インターンシップや立命館大学が進めるサービスラーニングを通じて、社会に求められる人材を養成したいという決意が述べられました。
またこの記念式典には、米田滋賀県副知事、橋川草津市長が臨席され、祝辞が述べられました。米田副知事、橋川市長ともに、人々の健康を守り、人々に感動を与えるスポーツについて、産官学が連携しながら、新学部と研究科で素晴らしい人材を輩出してほしいという期待が述べられました。
また式典では、スポーツ健康科学部の第一期生を代表して、植村君がスポーツや健康づくりを科学的に捉えるための知識や技術を身につけるとともに、スポーツを通じて人々に感動が与えられるように、この学部でしっかりと学び、新しい伝統を築き上げたいという決意を述べました。
本当に立派な挨拶でした!
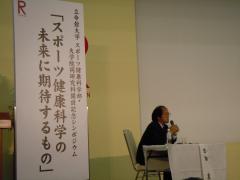

式典の後、「スポーツ健康科学の未来に期待するもの」というテーマで、記念シンポジウムが行われました。田畑先生がコーディネーターを務めGE Health Care Japan株式会社取締役副社長の河上氏、公益法人ヤマハ発動機スポーツ振興財団常務理事の岸川氏、滋賀大学教育学部特任准教授の江崎氏、そして株式会社ルネサンス取締役執行役員の高崎氏が登壇され、それぞれの分野からこの学部・研究科に対する想いが語られました。
中でも高崎氏が「孟子の言葉から来た"立命"という言葉をかみしめて、"未来を生み出す人になる"と唄う立命館大学の使命に基づき、しっかりと学び、社会で羽ばたいてほしいと述べられました。
皆さんは、この立命館大学で未来を生み出し、未来を創り出す人になるために、どのようなキャリアをデザインしようと考えているでしょうか?
そもそも"キャリア"とは、何のことを意味しているのでしょうか?
キャリアという言葉を聞いて、多くの人が思い浮かびそうな意味が「高い役職」や「優れた経歴」ということでしょう。国家公務員の高級官僚を"キャリア組"と呼んで、それ以外を"ノンキャリア組"と区別して用いることからも想像がつくでしょう。
キャリアの概念は、1950年代から1960年代にかけて、"ワークキャリア"、つまり、人生における仕事の部分として、職業生活を中心に捉えられてきました。その後、1970年代から80年代に単なる職業生活としてキャリアを捉えるのではなく、人々の生き方や生きざまを踏まえた"ライフキャリア"として捉えられるようになりました。それは、ライフコースや「人は生涯発達する」という生涯発達心理学の立場から人々のキャリアを人生の中で位置づける必要があると考えられるようになったからです。
したがって、"キャリア"とは、単なる職歴や経歴のことを意味するのではなく、仕事への憧れやこだわり、またその仕事を通じて実現できる生活水準などを含んだ、個人個人の生涯にわたるライフスタイルやライフコースを築くためのプロセスと考えた方がいいでしょう。
このように、キャリアが包括的な意味合いを持つことから、神戸大学の金井壽宏先生は、「働くためのキャリア・デザイン(PHP新書, 2002年)」という本の中で、"長い目で見た仕事生活のパターン"としてキャリアを定義づけています。
そのように考えれば、個人個人が他者や社会からの影響を受けながら、仕事と人生の両者の関係や、自己実現、目標設定など、自分自身が何をいつまでに、どの程度成し遂げようとしてるのかというプロセスについて考え、それを描くことを"キャリアデザイン"と考えればいいでしょう。
このキャリアデザインについては、2つの側面からアプローチが考えられます。1つは、皆さん自身の立場からキャリアについて考えることです。つまり、先に述べたような自分自身の人生や職業についての夢を描き、いまどのような能力を有してるのか、またどのような能力を身につけるべきなのか、日々の活動や仕事を通じて何がしたいのか、また何を成し遂げたいのか、さらには、自分がどのようなことをしてるときに価値を抱き、充実した毎日を過ごすことができるのか、といったことを個人個人が考えるという立場です。
またその一方で、組織の中で働く従業員を採用する企業、また社会に求められる人材を輩出すべき大学を始めとした教育機関の立場から捉える側面もあります。経営学には、ヒューマン・リソース・マネジメント(人的資源管理)という研究領域がありますが、組織は貴重な人的資源を活用し、組織の目的を達成するために、従業員個人のキャリアを設計し、運用する必要があります。企業が採用試験を行ったり、従業員として採用した後、研修などを通じて、知識やスキルアップに努めるのは、人の育成なくして、組織の発展は成し遂げられないからです。
そのように考えれば、今回のシンポジウムは、スポーツ健康科学部の教職員が、学部生や大学院生に対して、どのような人材となってほしいのか、またどのような能力を身につけてほしいのかというメッセージを送っているということに他なりません。
経営学者のゲラマンは、キャリアデザインのための重要なポイントとして、「明確なイメージを自らの中につくり、イメージを実現する方向に自らの行動を向け、周囲からの評価を参考にしながら、自らの手でその結果を検証・評価すること」と述べています。
参加した学生の皆さんは、君たち自身の幸せな人生を築くために、あなたと大学、あなたと企業、あなたと社会との関係をいかに捉え、いかに構築するかということを考えてほしいと思います。