最新号・バックナンバー
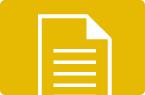
立命館CLUB 【VOL.269】
2025 年06月27日
立命館CLUB【VOL.269】
立命館CLUB会員の皆様こんにちは。
梅雨明けが待ち遠しいこの頃、いかがお過ごしでしょうか。京都では、しっとりとした雨に洗われた新緑が一段と輝きを増し、風情ある景色が広がっています。さて、今年学園創立125周年を迎える立命館では、障害のイメージ変容と福祉を起点に新たな文化の創出を目指す「ヘラルボニー」や、伝統と革新を融合させながら個性を尊重するライフスタイルの提案を行う「ユナイテッドアローズ」などとのオリジナルコラボグッズを開発し、立命館大学生協およびオンラインショップにて販売を開始しています。
◆ユナイテッドアローズ立命館学園創立125周年記念オリジナルグッズ
立命館のタグライン「Futurize.」をデザインアイコンに据え、学園の目指す未来像を表現したTシャツ、ソックス、ハンドタオルなどを展開。
◆立命館オリジナルボールペン・ノートブックwith HERALBONY
独創的なアート作品に、「RITSUMEIKAN」の文字が入ったオリジナルボールペン、ノートブックを展開。
125周年関連グッズ、その他立命館オリジナルグッズもございますので、ぜひオンラインショップ(https://creohuman.square.site/s/shop)をご覧ください。
▼学園ニュース▼
【1】衣笠アートヴィレッジ フェスティバルを初開催
6月1日(日)、立命館大学衣笠キャンパスおよび衣笠周辺エリアにて「衣笠アートヴィレッジ フェスティバル」を開催しました。当日は地域の皆さまをはじめ、小さなお子様連れのご家族からご年輩の方まで、およそ12,000名もの方々にお越しいただき、キャンパス内外70を超えるアート企画やパフォーマンスなどをお楽しみいただきました。衣笠キャンパスでは、アートをテーマとした多くの作品を執筆されている原田マハ氏と、ARTISTS’ FAIR KYOTOなどをプロデュースする高岩シュン氏によるアート対談をはじめ、日本・世界を舞台に活躍される方々をお招きしたアートイベントや、ヘラルボニーによるアートエキシビション、2026年度に開設予定のデザイン・アート学部/研究科に関連した企画などが行われました。
【2】国家公務員総合職試験 合格者数62人で西日本私大1位に
5月30日(金)、2025年度春の国家公務員総合職試験の最終合格者が人事院より発表され、立命館大学からは62人が合格。合格者数で全国6位、早稲田大学に次ぐ私立大学2位、西日本の私立大学で1位となりました。立命館大学では、現役の国家公務員総合職による講演会・ディスカッション、政策立案ワークショップなどを通じて、低回生時から行政リーダーとしての素養やマインドを養成するプログラム「立命館霞塾」を2013年から開講するなど、公務員を目指す学生のキャリア支援に力を入れて取り組んできました。また、エクステンションセンターでは、高い合格実績を誇る公務員講座の運営や、充実した奨励金制度など、国家公務員総合職にチャレンジする学生を積極的にサポートしています。今後も学生たちの進路希望に寄り添いながら、日本の未来を担う公務員の養成に努めてまいります。
【3】サンフランシスコ事務所開設1周年記念イベントを実施
【4】【陸上日本インカレ】女子陸上競技部が総合の部で2位、トラックの部で優勝 女子400mHで瀧野未来選手、10000mWで柳井綾音選手が優勝
【5】第81回学生名人戦 将棋研究会の竹田健人さんが準優勝
写真左:竹田さん
【6】「月面探査・利用を産業化するための宇宙機器開発・人材育成拠点」を本格始動
【7】漕艇部が第103回全日本ローイング選手権大会で女子舵手つきフォア5連覇
【8】第20回「平井嘉一郎研究奨励賞」、第2回「平井嘉一郎優秀論文賞」授賞式を開催
平井嘉一郎研究奨励賞は、ニチコン株式会社の創業者として社業の発展に努められ、同社代表取締役会長、名誉会長として、地元京都はもとより、我が国の工業界の発展に貢献された 故・平井嘉一郎氏<本学法学部1940(昭和15)年3月卒業>のご令室 平井信子様のご厚意にもとづき、本学法学研究科ならびに法務研究科の大学院生の研究を奨励することを目的として2006年に創設されました。また、平井嘉一郎優秀論文賞は、志望進路を目指して日々勉学に励む本学法学部の学生を奨励し、これにより社会の発展に寄与する人材を育成することを目的として設けられ、今回が第2回目です。式典では、仲谷善雄学長が受賞者に祝辞を述べ賞状を授与、平井信子様から副賞が贈呈されました。平井嘉一郎研究奨励賞を受賞した法学研究科博士課程前期課程1回生の金原悠介さんは、「応援してくださる周りの方々、そしてこの図書館で研究することができる日々に心から感謝し、これからも研鑽に励みます」と今後の抱負を述べました。平井信子様は、「全ての人が平等に、楽しく、平和な生活ができる社会づくりのため、自らの研究に一層励んでいただき、グローバルな人材になっていただきたい」と受賞者への励ましと期待のお言葉を送られました。
【9】塩野麻子専門研究員が 第19回日本科学史学会学術奨励賞を受賞
──────────────
その他学園ニュースはコチラ≫
──────────────
▼EVENT(公開講座など)▼
【1】[オンライン][無料][要事前申込]【現代社会を読み解く】災害から考える人間の尊厳と暮らし-レジリエンス社会への希求
日本は、「災害列島」と呼ばれるように、地震・津波・台風・火災あるいは人為的災害など、多くの災害を経験してきました。災害は、人びとの暮らしやいのちを脅かし、時に大きな被害をもたらします。2011年の東日本大震災および原子力災害を経験した「ふくしま」を題材にして、災害が起きても尊厳のある暮らしを維持するために、私たちはどんなことを考えていかなければならないか。一緒に考えていきましょう。
[日時]7月17日(木) 19:00~20:30
[会場]オンライン
[講師]丹波 史紀(立命館大学産業社会学部 教授)
[定員]1000名 ※先着順となっておりますのでお早めにお申し込みください
[詳細・お申込み]https://www.ritsumei.ac.jp/open-univ/course/detail/?id=372
【2】[オンライン][無料][要事前申込]
【現代社会を読み解く】「調べて終わる探究」から「問いを育てる学び」へ ― 主体的に考える力を育む教育心理学の視点から
探究的な学びが広がる中で、子どもたちの学びが「調べて終わる」段階にとどまり、思考の深まりにつながらないという悩みが多く聞かれます。その背景には、思考そのものの不足だけでなく、「考えたつもり」になってしまう心理的な傾向があるのではないでしょうか。この講義では、教育心理学の視点から、そうした現象をひもときながら、子どもが問いを立て、自ら考える力を育んでいくために、大人がどのような関わりをすればよいのかを探っていきます。
[日時]7月22日(火) 19:00~20:30
[会場]オンライン
[講師]川那部 隆司(立命館大学文学部 准教授)
[定員]1000名 ※先着順となっておりますのでお早めにお申し込みください
[詳細・お申込み]https://www.ritsumei.ac.jp/open-univ/course/detail/?id=373
【3】[@衣笠][オンライン][無料][要事前申込]
立命館土曜講座
<7月のテーマ>
在りし琉球王国を甦る~琉球人行列絵巻と首里城復元
企画:立命館大学アート・リサーチセンター
7月12日(土)10:00~11:30
絵巻に息づく琉球使節
立命館大学衣笠総合研究機構 准教授 Seifman Travis
[会場]衣笠キャンパス末川記念会館+ZOOMウェビナー
7月19日(土)10:00~11:30
平成と令和の復元首里城について:復元根拠の変遷
京都大学大学院 人間・環境学研究科 名誉教授 伊從 勉
[会場]衣笠キャンパス末川記念会館(後日見逃し配信あり)
詳細はコチラ≫
【4】[@OIC][オンライン][無料][要事前申込]
2025年度RARA主催シンポジウム「アート×テクノロジーが“可視化”する未来研究デザイン── 異分野融合で挑むデジタル・パブリックヒューマニティーズ」
先端技術が飛躍的に発展する今、身体感覚を伴うアートやデザインの価値が再認識され、領域を超えたコラボレーションが世界規模で生まれ始めています。RARAにおいても理工系の技術と人文・芸術研究を横断し、学内外の先端知を結ぶNodes(結合点)の形成と新たな知の創出に取り組んでいます。そうした知を共有し、アートとテクノロジーが可視化し拡張する私たち人間の叡智や体験、場所、研究の未来を考えるシンポジウムを開催します。
[日時]7月12日(土)13:00~17:40
[会場]場所:大阪いばらきキャンパス H棟2階 ラーニングインフィニティホール
※オンラインライブ配信とのハイブリッド形式
[講師]西浦 敬信 (立命館大学RARAアソシエイトフェロー/情報理工学部教授)
田中 覚 (立命館大学RARAフェロー/情報理工学部特任教授)
中山 雅貴 氏 (Senior Vice President, Studio Head, Sony Innovation Studios)
廣田 ふみ 氏 (プロデューサー/株式会社イッカク代表取締役)
モニカ・ビンチク 氏 (メトロポリタン美術館ダイアン&アーサー・アビー日本工芸キューレーター)
赤間 亮 (立命館大学RARAフェロー/文学部教授/アート・リサーチセンターセンター長)
松葉 涼子 (立命館大学文学部教授/デザイン・アート学部、デザイン・アート学研究科設置委員会委員)
[定員]現地200名/オンライン400名 ※先着順となっておりますのでお早めにお申し込みください
[詳細・お申込み]https://rararits250712.peatix.com
─────────────
その他の公開講座はコチラ≫
─────────────
▼EVENT(スポーツ/学芸)▼
【1】[@大阪府][有料][申込不要]ホッケー部(男子・女子)第44回全日本大学ホッケー王座決定戦・東西交流戦
[場 所]立命館 OIC フィールド
[入場料]【10・11日】大人:500円/高校生以下:無料
【12・13日】大人:1,000円/高校生:500円/中学生以下:無料
[その他]アベックで2連覇します!応援よろしくお願いします!
キッチンカーや最終日のイベント企画等、試合以外でもお楽しみいただけるよう、準備してお待ちしております!
詳細はコチラ≫
【2】 [@東京都][有料][申込要]
男女陸上競技部 第109回日本陸上競技選手権大会
[場 所]国立競技場
[入場料]有料(通し券・1日券など各種チケットあり)
[その他]全日本インカレも終わり、いよいよ日本選手権が始まります。各選手がこの試合のために準備してきました。最高のパフォーマンスを発揮できるよう頑張りますので応援のほどよろしくお願いします!
詳細はコチラ≫
【3】[@シンガポール]
水泳部 滋賀・立命館ダイビングクラブ所属 玉井陸斗選手
世界水泳シンガポール2025
[その他](玉井選手コメント)
金メダル獲得という目標を達成するために、日々練習を重ねています。本番でいつも通りの演技ができるようにベストを尽くします。
詳細はコチラ≫
【4】[@三重県][無料][申込不要]
卓球部 第94回全日本大学総合卓球選手権大会(団体の部)
[日 時]7月3日(木)~6日(日)
[場 所]四日市市総合体育館
[入場料]無料
[その他]こんにちは。立命館大学体育会卓球部です。関西春リーグでは男女アベック優勝し、インカレはより上の成績を目指します。応援よろしくお願いします。
詳細はコチラ≫
▼輝く学生インタビュー▼
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━第233回 輝く学生インタビュー
学生たちがアートで繋いだ新入生の輪
村田 美月さん(国際関係学部4回生)
三川 聡文さん(文学部4回生)
土橋 由愛さん(法学部4回生)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
このコーナーでは、立命館でいまを精一杯頑張り、輝いている学生や団体を紹介します。
2025年6月1日(日)、立命館大学衣笠キャンパスおよび衣笠周辺エリアにて開催された「衣笠アートヴィレッジ フェスティバル」。衣笠エリア全体がアートに染まったこのイベントは、大学生活のスタートラインに立つ新入生たちが、多様なアート企画「FRESH ART」を創りあげる過程を通じて、学部の垣根を越えて繋がり、大学生活をより豊かなものにするための大きな一歩でもあった。
今回、この祭典の企画・運営を牽引した3人の学生、村田さん、三川さん、土橋さんに、その構想のきっかけから、企画・運営における苦労、そして当日得られたかけがえのない達成感、そして未来へのビジョンについて語ってもらった。
◎村田 美月(むらた みつき)さん
立命館大学学友会 全学自治会初年次担当 衣笠キャンパス代表。
鹿児島県奄美大島出身。国際関係学部国際関係学科4回生。
中学生時代のテキサス留学をきっかけに国際関係を深く学びたいと志し、キャンパスの写真を見て一番ワクワクした立命館大学に進学。ゼミでは、「国内外のジャーナリズム実践方法」を研究。
◎三川 聡文(みかわ さとふみ)さん
立命館大学学友会 全学自治会初年次担当
福井県越前市出身。文学部日本文学研究学日本語情報学専攻4回生。
関西の様々な大学を見る中で、キャンパスや学部の充実度から立命館に進学。昔からの“国語好き”で、ゼミでは、「SNSなどで使われる現代の日本語『打ち言葉』の現状と将来」について研究中。
◎土橋由愛(どばし ゆうあ)さん
立命館大学学友会 全学自治会初年次担当
奈良県奈良市出身。法学部4回生。
幼い頃から抱いていた「警察官になりたい」という目標から、法律を学ぶために立命館大学法学部を選択。歴史文化コースに所属し、日本法に加え、西洋法史や英米法など、多岐にわたる法律を比較して学ぶ。副専攻では朝鮮語も履修。
このイベント「FRESH ART」の核となったのは、彼らが所属する「学友会全学自治会初年次担当」という組織だ。これは、“オリター”や“ピア・サポーターズ”といった、各学部の新入生サポート団体を支援する上部組織である。村田さん、三川さん、土橋さんは、それぞれ異なる学部で「オリター団長」を務めてきた経験を持つ。
-まずは、皆さんがどのような経緯で新入生サポート団体の活動に関わることになったのか、教えてください。
三川「1回生の時、私自身がオリターの先輩たちにたくさん助けてもらってきた経験から、今度は自分が新入生をサポートしてあげたいという気持ちがオリターになったきっかけです。オリターの人たちが楽しそうに活動していたので、私もこういうコミュニティで活動したいと思いましたね」。
村田「私は新しいことにチャレンジするのが好きで、2回生から新たに始められるオリター活動に興味を持ちました。特に、国際関係学部のオリター団は企画が少なく、日本人と外国人学生がそれぞれのコミュニティ中心で交流し、壁を越えた情報共有ができていないと感じていたので、そこを改善したいという思いがありました」。
土橋「私は小学校の頃から企画や運営が好きで、大学でも何かやってみたいと思っていました。オリターの先輩たちがすごくかっこよくて、楽しそうに活動していたので、私も関わりたいと強く思いました」。
2回生時のオリター活動、さらには各学部のオリター団長の経験を経て、3人は全学自治会初年次担当として、“学部を超えた新入生の交流を促進する”という新たな目標を抱くことになった。
●新入生のための「アート」な祭り
-どのような経緯でこのイベントを企画することになったのでしょうか?
#村田さん(主に模擬店企画を担当)
村田「村田「昨年の7月に、各キャンパスのオリター団の活動振り返り会があったんです。その時、BKC(びわこ・くさつキャンパス)ではスポーツイベント、OIC(大阪いばらきキャンパス)では地域を巻き込んだイベントが活発に行われていると聞いて。でも、衣笠キャンパスには、サークルに入っていない新入生でも気軽に楽しめるような大規模なイベントが少ないと感じていました。そこで、大学の職員の方から『そういう企画をやってみないか』と声をかけられて、思わず『やりたい!』と言ってしまったのが始まりです(笑)」。
三川「企画がスタートしたのは2024年の2月で、そこから3ヶ月という短い期間で、ゼロからこの『FRESH ART』を作り上げていきました。かなりの忙しさでしたね」。
●企画の舞台裏-3ヶ月での「ゼロからの創造」と苦悩
新入生が自ら作り上げるアート企画「FRESH ART」は、アート展示企画、模擬店企画、地図・看板制作などで構成されていた。これらの企画を3ヶ月でゼロから立ち上げることは、並大抵の苦労ではなかった。中心となって動いたのは彼ら3名だが、運営には現オリター団長や元執行部のアドバイザー、そして各学部の現役オリター団からのサポートを含め、総勢17名が関わってくれた。
-企画を進める上で、特に苦労されたことや難しさを感じたことはありますか?
#三川さん(主にアート展示企画を担当)
三川「僕は、以前オリター団長を経験した時に、なんでも自分でやってしまうのが反省点でした。だから今回は、なるべく仕事をチームのメンバーに任せることを意識していました。正直、骨の折れる部分もありましたが、最終的にはコアメンバーがしっかり動いてくれて成果につながったと感じています」。
村田「正直うまくいったことばかりではありませんでした。時間が本当にない中で、他学部の後輩やアドバイザーなど、初対面のメンバーにどうやって仕事を振り、どう伝えたら良いか全然わからなくて…。迷った結果、自分でやってしまうという状況になってしまいました。うまくコミュニケーションが取れなかったのは、大きな反省点ですね」。
#土橋さん(主にイベント看板・地図製作を担当)
土橋「私も同じく、自分でやってしまいがちなタイプです。そのため、今回はアドバイザーとして元々一緒に活動していた仲間には、『これはもう任せる!』と伝えました。あとは、スケジュール管理は私が担当し、タスクを振って、全体像を把握した情報を共有するようにしていました。看板や地図のような大きな作品は重くて運べず、人手が足りない時には他の担当のメンバーが手伝ってくれて、すごく助かりました」。
彼らは、全体の進捗を共有するための会議を定期的に開催し、問題点について話し合ったり、人手の足りない部分を共有したりと、部門間の連携を図ろうと努力した。しかし、多忙な学生生活の中で、情報共有の徹底やスケジュールの調整は困難を極めたという。
土橋「自分たちも手一杯なので、何を共有したか、何ができていないかを全て把握しきれませんでした。職員さんとの連絡もタイムラグがあったりして、予定通りに進まないこともあり、新入生に迷惑をかけてしまったこともありました」。
三川「でも、各学部の現役オリター団長たちは本当に頼りになりました。人手が足りない時は、彼ら自身はもちろん、他のオリターも何人、何十人と連れてきてくれるので、とても助けられました」。
●熱狂と達成感-想像を超えたフェスティバルの成功
そして迎えた6月1日。彼らが3ヶ月かけて作り上げたアートフェスティバルは、衣笠エリア全体で12,000人を超える来場者を記録し、想像以上の盛り上がりを見せた。
三川「当日、忙しすぎてあまり覚えていない部分もありますが、想像以上の成功だったと思います。私たちが考えていた以上に、来場者が多くて本当に驚きました」。
村田「模擬店もすごく賑わっていました。本当に小さな子どもからご年配の方まで、幅広い層の方が来てくださって、圧倒されました」。
模擬店担当だった村田さんは、特にイベント終了後の新入生たちの様子に心を打たれたという。
企画を終えて、彼らは「大変だけど、やってよかった」という達成感を強く感じている。来場者が楽しそうに参加している姿、そして新入生たちがイベントを通じて仲間と繋がっていく様子を見ることが、何よりの喜びだった。
●それぞれの成長と立命館での学び
この大規模なイベントの企画・運営を通じて、3人はそれぞれ大きな学びと成長を実感した。
三川「達成感はもちろんありますね。想像以上に成功して、何よりも多くの人が来てくれて、模擬店や他の企画もみんな楽しそうにしているのを見られたことが一番の喜びです。それに、企画に参加してくれた新入生たちが実際に仲良くなっているのも間近で見ることができました。また、大学職員の方々と仕事としてメールしたり、大勢の大人と会議する経験は、なかなかできることではありません。想像以上の経験ができて本当に良かったと感じています」。
村田「もちろん達成感はあったのですが、それ以上に『こうしたら良かった』とか、『自分ができていなかったこと』の方がたくさん頭に浮かびました。三川さんと同じようにメールでのやりとりや、色々な人と関わったりすることでの成長感は得られましたが、人への伝え方や要領の良さなど、自分に足りない部分もたくさん見つかりました。この経験があったからこそ、見えてきた課題を今後の成長に繋げていきたいと思っています」。
土橋「準備している1回生たちが、自ら『これやります!』と積極的に声をかけてくれたのがすごく嬉しかったですね。自分のクラスだけでなく、他のクラスにも声をかけて一緒に作業したり交流する姿が見られて、『この企画をやってよかった』と強く思いました。実際にできた看板や地図を見て、職員の方々に『すごかった』と言っていただけたのも嬉しかったですし、『イベント終了後も継続して看板を展示したい』と言ってくださった時は、自分たちの努力が形として評価されたことに喜びを感じました」。
この経験は、彼らが立命館大学で得たかけがえのない学びの一部でもある。
村田「京都で3年強過ごしてみて、東京などの都会に行っていたら感じられなかったであろう、自然や街、そして人と人との距離が近い“風土”を感じました。特に今回の「FRESH ART」では、小さいお子さんからご年配の方まで、大学とは関係ない地域の方々がたくさん来てくださって、京都という街が人との繋がりを大切にしていることを実感しました。立命館大学のオリター団というシステムがあったからこそ、様々な人と関わることができ、とても良い機会だったと感じています」。
土橋「立命館大学は、他の学校よりも学生が大学の自治に深く関わっていると聞いたことがあります。だからこそ、オリターや初年次担当、そして今回のイベント企画のような貴重な経験ができているのかなと思います。また、衣笠キャンパスには下宿生や留学生が多く、地元の人だけでなく、様々な都道府県や海外の友人と深い関係を築けたことも、私が立命館に来て変わったことですね」。
●未来へのビジョン-学びを活かして次なる一歩へ
4回生として、彼らは残りの大学生活と卒業後の進路について、それぞれのビジョンを語ってくれた。
-残りの大学生活と、その先の将来のビジョンについて教えてください。
三川「残りの大学生活では、車の免許を取ったり、株の勉強をしたりと、社会に出るための準備をしていきたいです。あとは、友人と仲良く過ごしたり、旅行にも行きたいですね。卒業後は名古屋の会社に就職する予定です。そこでは、お客様とのコミュニケーションやチームでの動きを大切にしながら、しっかり自分のキャリアを積んでいきたいと考えています。大学4年間で、様々な人と関わる中で学んだコミュニケーションや自分自身のあり方を、社会に出てもさらに深めていけたらと思っています」。
村田「来年4月からは映像プロダクションに就職し、映画やドラマ、CMなどを制作するプロデューサーを目指します。元々映像作品が好きで漠然と携わりたいと思っていましたが、今回ゼロから企画を立ち上げて、物や人、場所を集めて最後まで作り上げる経験をしたことで、映像の世界でも同じようにゼロから立ち上げに携わりたいと強く実感しました。今回の企画を通して自分の課題も見えてきたので、それを忘れずに、今後もゼロから何かを作り上げる人間になりたいと思っています。大学生活の残りでは、今まであまりできていなかったこと、例えば海外旅行など、この時期にしかできないことをもっと楽しみたいです」。
土橋「残りの大学生活では、村田さんと同じように今までできなかったことにチャレンジしたいです。昔から音楽をやっていましたが、ずっとキーボードだったので、違う楽器にも挑戦してみたいですね。卒業後は警察官になりたいと思っていて、現在試験を受けている途中です。困っている人に寄り添い、安心を届けられる存在になりたい。人のために真剣に向き合い、誰かのために力を尽くせる人であり続けたいと思っています」。
今回の彼らの経験は、単なる学生イベントの成功に留まらず、企画力、リーダーシップ、チームマネジメント、そして何よりも人との繋がりを大切にする姿勢という、社会で生きるための大切なスキルと精神力を育むものとなった。彼らが立命館大学で培った学びと経験は、それぞれの未来において大きな推進力となるだろう。
▼立命館学園創立125周年「Social Impact 寄付」へのご協力のお願い▼
立命館が歩んできた125年。それは、社会の変化とともに、常に未来を見つめ、挑戦を重ねてきた歴史です。立命館は、学園創立125周年を機に「RITSUMEIKAN FOR SOCIAL IMPACT」 を合言葉に、未来社会への貢献を目指す新たな挑戦を始めました。社会を動かす知を生み出すこと。困難な時代を切り拓く力を、次世代に託すこと。その実現には、立命館CLUB会員の皆様の皆さまのご支援が必要です。立命館の新たな挑戦に想いを寄せていただきたく、心よりお願い申し上げます。プロジェクトの詳細は以下からご覧ください。https://www.ritsumei.ac.jp/125th/donations/
<ご寄付をいただいた方への御礼について>
学園創立 125周年記念 「 Social Impact 基金」(立命館大学)では、インターネットでお申し込みいただいた個人の方に、1 回のご寄付額に応じた返礼品をご用意しています。詳しくはこちらをご覧ください。
▼第269号読者プレゼント▼
今回は、「立命館オリジナルキーホルダー」を3名様にプレゼントします!
(黒く見えていますが、シルバーです。)
なお、プレゼントの抽選結果は次号でお知らせします
<応募締切:7/23(水)>
【パソコンの方はコチラ】
https://reg34.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=mbsd-oekcs-56c4828b83b7298508e5197dc24b61ce
【携帯電話の方はコチラ】
https://reg34.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=mbsd-oekbt-021bc76cab8b8dee6fb681ad47bb33dc
※上記フォームがご利用できない場合は、下記必要事項を明記のうえ、
立命館CLUB事務局までメールにてご連絡ください。
応募先:立命館CLUB事務局(rclub@st.ritsumei.ac.jp)
応募必要事項
(1)名前: (2)プレゼント送付先住所:
(3)電話: (4)今回のメルマガ内容に関する感想:
(5)プレゼント発表時の氏名公開:可 否
(否の場合はイニシャルで表記いたします。
ご希望のペンネームがございましたらご連絡ください。)
▼第268号読プレ当選発表▼
多数のご応募ありがとうございました。268号の読者プレゼントの当選者発表です。プレゼント到着まで今しばらくお待ちください。
・しげやんさん(奈良県)・F・Eさん(長崎県)・ぱちさん(大阪府)
次回のご応募もお待ちしています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
次回の配信は7月25日(金)です。お楽しみに。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆バックナンバー
http://www.ritsumei.ac.jp/rclub/magazine/
◆立命館CLUBホームページ
http://www.ritsumei.ac.jp/rclub/
◆立命館大学ホームページ
http://www.ritsumei.ac.jp/
◆配信先の変更・解除
https://reg34.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=mbsd-meljr-a849c83c0a4b477a2a6d631dde627b21
[注意]
※リンク先は、時間の経過と共に変更・消去されることがあります。
ご了承ください。
※メールマガジンを転載、その他の利用によって生じる事象につい
て、立命館大学では一切の責任を持ちません。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■ 発行:立命館大学立命館CLUB事務局
■■ 〒604-8520京都市中京区西ノ京朱雀町1番地
■■ TEL:075-813-8118
■■ FAX:075-813-8119
■■ ご意見、お問い合わせなどは、下記までお願いいたします。
■■ メール rclub@st.ritsumei.ac.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

